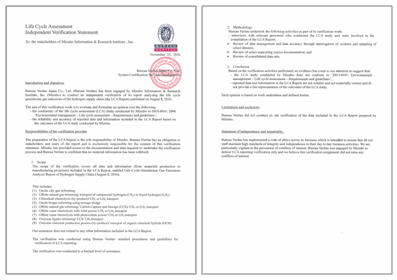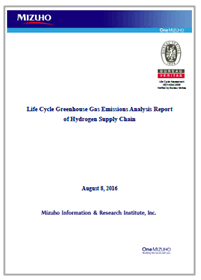みずほ情報総研株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:西澤 順一)は、燃料電池自動車(FCV)の燃料となる水素を製造する際のCO2等の温室効果ガス排出量をライフサイクルアセスメント(LCA)の手法を用いて算出し、その内容について、ビューローベリタスジャパン株式会社から第三者検証を受けました。
FCVは2014年より市場投入が始まり、その燃料となる水素を供給する水素ステーションも全国で整備が進んでいます。水素は、その利用(車両の走行)段階での温室効果ガス排出量はゼロであるものの、製造や輸送、水素ステーションでの充填においてエネルギーを消費し、温室効果ガスが排出されます。また、水素製造時のエネルギー源の種類と製造方法の組み合わせ(製造パス)の違いによっても、温室効果ガス排出量は異なります。みずほ情報総研は、異なる水素製造パスの温室効果ガス排出量を定量的に把握し、将来の排出削減の可能性を考察することを目的として、日本で利用する水素の製造過程(Well-to-Tank*)で発生する温室効果ガス排出量の算出を行いました。また、その内容について、2016年11月に第三者機関であるビューローベリタスジャパン株式会社の審査を受け、LCAの国際規格(ISO 14040:2006(JIS Q 14040:2010)およびISO14044:2006(JIS Q 14044:2010)に準拠していることが確認されました。
今回の評価において、温室効果ガス排出量は天然ガス等の化石燃料から製造した水素で最も多く、次いで副生水素(苛性ソーダ等の化学品製造時の副生物)や下水汚泥から製造した水素で多いという結果が得られました。一方、最も温室効果ガス排出量が少なかったのは、製造時のエネルギー源として風力発電や太陽光発電といった再生可能エネルギーを利用した水素でした。
また、水素の温室効果ガス排出量に影響する要因としては、化石燃料から製造した水素は、原料に元々含まれている炭素の寄与が大きく、一方、化石燃料以外から製造した水素は、水素の製造や輸送、充填に由来する電力の寄与が大きいことが示されました。
みずほ情報総研は、環境保全や資源エネルギー問題に取り組む機関がこれらの基礎情報を活用することで、将来の輸送用燃料に関する調査研究や議論がより活発に行われることを期待し、結果の概要を一般に公開するとともに、今後も引き続き輸送用燃料に関する調査研究を行っていく予定です。
- *一次エネルギーの採掘から燃料を製造し、燃料タンクに充填されるまで
本調査の概要については、こちらをご覧ください
「ライフサイクルを考慮した水素の温室効果ガス排出量に関する評価報告書(概要版)」
https://www.mizuho-ir.co.jp/publication/report/2016/wttghg1612.html
ニュースレターに関するお問い合わせ
調査内容に関するお問い合わせ
みずほ情報総研株式会社
環境エネルギー第2部
大山 祥平