みずほ情報総研株式会社
みずほ情報総研株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:西澤 順一)は、最近10年間に家族・近親者を看取った経験のある50代60代の男女(1,000人)を対象に「エンドオブライフ・ケアの現状に関する調査」を実施し、調査報告書としてまとめましたのでご案内いたします。
2000年4月にスタートした介護保険制度の要介護認定者数は、高齢化に伴って、当初の218万人から、2018年4月時点で644万人にまで増加しています。死亡数も年々増加し、2000年時点の96万人が、2016年には130万人にまで増加しています。一方、同時期の出生数は119万人から98万人に減少しており、わが国は既に少産多死社会を迎えています。
本調査で取り上げたエンドオブライフ・ケアとは、「いのちの終わりについて考える人が、最期までその人らしく生きることができるように、いろいろなつらさに対してかかわり、いのちや生活の質を高めることを目指すケア」を表すものです。人は自分の死を看取ることはできず、誰かの手を借りなくてはなりません。
死や看取りの際の、本人、家族・近親者の現状を明らかにした調査は多くはありません。しかし、長寿化、人口減少、核家族化が進む中、看取りの実態と課題を把握することは避けて通れなくなっていると考えられます。本調査の結果をもとに、亡くなられた方(以下、本人といいます)、家族・近親者が抱える困難さや苦しみの実態と、どのような援助・支援が望まれているかについて検討を行い、エンドオブライフ・ケアのあり方について取り纏めました。
主な調査結果は以下のとおりです。
- 1.亡くなる1年前と2~3カ月前との支援の頻度を比較すると、「定期的(月数回以上)に世話をしていた」が45.3%から55.8%に増加。また、「病院・施設の利用」は12.4%から21.0%に増加。看取りを行った方の実感としても、支援の頻度や手間が「増えた」が48.2%。(図表6-1、6-2)
- 2.医師などから聞いていない場合、家族・近親者が死期を意識することは難しく、本人が亡くなる2~3カ月前でも、「本人の死が近いとは思っていなかった」が37.3%。(図表7)
- 3.
死を前にした時に本人が感じる解決することが困難な苦しみ(「スピリチュアル・ペイン」とも呼ばれる)に向き合うのはつらい」とする家族・近親者は61.1%。(図表8)
- *「スピリチュアル・ペイン」とは、具体的には以下のように様々な言葉で表現される。
「まわりに迷惑ばかりかけて情けない」「トイレの世話になるくらいなら、死んだほうがましだ」「死ぬのがこわい」「今までしていた仕事や家事を続けたい」「家族を残していくのが心配」「さびしい」等
- *「スピリチュアル・ペイン」とは、具体的には以下のように様々な言葉で表現される。
- 4.求められる支援としては、亡くなったご本人(32.7%)や家族・近親者(28.5%)への支援以外でも、「家族・近親者、介護従事者、医療従事者への教育・研修(看取りで連携するために必要な情報提供)」に対し、14.1%~19.1%の要望がある。(図表9)
アンケート調査の概要
最近10年に家族・近親者を看取った経験のある方に対するアンケート調査
|
調査期間 |
2018年1月 |
|
調査対象 |
インターネット調査会社のモニターのうち、50代60代の男女を対象としてスクリーニング調査を実施して、最近10年に家族・近親者を看取った経験のある方1,000人を抽出して、本調査を行った。 |
|
有効回答数 |
1,000人 |
|
主な調査項目 |
4つの時点(亡くなる一年前、2~3カ月前、亡くなられた時、亡くなられた2~3カ月後)で比較を行なった。
|
- *アンケートの中では、回答者が理解しやすいように「エンドオブライフ・ケア」を「人生の最終段階」と表記。
看取りの状況に関する基礎情報
亡くなられた方の続柄
図表1 亡くなられた方の続柄
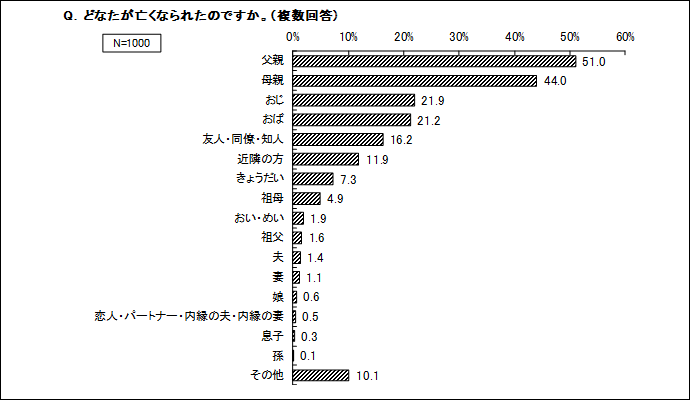
支援が必要となった原因と死因
- 人生の最終段階で支援が必要になった原因の上位3位は、「がん」が32.7%、「高齢による衰弱」が27.1%、「認知症」が18.3%である。死因は、支援が必要になった原因と同様に「がん」が31.3%、「高齢による衰弱」が23.3%と高く、次いで「肺炎」が17.5%だが、「認知症」は1.7%と低い。支援を必要としていなかった人は3.2%にとどまる。
図表2 人生の最終段階で支援が必要となった原因と死因
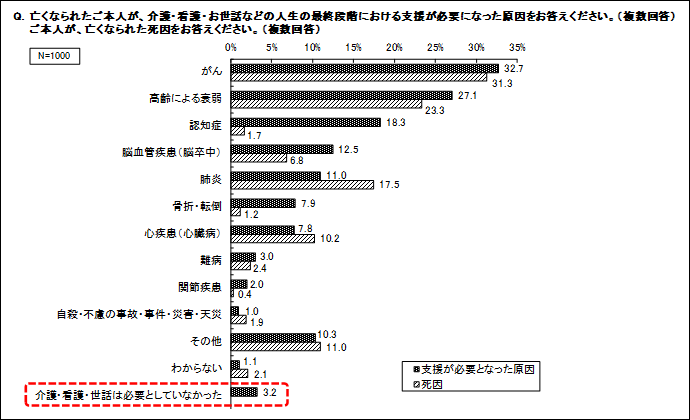
(注)「わからない」、「介護・看護・世話は必要としていなかった」を選択した場合、それ以外の選択肢は選べない設定となっている。
人生の最終段階における要介護認定
- 人生の最終段階における要介護認定については、要介護度3以上の「中重程度」が亡くなる1年前は28.7%だが、亡くなる2~3カ月前は36.3%に増えている。
図表3 人生の最終段階における要介護認定
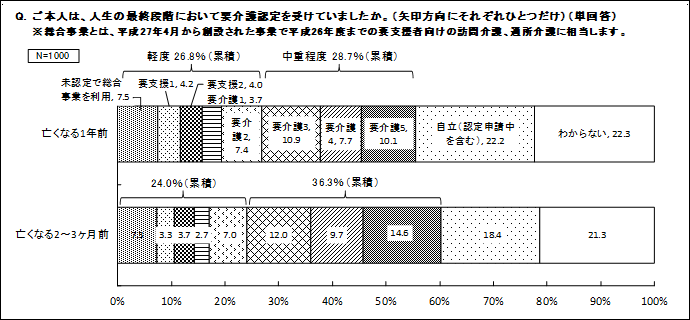
死を迎えた場所
- 本人(亡くなられた方)の居場所を時間の経過とともに追ってみると、時間の経過とともに自宅や施設から医療機関へのシフトがみられ、医療機関で亡くなる方が7割近い。
「亡くなる1年前の居場所」は、「自宅」63.1%、「施設」20.6%、「医療機関」13.3%
「亡くなる2~3カ月前」は、「自宅」40.0%、「施設」20.8%、「医療機関」37.4%
「亡くなられた時」は、「自宅」18.9%、「施設」12.4%、「医療機関」67.1%
図表4 本人が人生の最終段階を過ごした場所
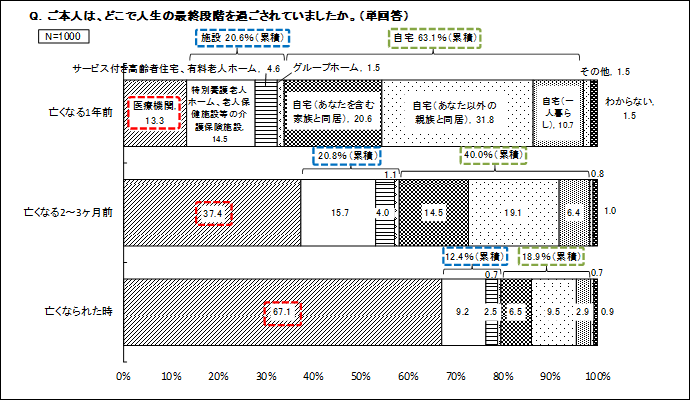
行った支援と亡くなった後の手続き
- 回答者自身が本人の人生の最終段階で行った支援については、「病院、施設を訪問して話をする」、「医師やケアマネジャーとの面談、付き添い」、「買い物」が上位3項目となっている。
「会話、食事、見守り」、「介護・看護」、「家事・生活支援」、「経済的支援」、「死亡後に行ったこと」と、本人の人生の最終段階で行った支援は多岐にわたっている。
図表5 人生の最終段階で行った支援と亡くなった後の手続き
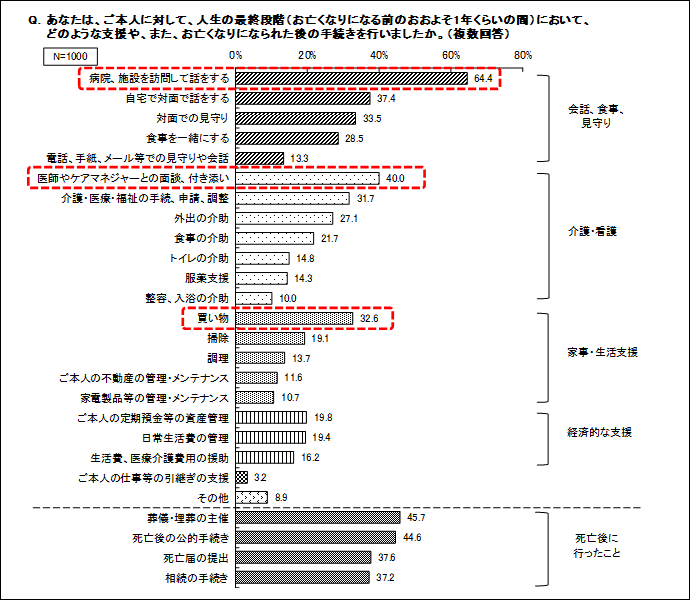
主な調査・分析結果(看取りや支援の難しさに関する調査項目)
人生の最終段階における支援の頻度
- 人生の最終段階における支援の頻度については、「定期的に世話をしていた」が、亡くなる1年前は45.3%、亡くなる2~3カ月前は55.8%とより増えている。「病院・施設」が亡くなる1年前は12.4%だが、亡くなる2~3カ月前は21.0%と倍近く、増えている。
図表6-1 人生の最終段階における支援の頻度
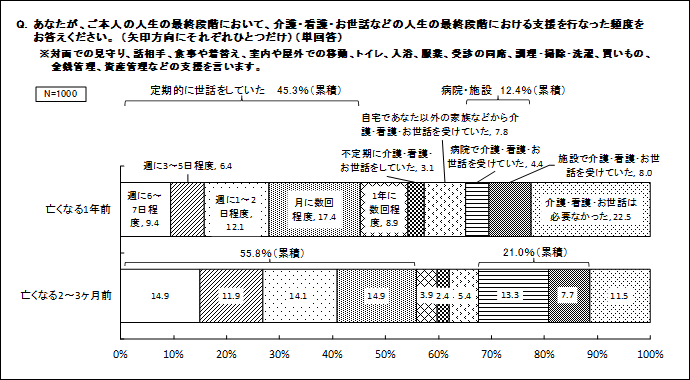
- 亡くなる2~3カ月前の介護・看護・お世話等の支援の頻度と量については、「増えた」が48.2%に対して、「減った」は2.8%と、看取りにおいて家族・近親者の負担は増える傾向がうかがえる。
図表6-2 亡くなる2~3カ月前の支援の頻度と量
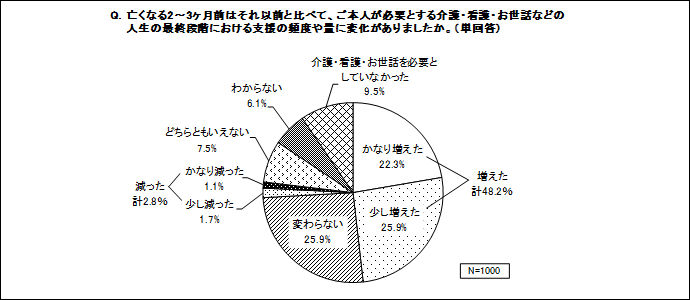
死期についての認識
- 亡くなる2~3カ月前の死期についての回答者の認識については、「かかりつけ医から説明を受けた」が37.3%で最も多く、次いで「本人の心身状態を見て」が22.0%であった。
- 一方、「もっと先だと思っていた」と「突然でまったく予期していなかった」を合わせると37.3%に上り、家族等近親者でも死期の予測は難しいことがうかがえる。
図表7 亡くなる2~3カ月前のご本人の死について
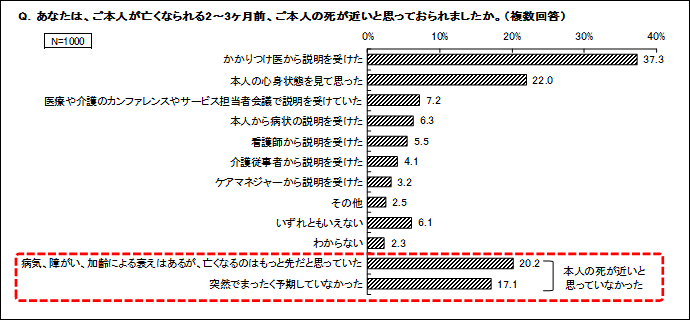
(注)「わからない」、「病気、障がい、加齢による衰えはあるが、亡くなるのはもっと先だと思っていた」、「突然でまったく予期していなかった」を選択した場合、それ以外の選択肢は選べない設定となっている。
8 「スピリチュアル・ペインに向き合うのはつらい」は家族・近親者の6割以上
-
「スピリチュアル・ペイン」を抱えた本人に接するとき、「つらい」と感じる家族・近親者は61.1%と6割以上にのぼり、本人だけでなく、家族・近親者も苦しみを抱えることが明らかとなった。
- (注)「死を前にした時に感じる解決することが困難な苦しみ」(スピリチュアル・ペインと呼ばれることがある)具体的には以下のように、様々な言葉で表現される。
「まわりに迷惑ばかりかけて情けない」「トイレの世話になるくらいなら、死んだほうがましだ」「死ぬのがこわい」「今までしていた仕事や家事を続けたい」「家族を残していくのが心配」「さびしい」など。
- (注)「死を前にした時に感じる解決することが困難な苦しみ」(スピリチュアル・ペインと呼ばれることがある)具体的には以下のように、様々な言葉で表現される。
図表8 本人に接するときのつらさ
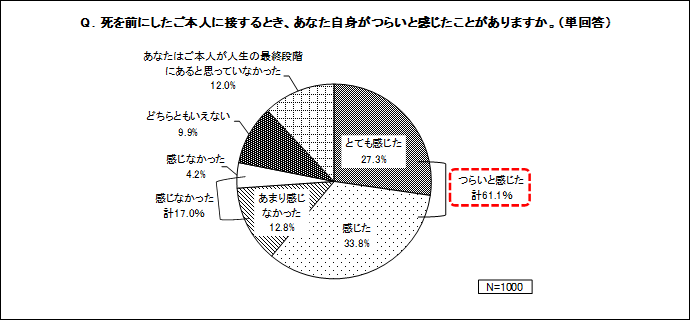
今後、充実を望むことは「本人支援」、「家族・近親者支援」、「研修・教育」
- 多死社会において、今後のエンドオブライフ・ケアについて、「充実の必要性を感じない」は少数にとどまっている。「充実してほしいこと」としては、「本人への支援」、「家族・近親者・遺族への支援」、「家族・近親者・援助者・支援者に対する研修・教育の支援」など多岐にわたっている。
図表9 エンドオブライフ・ケアの充実について
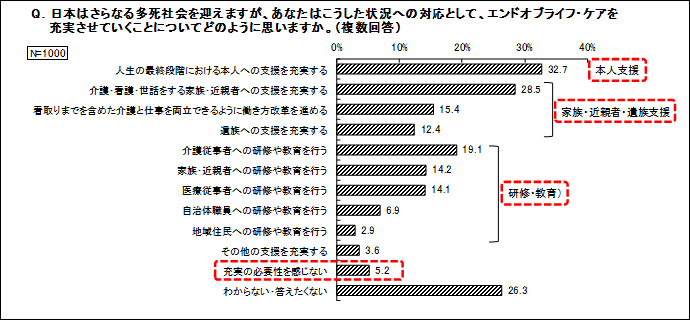
(注)「充実の必要性を感じない」、「わからない・答えたくない」を選択した場合、それ以外の選択肢は選べない設定となっている。
考察
エンドオブライフ・ケアにおいて、家族・近親者の負担や苦しみは増す
- エンドオブライフにおいては、家族・近親者の行う介護・看護・お世話等の頻度が増えたという回答が約5割となっており、家族・近親者の負担が増える傾向にあることが明らかとなった。
- 介護・看護・お世話等に加え、いわゆる「スピリチュアル・ペイン」と呼ばれる「死を前にした時に感じる解決することが困難な苦しみ」を抱えた本人に接して、向き合うことに対するつらさや苦しみを感じる家族・近親者は約6割にも上った。
- エンドオブライフ・ケアを行うことによる家族・近親者の心身への負担、精神的な負担感は多大なものであることが明らかとなった。エンドオブライフにおいては、死にゆく本人だけでなく家族・近親者もつらさや苦しみを感じることが多く、ケアの対象としては、本人のみならず、家族・近親者も同じように重要であることが明らかとなった。
多職種連携でエンドオブライフ・ケアを
- 本人は、亡くなる1年前には約6割が自宅、約2割が施設、約1割が医療機関(病院)で過ごしていたが、亡くなられた場所は、病院が約7割、施設は約1割、自宅は約2割と変化がみられた。
- 支援を必要とするようになった原因や死因は、「がん」、「認知症」、「高齢による衰弱」、「肺炎」、「心疾患(心臓病)」、「骨折」等であった。病気や障害等により、医療・介護・福祉分野の関係機関、関係者の援助・支援を受けた人が多かった。
- 現在、家族・近親者だけで、本人のエンドオブライフを支えることは難しくなっており、医療・介護・福祉をはじめとする様々な援助・支援を受けながら亡くなっている実態が改めて明らかとなった。エンドオブライフ・ケアにおいては、医療・介護関係者、自治体の福祉関係者等が、多職種で連携して、チームで本人、家族・近親者を支えることが重要である。
エンドオブライフ・ケアを地域で支えあう社会的な合意形成を
- 今回調査は、看取りをした家族・近親者を対象に調査を行ったが、近年では頼れる家族・近親者がいない単身者も増えている。長寿化、人口減少、核家族化により、家庭の介護力は低下している。
- 一方、家族・近親者の約4割が、本人が亡くなる2~3カ月前でも、「本人の死を予期していなかった」と回答しており、予め死期を予測して準備することの難しさも明らかとなった。
- 死期を予測することは難しいが、だからこそ、元気なうちからエンドオブライフをどこで、どのように過ごすのかといった自分の意思を、もう少し早めに信頼できる人に伝えておくこと等により、自分の希望を実現する可能性を高めることができるであろう。
- エンドオブライフ・ケアにおいては、死に行く人のそれまでの人生や価値観を尊重しながら、痛みや苦しみを和らげ、おだやかに過ごすことができるように、最期まで寄り添うことが重要だといわれる。本人、家族・近親者を主役として、様々な援助者・支援者が協働できるための具体的なしくみが、地域包括ケアの一貫として、地域に構築され推進されることが期待される。
その他の主な結果は、以下をご覧ください。
看取りの経験者を対象にしたアンケート結果について【資料編】(PDF/423KB)
本調査の詳細な内容については、こちらをあわせてご覧ください。
平成29年度老人保健健康増進等事業の事業報告書
エンドオブライフ・ケアの現状に関する調査研究
●みずほ情報総研の「社会保障関連」領域の取り組みについて
みずほ情報総研は、過去30年にわたる中央省庁の政策策定に関わるコンサルティング、現在の制度運用を支える多数のシステム開発実績があり、総勢150名のスタッフが、本領域に取り組んでいます。近年、我が国では先進国では例を見ないほどの少子・高齢化や労働市場の変化に伴い、福祉ニーズの多様化や高度化が進むなど、社会変動への対応に迫られています。当社では、社会・経済の構造的な変動に対応するために、より一層柔軟な社会保障政策立案が必要であると考え、これまでの知見を活かしながら、社会保障関連領域での取り組みを強化してまいります。
本件に関するお問い合わせ
報道関係者からのお問い合わせ
アンケート調査に関するお問い合わせ
みずほ情報総研株式会社
社会政策コンサルティング部
羽田 圭子