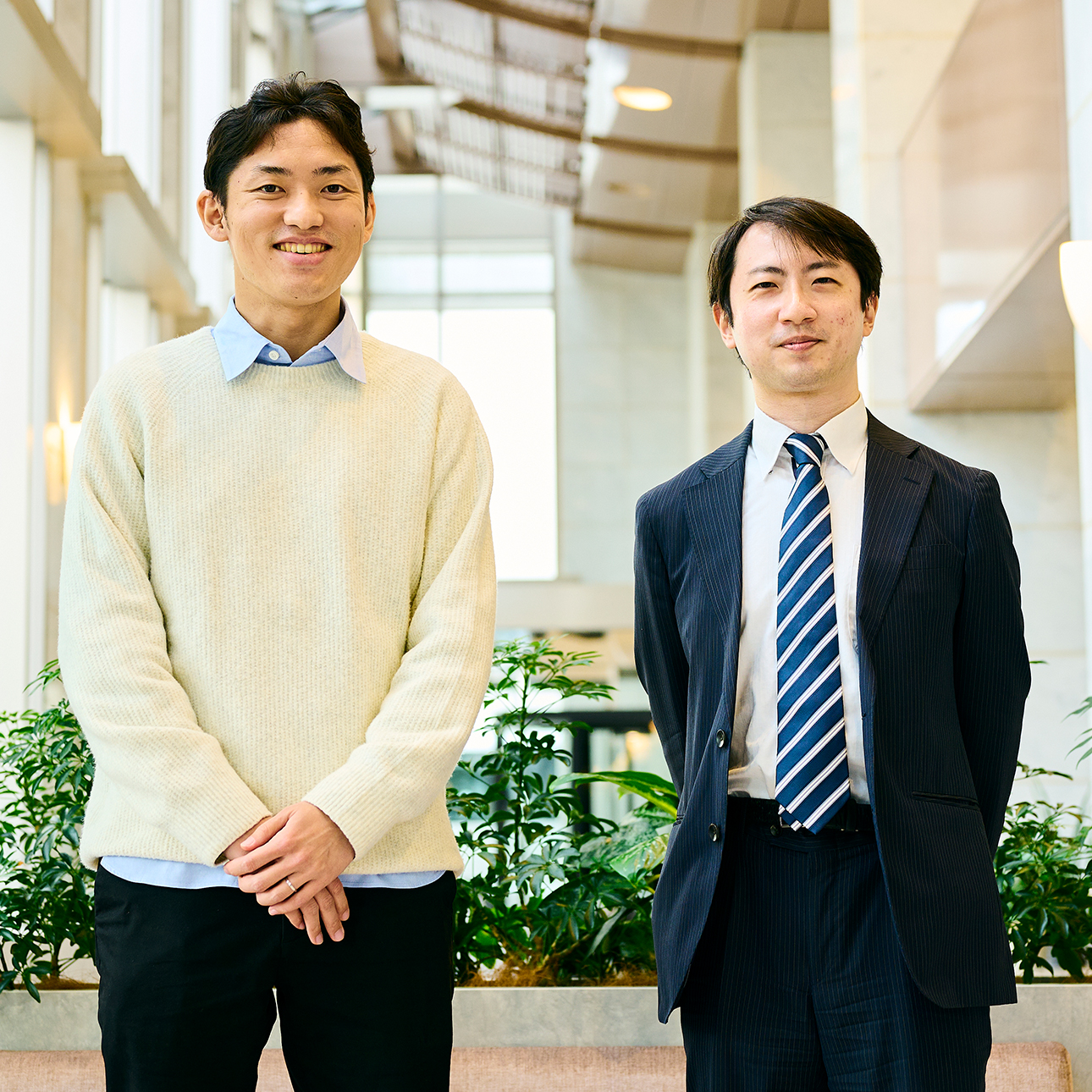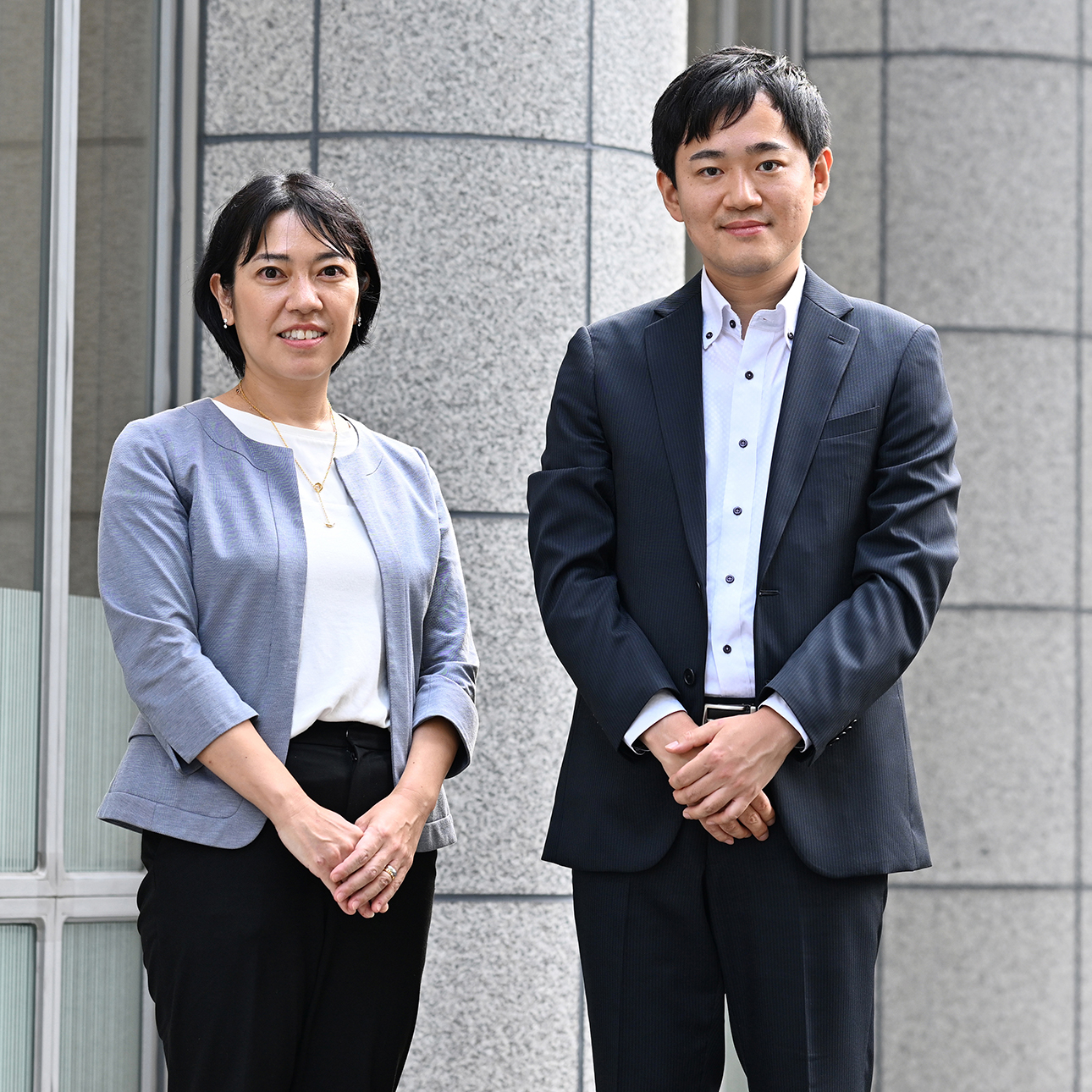(FOCUS on CONSULTING)
未来を共創する
新しいコンサルティングへの挑戦
OUTLINE
近年、コンサルティング業界では、多くの同業他社が採用を強化し陣容を急拡大させてきましたが、今後もその傾向が続くのか、それとも市場拡大は一過性のものなのか、先行きは不透明な状況です。
また、COVID-19(新型コロナウイルス感染症)のパンデミック、地政学リスクの顕現化、気候変動対策、金利のある世界、新しいデジタルテクノロジーの急速な発展、少子高齢化を含むさまざまな社会問題など、世の中の不確実性は高まるばかりです。
このような状況下、コンサルティング本部長を務める豊澤 泰寿がめざすコンサルティング会社について語ります。

豊富な知見を有するプロフェッショナル集団
──コンサルティング本部とはどのような組織でしょうか。
コンサルティング本部は、みずほ情報総研とみずほ総合研究所の両コンサルティング部門を統合し、2021年に設立されました。豊富な知見を持つ約470名のコンサルタントが、お客さまの経営課題解決を支援する戦略コンサルティング領域と、社会的テーマを切り口にお客さまや社会の課題解決を支援する専門コンサルティング領域をカバーしています。
専門コンサルティング領域では、サステナビリティ、ソーシャルイノベーションおよび、ヒューマンキャピタルなどの社会的テーマを幅広くカバーしており、最先端の専門知見を持つ約330名のコンサルタントが、官公庁の政策立案・推進や民間企業の課題解決を支援しています。約6割が修士・博士号を保有するプロフェッショナル集団です。近年注目を集めるようになったサステナビリティ領域は、約140名のコンサルタントが所属しており、1970年代の環境問題の調査受託研究業務などを起源とする歴史に裏打ちされた豊富な知見を有する業界随一のチームです。
戦略コンサルティング領域は、ストラテジーやヒューマンキャピタルの一部で構成されます。約140名の経験豊富なコンサルタントが、中堅中小企業や上場企業の大宗をカバーするみずほグループの幅広いお客さまを中心に、経営戦略や組織戦略、人事戦略、事業戦略、SX/DX共創戦略、官民共創戦略などの戦略策定から、経営管理高度化や事業変革まで、経営課題解決を幅広く支援しています。
近年、とくに注力しているのは、サステナビリティやデジタルイノベーションといった専門コンサルティング領域の専門知見を組み合わせたSX/DX共創戦略策定支援ですが、この新しい挑戦を牽引する専門組織を持つことも大きな特徴と言えます。
みずほグループは、2016年にグループ横断のカンパニー制を導入しており、現在は、5つのカンパニーと、2つのユニットで構成されています。その中の1つが、リサーチ&コンサルティングユニット(以下、RCU)ですが、所謂シンクタンク機能をグループ戦略上の中核機能として位置付けているのは〈みずほ〉のみです。
RCUのリサーチ領域には、当社調査本部、みずほ銀行の産業調査部やみずほ証券のリサーチ関連部署などが所属しており、経験豊富なエコノミスト・アナリスト約400人が、金融・経済、産業、企業、証券などのリサーチをカバーしています。コンサルティング本部は、RCUの過半を占める中核部隊として、コンサルティング領域をカバーしていることも組織的特徴の1つと言えます。

コンサルティング本部のDNAとグループ力を掛け合わせ、同業他社にはない独自の強みを発揮する
──コンサルティング本部の強みを教えてください。
私たちには、同業他社にはない3つの強みがあると考えています。まずは、中長期的な時間軸で、お客さまとの課題解決、人材育成および、新しいテーマの開発などに取り組めることです。コンサルティング本部において脈々と受け継がれてきたDNAとも言えますが、私たちは、単に儲かれば良いということではなく、社会のために、未来のために、今取り組むべきことは何かを真摯に考え、テーマを選択し、専門家を育成し、お客さまとともに課題解決に挑んできました。
一例ですが、コンサルティング本部には、コンサルタントが自らの問題意識から取り組みたいと考えている先進的なテーマを、取り組み意義で選定しプロジェクト化する「チャレンジ投資」という制度があります。若手コンサルタントたちが毎年20件前後のプロジェクトに挑戦しており、これまでの投資実績の中には、現在、主力業務にまで成長しているテーマも多数あります。
お客さまとともに、腰を据えて課題解決に挑むことができる環境だからこそ、社会をより良くしたい、未来のために貢献したいという高い志を持った強力な人材が集まり、育ち、コンサルティング本部の強みになってきたのだと考えています。
次に、複合的な課題解決に幅広く対応できることです。先に触れましたが、コンサルティング本部は、戦略コンサルティング領域と専門コンサルティング領域の両領域をカバーし、RCUの一員として、金融・経済調査に強い調査本部や50年以上にわたる伝統と国内随一の業種知見を持つ産業調査部などの専門家たちと組織横断的に連携を図り、さまざまな知見を活かした課題解決に取り組むことができます。
また、当社内には、最先端の情報技術や生成AIなどのデジタルテクノロジーの専門家も多数在籍しており、お客さまへのソリューションの提供や、私たち自身の業務プロセスの改善などを協働で進めています。このような多様な専門家と、互いに、知的好奇心を刺激し合い、学び合い、切磋琢磨し合うことができる環境であることも強みと言えます。
最後は、みずほ銀行、みずほ信託銀行および、みずほ証券などのみずほグループのさまざまな組織・機能や世界中に広がる拠点とグループワイドに連携することで、従来のコンサルティングの枠を超えるような課題解決にも取り組めることです。
私たちは、グループ各社と、人的関係の強さだけではなく、事業面でも、戦略コンサルティング領域を中心に年間600件超のプロジェクトを連携・共創しており、緊密な関係を築いています。これは、RCUを中核機能に位置付ける唯一の金融グループである〈みずほ〉ならではの強みだと言えます。

コンサルティングだけで終わらない、新しいコンサルティングへ
──どのような姿をめざしていますか。
世界各地で地政学リスクが顕在化し、日本でも金利のある世界への復帰も現実味を帯び始めるなど、社会・事業環境の不確実性は増すばかりです。
同時に、地球規模の持続可能性が最重要テーマの1つとなり、生成AIなどの先端デジタルテクノロジーの発展は今後の社会のあり方を大きく変えてしまう可能性を秘めています。日本では、長年の課題である少子高齢化に伴う労働力不足が現実問題となりつつあり、社会保障制度・医療保険制度の持続可能性も懸念される状況です。
しかしこれらはほんの一端に過ぎません。企業経営者や政策立案者が直面する課題は、多様化し、それぞれが複雑化し、各課題の複合化も進んでいます。そして、戦略や計画を実証・実行・実装する実現フェーズも格段に難しくなってきています。
このような状況下で、民間企業や官公庁が取り組まなければならない課題の難易度は高まる一方です。私たちは、同業他社にはない強みを活かし、多様化・複雑化・複合化が進む企業経営者や政策立案者の意思決定や課題解決を、しっかりと支援できる存在でありたいと考えています。
また、幅広い先進的な専門知見を起点に、想定される日本の社会や産業の課題を導き出し、あるべき姿を構想し、グループの仲間とともに、官公庁や民間企業を巻き込み、プロアクティブに社会課題解決にアプローチする、そんなコンサルティング本部をめざしたいと考えています。
そのためには、各コンサルタントが、時代の先を読み、社会的インパクトが大きいテーマを見定め、深く掘り下げ、お客さまに仮説や解決策を提案できる存在でなければなりません。互いを認め合い、鍛え合い、組織知を高め、先輩たちが積み上げてきた知見に新しい知見を積み重ねていくことができる組織となることが必要です。コンサルティング本部では、2022年度から、テーマごとに成長戦略を策定し、将来を見据えた知見の蓄積と競争力強化に取り組んでいるところです。
複合化が進む課題については、コンサルティング本部のカバレッジの広さやRCUに属するという強みを発揮することで幅広く対応できると考えています。強みを発揮するためには、お客さまのニーズに合わせて、コンサルティング本部内のさまざまなコンサルタントと、RCUの多様な専門家が縦横無尽に連携する必要があります。
現在でも、エネルギー業界の大手企業の脱炭素移行計画策定ニーズに対し、戦略コンサルティング領域のコンサルタントと、サステナビリティを専門とするコンサルタント、エネルギー業界を担当する産業調査部の専門家がチームアップしてプロジェクトに臨むなど、すでに密接なつながりがありますが、よりスムーズに、より多様な課題に対応できるようなることを企図した施策「戦略知見×専門知見」「専門知見×専門知見」にも取り組んでいます。
社会・経営課題解決は、単に政策や戦略、計画を立案しただけでは実現しません。私たちは、その一歩先、いかに、ヒト・モノ・カネを調達・活用し、実証、実行、社会実装にスムーズにつなげていくかが重要になると見ており、今後は、実現フェーズまで視野に入れた課題解決支援が競争力の源泉になると考えています。
コンサルティング本部は、みずほグループのファイナンスをはじめとするさまざまな機能やネットワークと連携することで、お客さまとともに、実現フェーズまで見据えた課題解決支援に挑戦することができます。1つのプロジェクトで終わる必要はなく、複数のプロジェクトや複数年にわたる取り組みとなることもあります。官公庁との調査・研究フェーズから始まることもあります。場合によっては、コンサルティング本部が関わるのは最初の1ステップだけかも知れません。私たちは、みずほグループ全体で力を合わせ、お客さまとともに課題解決の実現まで想定しプロジェクトに打ち込む、そのようなコンサルティング本部をめざしています。
言い換えれば、私たちがめざすコンサルティングは、従来のコンサルティングでは終わらない、お客さまやグループ内外のさまざまな仲間と縦横無尽に連携し共創を進める「新しいコンサルティング」です。まさに、みずほグループの新しいパーパス「ともに挑む。ともに実る。」を体現するような取り組みだと考えています。
そして、この新しいコンサルティングへの挑戦を「グループ共創」と呼び、その強化を企図し、SX/DX共創戦略を牽引する新しい組織の設置などの体制整備、インセンティブ体系の整備、人事交流および、啓蒙活動などに取り組んできました。現在の中期経営計画においても、重点戦略の1つとして位置づけ、さまざまなハードルを一つひとつ乗り越えているところです。
(関連記事)
──グループ共創について、もう少し詳しく教えてください。
グループ共創は、端的に言えば、お客さまやグループの仲間とともに社会・経営課題解決に取り組むコンサルティング、となりますが、みずほグループへの直接的なソリューション提供や、みずほグループのブランド力を大きく引き上げるような取り組みも含みます。その中から、サステナブルファイナンス関連の取り組みと、実現フェーズまで見据えたコンサルティングについてお話しします。
コンサルティング本部では、お客さまのサステナビリティ対応を後押しすべく、みずほグループのサステナブルファイナンスの開発を支援してきました。2019年のMizuho Eco Financeを皮切りに、2021年にMizuho ポジティブ・インパクトファイナンス、2023年にはみずほ人的資本経営インパクトファイナンスの評価方法を開発・ローンチしました。
これらの組成額は、右肩上がりで増加しており、2022年度には1兆円超を記録しています。専門知見を詰め込んだ評価方法も、発行体から高く評価いただいています。
(関連記事)
- 多様な人材の活躍で、持続可能な組織へ。「インパクトファイナンス」で目指す、人的資本経営の未来。(株式会社IHI/SXサイト)
実現フェーズまで見据えたコンサルティングは、戦略や計画、アイデアなどを纏めた綺麗な紙を作って終わり、ではなく、みずほグループの仲間と連携しお客さまとともに実現フェーズまで共創することを狙うコンサルティングです。
類型化すると、経営・事業戦略関連、新規事業関連および、地域社会・インフラ関連となりますが、いずれにおいても、サステナビリティやデジタルイノベーションなどの知見も求められるケースが増えてきています。
最近の代表的な事例を採り上げると、経営・事業戦略関連では、事業再編・転換につながるような経営・組織戦略策定支援や経営戦略のサステナビリティ対応支援、カーボンニュートラル戦略策定支援などがあります。新規事業関連では、大規模な設備・不動産投資やアライアンスの構築などが必要となる、洋上風力発電の実現支援、CCUSなどの実証事業支援、SAFや水素などの次世代燃料の事業化検討支援、サブスクリプション・ビジネスの導入支援および、さまざまな先端技術やデジタルイノベーションを活用する新規事業開発支援などがあります。
地域社会・インフラ関連では、空港や鉄道、スタジアムなどの大規模社会インフラの整備、MaaSなどの先端技術を活用する地域社会のスマート化の支援などをあげることができます。その他も含め、ワクワクするプロジェクトばかりです。
(関連記事)
- 都市の移動をデザインする(Osaka Metro Group/MIZUHO次世代金融推進プロジェクト)
- 注目されているクルマの自動運転の実現に向けて、〈みずほ〉が議論を深め、前に進める(経産省・国交省など/DXサイト)
- DXで日本の企業を元気にして、社会課題を解決するため、技術と経営に強い〈みずほ〉のコンサルタントにできること(DXサイト)
- デジタルで、離島の可能性をカタチに。(八丈町/みずほフィナンシャルグループ採用情報サイト)
- 地域での水素社会実現へ。お客さまと〈みずほ〉の知見を結集し、次世代ビジネスを切り開く。(JX石油開発株式会社 電源開発株式会社 /SXサイト)
- 衛星データと現地調査を掛け合わせたサービスで、企業のネイチャーポジティブなビジネス実現をサポート(国際航業株式会社/SX サイト)
- 国内最大規模の「バーチャルPPA」で、前例なき再生可能エネルギー調達に挑む(花王株式会社/SXサイト)
グループ共創コンサルティングは、ここ数年順調に拡大しており、創出している社会的な付加価値は従来のコンサルティングの範疇を大きく超えています。困難も多いですが、コンサルティング本部の強みが発揮され成果となりつつあり、私たちは正しい方向に進んでいると確信しています。

多様な人材が活躍できる魅力的な職場に
──そのほかに力を入れていることはありますか。
持続的に力を発揮できる組織をつくるためには、安定した採用と多様な人材が活躍できる魅力的な職場であることが大切です。その実現に向けて、処遇の改善、新卒・キャリア採用の強化、多様な働き方ができる制度の構築、人材育成プログラムの強化、互いを認め合い組織知を高め合うカルチャーの醸成、異業種交流ならぬ異「専門」交流、みずほグループの幅広いビジネスフィールドを活かしたキャリア機会の提供および、職場環境の整備など、多くの改善施策に取り組んでいます。
組織改善は、定性的な議論やロジックに終始し、実際には効果が確認できない施策を乱立しがちな領域です。私たちは、その罠を避けるべく2022年に最先端ツールを導入することでエンゲージメント状況を可視化し、タイムリーに改善施策に反映する定量的なアプローチを取り入れています。これらの一連の取り組みによって、コンサルティング本部の自発的貢献意欲状況は同業他社を上回る水準にまで改善し、退職率も大きく低下してきています。まだまだ改善すべき点は多く残っていますが、魅力的な職場に一歩ずつ近づいていると感じています。
最後になりますが、ブランド力の向上も大事な取り組みの1つであると考えています。このインタビューもその一環ですが、興味深いプロジェクトやテーマ、コンサルタントの活躍、専門知見に基づいたレポートやコラムなどを積極的に対外発信し、もっと多くの人に、コンサルティング本部の魅力を知ってもらいたいと考えています。今回リニューアルしたコンサルティング本部の特設サイトは、デザインや回遊性、検索性が大幅に改善しましたが、これは第一段階であり、今後は、この特設サイトと外部媒体を組み合わせ効果的なプロモーションを打っていきます。
※ 記載内容は2024年1月時点のものです
(CONTACT)

お問い合わせ
お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。
サービスに関するお問い合わせはこちら
メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。
mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp
その他のお問い合わせはこちら
mhricon-info@mizuho-rt.co.jp