社会政策コンサルティング部 片岡 千鶴
社会的背景
日本では、少子化や急速な高齢化と共に人口減少が進み、都市部への人口集中や核家族化、単身世帯の増加、個人主義の傾向の強まり等の影響もあいまって、世代間の交流や地域のつながりが希薄となっている。その結果、都市部や地方部を問わず多くの地域で、身近な地域課題への対応力が低下している。このような「課題先進国」日本におけるサステナブルな地域社会づくりに向けて、公助から共助へと向かう流れは年々勢いを増している。
政策的には、今年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2019(骨太の方針)」において「共助・共生社会づくり」が取り挙げられたところである。また、厚生労働省が中心となって進められている「地域共生社会」の取組みにおいても、今年7月に公表された「地域共生社会推進検討会中間とりまとめ」*1の中で、福祉の観点を中心にしつつも、福祉サイドとまちづくり・地方創生サイド両方向からのアプローチによる、多様な主体による地域活動の展開が期待されている。さらに、今年11月に公表された「SDGs実施指針改定案(骨子)」*2では、主なステークホルダーのひとつとして、「新しい公共」(地域の住民が共助の精神で参加する公共的な活動を担う民間主体)が挙げられ、「各地域に山積する課題の解決に向けて、自立と共生を基本とする人間らしい社会を築き,地域の絆を再生し、SDGsへ貢献していくこと」が期待されている。
一方で、民間・地域社会の動向としては、「シェアリングシティ」の取組みが挙げられる。シェアリングサービスと自治体が連携して、さまざまな生活課題を「公共サービスだけに頼らず、市民ひとりひとりが「シェア」しあうことで解決し、自治体の負担を削減しながら、サステナブルで暮らしやすい街づくりを実現する」ことを目的としており、まさに「公助から共助へ」がスローガンとして掲げられている取組みである*3。
個人(地域住民)の意識
こうした中、主要ステークホルダーである一般の地域住民は、地域での共助・助け合いにどのような意識を持っているのだろうか。
当社が2017年12月に実施したアンケート調査*4によると、地域に住む家族・友人以外の方に対して何らかの手助け(買い物の代行や付き添い、車での送迎、パソコンやスマートフォン等の使い方を教えるなど20項目で質問)を行ったことがある人は、約半数(49.6%)であった。一方、「できる手助け」については、86.1%の方が1つ以上の項目を回答している。
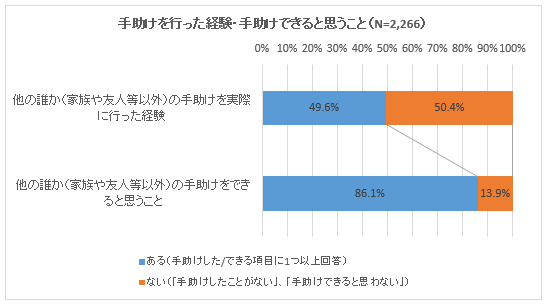
また、「今後はこれまで以上に『他の誰か(家族や友人等以外)の手助けをしたい』」と回答した方が56.6%であり、思いのほど手助けができていない理由については、「きっかけがなかったから」が最も多く(51.7%)、次いで「時間がなかったから」(29.3%)、「実際に誰がどこで困っているかわからなかったから」(27.4%)、「普段あまり気にしていなかったから」(24.0%)が多くなっていた(複数回答)。
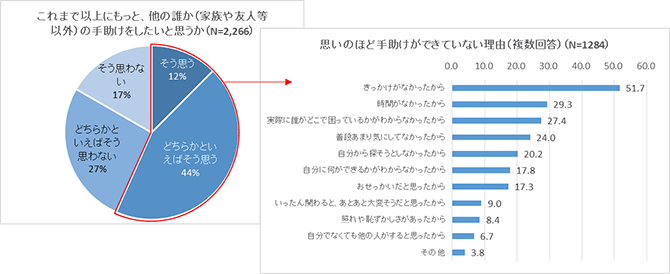
地域での助け合いにおける課題とデジタルソリューションへの期待
これらの結果からは、「もっと手助けしたい」「手助けできることがある」と思っている人は多いものの、必ずしもその思いが実際の行動につながっていないことがうかがえる。普段の生活の中で「身近に困っている人がいることを意識することも少なく」、意識したとしても「誰がどこで困っているのかわからず」、できることがあったとしても「手助けするきっかけもない」まま過ごしている場合も多いのが現状と考えらえる。
地域での共助・助け合いが求められるなか、このような状況を変えるためには、[1] 地域の人の困りごとや助け合いの存在に気づきやすくし、[2] 手助けを必要としている人がどこにいるのか、具体的にどのような手助けが求められているのかを可視化し、[3] 手助けしてあげられる人が自分のタイミングで手助けに踏み出せるようなきっかけを提供する、ことがカギになるのではないだろうか。
ここで期待したいのが、「可視性」「リアルタイム性」「手軽さ」という点で特に力を発揮しやすいデジタルソリューションの活用である。
ソリューションのひとつとしてのSmiile
ソリューションのひとつとして当社が注目しているのが、フランスで50万以上のユーザーを獲得している「Smiile(スマイル)」*5というご近所シェアサービスである。Smiileでは、小・中学校区程度のエリア内で他ユーザーと情報の共有や知識・スキルの提供、助け合い、モノの貸し借りなどのちょっとした「ご近所シェア」をスマートフォンやパソコンで簡単かつリアルタイムに行うことができる。
手助けを必要としている人がリアルタイムで周囲に「リクエスト」を発信することで、そのとき都合のつく「ご近所さん」が有償/無償で助けてあげたり、その反対に、「自分の得意なこと・できること・提供できるモノや空間」を発信することで、興味のある「ご近所さん」が必要なときにその人に問い合わせたりすることができる仕組みである。また、個人だけでなく、地域のお店や地域活動グループ、行政も参加することができ、ローカルエリア内に特化した情報発信が可能となっている。
実際にフランスでは、日常的に、地元のお店やグループによるイベント情報の共有、近所どうしだからできるちょっとした手助け(相乗り、子どもの送迎、外出時のペットシッター、家具の組み立てなど)やモノ・空間のシェア(子ども用品のおさがり、レジャー用品のシェア、空き部屋のシェアなど)が行われている。また、防災・防犯情報などがリアルタイムでシェアされていたり、レスキューなどの有資格者がその情報を登録・公開している場合もあるなど、災害時等に活用可能な使い方も見受けられる。
共助・手助けの行動促進とデジタルソリューション活用への期待(イメージ)
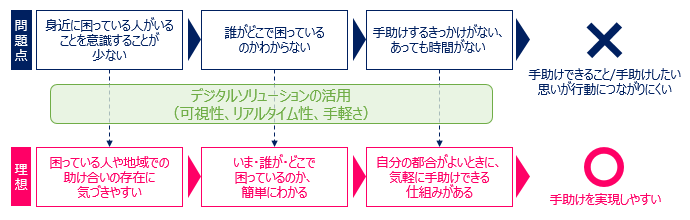
日本展開に向けた実証事業
当社では、Smiileサービスの日本展開に向けた実証事業を予定しており*6、日本の課題や社会・文化にマッチしたローカライゼーションを施して、日本ならではの「ご近所シェア」に貢献することを目指している。
地域での助け合いに、対面コミュニケーションは必須である。しかし、自分の住む地域で「助け合い」が行われていることに気づき、助けを求めている人・助けてあげられる人の双方が気軽に声をあげ、お互いの存在に気づいてちょっとした日常の助け合いに踏み出すには、入り口としてデジタルの果たす役割も大きいのではないだろうか。
ICTの浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させるデジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation)が進みつつある現在、地域の共助という面においても、デジタル活用していくことで、より助け合いの輪が広がるような変革をもたらすことができる可能性があるだろう。
- *1)「地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会(地域共生社会推進検討会) 中間とりまとめ」(令和元年7月19日)
- *2)「持続可能な開発目標(SDGs)実施指針(改定版)」(令和元年11月8日SDGs推進本部幹事会決定)
- *3)
- *4)WEBモニターアンケートによる。調査期間:2017/12/15(金)~2017/12/18(月)、調査対象:首都圏(埼玉、千葉、東京、神奈川の1都3県)在住の25歳以上の男女2,220人を対象に実施(性・年代別(25-34歳/35-44歳/45-54歳/55-64歳/65-74歳/75歳以上)にほぼ同数のサンプルを割当。学生除く)。
- *5)
- *6)
2019年12月5日ニュースリリース
地域コミュニティの助け合いを支援するご近所シェアサービス「Smiile」の展開に向けて協業を開始