社会政策コンサルティング部 田中 陽香
高齢者の健康課題としての「フレイル」
高齢化の進展が著しい我が国では、健康寿命の延伸が至上命題であり、高齢者が長期間にわたり自立した生活を送り続けるよう、健康と要介護状態との中間的にあるフレイルと呼ばれる状態への対応が注目されている。
フレイルとは「加齢に伴う予備能力低下のため、ストレスに対する回復力が低下した状態」を指し、身体的問題、精神・心理的問題、社会的問題など多面的な問題を抱えやすく、放置すると容易に介護が必要な状態に至ると考えられている。ただし、フレイルは進行するだけではなく、運動や食生活、社会参加等の適切な対応をとると回復できるとも考えられている。そのため国は、社会保障費抑制の突破口としてフレイル対策を重要視している。
図 フレイルの概念図
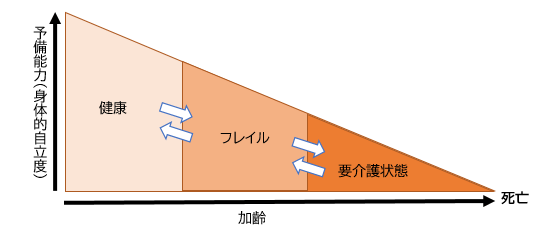
出典:葛谷雅文「老年医学におけるSarcopenia&Frailtyの重要性」(日本老年医学会雑誌2009;46:P.281)に基づき作成
市町村によるフレイル対策の目玉としての「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」
令和元年5月に国が策定した健康寿命延伸プランでは、「『通いの場』のさらなる拡充」と並び「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」(以下「一体的実施」という)が介護予防・フレイル対策の主要事項として掲げられた。
高齢者を対象とした保健事業(健康づくり事業)や介護予防事業は、市町村で実施されている。「一体的」という言葉が用いられたのは、同じ市町村の中でも国民健康保険や後期高齢者医療制度という医療保険を財源とした保健事業と介護保険を財源とした介護予防事業が別々に運営され、類似事業が併存していることが多いからである。国はそうした縦割り状態に一石を投じるため、医療専門職を中心に複数部署が連携し、高齢者が抱える健康課題を十分に分析・把握したうえで以下のような取組を実施する市町村に対し、特別調整交付金による財政的支援を行うことにした。
- 栄養状態、口腔機能、運動機能等が低下するリスク、重複頻回受診・重複投薬等や糖尿病をはじめとした疾患の重症化リスクを抱える人への個別支援によるハイリスクアプローチ
- 通いの場等高齢者が集う場に医療専門職が出向き、フレイル予防等に資する情報提供を行うポピュレーションアプローチ
- 医療機関の利用がなく健康診査も受診していないため、健康状態が分からない人の状態把握
一体的実施スタート年におけるコロナの影響
令和2年2月に国が実施した調査*1によると、令和2年度から一体的実施に係る特別調整交付金の申請を予定する市町村は、全国の2割、400弱であった。これらの市町村は令和2年度前半に事業企画し、後半に事業に取り組む予定であったと考えられるが、コロナの影響を受けたことは否めないだろう。市町村は高齢者との接触を極力避けるために様々な事業の実施を控える傾向にあった。
国や学会、研究機関等は、外出自粛等によるフレイルの進行を危惧し、高齢者や彼らを支える市町村に対して様々な情報発信をしてきた。国は例えば、外出自粛期間中の対面によらない高齢者との連絡の取り方等の事例や、通いの場等高齢者との接触を伴う事業を再開する際の感染予防策を紹介してきた。学会や研究機関も、高齢者が自宅でも気軽に実践できる運動等を文書や映像で紹介していた。
全国の市町村は、これらの情報も参考に様々な対応をとっていた。緊急事態宣言解除後には、感染予防策を講じながら通いの場の活動やハイリスクアプローチ等の事業を徐々に開始もしくは再開しつつある。実際に活動を再開した市町村は、3密を避けるため高齢者が集う場合は広い空間のある場所に会場を変更したり、グループを複数に分けて活動時間をずらす等の工夫をしていた。
表 コロナに対応したフレイル対策に関する各種情報
| 作成者 | タイトル |
|---|---|
|
厚生労働省 |
|
|
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター・金城大学 |
|
|
東京都健康長寿医療センター研究所 |
|
|
公益社団法人地域医療振興協会 ヘルスプロモーション研究センター |
コロナに負けない!高齢者向けチェックリスト |
各種資料よりみずほ情報総研作成
withコロナ時代の市町村によるフレイル対策を進めるために
これからのフレイル対策では、ソーシャルディスタンスの確保や人と人との接触機会を減らすことが求められる。しかしフレイルは身体的機能だけではなく、社会的・精神的要因の影響も受けるため、人と人との交流は非常に重要である。外出自粛期間中に希薄であった人との触れ合いを求めてか、通いの場の活動が再開されると参加者数が増えたり、休止していた通いの場の活動が復活したところもあった。
接触機会を減らしながらも人との交流を確保するには、様々な職種の人によるアイデアが求められる。オンラインでの個別面談やフォロー等ICTの活用を含め、これまで想定していなかった新たな実践方法が生まれ事業内容がより充実していく可能性もあるだろう。
地域で暮らす高齢者を支えるには、コロナ対応も含め皆が知恵を出し合うことが求められる。住民に最も身近な市町村には、一体的実施をきっかけに、全庁一丸となったフレイル対策の推進に期待したい。
- *1)https://www.mhlw.go.jp/content/000653423.pdf
(PDF/1,910KB)