社会政策コンサルティング部 チーフコンサルタント 森安亮介
行政の諸現場で新たなキーワードが注目されている。「エビデンスに基づく政策立案」 (Evidence Based Policy Making。以下EBPMという)である。2015年頃からの導入検討段階を経て、2018年度以降、各府省等の実行段階に移っている。2020年11月現在、1府11省及び各庁・院・委員会に専門組織ないし担当者が置かれ、EBPMが推進されている。
2018年度以降、各府省等でまず進められている取り組みの1つが、ロジックモデルによる政策立案の点検・見直しである。ここでいうロジックモデルとは、政策遂行によって政策課題が解決されるまでの論理的な道筋を示したモデル図を指す。具体的には、現状分析により政策課題を定義した上で(現状・課題)、人員・予算をどれぐらい投入し(インプット)、何を実施し(アクティビティ)、どのような実績を出すか(アウトプット)。そうした実績を通して、どのような成果(アウトカム)や影響(インパクト)を及ぼす見込みか、といった流れを明示的に示すものである。
ロジックモデルのイメージ
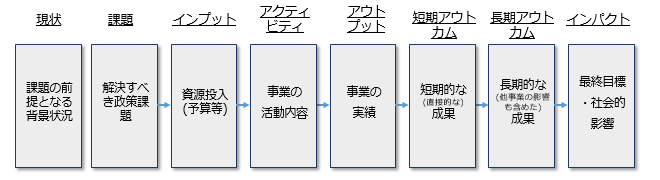
2019年度に各府省等で作成されたロジックモデルの一部は首相官邸HP内でも公表されており、1府10省及び9つの庁・院・委員会で合計25事業のロジックモデルが掲載されている*1。2020年度は更なる実践に向けた一環として、[1] 新規予算要求事業(10億円以上)及び公開プロセス対象事業について原則ロジックモデルを作成・公表すること*2、[2] 省内の予算プロセスにおいてロジックモデルを活用すること等が推進されている*3。
では、なぜEBPMの推進にこうしたロジックモデルが求められるのであろうか。実はロジックモデル作成を通し政策立案の論理を精査することは、2つの点で重要な意味を持つ。
第1に、政策遂行の仮説が明示的に示される点である。政策が対応すべき社会問題は、往々にして様々な要因が複雑に絡まって問題化しているケースが多い。そのような問題の解消のためにどの課題に特化して政策的対応を取ろうとしているのか?また、複数考えられる政策手段の中でなぜその手段を選択したのか?といった政策課題・手段の仮説がロジックモデルによってまず明らかになる。さらに「アクティビティ→アウトプット→アウトカム→インパクト」のように、因果関係という形で、政策遂行による効果や影響が明示化されることもロジックモデルの重要な役割である*4。筆者のレポート*5でも述べたように、エビデンスとは因果関係を示すものである。エビデンスを用いて政策効果を事後検証する際、因果関係の仮説が予め提示されていることで、一体どのプロセスで事前想定と齟齬があったのかが検証でき、政策の改善につなげることが出来るようになる。
第2に、因果関係の仮説が事前に明確に示されることによって、政策効果検証に向けた事前設計(リサーチデザイン)が初めて可能になる点である。前述のレポートでも一部紹介したように、政策効果の検証には政策実施対象層と比較するための非対象層(政策非実施対象層)を必要とする。このような比較対象が予め設定・想定されずに政策が遂行されてしまうと、事後的な検証はどうしても質の低いものになってしまう。政策遂行前の段階で、想定している因果関係が明らかになることによって、事後的な効果検証に向けたデータの取得方法や比較対象の設定について点検・議論できるようになる。筆者も2019年より厚生労働省に毎週常駐し、これまで60事業以上のロジックモデル作成・点検支援や事業効果分析支援を行ってきた。その際、事業効果の分析に向けた指標や変数の選択において、ロジックモデルが非常に有益なコミュニケーションツールとなっている。もしこのようなツールが無ければ、検証に向けた設計(リサーチデザイン)は五里霧中の作業になっていたであろう。
以上のように、エビデンスを参考に政策を立案し、事後的な検証で政策の改善を図る上で、ロジックモデルは重要な役割を果たすものである。一見遠回りのようで、行政のEBPM浸透に向けた土台作りが今まさに進められている。
- *1)第5回EBPM推進委員会 参考資料1「各府省の取組において作成されたロジックモデルの例(令和元年度)」(2020年5月20日)
(PDF/3,330KB) - *2) 公開プロセスとは、各府省が実施する自己点検のうち、「外部の視点」を活用して「公開の場」で行うものである。詳細は以下ページで紹介されている。
- *3)第5回EBPM推進委員会 資料2「令和2年度におけるEBPMの取組について」(2020年5月20日)
(PDF/305KB) - *4)尚、「アウトカム」は政策による直接的な成果と間接的な成果に分けて記載することが一般的であり、通常「短期アウトカム / 長期アウトカム」や「中間アウトカム / 最終アウトカム」のように複数段階に分けて記載される。このように分けることで、政策遂行による直接的な因果効果の仮説がより明確になる。
- *5) みずほ情報総研レポート『行政への浸透に向けた EBPMの課題とその一方策 ―EBPM を契機とした行政・研究の連携を―』(2019年12月)
関連情報
この執筆者はこちらも執筆しています
-
2019年12月
―EBPMを契機とした行政・研究の連携を―