みずほ情報総研 経営・ITコンサルティング部 シニアコンサルタント 剣持 真
- *本稿は、『宣伝会議』 2020年7月号(発行:株式会社宣伝会議)に掲載されたものを、同編集部の承諾のもと掲載しております。
エンゲージメントが価値を生む顧客ロイヤルティを見極める
ロイヤルティが高まると、顧客は企業にとって有益な行動をとるように、つまり「エンゲージメント価値」を生みだすようになるため、企業は顧客ロイヤルティがどのようなもので、いかにして顧客ロイヤルティが高まるのかを知っておく必要があります。
顧客ロイヤルティは、論理的、感情的にその製品やサービスが良いと思うことを示す「態度的ロイヤルティ」と、製品やサービスを繰り返し購買することを示す「行動的ロイヤルティ」に分類されます。
Dick & Basu (1994)*1は、この2つのロイヤルティの高低の組み合わせによって「ロイヤルティなし」「潜在的ロイヤルティ」「見せかけのロイヤルティ」「真のロイヤルティ」と4分類する考え方を示しました(図表1参照)。この考え方では「見せかけのロイヤルティ」が特徴的です。これは態度的ロイヤルティが低いのに、行動的ロイヤルティが高いという状態を指します。
例えば、会社に行く前にコーヒーを買う人が、通勤途中にあるという理由だけで、特に好きでもない(=態度的ロイヤルティが低い)ショップで、ほぼ毎日購買している(=行動的ロイヤルティが高い)状態がこれにあたります。これは見せかけのロイヤルティといえます。
図表1 顧客ロイヤルティの4分類
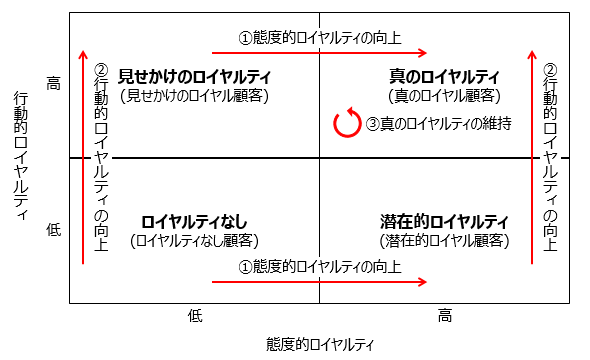
出所:Dick & Basu(1997)をもとにみずほ情報総研作成
真のロイヤル顧客がもたらすエンゲージメント行動価値
かつて、ある小売業の方から「見せかけのロイヤルティも真のロイヤルティも、行動的ロイヤルティが同じならば、売上は同じということ。売上が同じなら別に好かれていなくても良い」とのご意見を伺ったことがあります。短期的な売上高のみの視点で考えると、この意見には一理ありますが、これは経営環境が全く変わらないという前提の下でしか成立しない話です。
新型コロナ関連の出来事は、私たちの購買行動を大きく変えました。外出を控えつつ、必要なものを得るには、宅配が非常に便利です。物流の課題を抱えていますが、宅配は今後ますます増えていくことでしょう。店頭での購買を考える上では、立地が極めて重要な要素であり、消費者はその店があまり好きでなくても、立地が良ければ買うこともあったと思います。
これが今回の環境変化により、消費者は立地にとらわれず、宅配している企業を自由に選んで買い物ができるようになりました。「どうせ買うなら大好きなあの店で…」となり、特に好きでもない立地だけが魅力の店を、宅配の店の選択肢として挙げないであろうことは容易に想像できます。企業は見せかけのロイヤル顧客でなく、真のロイヤル顧客を増やすことにより、経営環境に左右されにくい「安定的・持続的な売上高」という価値を得られることがわかります。
真のロイヤル顧客は以下に示すような、エンゲージメント行動価値を企業にもたらします。
- 安定的・持続的な売上高
- 口コミを通じた製品・サービスのプロモーション
- 新規顧客の紹介とサポート
- 競合企業の情報提供
- 製品・サービスの改善案提案と新製品・新サービス開発支援
真のロイヤル顧客を育むための3つのステップ
好ましいエンゲージメント価値を得るために、企業は(1)態度的ロイヤルティの向上と、(2)行動的ロイヤルティの向上とともに、(3)真のロイヤルティを維持するマーケティングを行い、真のロイヤル顧客を増やしていく必要があります(図表1参照)。
態度的ロイヤルティの向上
剣持 (2017)*2では、態度的ロイヤルティに影響を及ぼす要素として「顧客満足」「自己・ブランド連結性」「顕現性」の3つを挙げました。ここでは顧客満足(CS)に着目し、態度的ロイヤルティを高めるために改善すべき満足度要素を明らかにするCSマトリクス分析をスーパーの事例をもとに紹介します。
CSを重要な経営指標として捉えている企業も多いので、CS調査により顧客満足度を把握しているという企業も多いことでしょう。ここで、図表2をご覧ください。左側の図は、CS調査結果の典型的なグラフを示したものです。これを見ると、満足度平均点の低い「粗品等のプレゼントサービス」「欠品の少なさ」を改善すべき要素と考えるかもしれません。
しかし、CSマトリクス分析による解釈は異なります。図表2内、右側の図のように、満足度の高さを縦軸に、態度的ロイヤルティへの影響度の高さ*3を横軸にして表すと、「粗品等のプレゼントサービス」「欠品の少なさ」は、態度的ロイヤルティへの影響度が有意でない(=あまり影響を与えない)ことがわかります。一方で満足度が低く、態度的ロイヤルティへの影響度が有意な(=強い影響を与える)「品質の高さ」「店員の対応」「店内の雰囲気」は、この要素の満足度を高めることで態度的ロイヤルティも高めることができるため、優先的に改善していくべき要素であることがわかります。このように、CSマトリクス分析を活用すると、態度的ロイヤルティを高めるために優先的に改善すべき満足度要素がわかります。
図表2 典型的なCS調査のグラフとCSマトリクス分析の比較
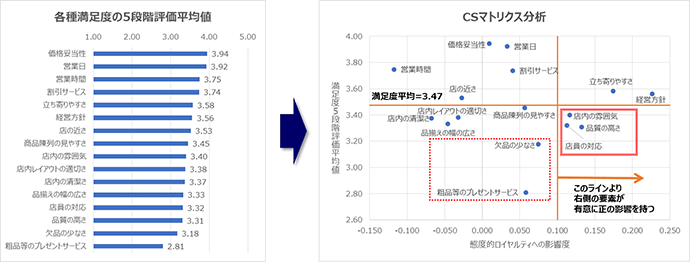
顧客満足度だけでなく、態度的ロイヤルティへの影響度を加えた二次元で見ることによって、優先的に改善すべき課題を発見できる。
行動的ロイヤルティの向上
剣持 (2017)では、行動的ロイヤルティに影響を与える要素として、「顧客満足」「バラエティ・シーキング」「習慣的行動」「立地利便性」を挙げました。ここでは習慣的行動に着目し、行動的ロイヤルティ向上に成功した事例をご紹介します。
近年、LINE Pay、au PAY、J-Coin Payなど、様々なキャッシュレス決済サービスが登場しています。これらの利用を促進するには値引が有力な手段であるため、各社様々な販売促進を行っていますが、多少の値引では習慣になるほどの購買を促せないため、一筋縄ではいかない側面があります。
その点、PayPayが実施した「100億円あげちゃうキャンペーン」は、インパクトのある大型値引で参考になります。この販売促進が優れていたのは、100億円を使い切ると終了してしまう点。顧客はより多くの値引を得るために、短期間に繰り返しPayPayを利用します。PayPay払いに慣れてもらうことで、この行動が習慣化されたのです。行動的ロイヤルティを向上させた好事例と言えるでしょう。
真のロイヤルティの維持
真のロイヤル顧客を増やしても、それを維持できなければ、いずれ減少してしまいます。企業は真のロイヤル顧客から意見を聞く場を用意するなど、ロイヤルティを維持するためのマーケティング施策を行う必要があるのです。例えばビールは嗜好性が高い製品であるため、真のロイヤル顧客も多く、アサヒ、キリン、サッポロ、サントリーなどのビールメーカーでは、SNSなどを通じてブランド・コミュニティの場を提供し、ロイヤルティの維持を図っています。ここでは、バーチャルとリアルの双方の場を有効活用している、クラフトビールメーカー・ヤッホーブルーイングの事例をご紹介します。
ヤッホーブルーイングのブランド・コミュニティ最大の特徴は「超宴」というリアルで大規模な飲み会イベントの場です。社員もイベントに参加し、顧客と楽しい場を共有するとともに、顧客から意見収集も行っているようです。イベント情報や製品情報は会員制公式ウェブサイト「よなよなの里」や各種SNSなどのバーチャルの場で発信・共有されるため、顧客はリアルとバーチャル、双方の場で同社のビールを楽しみ、ロイヤルティを深めています。一方の企業側も、この場を通じて真のロイヤル顧客から収集した意見を経営改善に活用するという好循環をつくり上げており、真のロイヤル顧客を維持している好事例と言えます。
経営環境が激変する現在、これまで以上に真のロイヤル顧客の価値が高まっています。見せかけのロイヤル顧客に惑わされず、真のロイヤル顧客を育み、維持していくことが今後ますます重要なテーマになることでしょう
- *1)Dick, A. S. and K, Basu(1994),“Customer Loyalty Toward an Integrated Conceptual
Framework,” Journal of the Academy of Marketing Science, 22(2), 99-113. - *2)剣持真 (2017)「顧客ロイヤルティの先行要因・結果行動」『みずほ情報総研レポート』, 14,50-68.
- *3)態度的ロイヤルティを目的変数、各種満足度を説明変数として重回帰分析にて算出した標準化偏回帰係数。