みずほ情報総研 環境エネルギー第2部 柴田 昌彦
- *本稿は、『環境管理』 2019年3月号 Vol.55 No.4(発行:一般社団法人産業環境管理協会)に掲載されたものを、同編集部の承諾のもと掲載しております。
シナリオ分析の重要性・有効性の「腹落ち」理解に向けて
2.1 「腹落ち」理解はなぜ重要か
TCFDシナリオ分析、すなわちTCFDが企業に実施を推奨するシナリオ分析は、将来の気候関連リスクのシナリオを踏まえて自社事業の今後を考えるプロセスである。そのため、サステナビリティ部門あるいは経営企画部門やIR部門に閉じた取組みでは終わらないことが多い。事業部門や開発部門、マーケティング部門の知見を何らかの方法で取り込むことが求められ、組織横断的な「TCFDシナリオ分析ワーキンググループ」が設立・運営されることになるケースも少なくない。こうした場合、「何を、どこまで検討するか」の設定が重要であり、不可欠であることはいうまでもない。
しかし、「何を、どこまで検討するか」の設定は簡単ではない。単に「権威ある国際組織であるTCFDがシナリオ分析を推奨するから」という理由でシナリオ分析に着手する場合、「何を、どこまで」の答えはTCFD文書に求められることになる。そして前章でみたとおり、TCFDはそのような答えを用意していないのだ。
ではどうすればよいか。
「何を、どこまで検討するか」の設定に必要なのは、「シナリオ分析はなぜ重要で、どう役立つのか」という根本的な理解、そしてその根本的な理解を自社に当てはめることで得られる「自社がシナリオ分析に取り組むのは、何を求めてのことなのか」という自社のためのシナリオ分析活用の視点である。この根本的な理解が、筆者のいう「腹落ち」理解である。
2.2 ロイヤル・ダッチ・シェル社に学ぶ
「シナリオ分析はなぜ重要で、どう役立つのか」との問いには、「この手法はそもそもなぜ生まれたのか」との問いがヒントを与えてくれる。
シナリオ分析がロイヤル・ダッチ・シェル社によって開発された手法であることはよく知られている。TCFDも、『技術的補足』において「ビジネス文脈におけるシナリオ分析は、もともとはRoyal Dutch Shellによって構築された。シェル社は1970年代初めから、戦略的選択肢を創生し評価するプロセスの一環としてシナリオを使用してきた。それ以来、その他多くの企業がシナリオ分析に取組み、便益を得ている」と述べている。そして、「しかし、企業が気候関連事項にシナリオ分析を適用することは、比較的新しい現象である」と続けている。
TCFDのこの記述は興味深い。TCFDは、ロイヤル・ダッチ・シェル社が1970年代から誰に求められるわけでもなく自主的にシナリオ分析に取組み便益を得ていることを認識した上で、今やこの手法がロイヤル・ダッチ・シェル社以外の企業が、気候変動によって事業が被る潜在的な影響を評する際に有用であると推奨しているのだ。言い換えれば、TCFDは、気候関連のリスクと機会が不確実性を伴いつつも予見されるようになった今日において、多くの企業が、以前からロイヤル・ダッチ・シェル社が置かれた状況と似た状況に置かれつつあると考えていることになろう。
ロイヤル・ダッチ・シェル社がシナリオ分析の開発と適応に着手した背景や狙いは、同社自身によって多くの発信が行われており、シナリオ分析の教科書とされる書物*3でも様々に語られている。同社がシナリオ分析によって第一次オイルショックの影響を最小限に抑えたことは、筆者はそれを語る立場にいないが、そもそも語る必要もないであろう。
参考となる資料は多様すぎるほどである同社のシナリオ分析であるが、そのエッセンスを要領よく学ぶのであれば、筆者は、経済産業省が2018年1月30日に開催した「エネルギー情勢懇談会」の第5回会合におけるロイヤル・ダッチ・シェル社のガイ・オーテン氏の資料*4を推奨したい。オーテン氏の資料の素晴らしさは、シナリオ分析の本質を突いた『Decision-making in theface of a radically uncertain future(根源的に不確実な将来に対する意思決定)』というタイトルに現れている。同資料は、エネルギー資源会社を巡る状況が根源的に不確実であるがゆえに、未来像を一つに絞って予測を行うことそのものがもはや妥当なアプローチではないことを視覚的に示している。同社が置かれた状況においてシナリオ分析の重要性と有効性は明らかであり、同社が、誰かに推奨されてではなく自主的に、そして必要に迫られてシナリオ手法に取組み続けていることがわかる。
では、シナリオ分析が重要・有効である同社が置かれた状況とは何か。筆者の文責の下で述べるならば、それは「根源的に不確実な将来に向けて、長期操業によってしか回収できない巨額な投資判断をしなければならない」という状況である。
資源開発を行うエネルギー資源会社は、一般的に地政学的リスクを抱える地域の現地政権と交渉し、莫大な資金を投じて採掘権を獲得し、採掘・精製設備を建設しなければならない状況に置かれている。長期に渡って操業を続けなければ回収できないような大規模な投資判断(換言すれば、長期に渡って未来を拘束する意思決定)を下さねばならないにもかかわらず、その事業環境の継続性は不確実性に満ちている。現地政権がある日革命で倒れる、あるいは隣国との戦争で同国が戦場となるような事態が生じれば、投資回収の前に操業を止めざるを得なくなる。また、長く操業を続ける間には、シェール革命のような技術革新が再び生じることも想定される。操業によって得られたガスやオイルが、当初想定価格より遥かに低い価格でしか取引されない未来が訪れれば、投資回収は困難となるのである。
このような状況で、未来像を一つに絞って予測し、その一つの未来に社運をかけた大規模投資を行おうとするのは、妥当な意思決定とはいえないであろう。複数の起こりえる未来像を想定し、どの未来が訪れても生き残れるように備えをしておくことは、むしろ不可欠なアプローチである。そのツールとしてシナリオ分析が必要とされ、有効性を発揮したのである。
2.3 逆説として:シナリオ分析が不要な状況
ロイヤル・ダッチ・シェル社からの学びを応用すれば、その逆説として、シナリオ分析が重要でなく、有効でない状況も想定することが可能となる。その一つの例が、
- [1]ほぼ確実な一つの未来像を想定することができる
- [2]どのような未来がきても事後対応で対処可能である
という状況である。
[1]は、説明は不要であろう。仮に中長期に渡って未来の自社を拘束するような意思決定をする必要があろうとも、未来に不確実性がないならば、意思決定に躊躇は不要だ。
[2]は、製造業を例に挙げれば、「調達品、調達先を変える」、「使用エネルギーを変える」、「製造方法を変える」、「製造設備を変える」、「製品設計・仕様を変える」等の対応が、未来像がほぼ確定してからでも事後対応で迅速に実現できる状況であろう。さらに、事後対応であっても、他社に対応速度や品質、コストでさほど劣後せず、しかも顧客の囲い込みにおいてもさほど不利とならない状況である。こうした状況であれば、事前に起こりうる複数の未来像を想定し備える、というシナリオ分析は不要である。事前の備えは自社に何ら優位性をもたらさず、事前の備えがなくとも不利とはならないからだ。
いうまでもなく、ロイヤル・ダッチ・シェル社には[1]も[2]も当てはまらない。それゆえに、シナリオ分析が重要であり有効だったのである。
では、気候リスク・機会への対応が迫られようとしている現代の他業種の企業にとっては、どうであろうか。
2.4 気候リスクの未来は確実か
まずいえるのは、気候関連のリスク・機会の世界では、確実な一つの未来像の想定は困難だということである。
よくいわれるように、気候変動の物理的影響は、それがいつ、どの地域で、どの程度の規模と頻度で発現するかを確定的に予測することができない。予期されたほどの物理的な影響が発生しないことや、想定を超えた影響が発生することも、どちらも想定される。
気候変動を防ぐための「移行」の取組みが、どの程度の規模とスピードで行われるかもまた不確実である。パリ協定の締結後、「2℃目標」は世界目標となったが、これによって脱炭素化の未来の到来が確定的になったわけではない。IEA等の国際機関が発表する2℃目標実現シナリオ*5をみれば、目標実現のために必要な社会変革がどれほどドラスティックであるかがわかる。気候変動の事業への影響に関するシナリオ分析の導入で先進事例とされるBHPビリトン社のシナリオ分析*6が、2℃目標実現シナリオをセントラルケースとしていないことも、目標実現の困難性を踏まえてのことであろう。その一方で、ESG投資の加速や、再エネ発電コストの低下、IoTやバッテリー技術の急激な進歩、そして先進国の技術覇権に挑む中国が先進国側のアドバンテージの少ないEVへのシフトを打ち出したこと等が、旧来の常識を越えた力学と速度で脱炭素への移行の圧力をもたらしていることも事実である。
すなわち現在は、
- 「技術的・コスト的に考えて2℃目標実現は現実的ではない。2℃シナリオが実現するような脱炭素社会への移行を、可能性の高い未来と捉えて意思決定を行うのは危険だ」
とする見解も、
- 「世界の潮流の変化は本物。2℃シナリオが実現するような脱炭素社会への移行下での自社のビジネスモデルが生き残れるかを真剣に検討すべき」
とする見解もどちらも成立し、どちらにも説得力もある時代なのだ。
読者は、どちらの見解に自社の運命を賭けるべきだと思われるだろうか。
筆者ならば、どちらか一方に賭けることはしない。なぜなら、どちらの未来も起こりえるからだ。こうした状況下では、未来像を一つに絞って予測を行うことそのものがもはや妥当なアプローチではないだろう。直面しているのは「根源的に不確実な未来」である。必要なのは、起こりうる複数の未来を想定し、どの未来になっても生き残れるよう備えを打つこと。そう、シナリオ分析だ。
読者がサステナビリティ部門の担当者で、TCFD提言対応を進める中で2℃目標実現シナリオの実現性について社内で意見が割れているならば、むしろ喜ぶべきかもしれない。まさにシナリオ分析が求められる状況であるからだ。
図2 気候リスクにおける「根源的に不確実な将来」
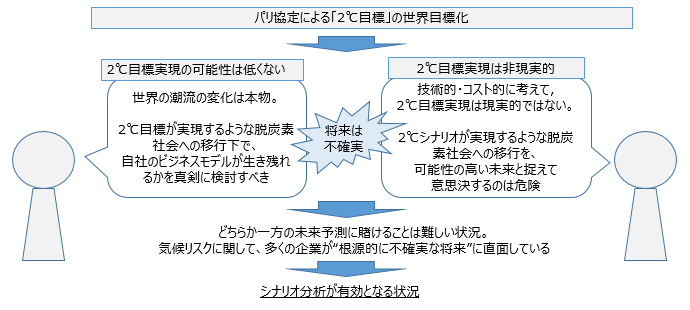
出所:みずほ情報総研
2.5 起こりうる気候リスクには事後対応で十分か
次に考えるのは、不確実でありながら起こりうる気候リスクに対して、事後対応が十分な対応となるか否かである。
これは、リスクが発現した際の総合的な状況に大きく依存する。
例えば、脱炭素社会に向けた移行がドラスティックに進み、予想以上のスピードで電動自動車(xEV*7)でなければ新車販売ができない世の中が到来したシナリオを考えよう。内燃機関車のみを製造・販売していた自動車メーカーは窮地に追い込まれることが予想される。
しかし、どこまで早期でドラスティックなxEV時代の到来を迎えても、そのスピードは、xEVの車両デザインや調達、製造、マーケティングのノウハウの大半を、先行する他社から容易に学び取るに十分なほど遅いかもしれない。あるいは、高性能化したバッテリーが一種の汎用品となってしまう未来がくるのであれば、後発組であっても競合に劣後することがない品質・価格・量の面での調達が実現するかもしれない。その場合、このメーカーは事後対応によってxEV時代にも十分対応が可能となる。むしろ、シナリオ分析によって早期のxEV時代の到来をシナリオの一つとして想定し、多くのコストを支払ってxEVの車両デザイン・部品調達・製造・マーケティングに取り組んでいた競合会社は、無駄なコストを支払うことになる。
他方、xEV時代が後発者の学びを振り切るスピードで到来し、車両デザイン・部品調達・製造・マーケティングが内燃機関車のそれと全く異なり、競争力のある品質・価格・量でのバッテリーを提供するサプライヤーが競合によって囲い込まれるような状況となっていたならば、事後対応による機会損失は膨大なものとなるだろう。
果たして、xEV時代の早期到来シナリオは事後対応で十分対処できるものなのか、あるいは事前の備えが必要なものなのか。これについては絶対的な解はなく、企業がそれぞれに考えていくしかない。
では、どう考えていけばよいのか。
ここで挙げた例の場合、それにはxEV時代の早期到来シナリオを想定し、その際のビジネス環境を考えていくことになる。事後対応でのキャッチアップを想定した際にそれを阻害する複数の条件は同時に現出するのか。自社の競争力の源泉は、新たな環境でも維持あるいは再構築できるのか。自社のコンピテンシーにはその力はあるのか……。お気づきの方も多いであろう。これこそシナリオ分析である。起こりうるが不確実な気候リスクに対して事後対応では不十分な可能性がみえているならば、シナリオ分析は柔軟で堅固な戦略を打ち立てるために重要であり、有効なプロセスとなるのだ。
このように考えていけば、気候リスク分野におけるシナリオ分析の重要性や有効性は、「TCFDが推奨しているから」ではなく、自社の事情を踏まえて「腹落ち」して理解することができるようになるだろう。むろん、そもそも気候リスクが自社にとって関わりが薄い場合もあれば、シナリオ分析は不要であろう。また、影響はあるが業界全体が等しく影響を受け、対策のしようがないという場合も、シナリオ分析の重要性・有効性は減じる。こうしたケースも含めて、まずは自身の言葉で「腹落ち」した理解を持つことをお勧めしたい。筆者の経験上、それがシナリオ分析検討の強固な基点となるためだ。