みずほ情報総研 環境エネルギー第1部 コンサルタント 長島 圭吾
- *本稿は、『みずほグローバルニュース』 Vol.102 (みずほ銀行、2019年4月発行)に掲載されたものを、同社の承諾のもと掲載しております。
はじめに
2015年12月、国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)では、新たな地球温暖化対策の国際的枠組み「パリ協定」が採択された。パリ協定は、世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求することや、先進国と途上国という二分論を超えた全ての国の参加を規定しており、国際枠組みとして画期的なものとなった。しかし、パリ協定の実施に必要な手順やメカニズムを規定する実施指針(ルールブック)の策定は、COP24に先送りされていた。本稿ではまず、COP24で採択されたパリ協定の実施指針について概説する。
次に、日本に目を向ける。我が国では現在、首相官邸で「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略策定に向けた懇談会」が開かれ、2050年を見据えた議論が行われているところであるが、こうした政府レベルでの議論を見据え、環境省では2018年3月に、中長期的な気候変動緩和策における国際協力のあり方に関するビジョン(「気候変動緩和策に関する国際協力ビジョン」)をとりまとめ、中長期的な気候変動対策の国際展開に関する重要な考え方として「コ・イノベーション(Co-innovation)」を提唱した。本稿の後半では、この新しい考え方であるコ・イノベーションについて紹介する。
国連気候変動枠組条約第24回締約国会議(COP24)
2018年12月、ポーランド・カトヴィツェでCOP24が開かれた。パリ協定の実施指針の採択がCOP24の最大の目的であったが、最終的に全ての国に共通の実施指針を採択し、パリ協定の条文の基本的な手順やメカニズムを規定した。主な内容は次の通りである*1。
- 緩和(パリ協定4条に関連):NDC(2020年以降の新たな温室効果ガス排出削減目標)で各国に提出が義務づけられる情報や、温室効果ガス排出量等の算定の際に従うべき原則等を規定。
- 適応(パリ協定7条に関連):適応報告書の記載事項や適応の方法論等を規定。
- 資金(パリ協定9条に関連):2025年以降の資金支援目標を2020年から議論すること等を規定。
- 透明性枠組み*2(パリ協定13条に関連):進捗状況の確認に必要となる情報や途上国に柔軟性を付与する項目等を規定。
- グローバルストックテイク*3(パリ協定14条に関連):実施手法等を規定。
では、実施指針の策定において、COP24では何が争点となったのか。(1)先進国・途上国の差異化、(2)先進国から途上国への資金支援、(3)削減の国際移転、の3つを取り上げたい。
先進国・途上国の差異化
COP24では、実施指針においてどの程度先進国・途上国の間に差異を規定すべきか、途上国との間で共通ルールを重視する先進国と、二分論を重視する途上国で交渉がなされた。交渉の結果、先進国・途上国で同じルールに従いつつ、途上国は透明性枠組み等でより緩やかな適用が認められた*4。
先進国から途上国への資金支援
パリ協定は先進国から途上国への資金支援の目標を「2020年までに1000億米ドル/年」としていたが*5、COP24ではこの目標が2025年まで継続されることが確認された。COP24で争点となったのは、2025年以降の資金支援であった。これまで、2025年以降の目標設定の交渉をいつ始めるのかは決めていなかった。先進国は、COP24で新資金目標の議論開始を決議するのは時期尚早と主張し、途上国はCOP24で新資金目標の議論開始を決議すべきと主張した。COP24での交渉の結果、2025年以降の資金目標の交渉は「1000億米ドル/年」を下限として2020年から始めるとした。
削減の国際移転
削減の国際移転とは、排出削減の一部を排出枠として認め、国際的に取引することにより、世界全体でより費用を効率的に削減することであり、パリ協定では、協力的アプローチ*6、国連管理型メカニズム*7、非市場アプローチ*8、の3つが6条に規定されている。これらのメカニズムは、複数の国で同時に自国の削減分としてカウントしてしまうおそれがあり、厳密なルール作りが必要とされていた。COP24では、それぞれのメカニズムの実施指針に各国がおおむね合意していたが、ブラジルが国連管理型メカニズムに関して、排出削減量の二重計上に係る厳格な規則に反対*9したため、COP24では調整がつかず、6条の詳細ルール全体が2019年以降の交渉に持ち越されることになった。
COP24では、これらの合意などを経て、パリ協定の実施指針が採択され、パリ協定の手順やメカニズムが規定された。総じて先進国・途上国双方の主張に配慮したバランスのとれた実施指針となっており、今後は各国の政府、自治体、業界団体、企業、専門家、NGO、研究機関等、さまざまなステークホルダーが実施指針に沿った形で、温暖化対策を実施することに期待したい。
日本の中長期の気候変動緩和策に関する国際協力
環境省は、長期の温室効果ガス低排出開発戦略の検討も見据えて、2018年3月、中長期的な気候変動緩和策における国際協力のあり方を「気候変動緩和策に関する国際協力ビジョン」としてまとめ、中長期的な気候変動対策の国際展開の重要な考え方として「コ・イノベーション(Co-innovation)」を以下の通り提示した:
コ・イノベーションとは、我が国の技術や制度をパートナー国にそのまま導入・普及させる一方向のものではなく、パートナー国と我が国の協働により、パートナー国に適した脱炭素製品・サービス・技術の市場創出と経済社会システム、ライフスタイルの大きな変革をもたらすイノベーションである。
世界の経済成長と脱炭素化をけん引するべく、次の2点を柱として国際展開を実施していく。
- 1)日本の強みである環境技術、質の高いインフラ・製品・サービスを世界に展開。
- 2)パートナー国と我が国の協働を通じて、双方に裨益(ひえき)あるイノベーション(コ・イノベーション)を創出。
このように、コ・イノベーションは、環境省において中長期的な気候変動対策に関する国際展開の重要な考え方として位置づけられている。一方で、未だその定義の解釈や具体的なイメージが定まっていない状況である。そこで、中長期的な気候変動対策の国際展開においてコ・イノベーションが必要とされる背景や、コ・イノベーションの考え方について説明を加えたい。
(1) コ・イノベーションが必要とされる背景
なぜコ・イノベーションが重要な考え方となるのか。第一に途上国の経済成長である。中国やインドの台頭にみるように、一部の途上国は社会経済が急速に発展し、今や世界経済に大きな影響を及ぼす存在となった。途上国は製品やサービスを消費するだけではなく、イノベーションを創出する役割を担いつつある。
第二に、日本のプレゼンスの低下である。かつて日本の家電製品がアジアを席巻したが、現在は新興国市場で力をつけたアジア製の家電製品が攻勢をかけている。加えて、欧米発のデジタル企業やスタートアップ企業が台頭し、既存のビジネスを大きく揺さぶるなか、日本がこれまで有してきたプレゼンスが低下するかもしれない。
第三に、途上国の多様性である。途上国は経済水準、気候条件、文化等、さまざまな面で多様である。制度の構築や人材育成等、社会基盤の整備を必要とする国もあれば、すでに技術が普及し市場が形成され、日本の高品質な製品・サービス等を必要とする国もある。相手国の発展段階やニーズに応じた、テーラーメイド型アプローチの必要性は高い。
以上のように、国際展開は、国内企業が国内のニーズに合わせて生産したものをそのまま展開するアプローチで事足りる時代ではなくなりつつある。中長期的に途上国がさらに経済成長することを考えると、その様相はさらに強まるだろう。そのような中では、途上国の成長を脅威ではなく機会とし、途上国を対等なパートナーとして捉え、お互いの強みやニーズを活かしつつ、一緒に製品やサービス、技術を創出していく考えが重要となる。
(2) コ・イノベーションの考え方
先に説明したように、コ・イノベーションとは、「我が国の技術や制度をパートナー国にそのまま導入・普及させる一方向のものではなく、パートナー国と我が国の協働により、パートナー国に適した脱炭素製品・サービス・技術の市場創出と経済社会システム、ライフスタイルの大きな変革をもたらすイノベーション」である。コ・イノベーションによるソリューション開発の過程を図表1に示す。途上国では、社会・経済の成長とともにビジネスの環境が徐々に整い、先進国と共通の課題が出現する([1])。途上国と先進国がそれぞれの強みを活かしつつ、両者の協働により共通のソリューションを生み出し([2])、そのソリューションで先進国・途上国の課題やニーズを解決する([3])。
「Co」という言葉には「一緒に」の意味がある。途上国の成長を脅威ではなく機会とし、途上国を対等なパートナーとして捉え、一緒にその国に合った脱炭素製品・サービス・市場を創っていく「コ・イノベーション」の考え方は、今後、世界の構図が変化するなか、日本が世界の脱炭素化を牽引する上で重要な考えの1つとなる。気候変動緩和策に関する国際展開の重要な考え方の1つとして、「コ・イノベーション」に期待したい。
図表1. コ・イノベーションによるソリューション開発
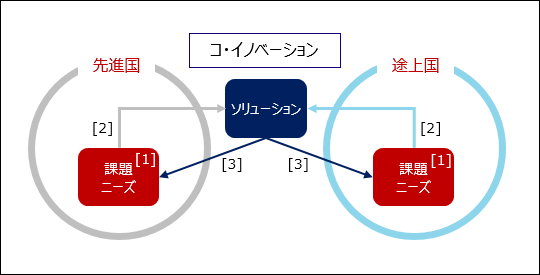
(出所)みずほ情報総研作成
おわりに
COP24では、パリ協定の実施指針(ルールブック)が採択され、同協定の基本的な手順やメカニズムが規定された。今後は、各国の政府、自治体、業界団体、企業、専門家、NGO、研究機関等、さまざまなステークホルダーが同協定に沿った形で、地球温暖化対策に取り組む必要がある。国内における温室効果ガス排出量の削減については2030年や2050年の目標があるが、本稿で言及した気候変動緩和策に関する国際協力については、具体的な目標は定められていない*10。中長期的な視点に立って、いかなる削減行動をすべきなのかについて具体的な目標が示され、各ステークホルダーが脱炭素行動を促す大きな契機となることを期待したい。
- *1)United Nations Framework Convention on Climate Change「The Katowice Climate Package: Making The Paris Agreement Work For All」、The International Institute for Sustainable Developmen(IISD) 「Earth Negotiations Bulletin」 、環境省「COP24の結果について」 (PDF/1,120KB) を参考
- *2)各国の温室効果ガス排出量、削減目標の進捗・達成状況等の報告制度
- *3)パリ協定のもとで2023年以降5年ごとに実施される世界全体の進捗評価
- *4)柔軟性の適用は途上国が自ら決定し、専門家レビューチームは当該途上国が柔軟性を自己適用することの是非、理由については立ち入らないこととされた。柔軟性の付与をレビュー対象とし、期限を設けるという先進国の主張は通らなかったが、一方で途上国が柔軟性の適用を自己決定するにあたり、個々の報告項目につき、柔軟性を必要とする理由、具体的な制約要因、状況改善の期限を説明することが義務づけられることとなった
- *5)2009年のCOP15で途上国への資金支援の総額の目標「2020年までに1000億米ドル/年」が設定され、パリ協定ではこの目標を継続することが定められている。これは緩和策と適応策の両方への支援を含み、官民の資金を合わせた金額となっている
- *6)制度に参加する国の承認を前提として、海外で実現した排出削減・吸収量を各国の削減目標の達成に活用するメカニズムであり、パリ協定の6条2項に規定されている。メカニズムの代表例として、日本が提案・実施している二国間クレジット制度(JCM:Joint Crediting Mechanism)がある
- *7)京都議定書のクリーン開発メカニズム(CDM:Clean Development Mechanism)の後継として国連管理の下に設立されているメカニズムで、パリ協定の6条4項に規定されている。この国連管理型メカニズムからの排出削減量は、他国が削減目標達成に活用した場合、ホスト国の削減目標の達成に活用できない特徴がある。これはホスト国とのダブルカウントを回避するために設けられた措置のためである
- *8)持続可能な開発のための緩和、適応、資金、技術移転、能力構築の全てに関連する枠組みで、パリ協定の6条8項により規定されている。しかし、現在は気候変動枠組条約の締約国会議の主要案件を事前に協議する「科学および技術の助言に関する補助機関(SBSTA)」で作業計画を策定中である
- *9)国連管理型メカニズムは、CDM(クリーン開発メカニズム)の後継として国連管理の下に設立されているメカニズムで、これまでCDMプロジェクトに多数の実績を有するブラジルは、COP24の交渉において、京都議定書に基づくCDMをパリ協定下の6条4項メカニズムに移管すべきと主張した。しかし、京都議定書に基づくCDMをパリ協定下に移管するにあたっては、パリ協定のダブルカウント禁止条項に抵触する。パリ協定の下では、先進国も途上国も、削減分を国際的に移転する場合、移転元の国の排出削減量からその分を差し引く必要がある。しかし、CDMは途上国が削減目標を持たない京都議定書のメカニズムであるため、こうしたダブルカウント禁止条項は適用されてこなかった。ブラジルはそのことを理由に、パリ協定に移管されるCDMをダブルカウント禁止条項の適用除外とすべきと主張した。この点について、COP24では調整がつかず、6条の詳細ルール全体が2019年以降に持ち越されることになった
- *10)気候変動緩和策に関する国際協力に関連して現在定められている目標として、日本の約束草案(2020年以降の新たな温室効果ガス排出削減目標)においてはJCM(二国間クレジット制度)(日本政府事業分)により2030年度まで累積で5000万から1億トンの二酸化炭素の削減目標が記載されており、内閣府「エネルギー・環境イノベーション戦略」においては、2050年に全世界で数10~100億トン規模の削減ポテンシャルが記載されている。長期についてはポテンシャルの記載にとどまっており、目標値はない
関連情報
この執筆者はこちらも執筆しています
-
2019年4月