
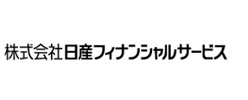
株式会社日産フィナンシャルサービスは、日産グループにおいて、オートクレジットやカーリース、カード、カーメンテナンス、自動車保険の金融事業を展開している。同社が取り組んでいたそのプロジェクトとは、お客さまの口座振替に必要な振替データの受け渡し方法を、およそ40年続いた磁気テープの搬送から伝送化に変更するという、思い切ったものだった。同社は、日産車を購入されるお客さまの約4割が利用する、オートクレジット・カーリースビジネスを中心に展開しており、お客さまからの代金回収はその生命線だ。それだけに、月間90万件を超える口座振替データについては、安全かつ迅速に金融機関に送り届けなくてはならない。口座振替データの受け渡しの伝送化に向けて、同社を踏み切らせたのは何だったのだろうか。
東日本大震災で顕在化したリスクとは

日産フィナンシャルサービス
取締役執行役員常務
澤田 恭明氏
「毎年、風雪水害などにより、口座振替データの搬送遅延リスクという問題に悩まされていました。しかし、そのリスクが顕在化した最たる事象は、2011年3月に発生した、東日本大震災でした。1,267社に及ぶ金融機関向けのデータは、139の金融機関及び集約センターに搬送していました。震災直後、東北3県は交通手段が寸断されていたために、そのうち5つの金融機関には、当社の社員が何とか飛行機やバス、タクシーを駆使して、カートリッジ磁気テープ(以下、CMTと表記)を直接持ち込みました。非常時の対応に、社員は細心の注意を払ってあたってくれました。しかし、CMTのデータは個人情報のかたまりです。不測の事態にも対応できるよう、代替策やリカバリーの方法を考えなければなりませんでした」と、取締役執行役員常務の澤田 恭明氏は震災当時を振り返る。そして、澤田氏は震災発生の直後から、経営層に対してCMTの搬送によるデータのやり取りの危険性を説き、より安全なデータの授受方法の検討に入ったという。
「毎年、風雪水害などにより、口座振替データの搬送遅延リスクという問題に悩まされていました。しかし、そのリスクが顕在化した最たる事象は、2011年3月に発生した、東日本大震災でした。1,267社に及ぶ金融機関向けのデータは、139の金融機関及び集約センターに搬送していました。震災直後、東北3県は交通手段が寸断されていたために、そのうち5つの金融機関には、当社の社員が何とか飛行機やバス、タクシーを駆使して、カートリッジ磁気テープ(以下、CMTと表記)を直接持ち込みました。非常時の対応に、社員は細心の注意を払ってあたってくれました。しかし、CMTのデータは個人情報のかたまりです。不測の事態にも対応できるよう、代替策やリカバリーの方法を考えなければなりませんでした」と、取締役執行役員常務の澤田 恭明氏は震災当時を振り返る。そして、澤田氏は震災発生の直後から、経営層に対してCMTの搬送によるデータのやり取りの危険性を説き、より安全なデータの授受方法の検討に入ったという。
紆余曲折したソリューション選定

日産フィナンシャルサービス
カスタマーセンター統括部
部長
吉本 明彦氏
お客さまの口座振替データ処理業務は、カスタマーセンター統括部が一手に引き受けている。部長を務める吉本 明彦氏は、「自前で伝送のためのシステムを保有して運用するという方法から、業務そのものを外注してしまう方法まで、改善方法については幅広く検討しました」と、ソリューション決定に至るまでの経緯を話してくれた。その中で、自前で金融機関へデータを伝送する方法は、業務の手間が掛かり過ぎるという理由から、一時は収納代行サービスを利用する、という方法に決めかけたという。しかし、その後、収納代行サービスの採用を諦め、新たな方法をさがすことになった。
「収納代行サービスの導入に至らなかったのは、当社が最も重視していた、お客さまや日産の販売会社に迷惑をかけることなく、スムーズに移行できるのかという点で、実現性が低いと判断したからです。収納代行サービスを採用すると、記帳される引落名が当社から収納代行会社名に変わります。また、振替日も現在の10日・27日が保証されず、収納代行会社が指定する日にちに、変更せざるを得ないケースがありました。変更事項をお客さまに通知すれば良い、という問題ではありません。特に、振替日に関しては、お客さまとの間でも重要な契約事項のひとつですので、当社の都合で変更することは出来ません。当社での作業だけでなく、お客さまや販売会社との取引も含めた、スムーズな移行のためには、従来の振替日や引落名を固持することが、必須であると考えたのです」と、カスタマーセンター統括部主担の山口 昌英氏は説明してくれた。すべては、お客さまや販売会社への混乱やご迷惑を避けるための、路線変更であったようだ。
お客さまの口座振替データ処理業務は、カスタマーセンター統括部が一手に引き受けている。部長を務める吉本 明彦氏は、「自前で伝送のためのシステムを保有して運用するという方法から、業務そのものを外注してしまう方法まで、改善方法については幅広く検討しました」と、ソリューション決定に至るまでの経緯を話してくれた。その中で、自前で金融機関へデータを伝送する方法は、業務の手間が掛かり過ぎるという理由から、一時は収納代行サービスを利用する、という方法に決めかけたという。しかし、その後、収納代行サービスの採用を諦め、新たな方法をさがすことになった。
「収納代行サービスの導入に至らなかったのは、当社が最も重視していた、お客さまや日産の販売会社に迷惑をかけることなく、スムーズに移行できるのかという点で、実現性が低いと判断したからです。収納代行サービスを採用すると、記帳される引落名が当社から収納代行会社名に変わります。また、振替日も現在の10日・27日が保証されず、収納代行会社が指定する日にちに、変更せざるを得ないケースがありました。変更事項をお客さまに通知すれば良い、という問題ではありません。特に、振替日に関しては、お客さまとの間でも重要な契約事項のひとつですので、当社の都合で変更することは出来ません。当社での作業だけでなく、お客さまや販売会社との取引も含めた、スムーズな移行のためには、従来の振替日や引落名を固持することが、必須であると考えたのです」と、カスタマーセンター統括部主担の山口 昌英氏は説明してくれた。すべては、お客さまや販売会社への混乱やご迷惑を避けるための、路線変更であったようだ。
採用の決め手は、金融機関との交渉力と人間力
次に検討を開始したのが、「口座振替データの代行送受信」であったという。企画室主担の本山 憲一氏は、同様のサービスを提供する4社を総合的に判断するために、比較検討を行ったと説明する。「事業規模や金融機関との接続実績、交渉サポート有無、コストなど、様々な観点から比較検討しました。また、当社には、極力短いスケジュールで導入したい、という想いがあったので、サポート体制を重要視していました。その点で、みずほ情報総研の、金融機関との折衝支援という他社にはないサービスが、大変魅力的でした」。また、BCP対策の一環として、口座振替データの伝送化を検討していた同社にとっては、みずほ情報総研が唯一大阪にもデータセンターを保有している点も、採用のポイントになったようだ。本山氏によると、競合する3社は、データバックアップの設備自体がない点に不安があったが、その中で、将来必要となるであろう、広域連携型のバックアップセンターが展開できる、みずほ情報総研の体制を高く評価したという。
「最終的に、価格をさらに下げると提示してくれた事業会社もありました。しかし、チーム全員でプロジェクトをいっしょに進める事業会社について話し合った結果、全員がみずほ情報総研にお願いしようと考えていたのです」と、本山氏は続けた。みずほ情報総研の担当者とは、課題が明らかになる都度、解決するためにどのような方法を取るべきかを本気で話し合い、一緒になって模索できたことで、信頼感が醸成されたのだと説明してくれた。
プロジェクトを統括する澤田氏も、みずほ情報総研を選んだ理由について同様に考えていたという。「私にとっての決め手は、信頼性と安心感でした。『当社の生命線となるお客さま情報を預ける上で、どこが一番安心できる事業会社だと思うのか』を私自身がメンバーに聞いたところ、全員がみずほ情報総研の名前を挙げました。担当者に対して絶対の信頼感があったようです。また、みずほ銀行の担当者が要所で強力にサポートしてくれたのも、嬉しかったですね。グループ全体で総力を挙げてサポートしてくれるという姿勢を強く感じました」。
こうして、約2年続いたソリューションや事業会社の選定が終了し、みずほ情報総研の提供する「口座振替データの代行送受信」の導入が決定した。

日産フィナンシャルサービス
企画室主担
本山 憲一氏
次に検討を開始したのが、「口座振替データの代行送受信」であったという。企画室主担の本山 憲一氏は、同様のサービスを提供する4社を総合的に判断するために、比較検討を行ったと説明する。「事業規模や金融機関との接続実績、交渉サポート有無、コストなど、様々な観点から比較検討しました。また、当社には、極力短いスケジュールで導入したい、という想いがあったので、サポート体制を重要視していました。その点で、みずほ情報総研の、金融機関との折衝支援という他社にはないサービスが、大変魅力的でした」。また、BCP対策の一環として、口座振替データの伝送化を検討していた同社にとっては、みずほ情報総研が唯一大阪にもデータセンターを保有している点も、採用のポイントになったようだ。本山氏によると、競合する3社は、データバックアップの設備自体がない点に不安があったが、その中で、将来必要となるであろう、広域連携型のバックアップセンターが展開できる、みずほ情報総研の体制を高く評価したという。
「最終的に、価格をさらに下げると提示してくれた事業会社もありました。しかし、チーム全員でプロジェクトをいっしょに進める事業会社について話し合った結果、全員がみずほ情報総研にお願いしようと考えていたのです」と、本山氏は続けた。みずほ情報総研の担当者とは、課題が明らかになる都度、解決するためにどのような方法を取るべきかを本気で話し合い、一緒になって模索できたことで、信頼感が醸成されたのだと説明してくれた。
プロジェクトを統括する澤田氏も、みずほ情報総研を選んだ理由について同様に考えていたという。「私にとっての決め手は、信頼性と安心感でした。『当社の生命線となるお客さま情報を預ける上で、どこが一番安心できる事業会社だと思うのか』を私自身がメンバーに聞いたところ、全員がみずほ情報総研の名前を挙げました。担当者に対して絶対の信頼感があったようです。また、みずほ銀行の担当者が要所で強力にサポートしてくれたのも、嬉しかったですね。グループ全体で総力を挙げてサポートしてくれるという姿勢を強く感じました」。
こうして、約2年続いたソリューションや事業会社の選定が終了し、みずほ情報総研の提供する「口座振替データの代行送受信」の導入が決定した。
大幅に短縮された金融機関との交渉期間

日産フィナンシャルサービス
カスタマーセンター統括部
主担
山口 昌英氏
プロジェクトを進める中で、みずほ情報総研だけが唯一提供可能だったという、金融機関との折衝支援サービスとは、どのようなものなのだろうか。山口氏は準備期間の苦労と合わせて説明をしてくれた。「CMTの送付先は分かっていても、各金融機関との伝送データのやり取りとなると、金融機関や処理センターのどの部署の誰が対応窓口なのか、全くわからない状態でした。勿論、金融機関との契約交渉もあるので、全てをみずほ情報総研にお願いすることは出来ませんが、それでも各金融機関の窓口の紹介や具体的なデータ授受の方法について、サポートしてもらえたのは、時間効率の面でかなり助かりました。実際、契約内容が金融機関によって異なるだけではなく、ひとつの金融機関内でも、データの送付先と交渉の窓口が異なるところがあるなど、金融機関とのやり取りは想像以上に大変でした。伝送に必要な価格の交渉から基本契約の締結まで、約3人体制で進めましたが、半年かかって全ての金融機関との折衝が完了しました。みずほ情報総研の金融機関との折衝支援がなければ、倍の1年は準備にかかっていたと思いますよ」。
なお、各金融機関とのデータのやり取りに必要な回線の接続やテストという面では、みずほ情報総研が全面的にサポートしたという。「自前によるデータ伝送を選択していたら、金融機関との折衝と並行して、伝送に関するシステムテストまで自前で行わなければならず、さらに期間が必要だったかもしれません」と言う吉本氏の顔からは、パートナー選定で正しい目利きをしたことへの、満足の表情が見て取れた。
現在、みずほ情報総研ではシステム構築を経て、同社より口座振替データを一括で受信し、金融機関ごとにデータを分割し、指定されたフォーマットに変換の上、毎月2回、1,267社に及ぶデータを伝送している。また、各金融機関の口座振替結果データも、みずほ情報総研が代行受信した後、同社用のフォーマットに変換し直して、一括で返送しており、全ての工程が順調に進んでいる。
プロジェクトを進める中で、みずほ情報総研だけが唯一提供可能だったという、金融機関との折衝支援サービスとは、どのようなものなのだろうか。山口氏は準備期間の苦労と合わせて説明をしてくれた。「CMTの送付先は分かっていても、各金融機関との伝送データのやり取りとなると、金融機関や処理センターのどの部署の誰が対応窓口なのか、全くわからない状態でした。勿論、金融機関との契約交渉もあるので、全てをみずほ情報総研にお願いすることは出来ませんが、それでも各金融機関の窓口の紹介や具体的なデータ授受の方法について、サポートしてもらえたのは、時間効率の面でかなり助かりました。実際、契約内容が金融機関によって異なるだけではなく、ひとつの金融機関内でも、データの送付先と交渉の窓口が異なるところがあるなど、金融機関とのやり取りは想像以上に大変でした。伝送に必要な価格の交渉から基本契約の締結まで、約3人体制で進めましたが、半年かかって全ての金融機関との折衝が完了しました。みずほ情報総研の金融機関との折衝支援がなければ、倍の1年は準備にかかっていたと思いますよ」。
なお、各金融機関とのデータのやり取りに必要な回線の接続やテストという面では、みずほ情報総研が全面的にサポートしたという。「自前によるデータ伝送を選択していたら、金融機関との折衝と並行して、伝送に関するシステムテストまで自前で行わなければならず、さらに期間が必要だったかもしれません」と言う吉本氏の顔からは、パートナー選定で正しい目利きをしたことへの、満足の表情が見て取れた。
現在、みずほ情報総研ではシステム構築を経て、同社より口座振替データを一括で受信し、金融機関ごとにデータを分割し、指定されたフォーマットに変換の上、毎月2回、1,267社に及ぶデータを伝送している。また、各金融機関の口座振替結果データも、みずほ情報総研が代行受信した後、同社用のフォーマットに変換し直して、一括で返送しており、全ての工程が順調に進んでいる。
伝送化へのシームレスな移行を実現
2013年度に入って徐々にデータ伝送への移行を開始し、約半年間で100%伝送化を実現した同社だが、社内ではどのように受け止められているのだろうか。「おそらく一般社員には、請求の方法が変わったという意識は全くないでしょう。一方で、経営の立場からすると、大きな変革です。40年近く抱えていた、媒体によるデータ授受に伴う紛失リスクや個人情報漏えいリスクも併せて、解消された訳ですから」と、山口氏は言う。システムの移行による混乱もなく、極力最小限のコストでシームレスに基盤となる仕組みの転換を図れたことこそが、今回の最大の利点であるようだ。
澤田氏は、「今回の伝送化への移行を最も喜んでいるのは、当社の社長ではないでしょうか。最大の目的であったBCP対策が実現したわけですから」と、経営層に今回のプロジェクトが高く評価されていることを教えてくれた。
今後の展開
2014年度に、一部大手都市銀行や地方銀行が、CMTの取扱いを全面的に中止すると発表している中、本プロジェクトの成功により、同社は見事にその先鞭をつけた格好である。「完全移行が実現し、安心してデータ授受を行うことが出来るようになりました。今年の2月に、大雪によって高速道路が封鎖され、CMTの搬送が止まってしまったことがありましたが、そのような、天候に左右される気苦労は一切なくなりました。実務を取り仕切る部門としては、心理的な負担が大変軽くなりました。今年の夏も、各地で大雨や土砂災害等がありました。CMTでの搬送を継続していたら、何らかの影響があったでしょうね」と、山口氏は伝送化により搬送リスクがなくなったことを、日々の業務の中で実感しているようだ。
しかし、BCPへの取り組みは、完了した訳ではないようだ。「これまでは伝送化への移行に全精力を注いできました。今後は、何らかのトラブルが発生した際の対応策も、考えていかなければなりません。問題が発生したときにどういう対応を取るべきなのか、また、どれくらいの時間で復旧できるのかを、みずほ情報総研と相談をしていきたいですね」と、山口氏は更なるリスクマネジメント体制の整備に余念がない。
「最先端の金融・サービスで、お客様のカーライフを豊かに」をビジョンに金融事業を展開する日産フィナンシャルサービス。金融事業という堅実な事業の裏には、お客さまや販売会社との信頼関係を重視する姿勢が見て取れる。それこそが、同社をBCP強化に向けて突き動かす原動力なのかもしれない。
- *この記事は、2013年9月の取材をもとに作成したものです。
お問い合わせ
担当:広報室
関連情報
おすすめソリューション
口座振替データ代行送受信
― 煩雑な口座振替データの送受信を代行し、事務負担を軽減
「口座振替データ代行送受信」は、金融機関ごとの口座振替データの作成・送信、口座振替結果データの回収・集約を当社がお引き受けいたします。