みずほ情報総研 事業戦略部 調査役 菊地 徳芳
- *本稿は、『みずほグローバルニュース』 Vol.101(みずほ銀行、2019年2月発行)に掲載されたものを、同社の承諾のもと掲載しております。
日本は、諸外国に先駆けて少子化と高齢化が進んできた。それらが引き起こす社会課題の解決が急務となる中、その環境を逆手にとる「課題先進国」アプローチが注目され始め、2019年で10年余りが経とうとしている。しかし、この間にどれだけの新しいサービスや解決策が生み出されてきただろうか。
確かに、内閣府発表の「平成30年版高齢社会白書」によると、2017年10月1日時点で、日本における高齢化率(65歳以上の高齢者が総人口に占める割合)はすでに27.7%であり、2036年には33.3%に達すると推計されている。日本は「3人に1人が高齢者」の社会となるのであるから、人口の「年齢構成」の観点からすれば、日本は諸外国に先んじて社会に大きな変革をもたらす製品やサービスが登場する土壌があるといえるだろうし、それが必要なことは間違いない。しかし、その頃には、ドイツやイタリアも日本と同程度、先進地域全体でも平均で25%程度の高齢化率となる(図表1)。さらに、高齢者の「数」で世界を眺めてみると、アメリカの高齢者数は以前から日本を上回っており、同じ頃には日本の2倍を超える(図表2)。日本が課題先進国と思っている間にも、日本以外のこれらの国から、高齢者をターゲットにした革新的な製品やサービスが登場し、世界に広まっていく可能性も十分にあるだろう。
実際、2018年までに当社が行った調査からは、多くの海外スタートアップ企業がこの領域に参入し、新たなテクノロジーの開発や、それを活用した顧客体験や付加価値の高いさまざまなサービスの実現に動き出している実態が見えてきた。今回は、その中から4つのトピックに着目して、先進的で特徴的なスタートアップ企業の取り組みを紹介する。
図表1. G7各国、先進地域、開発途上地域の高齢化率
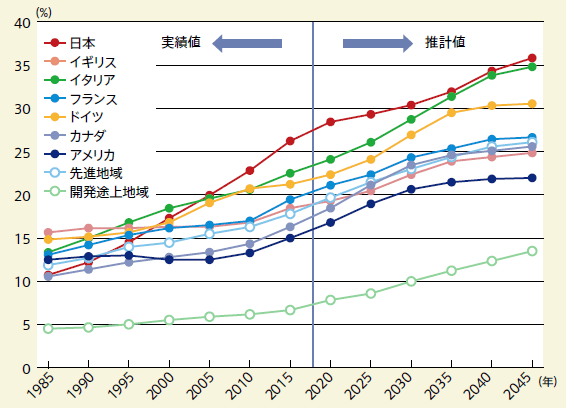
(出所)「UN World Population
Prospects:The 2017 Revision」より、著者作成
(注)先進地域:ヨーロッパ、北部アメリカ、日本、オーストラリア及びニュージーランドからなる地域
開発途上地域:アフリカ、アジア(日本を除く)、中南米、メラネシア、ミクロネシア及びポリネシアからなる地域
図表2. G7各国の65歳以上の高齢者数
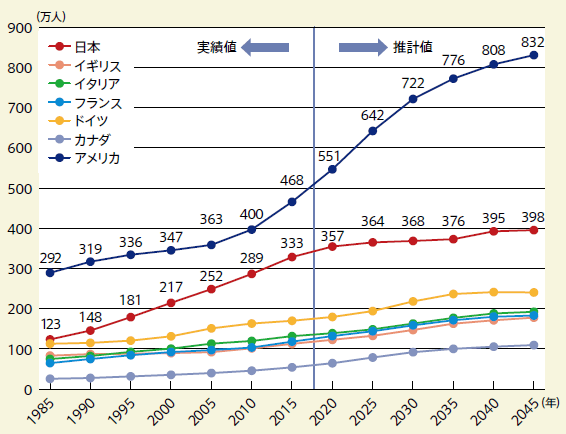
(出所)「UN World Population Prospects:The 2017 Revision」より、著者作成
認知機能の低下に早めに気づき対処するためのサービス
認知症関連は、今後市場拡大が想定される領域の1つである。厚生労働省は、2012年時点で、65歳以上の高齢者のうち約15%(約462万人)が認知症患者であり、認知症になる可能性のある軽度認知障害(MCI:Mild Cognitive Impairment)を持つ高齢者は約13%(約400万人)と推定している。65歳以上の高齢者の4人に1人以上が認知症もしくはMCIということになる。治療分野では、ほとんどの製薬会社がアルツハイマー型認知症の治療薬等の開発を断念しているものの、認知症手前のMCI段階で適切に対処すれば半数程度が回復するというデータもある。認知症は、早い段階で「気づき」「対処」することが重要なのだ。しかし実際は、認知機能の検査に踏み切れないまま、中度の認知症になってから対処し始めたという家族も多い。
カナダのWinterlight Labs社*1は、医療の臨床現場に、音声や機械学習に関するテクノロジーを持ち込むことで、患者の発話に混じる特徴的な波長から認知機能障害の兆候を早期に発見するツールを開発している。通常の認知機能の筆記テストなどは、頻繁に行うことが難しい。しかし、彼らの場合は「声」という日常生活で自然に得られる情報を使うため、週に何度でも簡単に確認することができ、状態が良い日と悪い日の両方を追跡し、時間をかけて認知機能をトラッキングできる。一方、アメリカのNeurotrack Technologies社*2は「視線」の動きに着目した。アルツハイマー型認知症では、短期記憶を長期記憶に移す役割も果たしている海馬が、最初に損傷を受ける領域の1つといわれている。彼らは、数十年も前に著名な神経科学者が開発した技術をベースに、視線追跡テクノロジーと機械学習等を利用して、認識メモリと海馬障害を評価する5分間のテストアプリを開発した。このアプリでは、アルツハイマー型認知症の症状が現れる20~25年前に、その予兆を検知できるという。
また、認知症の予防や進行抑制のためのセラピーの1つである回想法に関しては、イギリスのGreyMattersCare社*3が「双方向型のライフストーリーブック」アプリを提供している。認知症患者本人の人生の歩みを聞き起こしたうえで、世の中の出来事に関するコンテンツ、音楽やゲームをひも付けたライフストーリーブックが作成され、それをもとに、クイズ形式で記憶を確認したり、出来事を振り返る中で蘇った記憶により、その内容を随時更新したりできる。日本にも、新聞記事等とともに自分史を振り返るノート等が販売されているが、それをデジタル化し、回想法に活かしたサービスともいえ、認知症患者や介護者の暮らしの質を高めるのに役立っている。なお、このほかにも「バーチャルリアリティ(仮想現実)」を回想法に活用しようとするスタートアップも複数登場している。
認知機能の低下については、他の疾患に比べると、自分自身にもそのリスクがあるのではないかと感じる人のすそ野は広く、予防市場のマーケットはかなり大きいだろう。さらに、生活習慣病の1つである糖尿病の人は認知症にもなりやすいというデータがある。そのため、特に日本では、健康づくりサービスからの延長線上で利用者を獲得していけるように、健康づくりの一貫として認知症予防サービスをラッピングしてみせるなど、工夫を凝らしたサービスの登場も期待される。
高齢者のみの生活をそっと気遣うサービス
日本で、65歳以上の一人暮らし世帯は、1980年には約88万人(男性:約19万人、女性:約69万人)であったが、2015年には約592万人(男性:約192万人、女性:約400万人)と、約7倍に増加している(図表3)。これに加えて、家族と暮らしていても日中は一人になってしまう高齢者もいる。一人で暮らす高齢者がこれからも増えていくと見込まれる中、特に、転倒や心疾患等のアクシデントによるQOL(Quality of Life)の低下リスクが懸念されている。しかし、家族には家族の生活もあり、介護事業者等にケアを頼んだとして訪問頻度や負担できる費用にも限りがある。また、高齢者からすると、監視的な要素の強い見守りサービスへの抵抗感もある。しかも、高齢者は自身の健康状態に異変を感じていても、そのことを家族や介護事業者等には話さないケースも少なくない。
こうした中、世界のいくつかのスタートアップは、高齢者が身に付けるウェアラブル内の多様なセンサーから得られる加速度や脈拍等の身体データと屋内のビーコンセンサーから得られる位置データを収集し、それら多様なデータをAI(人工知能)で逐次分析することで、高齢者の行動を目にせずとも、外出や屋内移動、食事、睡眠、歯磨き、入浴、トイレ等といった「生活行動の種類」を推定できるサービスを開発している。それら生活行動のタイミングや長さ、回数等を記録し、毎日レポートとして整理するだけでなく、その習慣性を見いだしたうえで、そこから乖離する傾向がある場合や転倒・徘徊等の異常を検知した場合には、家族や介護事業者等に知らせることもできる。
このようなサービスを開発している代表的なスタートアップとしては、データを収集するプラットフォームや解析エンジンに特化したサービスを提供するアメリカのInhabitech社*4やイスラエルのPerlis社*5、専用のウェアラブルやセンサーも設計し独自性の高いサービスをパッケージで提供しているアメリカのCarePredict社*6やイスラエルのKytera Technologies社*7などがある。
しかし、これらのサービスも現時点では、介護施設等で施設スタッフが入居者を見守るような限定的な生活環境での利用にとどまっている。自宅に一人で暮らす高齢者に使ってもらうには、生活行動を解析する精度の向上や、解析した生活行動を高齢者や家族にほどよく見せる仕掛け、ウェアラブルを身に付けやすくする工夫等も必要となる。何より、高齢者本人が進んで利用したくなるサービスでなくてはならない。日本でも今後は、高齢者本人では気づきにくい日々のちょっとした変化や前兆を捉えて、それを本人や離れて暮らす家族にそっと伝えて、何をどうすべきかのサポートや「お勧めサービス」への橋渡しなどをさり気なく行う「コーチング」型のサービスが必要となるだろう。その際、日本の高齢者は、健康づくりへの意識が高く、ヘルスケア関連のモニタリングサービスには一定の需要があることから、「高齢者を他者が見守る」のではなく、「高齢者自らが自身の健康を管理する」サービスとして高齢者の懐に入り込み、結果的に高齢者の生活行動の衰えを気遣えるサービスへと拡張・展開していく戦略が有効ではないだろうか。
図表3. 65歳以上の一人暮らし世帯
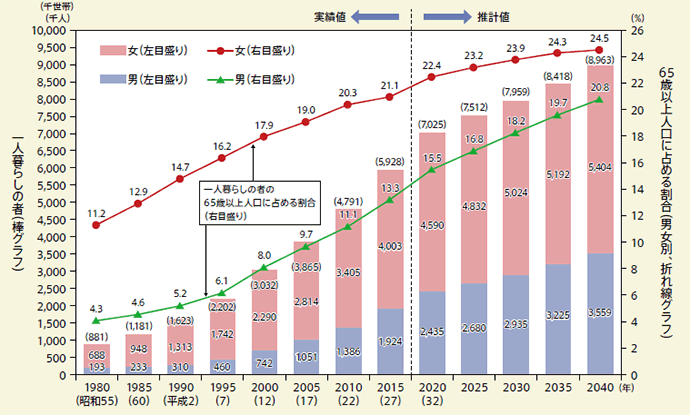
(出所)平成30年版高齢社会白書(内閣府)
(資料)平成27年までは総務省「国勢調査」による人数、平成32年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(全国推計)2018(平成30)年推計)」による世帯数
(注1)「一人暮らし」とは、上記の調査・推計における「単独世帯」又は「一般世帯(1人)」のことを指す
(注2)棒グラフ上の( )内は65歳以上の一人暮らし者の男女計
(注3)四捨五入のため合計は必ずしも一致しない