経営・IT コンサルティング部 川瀬 将義
人間拡張の活用方法、適用範囲
―人間拡張がもたらす効果―
本章では、「人間拡張がもたらす効果」を整理・類型化することで、今後の人間拡張の適用範囲や活用方法の可能性を示す。「人間拡張がもたらす効果」は「能力補完」「能力向上」「能力獲得」の3通りに大別できる(図表5参照)。
図表5 人間拡張がもたらす3つの効果
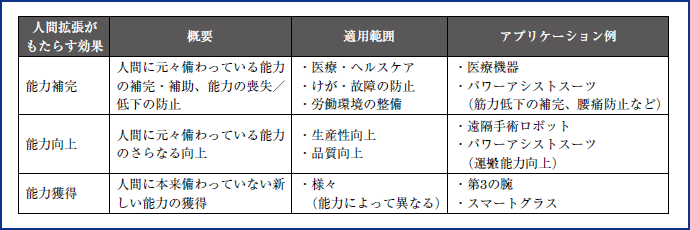
(資料)みずほ情報総研作成
[1] 能力補完
能力補完は人間に元々備わっている能力の補完・補助、能力の喪失/低下の防止を目的とした人間拡張である。つまり元々の能力をゼロとしたとき、何らかの理由(老化やけがなど)でゼロからマイナスになった能力をゼロに戻す/近づけること、また能力がマイナスにならないように防ぐことを目的としている。主に義手・義足などの医療機器やヘルスケア現場における介護機器などが該当するほか、パワーアシストスーツによる腰痛防止なども挙げられる。そのほか、人間拡張を活用することで高齢者や傷病者などが快適に生活できる環境を整備することも可能である。例えば、アバターロボットを遠隔操作することで、病院のベッドにいながら別の場所で働くなどが挙げられる(全身の補完と言える)。
[2] 能力向上
能力向上は人間に元々備わっている能力をさらに向上する、つまり元々の能力をゼロとしたとき、能力をプラスにすることを目的とした人間拡張である。例えば、遠隔手術ロボットはロボットアームの活用で本来の人間の手より可動域を拡大できるほか、手の震えが防止されるなど高精度な執刀が可能である(手術能力の向上と言える)。
[3] 能力獲得
能力獲得は人間に本来備わっていない新しい能力を獲得することである。もたらす効果は獲得した能力によるため一言で表すことは出来ないが、例えば、ロボットアームを人間に装着し、第3の腕を新たな能力として獲得する取組みがある*18。また、AR/MR グラスはカメラ映像を用いて振向かずに後方を確認する能力を獲得できるほか、天気予報や時間などを表示することで、情報を視覚で認識する能力を獲得可能である。アバターロボットは遠隔地に自身を存在させる能力を獲得できるほか、複数アバターの同時操作により複数の身体を獲得可能である。
最後に、人間拡張の代表的なアプリケーション例を図表6に示す。ここに記載した例は活用方法がある程度明確になっているほんの一例に過ぎないが、今後の研究開発の進展や技術革新、新しい発想・技術の組み合わせなどにより、新たな価値を創出するアプリケーションが次々と生まれてくるのではないだろうか。
図表6 代表的な人間拡張のアプリケーションの整理
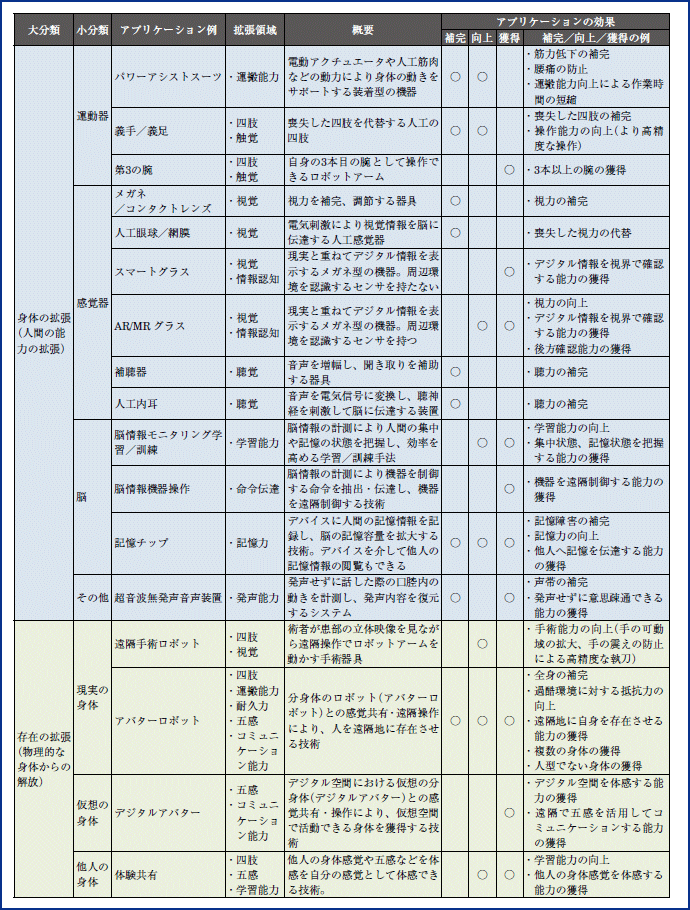
(資料)みずほ情報総研作成
人間拡張への期待
本稿では、人間拡張を定義・分類した上で、「デバイスとの一体感」を実現する技術の現状、「人間拡張がもたらす効果」や人間拡張の活用方法および適用範囲について紹介した。
「デバイスとの一体感」の観点では、ハプティクスなどの技術の適用によりデバイスの着用に伴う煩わしさの解消が可能となり、人間拡張の普及が促進される可能性について述べた。また、「人間拡張がもたらす効果」の観点では、効果を3つに分類([1]能力補完、[2]能力向上、[3]能力獲得)した上で、人間拡張の適用範囲や活用方法について整理し、新たな価値を創出するアプリケーションへの期待を述べた。
我が国においては、産総研が人間拡張研究センターを設立したほか、内閣府がムーンショット型研究開発制度において「2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現」を目標として掲げる*19など、政府主導の研究開発も始まっている。これらの研究開発は、少子高齢化に伴う労働力不足や医療・介護費の高騰など、社会課題の解決に向けた人間拡張の社会実装を目指しており、人間拡張の発展とそれに伴う社会変化は今後加速していくものと期待される。
ここまで述べた通り人間拡張は多様な適用範囲や活用方法が想定され、社会実装は段階的に進むと考えられる。まずは、危険作業や医療・介護などの人間拡張の恩恵が大きく他手法による代替が困難な場面で活用が進み、「デバイスとの一体感」の向上に伴い製造業、サービス業、娯楽、生活などと拡大していくだろう。将来的に人間拡張を日常で利用可能とするためには、我々自身が人間拡張を環境・状況に合わせて効果的に利用するスキルや、人間拡張による社会変化に柔軟に適応するスキルを身に付けていくことも必要である。人間拡張を実現するデバイスの研究開発の進展と、人間拡張の利活用への適応の双方が組み合わさることで、様々な社会課題を克服した未来が訪れるのではないだろうか。
注
- *1)ロボットスーツ、パワードスーツとも呼ばれる。
- *2)Artificial Intelligence、人工知能
- *3)Virtual Reality、仮想現実
- *4)Augmented Reality、拡張現実
- *5)Mixed Reality 複合現実
- *6)Haptics、触覚
- *7)暦本純一 監修「オーグメンテッド・ヒューマン AIと人体科学の融合による人機一体、究極のIF が創る未来」株式会社エヌ・ティー・エス、(2018年)
- *8)
- *9)
- *10)
- *11)
- *12)超音波を発生し、はね返ってきた超音波を探知する装置
- *13)
- *14)
- *15)
- *16)銀メッキを施した短繊維(導電性繊維)を、表面が柔らかくなるように植毛した電極
- *17)
- *18)
- *19)
参考文献
- 1.
【特集】さよなら重労働、パワーアシストスーツ“普及元年”で変わるもの〈株探トップ特集〉(株探、株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド)
- 2.
力触覚を伝え、記録、編集するリアルハプティクス技術(Medtec Japan、インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社)
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
脳波のモニタリングと機械学習で、人間の学習効率が2倍に!? バイオフィードバック装置による実験が進行中(livedoor NEWS、LINE 株式会社)
- 8.
- 9.
- 10.国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 技術戦略研究センター「コロナ渦後の社会変化と期待されるイノベーション像」(2020年)
(PDF/6,450KB) - 11.
- 12.
- 13.
細やかな触感を伝えるテレイグジスタンス遠隔操作ロボットを開発(国立研究開発法人 科学技術振興機構、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)
- 14.
慶應・野崎研、リアルハプティクスで力触覚を伝える双腕ロボットアームを開発(Impress Watch、株式会社インプレス)
- 15.
次世代ゴムはロボットの皮膚や筋肉になる 感じて動くゴム「e-Rubber」豊田合成・慶應大が共同開発、ロボデックスで展示へ(ロボスタ、ロボットスタート株式会社)
- 16.雑賀隆史「ロボット手術の現況と展望」岡山医学会雑誌、第123巻、pp.63-64
(PDF/1,057KB)
本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。
レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。