環境エネルギー第2部 コンサルタント 後藤 嘉孝
CLP規則に基づく中毒センターへの届出制度
2017年3月22日に欧州CLP規則の改正が行われ、製品をEU域内に上市する事業者(主に輸入者と川下ユーザー)が、危険有害性があると分類された混合物の情報を中毒センター(Poisoncentres)に対して、欧州における共通様式で情報提供を義務付けることとなった。
ここでは、CLP規則第45条及び緊急時の健康への対応に関する情報の調和に関するCLP規則の付属書VIII の施行に関する文書である「Guidance on harmonised informationrelating to emergency health response ?Annex VIII to CLP(Version 3.0)」より、新しい規則の内容と今後の利活用の展開を簡単に紹介する。
新規則における中毒センターへの情報登録義務は2021年1月1日より消費者用途の混合物*5及び業務用途の混合物に、そして2024年1月1日より工業用途の混合物に適用されることが見込まれている。ただし、既に市場に出回っており、かつ加盟国の中毒センターに情報が届け出られている製品については、届出情報に変更が生じない場合に限り、2025年1月1日までの移行期間が設けられている。
新規則において、図表8が事業者の情報提供すべき項目であり、Poison Centre Notification(PCN)formatに従って作成される必要がある。
この中で特に注目すべき新しい内容として、混合物組成又は製品特有のコードである固有の配合識別子(Unique Formula Identifier; UFI)の届出及びラベル表示(及び工業用途の場合にはSDS)を行う必要がある点である。
ユーザーは、中毒等の事故が起きたときに、中毒センターにUFIの番号を伝えることによって、毒性情報や医療情報等必要な情報が得られるとしている。
一方、事業者にとってはSDS記載内容以上の詳細な成分情報の開示(注:ただし、濃度範囲での登録が認められている)が求められることになり、また前述のUFIのラベルへの追記等の対応など、負荷は大きいことが予想される。
また欧州化学物質庁(ECHA)は、危険有害性のある混合物の情報を記載する文書の作成と提出を支援するポータルサイトを公表しており、申請に必要な各種支援ツール(UFI作成ツール、EuPCS選定システム及びPCNのための書類一式作成のためのIUCLID 6又はIUCLID Cloud)をダウンロードできる。
図表8 事業者が中毒センターに提供すべき情報の要件
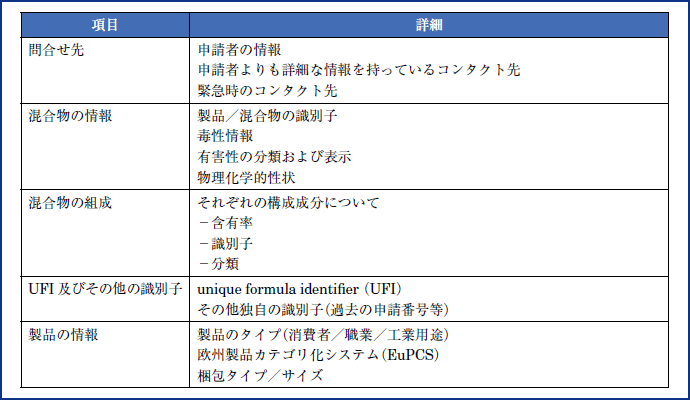
(資料)Guidance on harmonised informaton relating to emergency health response -Annex VIII to CLP (Version3.0)より、みずほ情報総研にて作成
図表9 UFI コードの活用シナリオ
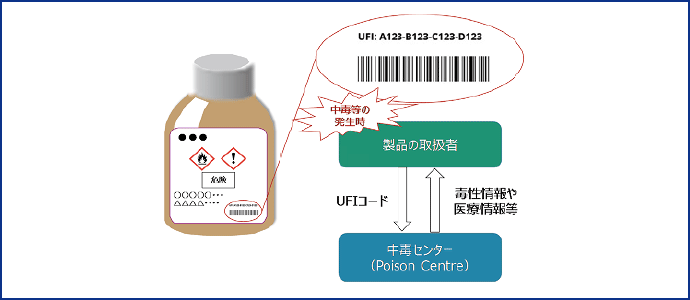
(資料)みずほ情報総研にて作成
図表10 CLP 規則における第45条緊急健康対応のための情報の利用目的
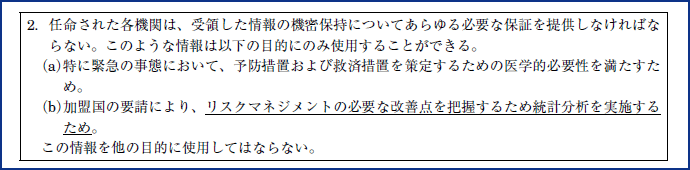
(資料)CLP規則第45条2項をみずほ情報総研が翻訳。下線は筆者が編集している。
今後の展望
リスクアセスメント支援ツールによって、事業者は簡単に化学物質のリスクを把握し、対策等を検討できるようになったが、特に中小規模の事業所においては、「リスクアセスメント実施方法がわからない」や「専門人材不足」*6よってリスクアセスメントが進んでいない事業場も多いと想像される。そのため国として、その実態を把握し、何らかの対策を進めていく必要がある。
第13次労働災害防止計画においては、労働現場における化学物質の取扱い等について「国がこうした事案を把握できる仕組みがないこと」から、対策の例として「化学物質による職業性疾病を疑わせる事例を把握した場合に国に報告がなされる仕組みづくり」を挙げている。
欧州においては、前述の中毒センターの届出によって、巨大な化学品データベースが作られてようとしている。当該データベースはCLP規則45条の目的にもある通り、緊急時の対応に活用されるのはもちろん、行政機関における化学物質の取扱い情報の把握・分析に用いられると考えられる。
我が国においても、欧州における化学品の届出制度は、我が国の職場における化学物質の取扱い実態把握に向けて、多いに参考になるものと考えられる。
そのため、引続き諸外国における化学物質管理の届出制度やそのデータ利活用に係る進展に注目することが望まれる。
注
- *1)安全データシート。取り扱い物質に関する情報(毒性情報、取り扱い方法、法規制情報等)が記載されている。
- *2)欧州における化学品の分類、ラベル表示、包装・梱包に関する規則のこと
- *3)CLP規則第45条の下に欧州加盟国は有害性混合物の成分に関する情報を受理するための指名された機関のことで、中毒センター(Poison centres)と呼ばれる。
- *4)実測の結果はサンプル数2であり、日内変動及び日間変動を考慮すると、幾何標準偏差(GSD)=2であれば、平均値に対して測定結果は最大3倍程度の幅を持つと考えられるが、推計値はいずれも殆どその範囲に収まっていることから、評価結果は「近い値が得られた」と判断した。なお、ECETOCの結果がやや過小に推計されている理由として、当該PROCでは少量(mL単位)の取り扱いが想定されているため、L単位を取り扱う今回の作業に対してばく露がやや過小になっていると考えられる。
- *5)当初は2020年1月1日からの適用を予定していたが延期された。
- *6)労働安全衛生調査(平成29年)によると、義務対象物質全てについてリスクアセスメントを実施している事業場の割合は53%(従業員50人未満の企業では実施率は4割以下)であり、未実施の理由は「十分な知識を持った人材がいない」55%、「実施方法が分からない」35%などが挙げられている。
参考文献
- 1.化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針(平成27年9月18日付け公示第3号)
- 2.
- 3.
Guidance on Information Requirements and Chemical Safety Assessment, Chapter R.14:Occupational exposure assessment, Version 3.0 August 2016
- 4.村井政志、馬場左起子「実験室等の有害物少量取扱い作業場におけるばく露評価のための各種気中濃度測定方法の活用─自律的管理のためのばく露濃度の推定─」労働安全衛生研究、Vol. 3, No.2, pp.129-136(2010年)
- 5.
- 6.厚生労働省「第13次労働災害防止計画(2018年度~2022年度)」
- 7.Regulation(EC)No 1272/2008 on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures (CLPRegulation)
本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。
レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。