社会政策コンサルティング部
チーフコンサルタント 高橋 正樹
任意後見制度を用いた認知症への対策
(1)好事例紹介(品川成年後見センター)
上記調査研究において好事例として取り上げた品川成年後見センターについて紹介する。品川成年後見センターは、品川区社会福祉協議会が運営する、高齢者や障害者の方々が地域で安心して生活できるよう、「成年後見制度」の情報提供・相談・申立手続きの支援をしているセンターである。
品川成年後見センターでは、任意後見制度を含めた総合的サービスを提供しており、任意後見契約に加えて、サポート契約や死後事務委任契約などの契約を同時に締結することで、本人が元気な段階から亡くなった後まで一貫した支援をおこなっている。このような社会福祉協議会による一貫したサービスは、認知症対策として非常に長期的かつ広範囲なサポートであり、認知症高齢者にとって心強いサービスとなっている。
図表7 任意後見契約の活用の好事例
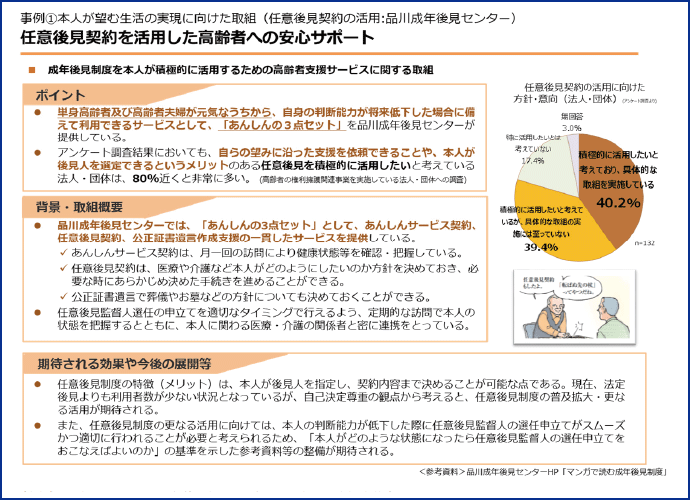
(資料)みずほ情報総研「厚生労働省平成30年度老人保健健康増進等事業
認知症の人の成年後見制度の利用における保佐・補助の活用及び成年後見人の確保に関する調査研究事業」
図表8 任意後見と信託の活用スキーム例
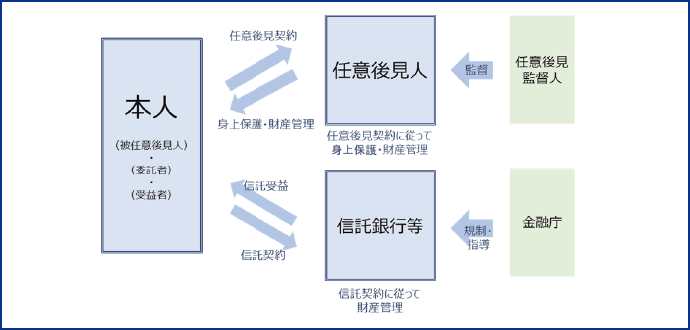
(資料)みずほ情報総研作成
(2) さらなる経済活動への対策(任意後見と信託の活用)
近年、任意後見の発展型として任意後見と信託との併用が注目されている。これまでも成年後見には後見制度支援信託があり、これは日常的な(小口)資金と、日常的ではない(大口)資金を区別して、詐欺などの被害防止、本人及び支援者、関係者による資金の使い込み防止などの効果がある信託制度である。また、このような制度に類似した後見制度支援預金もサービスとして開始されているところである。
発展型としての任意後見と信託の活用においては、上記のような資産の保全目的のみならず、相続や事業承継、持ち家等の不動産売却など、認知症高齢者が抱える経済活動の課題解決の有用な選択肢として期待される。
理由としては、任意後見は、本人が自由に設計できる上に任意後見監督人による管理体制があり、安全性が高いというメリットがある。加えて、信託による財産管理では受益者と受託者を分けることができるため資産に対するコントロール力を集中させながら経済的なメリットを分散できるなど、財産管理のスキームが組みやすい点がメリットである。特に相続や事業承継など複数利害関係者の調整に効果を発揮できるものと考えられる。信託銀行などが扱う商事信託では、財産を強固に保全できる点や高齢者向けの医療介護費等の支払代行サービスなどが利用できることが、支援のサポートになると思われる。今後、このような高齢者向け金融サービスの発展と共に、任意後見の活用がさらに促進されることが期待される。
おわりに
地域共生社会の時代を迎え、認知症に対する社会の支援力は着実に強化されてきている。一方で、日常生活の世話や身体的な介護以外での経済活動に対する認知症への対策は、発展途上となっている部分も多いと考えられる。任意後見制度は、認知症により判断能力が不十分となってしまうことに備えて本人が望む生活の実現を支援する制度である。本人の意思を尊重しながら本人の生活を法的に保護できる仕組みとなっている。利用者が増加しているところであるが、更なる活用及び利用促進が期待されるところである。
また、成年後見制度利用促進に向けた体制整備として、地域の権利擁護支援および成年後見制度利用促進機能の強化を進める中核機関の設置が全国にて進められている。今後、地域における権利擁護支援のネットワークが広がっていくことが計画されており、権利擁護の支援を受けやすい環境が広がっていくことが期待される。
認知症への対策では、本人がどのような状況であるのかを見定め、今後の人生計画について本人及び支援者が共に検討し、一つ一つ具体的に行動につなげていくことが大切である。長期的な視点をもって認知症の進行によって訪れる判断能力の低下と身体機能の低下の両面に備えるべく、本人にとって充実した人生を歩む方法について支援者・関係者の方々と話し合うことが何よりも重要と考えられる。本レポートにおける調査結果及び事例が一助になれば幸いである。
本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。
レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。