環境エネルギー第1部 渡邉 絵里子
ChLは我が国の化学物質管理手法として適用しうるか?
(1)導入可能性(導入に係る課題や障壁)
ChLは、サプライヤーがユーザーにおける化学物質管理の適正化に深く関与するものであるが、この際、サプライヤーには化学物質の使用工程に対する専門性や知見が必要となる。また、そうした知見を有していたとしても、複数のユーザー企業に対してそれぞれ適正化を行うのは非効率的なサービス提供であるため、費用対効果が悪ければサプライヤーはそうしたサービス提供を実施しない可能性が高い。
こうしたChL導入の障壁となりうる事項を以下の図表4に仮説として整理した。(サプライヤーがChLの取り組みに対してメリットを感じられるか?という課題については(2)将来性にて整理する。)
この仮説をまとめると、「比較的用途が限定される化学物質(主にプロセスケミカル)を製造するサプライヤーが、ユーザーに直販しているパターンにおいて、化学物質の使用工程に関する専門性を有する設備機器メーカーや外部有識者も参加すれば取り組むことができそう」である。これは我が国に限らず、世界でChLが普及する際にも同様のことが言えると考えられる。
この仮説を踏まえた、ChL を活用した化学物質管理のイメージを図表5に示す。これまでの「自主管理」は、業界団体による横のつながりや地域の工業地域での取り組みに関する情報共有の機会はあっても、あくまで実施するのは「事業者ごと」であった。しかし、事業者ごとの自主管理ではなく、削減対象となる化学物質のサプライヤーやユーザー、化学物質を取り扱う設備機器メーカー等を含めた、ビジネスに係るエコシステム全体で取り組み、管理コストを分配することができれば、排出量削減の推進・効率化につながる可能性があると考えられる。
なお、ChLと類似している取組として、民間による省エネの取組推進として実施されてきたESCO事業(12)がある。中小企業の場合は、省エネルギーは原資として少なすぎるためにビジネスとして成り立たず、効果は限定的であったとの指摘も存在しており(13)、ChLにおいても採算性については今後慎重な検討が必要であると考えられる。
図表4 ChL 導入に関する障壁
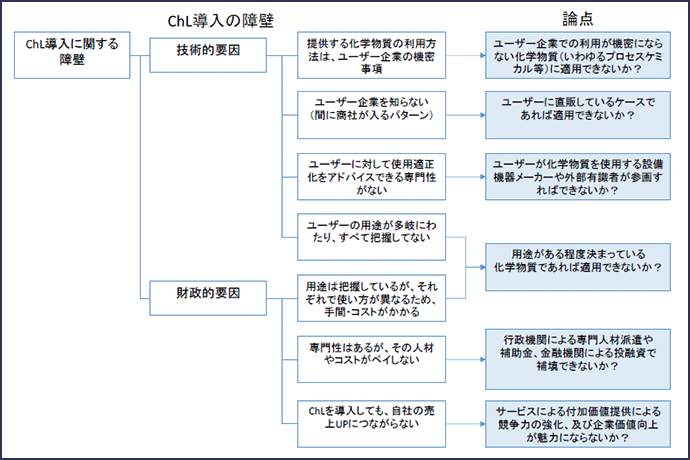
- (資料)みずほ情報総研作成
図表5 新たな化学物質管理エコシステムによる化学物質管理の在り方
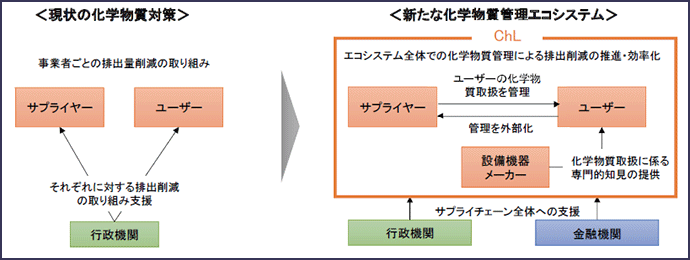
- (資料)みずほ情報総研作成
(2)将来性
ChLを含むサービス型ビジネスモデルが注目を集める背景には、顧客への提供価値をモノ自体の機能に依存しないビジネスが求められ始めてきたこと(「モノ」から「コト」)等があると考えられる。
また、欧州CEにおいては、サービス型ビジネスモデルがCE促進のためのビジネスモデルの一つとして欧州等の成長戦略で取り上げられている。2019年には、Black Rockとエレン・マッカーサ―財団による世界発のサーキュラー・エコノミーファンドが立ち上がる等、今後欧州企業のみならず、国際的にサービス型ビジネスモデルに取り組む企業への期待が高まることが予想され、我が国においてもCE促進のために持続可能なビジネスモデルへの転換を求められる可能性が高い。
我が国の化学物質管理はこれまで「規制と自主管理のベストミックス」による化学物質管理が進められてきたが、サービス型ビジネスモデルへの転換により、中長期的に投資が集まり企業価値が向上しうるのであれば、化学物質の自主管理は積極的に自主管理に取り組むインセンティブとなり得る。いわば、企業価値を下げないための「守り」の自主管理から企業価値を積極的に上げるための「攻め」の自主管理への転換とも呼べるだろう。
こうした国際的な潮流の変化や国内の更なる化学物質排出抑制の必要性を踏まえると、今後、我が国におけるChL等のサービス型ビジネスモデルの導入に関する機運は高まっていくものと予想される。
おわりに
本稿では、ChLが我が国で受け入れられるかについて、「導入可能性」及び「将来性」の観点で整理した。
ChLは万能なツールではなく、採算性を始めとした諸条件については、より詳細なシミュレーションや実証試験が必要となる。また、ビジネスモデルの転換は一朝一夕に進むものではない。
しかし、そうした課題を着実に解決しながら、これまでの「規制と自主管理のベストミックス」にChLのような新たなサービス型ビジネスモデルを組み合わせ、サプライヤーや設備機器メーカーも巻き込んだエコシステム全体での「攻め」の自主管理に取り組んでいくことが、今後の我が国における持続可能なビジネスの発展と化学物質の更なる自主管理との両立につながるものと期待される。
注
- *1)SAICM国内実施計画は、我が国におけるSAICMに沿った化学物質管理に関するこれまでの取り組みを概観するとともに、WSSD2020年目標(人の健康と環境にもたらす著しい悪影響を最小化する方法で使用、生産されることを2020年までに達成する)の達成に向けた今後の戦略を示すものとして策定。
- *2)経済産業省(2019)平成30年度化学物質安全対策(レスポンシブル・ケア活動におけるリスク情報を活用した地域対話の在り方に関する研究)
- *3)地球規模の環境課題の設定、政策立案者の支援、国連システム内にあって持続可能な開発の取り組みの中で環境に関連した活動の推進等を行う、環境分野における国連の主要な機関。
- *4)Schwager et al., (2016) Exploring Green Chemistry,Sustainable Chemistry and innovative business models
- *5)Jakl/Schwager (2010) Chemical LeasingGoes Global Selling ServiCEInstead of Barrels: A Win-Win Business Model for Environment and Industry
- *6)開発途上国や市場経済移行国において包摂的で持続可能な産業開発(Inclusive and Sustainable IndustrialDevelopment)を促進し、これらの国々の持続的な経済の発展を支援する機関。
- *7)UNIDO (2016) GLOBAL PROMOTION AND IMPLEMENTATION OF CHEMICAL LeasingBUSINESS MODELS IN INDUSTRY
- *8)OECD (2017) The Economic Features of Chemical Leasing
- *9)
- *10)EUROPEAN COMMISSION (2020) Chemicals Strategy for Sustainability Towards a Toxic-Free Environment, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN ARLIAMENT,THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS
- *11)
Chemical Leasingofficially recognized by the Government of Austria
- *12)エネルギー供給事業を行う事業者がESCO事業者としての認定を受け、顧客の省エネの取組(省エネ改に関する事業費等を保障)する仕組みである。エネルギーのサプライヤー(ESCO事業者)が、エネルギーのユーザー(顧客)における省エネの取組を支援するもの。
- *13)杉山大志・木村宰・野田冬彦共著「省エネルギー政策論」
本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。
レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。