ビジネス企画部 須田 陽子
対象範囲の決定のために整理しておくこと
Where|どこでテレワークを行うのか ―利用場面の定義
テレワークでは事業所外で会社の「情報資産」を取り扱うことになります。情報資産がウィルスの感染、テレワーク端末や記録媒体の紛失・盗難、通信内容の盗聴などの驚異にさらされやすくなります。
セキュリティの方針や行動指針に基づいて安全な利用を図るために、どのような場面での利用が想定されるかを洗い出し、それぞれのケースに合わせて保護するべき資産やリスクへの対策を考える必要があります。
暫定的措置
自宅でのテレワークが前提となりますが、病院や避難所など暫定的措置を決定した事由に合わせた場所も想定する場合があります。
恒久的措置
業務やライフステージから想定される場所を中心に、柔軟なシチュエーションを設定する一方、リスクへの対策や禁止事項を徹底し、セキュリティの確保を行います。
左右スクロールで表全体を閲覧できます
| 在宅勤務 | ||
|---|---|---|

|
自宅 |
通勤負担が軽減し、時間を有効に活用することができます。育児・介護期の従業員のキャリアの継続、通勤が困難な従業員の就労継続に効果が期待できます。 |
| 施設利用型勤務 | ||
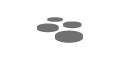
|
サテライト・オフィス |
他の事業所や遠隔勤務用の施設を就業場所とする働き方。自宅から近い場合は、通勤時間も削減することができ、遠隔勤務では組織の活性化や地方創生などが期待されています。 |
| モバイルワーク | ||

|
カフェ |
移動中や顧客先などを就業場所に含める働き方。営業などで頻繁に外出する業務の場合、隙間時間を利用した効率的な業務によって、生産性向上をはかります。 |
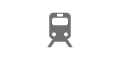
|
公共施設 |
|
Who|誰がテレワークを行うのか ―対象者の抽出
感染症や災害などの緊急事態における暫定的措置では、できるだけすべての従業員を対象に、スピード感をもって進めることが重要です。ビジネスの停止が想定される場合は、職種単位ではなく業務単位でグルーピングを行い、一部業務のテレワーク化が実施できるかを検討します。このとき、「従業員を守る」観点で経営判断を行った上で、優先順位を決定する必要があります。
一方で恒久的措置の場合は、対象者を選定する場合にもさまざまな範囲が考えられます。例えば、育児・介護などの特別な事情がある特定の従業員に限定するのか、その他の一般従業員も含めるか、非正規雇用者も含めるか、などです。しかし、働き方改革を進める上ではテレワークを対象とする従業員を増やし、従業員の各々がフレキシブルな働き方を選べる環境の整備を目指すことが望ましいと言えます。
また、特定の従業員だけを対象にした場合、現場の不公平感から特定従業員のテレワーク実施が困難になるというケースもあります。対象者の選定にあたっては、関係者の理解を得られるよう明確な基準を設けること、そして対象者が本人の判断でテレワークの実施を決定できる環境づくりが重要です。
暫定的措置
- 全従業員、または喫緊の課題の該当者が中心
- 業務単位でグルーピングを行い、一部業務のテレワーク化も検討し、「従業員を守る」観点で経営判断を行う
恒久的措置
- 育児・介護期、高齢などのメリットを享受しやすいライフステージの従業員が中心
- 初期段階では、試行的に導入する部署を選定し、効果検証を行った上で徐々に対象者を拡大
What|何を利用してテレワークを行うのか ―テレワークの手段
対象者の抽出と同時に、「何をやるのか」を考えておく必要があり、また何を選定するかによって策定するべき規定や手続きに影響します。例えば暫定的措置では、急なテレワークへの切り替えによって仕事内容に制限が生じてしまう可能性があります。あらかじめ業務の範囲や内容を確認し、オフィスに近い環境を整備することで、生産性の維持を目指します。
また、どのような手段であっても、デバイスの準備、通信環境の確保、セキュリティの強化の3点は必ず検討しなければなりません。
《テレワークで検討するテクノロジーやサービスの例》
| テレワークに必須となる環境 | ||
|---|---|---|
| デバイス | ||
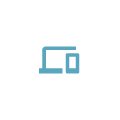
|
|
業務での利用は、PCを必要とするケースが多いため、従業員へノートPCが支給されているか、どのようにネットワークへ接続するか、が論点となります。 |
| 通信環境 | ||
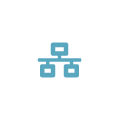
|
|
テレワーク導入によって自社の通信環境の利用者が増え、Web会議を行うと通信環境の不備で会議が実質的に成り立たないケースもよく耳にします。 |
| セキュリティ | ||
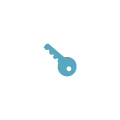
|
|
端末をオフィスの外に持ち出して業務を行う場合、盗難・紛失の他、公衆Wi-Fiの使用や不正ソフトウェアのダウンロードなどが考えられます。セキュリティは、大きく分けて3つの対策を検討します。
|
左右スクロールで表全体を閲覧できます
| 業務によって選定される環境 | |
|---|---|
| コミュニケーション手段 | |

|
|
| 勤怠管理 | |

|
|
| 事務手続き | |

|
|
| 情報/コンテンツ | |

|
|
最適な環境は業務によって異なる
テクノロジーとサービスの選択肢は多様化していますが、求められるスペックは業務によって異なります。何が最適かは一概には言えず、また緊急的措置と恒久的措置では、異なるインフラ環境が用意される可能性もあります。
暫定的措置によって導入した後、恒久的措置へとシフトする際には、暫定的措置によって整備された環境に過度に引きずられないように留意する必要があります。
How|どのようにテレワークを行うのか ―実施方法の策定
暫定的措置では、段階的な環境整備に合わせてテレワークに切り替えることができる対象者から順次移行を促していくことになるでしょう。一方で恒久的措置として実施する場合、テレワーク化の試行段階に合わせ、対象者やテレワークの頻度を拡大していくアプローチを検討します。
テレワークを実現するためには、まずテレワークのプロジェクトチームとなるCoE(Center of Excellence)を設置し、継続的な改善を行うオペレーションを確立します。
《 導入目的の例 》
暫定的措置
段階的な環境整備に合わせ、テレワークが可能である対象者から順次移行
左右スクロールで表全体を閲覧できます
| 対象 |
全社的/部分的 |
|---|---|
| 拡大のアプローチ |
全社的拡大 |
恒久的措置
試行段階に合わせ、対象者やテレワークの頻度を拡大
左右スクロールで表全体を閲覧できます
| 対象 |
部分的/条件付き |
|---|---|
| 拡大のアプローチ |
段階的拡大 |
| モデル例 | |
|---|---|
ステップ1 |
既に「事業外みなし労働時間制」で働いている外勤ワーカー |
ステップ2 |
管理職(特に中間管理職) |
ステップ3 |
一般従業員(内勤ワーカー)※新入社員は要検討 |
ステップ4 |
特定の従業員(介護や育児など) |
ステップ5 |
現場ワーカー(職種ごとに規定) |
終わりに
以上のように、導入の目的によってさまざまな違いがあります。自社の目的を明確化する際には、しっかりと今置かれている状況を把握し、それに沿った進め方で自社にどのような変化をもたらすのかをイメージしましょう。その上で、適切な導入ステップを踏んでいく必要があります。
また、暫定的措置によってテレワークの導入を実施した場合は、次のステップとして、恒久的措置へのシフトを検討するタイミングが来ると考えられます。最後に、そのときに備えてあらかじめ留意しておくべきポイントを例示します。
暫定的措置から恒久的措置へシフトするために留意しておくこと
メリットや成功を求めすぎない
大きな成果が見えないと、経営者や管理職は「実態が見えない」「テレワークで良くないことが起きないか?」といった不安から、次のステップへと進む機会を逸してしまいます。現場の何がどう変化したかといった小さな成功体験を受け止め、より広範囲にテレワークを広めていける可能性を模索することが大切です。
完璧なトレースを行わない
完璧な従業員の監視を求めすぎると、社内全体が疲弊してしまい、取り組みが継続しなくなる恐れがあります。 コミュニケーション、管理、モニタリングなどの頻度は、過度にならないよう適切に行いましょう。
無駄な管理を減らす
テレワークを導入したことによって余計に管理が大変になってしまい、対象者や関係者の労働時間が増えてしまっては、本末転倒です。働き方改革の観点からも、よりスムーズ、スマートになることを目指します。
注
本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。
レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。