情報通信研究部 コンサルタント 森 悠史
近年、人工衛星から得られる地球観測データを利用したさまざまなサービス(地球観測サービス)が展開されており、これまで宇宙とは無縁であった分野にも拡がりをみせている。本稿では、政府や産業界の現状や動向を概観するとともに、最新事例をもとに今後を展望する。
宇宙産業の現状と地球観測サービスの有望性
地球観測サービスは、宇宙産業の一部とされており、ここでは、まず、宇宙産業全体の産業規模について述べる。
米国の衛星産業協会(SIA:The SatelliteIndustry Association)が2018年6月に公表した「2018 State of the Satellite Industry Report」(1)によると、2017年における世界の宇宙経済(宇宙産業)の規模(売上高)は3,480億ドル(当時の為替レートで換算すると約39兆円。以下同じ。)である。このうち、有人宇宙飛行や非軌道宇宙船、政府支出等の非衛星産業を除く商業市場における衛星産業の規模は2,686億ドル(約30兆円)である。その内訳は衛星サービス(1,287億ドル、約14.5兆円)、衛星製造(155億ドル、約1.7兆円)、打ち上げ産業(46億ドル、約0.5兆円)、衛星通信・管制・電話設備等の地上機器(1,198億ドル、約13兆円)となっている(図表1)。因みに、我が国では官需と民需を併せた産業規模が、2016年度時点で約1.2兆円である(内閣府の試算)(2)。このうち、人工衛星(以降では単に「衛星」という。)を用いた測位、放送・通信、地球観測等のサービスに関連した産業である「宇宙利用産業」が約8,000億円、衛星、ロケット、地上設備などの製造に関連した産業である「宇宙機器産業」が約3,500億円である。集計した時期や集計対象に違いがある前提ではあるが、我が国宇宙産業の世界市場における比率は3%程度というのが現状である。
次に、地球観測サービスの規模について述べる。同サービスは、前述のSIAのレポートでは衛星サービスのひとつとして分類されており、その規模は2016年において20億ドル(約2,200億円)である(3)。衛星サービス全体の1%強の規模しかないものの、ここ数年は、毎年、前年比でプラス10%程度の成長をみせている。これは、衛星サービスの他の産業(衛星放送、衛星通信等)が数%しか成長していない中では、特筆すべき成長率であり、同レポートは、新規の競合先やパートナーシップの出現、衛星画像によるビジネスインテリジェンス製品への関心による投資などが高成長の要因であると分析している。 以降では、成長が著しい地球観測サービスについて、技術及び事業性の双方の観点から最新の動向及び今後の展望について述べる。まず第2節では地球観測の基礎知識として、観測の原理をセンサ別、計測する波長帯別に説明し、それらの得失について述べる。続く第3節では地球観測サービス成長の要因である「観測性能の向上」及び「データ利活用基盤のプラットフォーム化」について最新の動向を交えて解説する。前者では観測機器・システムの分解能の高度化について述べ、後者では国内外のプラットフォーム化の動向を紹介する。第4節では農業分野及び金融分野の先進的な事例を紹介し、最後の第5節において、最新動向を踏まえた上で、地球観測サービスの今後を展望する。
図表1 世界の宇宙産業の規模(2017年)
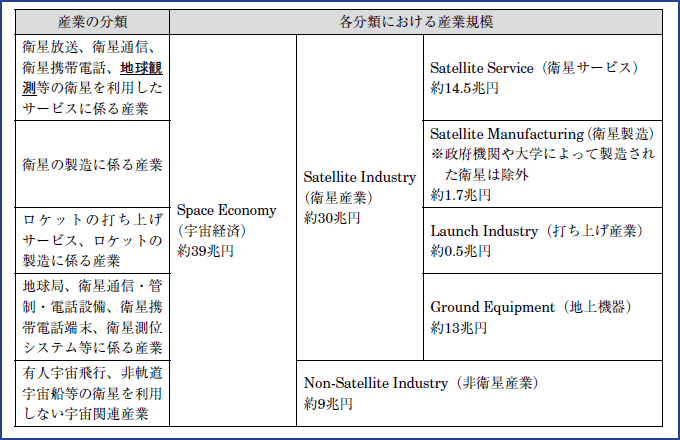
- (資料)2018 State of the Satellite Industry Reportをもとにみずほ情報総研作成
衛星による地球観測の原理
衛星による地球観測の最近の動向について述べる前に、観測の原理について簡単に説明する。因みに、地球観測といった場合、大気や降雨等の観測も含まれるが、ここでは特に、地表を観測する技術について、その原理を説明する。
衛星による地表観測では、衛星に搭載したさまざまなセンサで地表から到来する電磁波(光)を計測している。観測の目的や対象物によって計測する電磁波の波長(4)が異なるため、それぞれの波長に適したセンサが使い分けられている(図表2)。
可視光及び赤外光は光学センサで計測する。可視光(380~780nm)、近赤外光(780nm~2μm)、中赤外光(2~4μm)は、土地被覆(森林、草地、裸地、コンクリート、水面等)、地物(建造物、道路等)、植生分布、雲等の観測に用いられる。対象物に吸収されずに反射した太陽光を計測することで、逆に物質に吸収された波長がわかるため、その吸収特性から対象物の物質を特定することができる。ただし、雲の下や夜間の観測はできないという弱点がある。一方、遠赤外光(4μm~1mm)は、地上や海面等の対象物から放射される光を計測する。対象物の温度を計測できるため、海面、地表面、雲等の温度の観測や火山活動の観測等に用いられる。太陽光に依存しないため、夜間の観測が可能という特徴がある。
マイクロ波は1mm~1mの波長帯の電磁波であり、この波長帯に分類される電磁波を計測するセンサはマイクロ波センサと呼ばれ、能動型と受動型がある。能動型マイクロ波センサは衛星から地表にマイクロ波を照射し、その反射・散乱波を受信する。波長帯はXバンド(25.0~37.5mm)、Cバンド(37.5~75.0mm)、Lバンド(150~300mm)等である。合成開口レーダー(SAR:Synthetic Aperture Rader)は代表的な能動型マイクロ波センサであり、地表面の凹凸の状態を知ることができる。受動型マイクロ波センサは、地表面から発せられるマイクロ波を計測することで、海面や地表面の温度を観測することができる。波長帯はWバンド(2.7~4.0mm)、Kaバンド(7.5~11.5mm)、Kバンド(11.5~16.7mm)、Xバンド、Cバンド等である。遠赤外光と同じ理由で夜間の観測も可能である。能動型と受動型に共通の特徴として、全天候性という光学センサにはない長所がある。波長の長いマイクロ波は、雲や降雨の影響を受けずに地表を観測できるためである。
図表2 地表観測の原理
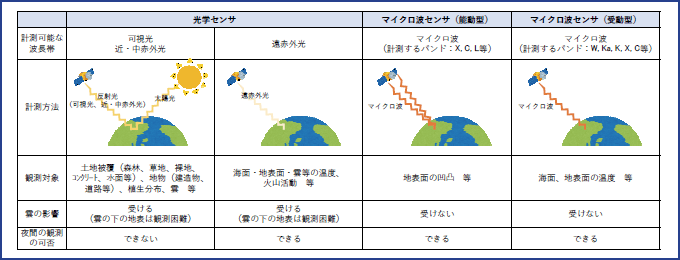
- (資料)みずほ情報総研作成
衛星による地球観測の最新動向
衛星による地球観測サービス成長の要因として、「観測性能の向上」及び「データ利用基盤のプラットフォーム化」が挙げられる。以下では、この2つの動向について事例を交えて解説する。
(1)最新動向[1] 〈観測性能の向上〉
近年打ち上げられた、または今後打ち上げ計画のある地球観測衛星の観測性能が格段に向上している。地表観測の性能はさまざまな指標によって表されるが、ここでは、空間分解能、時間分解能、波長分解能に絞って、高性能化の動向を解説する。
空間分解能とは、地表の物体の大きさを識別する能力のことであり、メートル等の長さの単位で表され、値が小さいほど分解能が高く、小さな物体の認識や詳細な形状の観測が可能となる。かつては10mオーダーであったが、近年では欧州AIRBUS Defence & Space 社のPleiadesシリーズ(5)など1m以下の分解能を持つ衛星も登場している。因みに空間分解能と観測幅(観測できる範囲)はトレードオフの関係にあるため、用途によっては、空間分解能はそれほど高くないが、観測幅が大きな衛星が選択される場合もある。
時間分解能とは、同じ場所を観測する際の時間間隔のことであり、日等の時間の単位で表される。値が小さいほど分解能が高く、観測対象の時間変化を短い周期で捉えることができる。かつては数日~十数日程度であったが、近年では、複数の衛星を協調させて運用する「衛星コンステレーション」(コンステレーション(constellation)は星座の意。)と呼ばれる技術によって1日という分解能を実現した米国Planet社(6)のようなサービスもある。
波長分解能とは、波長の違いを識別する能力のことであり、nm等の長さの単位で表され、値が小さいほど観測対象の光の吸収特性を詳細に観測することができる。欧州宇宙機関(ESA:European Space Agency)が運用するSentinel-2(7)は、地上の植生分布、土壌や水の被覆等の陸域観測を主な目的としており、可視光を中心に443nm~2,190nmの波長帯のうち13波長を計測することができる。また、衛星搭載型ではないが、約400nm~2,500nmの波長帯を185波長で計測可能なハイパースペクトルセンサHISUI(8)が、2019年に国際宇宙ステーションに搭載される計画もある。
(2)最新動向[2] 〈データ利用基盤のプラットフォーム化〉
もうひとつの重要な動向として、データ利用基盤のプラットフォーム化が挙げられる。
地球観測データは官民のさまざまな機関が観測・提供を行っており、このうち政府系機関等が運用する衛星の観測データが無償化され始めている。例えば、米国航空宇宙局(NASA:National Aeronautics and Space Administration)/米国地質調査所(USGS:United States Geological Survey)のLandsat-8(9)、ESA のSentinel-2、経済産業省等により提供されるASTER(10)等は無償である。しかし、無償化だけでは利用者数は必ずしも伸びない。データの形式を揃え、提供機関を跨ったデータ解析を容易にするなど、利用者側の視点に立ったサービスの提供が必要である。そこで登場したのが、地球観測データの利用を促進する「プラットフォーム」である。
メガプラットフォーマと呼ばれるAmazon 社やGoogle 社は、それぞれ「Earth on AWS」(11)、「Google Earth Engine」(12)という名のプラットフォームを提供しており、Landsat-8、Sentinel-2等の地球観測データの利用が可能である。特徴的なのは、地球観測データだけではなく、地球観測データと建物や道路等の地物のラベルがセットになった機械学習用のデータセットや数値標高モデル(DEM:Digital Elevation Model)等もプラットフォームから取得できる点である。また、データ解析に必要な機械学習用のツールも用意されており、大容量のデータをダウンロードせずにクラウド上でデータ解析を行える点も利用者の利便性向上に貢献している。
一方、国内では、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)の「G-Portal(衛星データ提供システム)」(13)、内閣府の「衛星データ利用促進プラットフォーム)」(14)、文部科学省の「DIASデータ統合・解析システム」(15)、国立研究開発法人産業技術総合研究所の「MADAS(衛星データ検索システム)」(16)等がプラットフォーム上で一部のデータを無償提供しているが、利用は研究目的に限られている。こうした中、経済産業省は、産業利用目的としては日本初となる地球観測データ提供用のプラットフォーム「Tellus(テルース)」(17)の構築をさくらインターネット株式会社に委託し、整備を始めた。また、Tellusの開発及び新規企業の参入によるデータの利用促進等を目的として、当社を含むさまざまな分野の21組織が参画するアライアンス「xData Alliance」が発足した。Tellusは、β版が2018年12月に、正式版が2019年2月にリリースされ、光学センサ及びマイクロ波センサで観測されたデータの提供が予定されている。また、利用促進を図るための情報発信、宇宙分野へのデータサイエンティストの参画を図るためのコンテスト、データ解析を行うためのツール群、さらにはユーザが作成したツールを販売するための仕組みも提供される予定である。
- 本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。
- レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。