サイエンスソリューション部 チーフコンサルタント 茂木 春樹
グローバルイノベーション&エネルギー部 コンサルタント 佐藤 貴文
環境エネルギー第1部 チーフコンサルタント 吉田 郁哉
次世代、革新型蓄電池の技術動向
現在広く普及し、さらなる発展も期待されているリチウムイオン電池は、このまま技術開発が進めば、さらに高性能(高容量、高電位、高サイクル寿命)となっていくように見える。しかしながら、リチウムイオン電池の改良を重ねても高性能化には限界があることがわかっており、たとえば重量エネルギー密度の理論的限界値は、およそ662Wh/kgと算出されている(10)。一方でガソリンの重量エネルギー密度は12,000Wh/kg以上(11)もあり、ガソリン車なみの蓄エネルギー性能を電池に求めることはいかに困難かが分かる。
また、限られた資源量の問題も重要である。現在のところリチウムイオン電池をめぐる資源問題は大きく顕在化していないが、地球上で採掘できる金属の資源量には限界がある。よく話題に挙がるのは正極に用いられているコバルトであり、その調達リスクや需給見通しに、しばしば注目が集まっている(12)。また、電池内部で電荷の移動を担っているリチウム金属においても、同様に資源量の限界がある。地殻中の元素存在量を表現する数値として「クラーク数」があるが、蓄電池内を移動するイオンとして利用できる金属のクラーク数は、マグネシウムが約2、アルミニウムが約7.5、ナトリウムが約3であるのに対し、リチウムは0.006しかない。今後、電気自動車をはじめ蓄電池のニーズが爆発的に高まることが予想されるなか、いずれリチウム金属の枯渇問題が顕在化する可能性もある。
それでは、リチウムイオン電池を凌ぐ他の金属イオンを用いた蓄電池は実現できないのだろうか。あるいは、蓄電池そのものの構造を変えた新しい蓄電池は実現できないのだろうか。
NEDO「二次電池技術開発ロードマップ2013」によると、現在のリチウムイオン電池を凌ぐ高容量・高出力の革新的蓄電池の実現には、2030年頃に〝ブレークスルーが必要〟との記載があるものの、どの蓄電池技術がブレークスルーとなるのかについては明示されていない。これについて、「革新的なエネルギー関連技術の動向・利用に関する検討」(みずほ情報総研、NEDO委託、2015年)によると、現行のリチウムイオン電池のエネルギー密度をはるかに凌ぐ革新的電池としては、次世代リチウムイオン電池、金属イオン電池、金属空気電池といった蓄電池が挙げられている(図表7)が、どの蓄電池がポストリチウムイオン電池を担う主役となるかについては、現時点では明らかでない。
本節では、これらのポストリチウムイオン電池となりうる次世代・革新型蓄電池を中心に、その特徴や課題、研究開発動向のトピックを述べていく。
図表7 重量エネルギー密度と体積エネルギー密度の関係
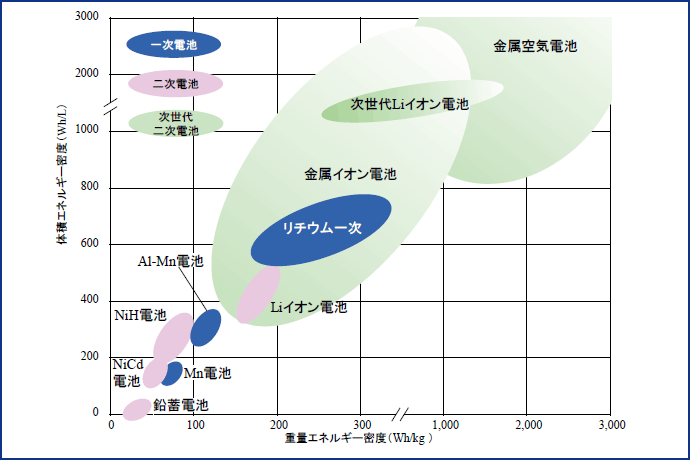
(資料)「革新的なエネルギー関連技術の動向・利用に関する検討」(みずほ情報総研、NEDO 委託、2015年)、データは石原達己「金属・空気2次電池の開発と最新技術」、小久見善八ら監修「図解 革新型蓄電池のすべて」、「Thermodynamic analysis on energy densities of batteries」(Chen-Xi Zuab ら)を参考に図化)
(1)全固体電池
全固体電池は、最近で最も報道を賑わせた蓄電池ではないだろうか。一言で説明してしまえば、従来型リチウム電池で使用される液体の電解質を固体の電解質で代替した電池である。しかしながら、報道されている全固体電池にはいくつか種類があることに注意が必要である。
まず、固体電解質には大きく無機系固体電解質と高分子系固体電解質が存在する。最近話題となっていたのは、前者の無機系固体電解質であり、粉状の物質をイメージすればよい。また、同じ無機系固体電解質を用いていても、薄膜型とバルク型の2種類の全固体電池が存在する。前者は既に実用化されているが、この薄膜型全固体電池は小型・小容量向けであり、自動車の駆動用蓄電池としては用いることができない。自動車の駆動用蓄電池として期待されているのはバルク型全固体電池であり、両者はまったく別の技術と言っても過言ではない。ここでは、このバルク型全固体リチウムイオン電池に着目して技術動向をまとめる。
全固体電池は1970年代から研究され始めたが、元々は内部抵抗が高いため高出力化に課題がある蓄電池とされていた。しかしながら現在では液系リチウムイオン電池より高出力化が可能とされており、全固体電池がここまでの注目を集めるに至った要因のひとつとなっている。全固体電池の高出力化を実現するにあたっては、大きく2つのブレークスルーが挙げられる。1つは、固体電解質の研究開発の進展である。従来の固体電解質では、液系電解質と比較してリチウムイオン伝導度が室温で一桁以上低く、蓄電池に適用しても高速な充放電ができない状況にあった。しかし、2011年に室温でも液系電解液と同等のリチウムイオン伝導度をもつ硫化物系固体電解質Li10GeP2S12が、東京工業大学のグループによって発見されたのを皮切りとして、2016年には同グループによって室温で液系電解質を凌駕するLi9.54Si1.74P1.44S11.7Cl0.3が発見された(13)。固体電解質には、他にも課題があるものの、室温におけるリチウムイオン伝導度が液系と同等かそれ以上になったことは、全固体電池の実用化に向けた大きな進展となっている。
2つ目のブレークスルーは、電極活物質と固体電解質の界面に数ナノメートル程の緩衝層を設けることで、全固体電池内部の反応に起因する内部抵抗を低減し、高出力化を実現したことが挙げられる。全固体電池で高速な充放電を行うためには、固体電解質のイオン伝導度向上だけでは不十分であり、化学反応が起こる電極活物質と固体電解質の界面における抵抗が問題であることを国立研究開発法人物質・材料研究機構の研究グループが突き止め、界面をニオブ酸リチウムLiNbO3などのリチウム酸化物で修飾して緩衝層を設けることで、内部抵抗を低減、高出力化を実現した(14)。どちらも国内の研究グループの手によって成し遂げられたことは、世界に誇るべき成果であるといえる。
それでもなお、全固体電池にはまだ様々な課題が残っており、現在も国の研究開発プロジェクトを通じて、産学官の総力を挙げて研究開発が進められている。たとえば、全固体電池は粉状の材料によって構成されることから、従来のリチウムイオン電池の製造プロセスをそのまま適用できないため、量産可能な製造プロセスを開発する必要がある。また、充放電によって電池内部の構造が壊れないよう高い圧力(15)による加圧拘束が必要であったり、固体電解質中で金属リチウムの析出が報告されたりするなど、全固体電池特有の課題も報告されている。
これらの課題を考慮すると、今後数年で実用化されたとしても、全固体電池のメリットを最大限に活かし、液系リチウムイオン電池を超えた性能および信頼性に達するまでには、まだ相当な時間がかかるのではないだろうか。今後も研究開発動向を注視し、実用化に向けた動向を詳細に追っていく必要がある。
(2)次世代リチウムイオン電池
次世代を担う蓄電池として、やはりリチウムイオン電池の技術動向を取り上げない訳にはいかないだろう。リチウムイオン電池の研究開発により、今後さらに高エネルギー密度化が進むことが予想されるが、これとトレードオフの関係にあるのが安全性の確保である。一般的なリチウムイオン電池では、有機電解液と負極に広く採用されているカーボンおよびセパレータは可燃性であり、金属酸化物で構成される正極からは材料によっては熱分解によって燃焼を助ける酸素が放出されるため、内部短絡等により充電されたエネルギーが一気に放出されると電池の破裂や場合によっては発火から火災に至る恐れがある。
現在では、バッテリマネジメントシステムによる電池の状態監視・制御技術の向上や製造プロセスにおける異物混入の排除、熱暴走しにくい電極材料であるLiFePO4やLi4Ti5O12の採用、耐熱性の高いセパレータの開発等、研究機関とメーカーの不断の努力により、安全性は飛躍的に向上してきている。しかしながら、それでもリチウムイオン電池搭載製品の普及拡大、ユーザーの使用過誤、海外無名メーカーの安価な製品の流通などを背景として、発火や火災に至る事故はいまだに発生し続けている(16)。また、毎年発生している大規模地震・災害や事故による圧壊、外部の火災など外的要因で発火、破裂が起こる可能性は、可燃性材料を用いる限り、どんなに安全性を追求しても最後まで残ることになる。
一方で、約4Vというリチウムイオン電池の高い電圧に耐えることができ、発火性を持たず高いイオン伝導性を示す電解液の存在が東京大学らの研究グループによって明らかにされ、安全性向上に資する発見として注目を集めている。
従来、リチウムイオン電池の電解液にはリチウム塩を溶解した炭酸エステル類が主として採用されており、これらは幅広い電位で安定であることや安価であることから広く採用されているが、発火点が低くリチウムイオン電池が熱暴走した際に発火する要因となっている。水系の電解液を用いれば可燃性という課題は解決できるが、最大4Vという高電圧に起因する水の電気分解や、水とリチウム金属の反応により水素ガスが発生するために水系の電解液は使えないというのがリチウムイオン電池の常識であった。
しかしながら、2016年には水をベースとしたリチウムイオン伝導性液体、水の電気分解される電圧を超える3V以上で作動するリチウムイオン電池が実現された(17)ほか、2017年には[1]発火点を持たない、[2]200℃以上への温度上昇時で蒸気が発生し自己消火性を示す、[3]優れた電極反応耐久性を示す電解液が発表され大いに注目を集めた(18)。
このような電解液の急速な研究進展により、前述の全固体電池に劣らない安全性を示す液体系リチウムイオン電池の実現が可能性を帯びてきた。液体の電解質を利用するということは、既に導入済みの量産ラインでも軽微な改変により適用できる可能性があり、製造コストを低く抑えつつ安全性を飛躍的に高めることができるポテンシャルがあるとも言える。負極にシリコン、セパレータにフッ素系樹脂、そして前述の電解液を利用すれば、原料価格が高くなる傾向はあるが、全体的に可燃性を示す材料を利用しない、全固体電池と同レベルの安全性を備え持つリチウムイオン電池を近い将来実現できるかもしれない。
本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。
レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。
関連情報
この執筆者(茂木 春樹)はこちらも執筆しています
-
2018年1月10日
―本当に“使える”設計者CAEとは―
この執筆者(佐藤 貴文)はこちらも執筆しています
-
2019年12月10日
―自動車における「創エネ」のすすめ―
この執筆者(吉田 郁哉)はこちらも執筆しています
-
2019年6月13日
―セクターカップリングで拓く低炭素・省エネ、そして強靭な社会―