社会動向レポート
出力抑制シミュレーションによる蓄電池併設の効果の分析
再生可能エネルギーの現状と将来(2019年版)(2/4)
グローバルイノベーション&エネルギー部
コンサルタント 境澤 亮祐 コンサルタント 古林 知哉 チーフコンサルタント 蓮見 知弘
2.出力抑制シミュレーションによる蓄電池併設の効果の分析(続き)
2.2 シミュレーション結果
太陽光発電の出力抑制の頻度に関するルールは、国が定めており、地域と契約時期によって、年間の上限は[1]最大30日間まで(30日ルール)、[2]最大720時間まで(720時間ルール)、[3]無制限(指定ルール)の3つの区分で、事業者ごとに設定されている。また、出力抑制の時間が上限値に到達するまでは、事業者間の公平性の観点から、抑制時間が均等になるように、電力会社が調整している。しかしながら、上限時間を越えると、[3]の無制限ルールだけが出力抑制の対象となる仕組みになっている。2019年3月時点の九州電力管内で、新たに太陽光発電事業を新たに行う際は、[3]の無制限の抑制(指定ルール)が適用される。本シミュレーションでは、出力抑制が生じる指標として出力抑制率を「本来発電することが見込まれた電力量に対し、出力抑制によって発電することができなかった電力量の割合」と定義し、以後、この指標を使って3つのシナリオの分析を行うこととする。
2030年における指定ルールの太陽光発電の出力抑制率の結果を図表5に示す。この図表のとおり、[1]併設なしのシナリオでは、年間の出力制御率は21.7%であり、年間で21.7%の発電機会損失が発生することを意味する。次に、蓄電池を併設した場合の年間の出力制御率は、[2]100万kWシナリオでは17.8%、[3]200万kWシナリオでは13.9%となり、蓄電池の併設によって出力抑制率が4~8%低減することを示した。
指定ルールが適用されている太陽光発電事業者の出力抑制率を各月で表示したものを図表6に示す。全てのケースにおいて、3月から5月の春季、10月と11月の秋季にかけて出力抑制率が大きくなっている。これは夏季や冬季にくらべて冷暖房需要が小さく、電力の供給過剰が発生しやすくなるためである。次に、各ケースの出力抑制率を比較すると、蓄電池の利用による出力抑制率の低減効果が月ごとに異なっていることがわかる。例えば、シナリオ1とシナリオ3を比較すると、5月の出力抑制率の差は2%程度であるが、11月や2月、3月については20%ほどの低減効果が見られる。一方で、11月は、シナリオ1とシナリオ2の間で出力抑制率の乖離が大きくなっている。これは、10月までは、出力抑制の年間上限値である30日または720時間に到達しておらず、すべての事業者が平等に抑制されていたが、11月中に年間の抑制時間が上限に到達したため、指定ルールが適用された事業者の負担が大きくなったことが原因である。
その他、5月と2月で蓄電池効果に差が見られることについては、電力の供給過剰の絶対量が影響している。2月は、シナリオ3の200万kWの併設では、蓄電池を運用することで電力の供給過剰を回避できたが、5月においては回避できないほどの供給過剰が発生していることを意味している(図表7、8を参照)。
図表5 3つのシナリオにおける年間の出力抑制率
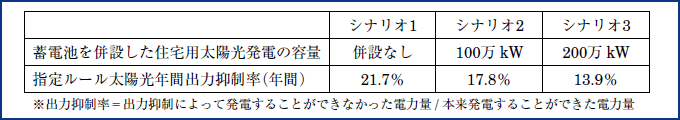
図表6 太陽光発電の出力抑制率の比較(月別:指定ルール)
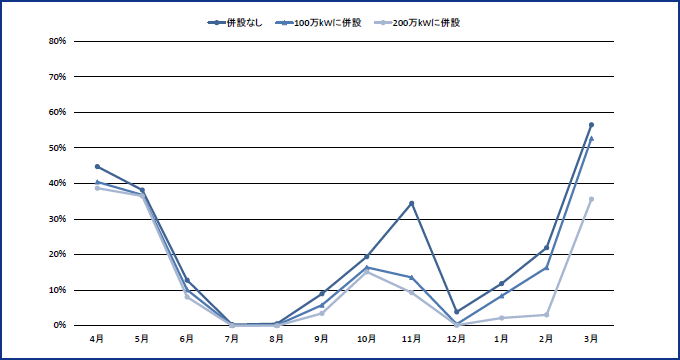
図表7 1時間ごとの太陽光発電の出力抑制率の比較(2月平均:指定ルール)
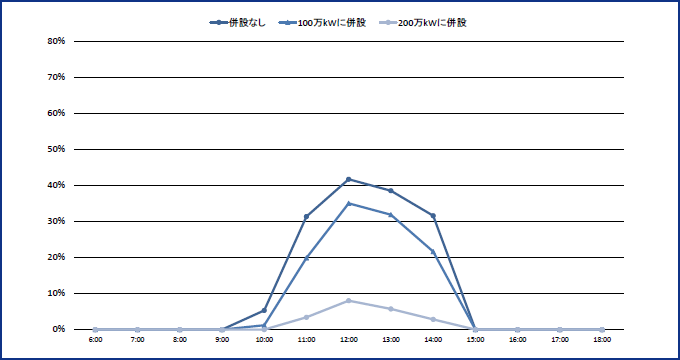
図表8 1時間ごとの太陽光発電の出力抑制率の比較(5月平均:指定ルール)
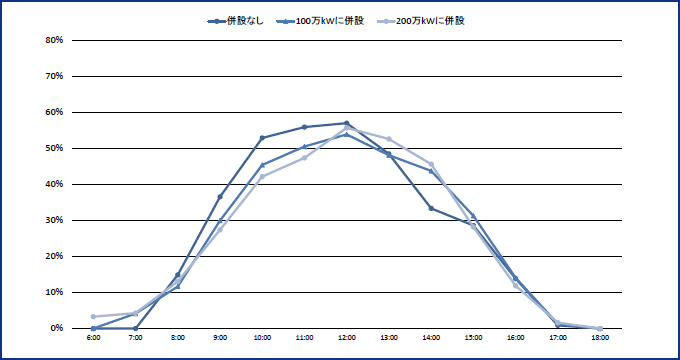
3.おわりに
本レポートでは、国が省エネ対策として推進している自家消費を目的とした蓄電池の導入が太陽光発電の出力抑制率に与える影響を分析した。その結果、住宅用太陽光発電に蓄電池を併設することは、電気料金の負担軽減だけでなく、太陽光発電事業者に課せられる年間の出力抑制率が4~8%程度低下し、再生可能エネルギーの利用可能量が向上することが明らかになった。一方で、電力の供給過剰量が大きい月では蓄電池に加えて何らかの対策が必要であることが示唆された。蓄電池は、日中の余剰電力を夜間に利用することができるので出力抑制率の低減に効果的だが、200万kW程度の蓄電池の導入では、電力の供給量と需要量のギャップが大きい5月における出力抑制率には波及しなかった。改善策としては、数日単位ではなく、季節をまたぐような時間スケールでの蓄電やPtG(Powerto Gas)に代表される新たな電力利用方法の検討、電力需要家のディマンドレスポンスを追加的な取り入れが期待される。
また、本レポートでは九州電力管内での電力供給量と需要量のバランスに関する出力抑制の評価を実施したが、さらに再生可能エネルギーの導入が進むと、同じ電力管内でも場所によって、送電線や変電設備の空き容量が異なることから、電力需要地や発電所の位置情報まで考慮した精緻な分析が求められる。今後、発電事業者は、設備導入地域近隣の送電容量を意識した発電見通しを計画的に検討することや、地域近隣での電力消費を想定し送電を最小限にする再生可能エネルギーの地産地消モデルの構築が必要となるだろう。
- 本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。
- レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。
関連情報
この執筆者(古林 知哉)はこちらも執筆しています
- 2019年6月3日
- 洋上風力発電導入のカギを握るSEPの動向
