多相流での流体移動
生成した油・ガスの移動は、現象的には石油生成以前の水の移動と同様の流体移動の一つであり、大局的には「ダルシーの法則」に従う。但し生成以前は、水という1相のみの移動であるが、油・ガスが生成した後は、「水・炭化水素」あるいは「水・油・ガス」という2相流あるいは3相流となる。
このためそのモデル化に際しては、
- 各相の流体移動を表現する複数のダルシーの法則による数式が必要である。
- それぞれの式における浸透率、粘性等の物性値は、各相のものを適用する。
- 「毛細管圧力(Capillary Pressure)」や「浮力(Buoyancy)」等の各相間に働く営力を考慮する。
- 生成による油・ガスという物質の湧き出し、つまり質量変化を考慮する。
という点に留意しなくてはならない。
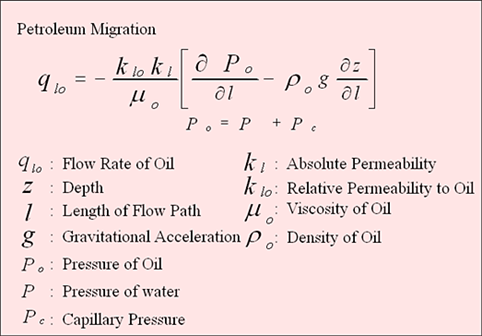
多相流における油移動を表現する数式(ダルシーの法則)
上図は、2あるいは3相流における油相の流量をダルシーの法則により表現した式(Bethke,1989年)であるが、上で述べたように、浸透率は絶対浸透率(kl)に油の相対浸透率(kro)を掛けた油相の有効浸透率であり、油の粘性(μo)を用いている。また営力では、油相の圧力(Po)を1相の時の圧力(P)に毛細管圧力(Pc)を加えたものとして与え、浮力を考慮するため標高差による営力の項には油の密度(ρo)を代入している。
なお、毛細管圧力は岩石が水に濡れている場合、径の小さい通路から大きい通路に移動する油には「正の営力」として、径の大きい通路から小さい通路に移動する油には「負の営力」として働く。キャップロックは後者の場合に相当し、毛細管圧力による負の営力の絶対値が、浮力等の他の正の営力の合計を上回れば、油は移動できなくなりトラップされることになる。
オイル・ガス排出の再現
油・ガスの移動は、大きく、
- 1)根源岩からキャリアベッドまでの「排出(1次移動)」
- 2)キャリアベッドに沿って、キッチンエリアから貯留岩に至る「2次移動」
に分けられるが、この内1排出(1次移動)は、
- 根源岩(泥岩)という極めて浸透率の低い岩石中の流体移動である。
- 石油生成に伴い発生する「生成圧力」が排出の営力になる可能性がある。
ことから、そのメカニズムが十分に解明されていない。そのため既存のソフトウエアの中で、排出現象を厳密に扱ったものはほとんどない。
油・ガス排出は、実際の堆積盆や坑井等で観察されにくい現象であるが、最近の研究結果によると、
- 1)油・ガスは「独立相」として排出される。(McAuliffe,1980)
- 2)排出の時期は、根源岩の「油飽和率」に支配されており、生成開始時期より遅れて始まる。(Tissot,1987;関口他1984年)
- 3)排出時の根源岩の油飽和率は「10~30%」である。(Rullkotter et al.,1988年)
- 4)排出効率は有機物に富む根源岩ほど良く、「約90%」に達する。(Cools et al.,1986年)
- 5)排出時の根源岩(頁岩)の絶対浸透率は「10(-4)~10(-5)md」である。(石油公団、1989;Sandvik and Mercer,1990年)
- 6)排出される油は「分別作用(Fractionation)」を受ける。
つまり「飽和炭化水素の方が、芳香族やNSO化合物より排出されやすい。」(Leythaeuser et al.,1987年)ということがわかってきている。
シミュレーションモデルは、これら観察事実を再現できるものでなくてはならないが、そのため排出営力の一つである可能性のある「生成圧力」については、当研究室(石油公団地質・地化学研究室)で室内実験と実験シミュレーターによる検討(大熊他、1991年)を行い、定量化とそのメカニズムの把握に取り組んでいる。
また、低浸透率の泥岩(根源岩)の物性値のうち実測が極めて困難な「相対浸透率曲線」についての検討も行っている(Okui and Waples,1991年)。幾つかの貯留岩(クリーンな砂岩)で実測された相対浸透率曲線が、その粒度(あるいは絶対浸透率)により系統的に変化することから、低浸透率な泥岩の曲線を外挿し推定した。
推定された泥岩の相対浸透率曲線では、鉱物マトリックスに吸着したり毛細管圧力により動けない水の割合(Irreducible Water Saturation)が高く、水、油それぞれの曲線が高水飽和率側に寄っている。またこの曲線は、石油生成開始直後は油生成量が少なく、根源岩孔隙中の油飽和率も低いが、生成が盛んとなり油飽和率が増加(水飽和率が減少)するにつれ、水相の相対浸透率が減少し、油飽和率が13%以上(水飽和率が87%以下)になると、油相の方が水相より動き易くなり、排出が盛んになることを示している。
この新しい相対浸透率曲線を用いて、排出現象をシミュレーションしてみると、深度(温度)増加に伴う生成・排出の様子を示しており、生成の様子はケロジェンの中で熱分解可能な部分(Reactive Kerogen)の質量減少で表されている。尚、根源岩はタイプIIで有機炭素量は3%である。これによると、
- 1)排出は生成のピークに始まっている。
- 2)排出時の根源岩の最大油飽和率は約25%である。
- 3)排出効率が良い。
- 4)ガスへのクラッキングが少なく、炭化水素の多くは油として排出されている。
ことが再現されており、堆積盆の観察事実と一致している。
2次移動の再現
2次移動をシミュレーションするためには、水の場合と同様、堆積盆のある地点における流体の全ての方向の「流入量」と「流出量」を「質量保存則」によって計算すれば良いが、但しその計算を各相について行う必要がある。
また、前に述べたように、石油生成に伴う物質量の変化を考慮するため、油の質量保存式に「生成量(Qo)」という項を加えている。
尚、堆積盆評価システムのプロトタイプでは、計算時間短縮のため、生成したガスを全量油に溶解させ、炭化水素相と水相の2相流として移動させており、移動する炭化水素のガス油比の変化によりガスの移動を仮に再現している。
これら2式を堆積盆の全ての地点で行えば2次移動の様子が、さらに各時間について行えばその歴史が再現できる。
出典:石油公団 地質・地化学研究室
「堆積盆評価システム」の概要-大型研究『原油・根源岩対比技術』における「堆積盆評価システム」の開発(その2)-石油の開発と備蓄 1991年8月
- 原理1.地質シミュレーションモデル
- 原理2.生成シミュレーションモデル
- 原理3.移動シミュレーションモデル
関連情報
おすすめソリューション
エネルギー分野の先端的な研究や豊富な知識・知見に基づき、地球環境問題や化石資源枯渇に関する政策・意思決定、技術評価などに対する充実した支援を行なっています。