社会政策コンサルティング部 研究主幹 仁科 幸一
入院診療と外来診療の補完関係は薄い
病床数が少ない県では患者は外来診療を選択し(あるいは選択を余儀なくされ)、病床数が多い県では入院する患者が多いために外来診療を受ける患者は少なくなるという一種の補完的な関係があると考えられる。その実態はどうなのだろうか。
図表5は、横軸に入院受療率、縦軸に外来受療率を、いずれも全国値を100とする指数にした散布図である。前述の仮説に従えば回帰直線は右肩下がりになるはずだが、傾きは小さいが右肩上がりになっている。両値の相関係数(R2)は0.22と低い。また、入院受療率と比べて外来受療率は都道府県間の差が小さい(3)。
つまり、病床数と相関の高い入院受療率と外来受療率とは相関が希薄であり、入院診療と外来診療は補完的な関係にはないといえる。
図表5 入院受療率と外来受療率
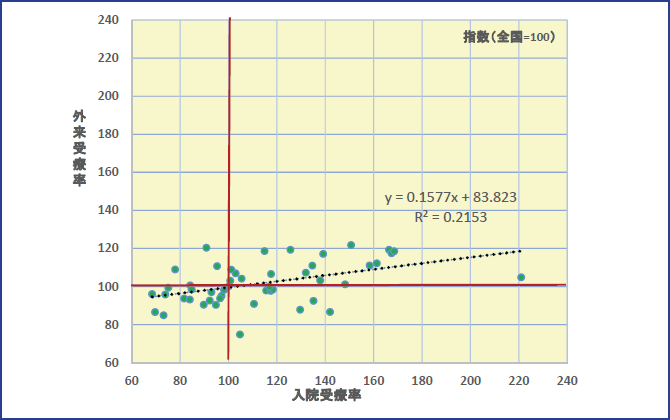
- (資料)2014年「患者調査」(厚生労働省)より作成
- ※1)全国を100とする指数
- ※2)図中の赤線は全国値
- ※3)一般・療養病床の受療率との整合性を確保するために、外来受療率から、主傷病が「精神及び行動の障害」(入院は主に精神病床で対応)と歯科傷病(齲蝕(虫歯)、歯肉炎及び歯周疾患、歯の補綴)を除いた。
療養病床と住まい施設定員に補完関係は薄い
都道府県・市町村老人保健福祉計画の策定法定化(4)から29年、介護保険制度の給付開始から19年を経て、介護サービスの拡充と多様化が進展した。ここで注目したいのが、この間に増加したいわゆる「住まい施設」、高齢者向け施設・居住系サービス(5)である。
図表6は、2014年の全国ベースの住まい施設の定員数(6)である。これをみると、定員の合計は約130万と一般・療養病床数(122万床)を上回っており、療養病床(34万床)の3.8倍に達している。
入院医療は、原則として常時医療施設内で医学的な管理を要する患者が対象である。しかし、医学的管理の濃度は患者によって異なり、特に療養病床の入院患者の場合、住まい施設の入所者と状態像がオーバーラップしている入院患者が少なからず存在する。そうであれば、療養病床数が少ない都道府県では住まい施設がこれを補うという補完関係がみられるという仮説が考えられる。その実態はどうなのだろうか。
図表7は、高齢者人口10万人あたり療養病床数と住まい施設定員数の合計を、全国を100とする指数で示している。これを図表1(人口10万人あたり一般・療養病床数)と比較すると、順位については多少の入れ替えがあるのは当然のこととして、病床・定員数が多い県は四国・九州地方が上位を占め、病床・定員数が少ない県は大都市圏に集中しているという傾向に変わりはない。ただし、最も多い県と少ない県の差は2.2倍(一般・療養病床数は3.2倍)と小さくなっている。
図表8は、全国値を100とする高齢者10万人あたりの療養病床数と住まい施設定員数の散布図である。前述の仮説に従えば回帰直線は右肩下がりになるはずだが右肩上がりになっている。両値の相関係数(R2)は0.03とかなり低い。
これらの結果から、住まい施設の定員数と一般・療養病床数との相関がみられず、病床の少なさ(多さ)を住まい施設が補うという関係にはないことがわかる。
図表6 住まい施設の定員数と一般・療養病床数(2014年)(全国)
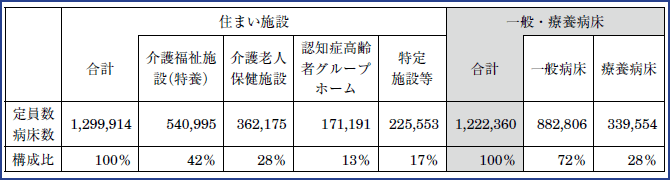
- (資料)2014年「介護サービス施設・事業所調査」、2014年「医療施設調査」(いずれも厚生労働省)より作成
- ※1)介護福祉施設及び特定施設の定員数には、地域密着型施設(定員30人未満の施設)を含む
- ※2)介護療養病床は療養病床に含まれる
図表7 高齢者10万人あたり療養病床数及び住まい施設定員数
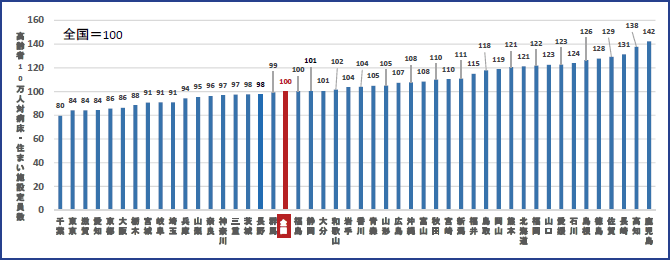
- (資料)2014年「医療施設調査」、2014年「介護サービス施設・事業所調査」(いずれも厚生労働省)より作成
図表8 高齢者10万人あたりの療養病床数と住まい施設定員数
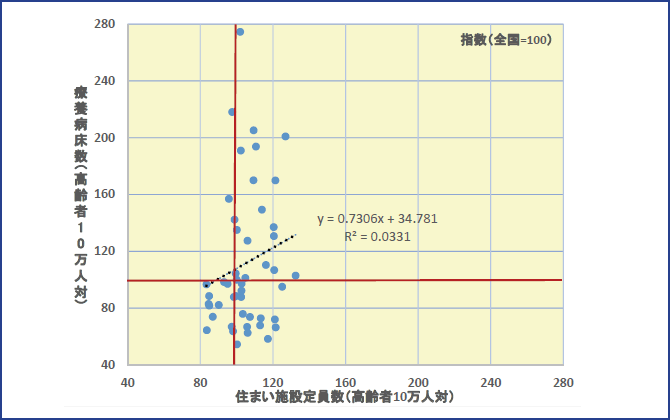
- (資料)2014年「医療施設調査」、2014年「介護サービス施設・事業所調査」(いずれも厚生労働省)より作成
- ※1)全国を100とする指数
- ※2)図中の赤線は全国値
- ※3)介護療養病床は療養病床に含まれる
人口あたり病床数の格差は一貫して拡大した
図表9は、10万人あたり一般・療養病床数が上位にある5県(徳島、高知、長崎、熊本、鹿児島)と下位にある5県(埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知)について、1955年を起点として10万人あたり一般・療養病床数、その分母である人口、分子である病床数の推移を示している。
図表9 病床数上位・下位5県の人口、病床数の推移
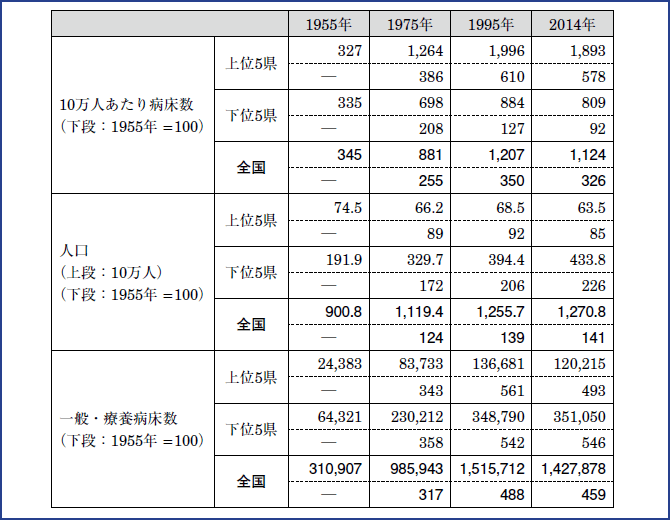
- (資料)2014年「医療施設調査」(厚生労働省)、「国勢調査」(総務省)、「人口推計(2014年10月現在)」(総務省)より作成
- ※1)下位5県:埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知
- ※2)上位5県:徳島、高知、長崎、熊本、鹿児島
[1] かつては10万人あたり一般・療養病床数の差は小さかった
1955年の時点では、上位5県(327)と下位5県(335)に大きな差はない。ところが1975年をみると、上位5県(1,264)と下位5県(698)の差は1.8倍、1995年には上位5県(1,969)と下位5県(884)の差は2.2倍とさらに拡大。2014年は上位5県(1,893)と下位5県(809)。2.3倍とわずかではあるが差は拡大している。
[2] 上位県は人口が減少し下位県は人口が増加した
10万人あたり病床数の分母に相当する人口の推移を、1955年を100とする指数でみてみよう。
1975年は、上位5県は89に減少しているが、下位5県は172に急増している。1995年は、上位5県は92と横ばい、下位5県は126とそれ以前と比べて沈静化したが上位5県に比べて増加幅が大きい。2014年は、上位5県は85に減少しているのに対して、下位5県は226に増加している。約60年の間に、上位5県は人口が15ポイント減少しているのに対して、下位5県は2倍強に増加している。
[3] 病床数は病床規制導入まで上位県も下位県も増加した
10万人あたり病床数の分子に相当する一般・療養病床数の推移を、1955年を100とする指数でみてみよう。
1975年は上位5県343、下位5県は358と、ほぼ同程度に増加している。1995年は、上位5県は561、下位5県は542とほぼ同程度の増加である。2004年は、上位5県は493に減少しているのに対して、下位5県は546とほぼ横ばいとなっている。上位県も下位県も、1980年代までは人口の動向とかかわりなく、同程度に病床が増加し続けたことがわかる。1995年以降の動向は、都道府県医療計画による病床規制(7)の影響であることはいうまでもない。
[4]上位県にみられる「高齢化ボーナス」
以上を要約すれば、人口10万人あたりの一般・療養病床の格差は、人口の増減に関わりなく病床が増加したことの結果といえる。そうであるならば疑問が残る。なぜ人口が減少ないし停滞する地域で病床が増加し続けることができたのか。その答えは人口の高齢化にある。
図表10は、全国の(8)入院患者の年齢別構成比の推移を示している。1960年の時点では、入院患者の87%は15~64歳の患者で占められ、高齢者(65歳以上)の患者は6%に過ぎない。その後、高齢者患者の占める割合は増加し続け、2014年には71%を占めるに至っている。高齢者の増加が病床増加を支えたものと考えて差し支えないだろう。
すなわち、上位5県は高齢者の増加が入院医療需要を支え、下位5県にあっては人口増加の中心が若年人口であるため病床の相対的不足があまり意識されなかったものと考えられる。
上位5県にみられる「人口減少下で高齢者の増加が入院需要を支える」という構図は、「高齢化ボーナス」ともいうべき現象である。しかし上位5県では実数ベースで高齢者人口が減少しつつあり、高齢化ボーナスは終焉をむかえつつある。
図表10 入院患者の年齢構造の推移(全国)
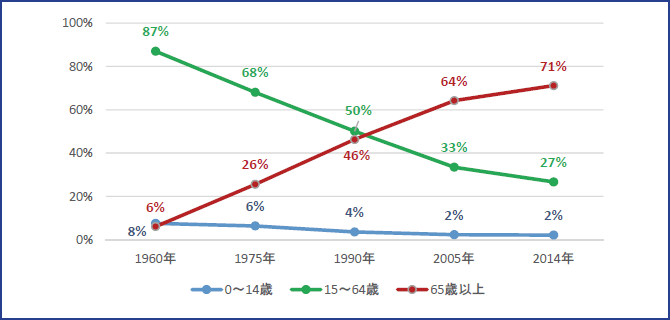
- (資料)「患者調査」(厚生労働省)より作成
- ※精神病床入院患者を含む
本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。
レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。