社会政策コンサルティング部 チーフコンサルタント 野中 美希 リサーチャー 杉田 裕子
「児童館ガイドライン」(2018年版)から読み解く現代における児童館の役割
(1)「児童館ガイドライン」改正の背景
2011年に「児童館ガイドライン」が発出されてから6年余りが経過し、主に2つの背景があって、「児童館ガイドライン」の改正が必要となっていた。
まずひとつが、児童福祉法をはじめとした関連法令が改正され、整合性を取ることが必要となっていたことである。なかでも、児童福祉法の理念に子どもの意見が尊重されるべきこと、子どもの最善の利益が優先されること等が明文化されたことは、児童館のあり方を考える上で欠かせない視点であった。
2つ目が、児童虐待の通告件数やいじめの発生件数の増加、子どもの貧困の社会問題化、配慮や支援を要する子どもの存在等、子どもと家庭をめぐる今日的課題として指摘されていることに対応できるよう、児童館の機能・役割の強化をしていくことが期待されるためである(16)。
なお、こうした現代における児童館の役割変化にいち早く気付き、すでに現場で取組や実践を行っている児童館もある。先行的な取組の例として、弊社が2017年度に実施した「児童厚生員の処遇や資格の現状と課題に関する調査研究」(17)より、京都市(京都府)とうるま市(沖縄県)を紹介したい。
京都市では、「児童館活動指針」で示す児童館の期待役割と子どもや家庭を支える取組を推進している(18)。京都市内には100を超える児童館があり、全て運営委託事業として実施され、委託先の団体は複数に分かれている。そのようななかでも、京都市内の児童館が同じ考え方の下に運営されるよう、「京都市児童館活動指針」が策定されている。現在、2015年発行の第3次改訂版に基づき運営されているが、当該活動指針のなかでは、児童館の施設特性から期待される役割が、[1]子どもの自立支援─子どもの主体的な参画から期待される役割、[2]子育ての社会連帯─子どもや家庭との信頼関係や親同士の交流から期待される役割、[3]共生のまちづくり─地域住民の幅広い交流と社会参加から期待される役割の3つに整理されている。いずれも、施設が存在し、すべての子どもを対象に、地域に根差した活動を継続的に行える児童館だからこそできるものである。
また、京都市では、日々の活動のなかで子どもや家庭における課題に児童館が気付いたとき、あるいは子どもや保護者からの悩みや相談を受けたり、地域住民から子どもや家庭に関する情報が寄せられたとき等に、子どもや家庭が抱える福祉的な課題に対して児童館が支えとなり、支援を行うことも、児童館の役割として意識している。主に「子育て相談」、「発達課題」、「虐待が疑われる事例」等に対応しており、実際に児童館で行われている支援事例を「子どもを通した家族支援に関する児童館実践事例集」として2016年度に取りまとめた(図表2)。当該事例集では、児童館内で活動している放課後児童クラブの利用終了後も長期にわたって子どもを支え続けていたり、虐待が疑われて他機関と連携しながら、支え続けているような事例等、子どもや家族を支える児童館の日々の実践が紹介されている。児童館が子どもの遊びを通じた健全育成を行う場であると同時に、家庭や地域を視野に入れてソーシャルワーカーやコミュニティワーカーとしての役割を果たしていることがわかるものとなっている。
別の事例として、うるま市にあるみどり町児童センターを中心として実施されている児童館で開催する子ども食堂と障がいのある子どもがいる保護者の会の支援(19)がある。
沖縄県では、県を挙げて推進する子どもの居場所づくりの一環として子ども食堂が県内各地で開催されている。うるま市みどり町児童センターでは、「スマイルカフェ」と名づけ、学校のある期間には毎週土曜日に、また長期休暇時には休館日である日曜日を除く毎日開催している。子ども食堂は全国各地で増えてきているものの、多くは開催回数が少なかったり、不定期の開催で、公民館等の会場を一時的に借りて開催されていることも多い。しかし、みどり町児童センターの子ども食堂は、開催頻度が高いだけでなく、たとえ子ども食堂を開催していない日であっても、児童館は開館しており、いつも児童厚生員がいて、子どもの居場所となることができる。このような役割は、やはり施設として地域にある児童館だからこそ果たせる機能といえるのではないであろうか。なお、子ども食堂を始める前には、子どもの貧困について地域の理解を得るための勉強会を開催し、ボランティアを募ったり、子ども食堂に子どもをつないでもらうために、案内カードを作成して、自治会や学校、民生委員、行政、保健師などから気になる子どもに配布してもらうなど、地域との連携も積極的に行っている。
他にも、障がいのある子どもの保護者からの希望で「ゆんたく会」の立ち上げをみどり町児童センターが支援した。現在、会のリーダーは保護者が担っており、保護者が主体となって活動しているが、児童厚生員を療育グループの活動に定期的に派遣して、障がいのある子どもに関する知識や接し方を学び、活動を支援している。 このように、みどり町児童センターでは、児童館の施設特性をうまく利用して、子どもの居場所としての機能を最大限発揮させるとともに、地域との関係づくり、保護者の支援などにも積極的に取り組んでいる。
先に述べた2つの背景を受け、社会保障審議会児童部会「遊びのプログラム等に関する専門委員会」(以下、「専門委員会」という。)及び同委員会の下設置された「今後の地域の児童館等のあり方検討ワーキンググループ」(以下、「WG」という。)において、「児童館ガイドライン」改正に向けた議論がなされ、改正「児童館ガイドライン」(案)が取りまとめられた。
専門委員会並びにWG では、先行研究の提言等を参考に、児童館のあり方を議論する前提として、今日的課題への対応が児童館の普遍的機能になりつつあること、子ども・子育て家庭の身近な相談窓口としての機能の強化が求められていること、児童厚生員の資質向上が必要であること、2011年以降の法改正への対応が必要であることなど8つの課題認識(20)を持って取り組まれた(図表3)。
図表2 子どもを通した家族支援に関する児童館実践事例集(抜粋)
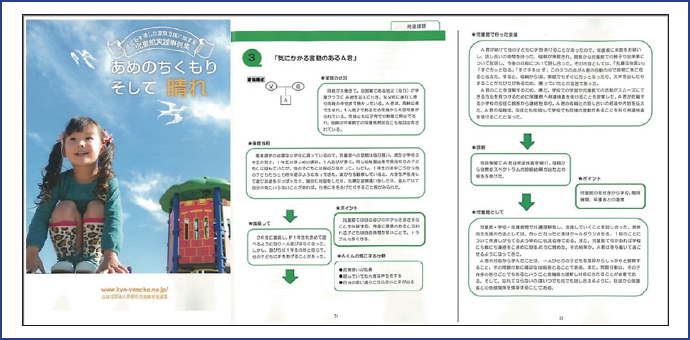
- (資料)厚公益社団法人京都市児童館学童連盟(2017)「子どもを通した家族支援に関する児童館実践事例集」より作成。
図表3 「児童館ガイドライン」改正に向けての課題認識
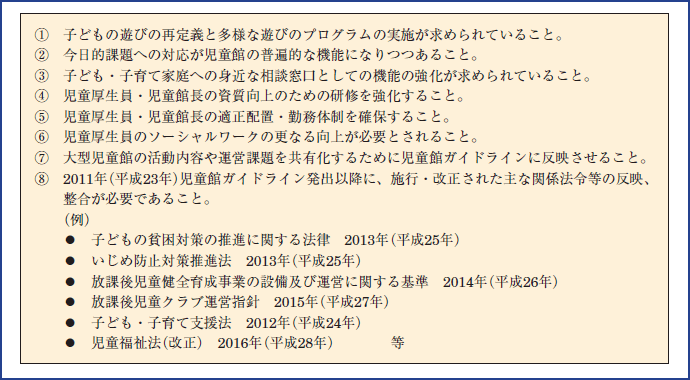
- (資料)社会保障審議会児童部会遊びのプログラム等に関する専門委員会「遊びのプログラムの普及啓発と今後の児童館のあり方について 報告書」,pp.14-15(2018年9月20日)より作成。
(2)「 児童館ガイドライン」(2018年版)のポイントと現代における児童館の役割
専門委員会やWGでの議論を経て、2018年10月、「児童館ガイドライン」(2018年版)が発出された。
改正のポイントは、[1]児童福祉法改正及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、子どもの意見の尊重、子どもの最善の利益の優先等について示したこと、[2]児童福祉施設としての役割に基づいて、児童館の施設特性を拠点性、多機能性、地域性に整理したこと、[3]子どもの理解を深めるため、発達段階に応じた留意点を示したこと、[4]児童館の職員に対して配慮を必要とする子どもへの対応として、いじめや保護者の不適切な養育が疑われる場合等への適切な対応を求めたこと、[5]子育て支援の実施について、乳幼児支援や中・高校生世代と乳幼児の触れ合い体験の取組の実施等の内容を追加したこと、[6]大型児童館の機能・役割について整理したこと、の6点である(21)。
なかでも、ポイントの2点目にあたる、児童館の施設特性(拠点性、多機能性、地域性)は、今回の改正で新設された「総則」のなかに、児童館の理念や社会的責任等とあわせて明記された事項であり、個々の活動の前提として、現代における児童館のあり方を示すものといえる。
「児童館ガイドライン」(2018年版)の該当部分を図表4に抜粋しているが、本文の記述を読み解くと、児童館は子どもの意思で自由に過ごすことができる居場所であること、子どもを支える児童厚生員がいること、児童館・児童厚生員は子どもとの関わりの中で子どもが抱える課題に直接関わり、必要に応じて関係機関と連携しながら対応できること、子どもが児童館内にとどまらず地域全体に活動を広げていくことができること、児童館は地域住民や関係機関等と連携して子どもの成長に向けての環境づくりを行うものであること等が明示されている。
児童数の減少、母子世帯・父子世帯の増加、地域との関係の希薄化等の社会の変化のみならず、いじめ、児童虐待、子どもの貧困など、子どもや子育て家庭が抱える課題が多様化・複雑化するなかで、遊びや生活を通した子どもの発達の増進を図っていく児童館の役割は重要性を増してきている。また、子どもや子育て家庭の相談にのったり、支えになること等も、これからの児童館に求められているといえよう。
図表4 児童館の施設特性(「児童館ガイドライン」(2018年版)より抜粋)
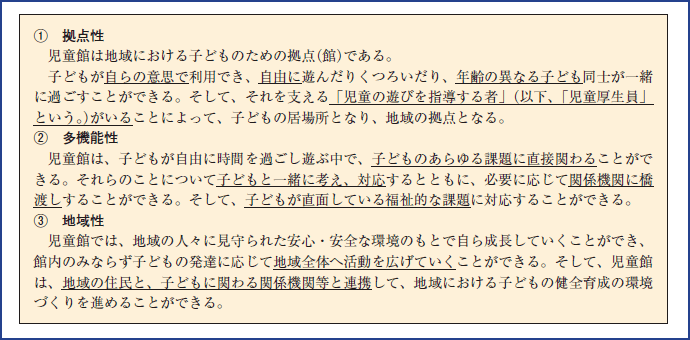
- (注)下線は、筆者が編集している。
- (資料)厚生労働省「児童館ガイドライン」(子発1001第1号平成30年10月1日厚生労働省子ども家庭局長通知),p.2より作成。
本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。
レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。