社会政策コンサルティング部 チーフコンサルタント 羽田 圭子
人生の最終段階も見すえ、高齢期のために取り組むべきこと
人生の最終段階を含む高齢期について、個人としてどのような準備をしたらよいのかについて、以下の5点にまとめた。いわゆる「終活」よりは、範囲が広いものとなっている。
人はいつどのように死ぬかを選べないが、どう生きるかは選べる。息を引き取る瞬間まで人は生きているのだから、最期まで自分らしく生きられるよう、生き方を自ら選ぶことが望まれる。
本提言は、人生の最終段階を含む高齢期について考える人を対象としており、年齢、立場(死を目前にした本人か、家族介護者か、高齢者を対象とする職業か等)を問わない。
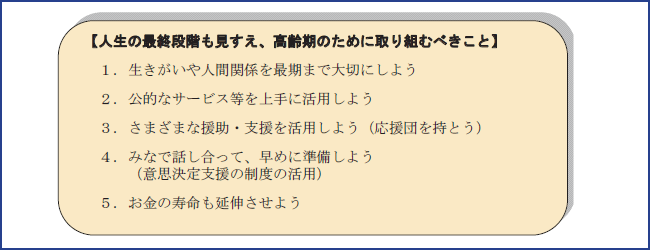
(1) 生きがいや人間関係を最期まで大切にしよう
調査結果では、人生の最終段階における支え手は、「家族・近親者」が突出して高かった。また、「家族・近親者」「親族」は、本人の死後も支えであったと回答する人が多かった(図表4)。当たり前の結果だと思われるかもしれないが、改めて人生の終わりを支える存在について考えてみたい。
高齢期になると、それまで仕事や趣味や社会貢献などを生きがいとしていた人も、家族や親族との交流を生きがいとする人が多くなる。人とのつながりは、お金で買うことができない。また、個人の価値観や行動によるところが大きく、他人が代わりに行うこともできず属人的である。だからこそ、最期まで残り続ける、人として最も重要な営みだということが改めて調査結果からも確認されたのではないかと考える。
本調査のインタビュー調査で、エンドオブライフ・ケアの医療分野における第一人者の方が、望まれるケアのあり方としては、「お母さんのように、自然に生活をする中で、死にゆく人に寄り添いそばにいること」だとおっしゃっていたことが印象深い。
人はみな母親から生まれる。とすれば、死ぬ時も「母親」に見守られるように死ぬことが理想的なのかもしれない。もちろん、個々人で希望するケアは異なって良いのだが、死を目前にした本人をケアする側の姿勢として、傾聴に値する意見ではないだろうか。
契約に基づく関係であれば、権利・義務は契約の範囲内にとどまり、契約が終了すれば相手は去っていくが、母親と子どもは契約を交わしたわけではない。人の存在とは、契約を超えた人と人とのつながりがまず先にあると考えられる。そうしたつながりには、血縁、婚姻、愛情、友情、同窓、師弟、同僚、地縁、知縁等のさまざまな関係がある。自身のアイデンティティと密接な関係がある人だと考えられる。
自分の人生において、大切に思う人は誰かを考えてみてほしい。多くの場合、その人は、契約に基づかないが、長期にわたって、あなたのそばにいる人ではないだろうか。その人とのつながりを今後も大切にするとともに、そうした人をさらに見つけ、つながりを強めてほしい。そのつながりが人生の最終段階においても、お互いの支えとなるだろう。
(2)公的なサービス等を上手に活用しよう
現在、家族だけで高齢者の介護や世話をすることは難しくなっている。前述した高齢期のライフステージをうまくシフトしていくためには、ニーズに合わせて、公的なサービス、自費サービス、ボランティア等によるさまざまな援助・支援を利用することが有効である。中でも公的サービスは、税金や保険料が投入されるため、自費サービスに比べ費用対効果の面などで優位にあると考えられる。
しかし、医療・介護・福祉・年金等の公的制度はニーズの多様化により、高度化すると同時に複雑化している。申請をしないとサービスを受けられないしくみであり、事務手続きも煩雑なことから、必要とする人が利用につながらないこともある。高齢期になる前に、社会保障制度の概要と相談先を確認しておいて、必要とする時がきたら申請をすることが重要である。
心身状態や生活に不安を感じた時は、本人、家族・近親者、地域住民等は、かかりつけの医療機関や市町村の地域包括支援センター等の公的機関に相談することができる。必要に応じ、ケアマネジャー、医療・介護・福祉の関係機関につないでくれる。
将来の病気や死期を正確に予測することは難しいものの、人生の最終段階も、連続したライフステージの延長にある。本人の死後も、遺族等には死後の事務処理や大切な人を亡くした悲嘆(グリーフ)がふりかかる。必要とする場合は、公的サービスをはじめとするさまざまなサービスを利用しながら、高齢期のライフステージをうまくシフトさせることで、最期まで自分らしい生活を送れる可能性を高めることができるであろう。
(3)さまざまな援助・支援を活用しよう(応援団を持とう)
心身状況や判断能力が衰えてくると、本人、家族・近親者だけで日常生活を支えることは難しくなり、さまざまな援助や支援を必要とするようになる。調査結果では、約7割が医療機関で、約1割が施設で最期を迎えており、医療・介護従事者が大きな役割を果たしていた。医療・介護分野以外にも、さまざまな援助者・支援者が関わっており、援助や支援の内容によっては、人生の最終段階の前後も継続することが明らかとなった(図表2参照)。
援助者・支援者をみると、生活に密着した身近な機関が多く、人生の最終段階よりも前の段階から本人、家族・近親者と付き合いがあることが推察される。各機関は、専門分野について情報やノウハウを蓄積してサービスを提供しているため、高齢期における悩みについて、もっと気軽に相談をして、活用することで、本人、家族・近親者の不安や負担を軽減することが期待される。
高齢期においても、それまでの関係を維持しながら、ライフステージを円滑にシフトしていくことが望ましい。近年、離れて暮らす子どもや孫とのコミュニュケーションに携帯電話やスマートホンを利用する高齢者が増えているが、こうした社会的な基盤や技術も「支え」といえるかもしれない。
高齢期においては、本人と家族・近親者が「主役」となって、援助者・支援者のそれぞれの強みや専門性を活かし、援助・支援をしてくれるチーム、すなわち「応援団」を持つことが大切である。
図表2 高齢期のライフステージにおける援助者・支援者
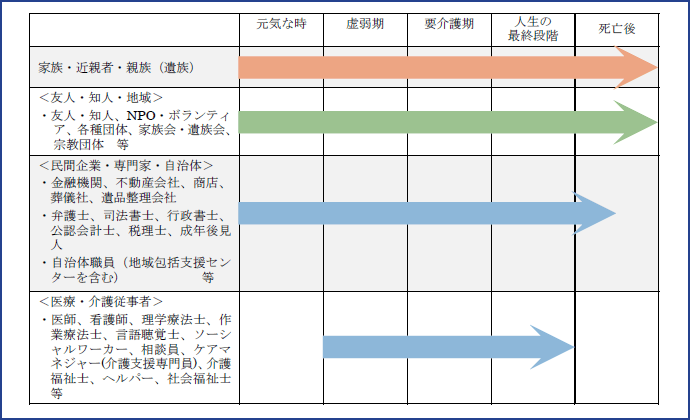
(4)みなで話し合って、早めに準備しよう(意思決定支援の制度の活用)
調査結果では、人生の最終段階においては半数以上の人に判断能力の低下がみられた。長命化の時代、認知症は「万に一つ」ではなく、誰もがなりうる病気となっている。
現在、判断能力が低下した人を支援するしくみとして、成年後見制度、日常生活自立支援事業がある。成年後見制度とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち、判断能力が不十分な人を、法律面や生活面で保護したり支援したりする制度である。日常生活自立支援事業とは、判断能力が不十分な人が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うしくみである。しかし、現在のところ、成年後見制度、日常生活自立支援事業ともに利用率は低い。制度への理解を促進するとともに、制度そのものを使いやすく改正する動きもあり、今後は利用が促進される見込みである。
また、人生の最終段階における今後の治療・療養について、患者・家族と医療・介護従事者があらかじめ話し合う自発的なプロセスとして、アドバンス・ケア・プランニング(ACP と略)がある。国は、2018年3月に「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」を改定し、ACP を推進している。同年11月、ACP について、愛称を「人生会議」として、11月30日(いい看取り・看取られ)を「人生会議の日」とし、人生の最終段階における医療・ケアについて考える日とした。
人生の最終段階における医療及びケアの提供については、患者のこれまでの人生観、どのような生き方を望むかを含め、できる限り把握すること、患者と、患者が信頼できる家族等を含めて、医療・ケアチームとの話し合いが繰り返し行われた上で、患者が意思決定を行うこととしている。その際、患者の意思は変化しうるものであることや、患者自らが意思を伝えられない状態になる可能性があることに留意する必要がある。現在、各地域において取組が進んでおり、今後、「人生会議」を行う人が増えていくであろう。
高齢期、特に人生の最終段階においては重大かつ難しい決断を求められるようになる。判断能力が低下していれば、意思決定のつらさはさらに増し、決断がゆらぐことも多い。本人、家族・近親者だけで抱え込まずに、専門家や公的機関に相談して、チームとして一緒に意思決定をしてもらうことが望ましい。自分の意思や希望を伝えるだけでなく、迷いや不安も相談しながら、選択をすることで、より良い選択につながることが期待できる。
(5)お金の寿命も延伸させよう
現実的な問題として、人は生きている限り、生活費、サービスの利用代、交際費等、さまざまなお金がかかる。死亡後は葬儀や埋葬費用等が必要になる。こうした費用は、高齢者自身の年金や資産でまかなうことが望ましく、寿命の延伸に合わせ、お金の寿命も延伸させなくてはならない。高齢期においてもいきいきした生活を送り、かつ、生きている間にお金がショートしないだけの収入や資産を確保しておく必要がある。
誰もが100歳まで生きる可能性があるという想定で、経済的な面でも具体的な備えが必要な時代となりつつある。子どもの頃からの金融教育、公的年金制度の整備等、国の取組はもちろん重要であるが、長寿化により自助の必要性はさらに高まっている。
お金の管理、運用は本人の意思決定が前提となるが、加齢に伴い、認知機能や判断能力が低下していくことが避けられないため、高齢者の経済活動にかかる意思決定支援が社会的な課題として顕在化しつつある。金融商品も、高度化し、複雑になっている。
一般に、専門的な相談は早い時期に行う方が、対応の選択肢が多く、有利な選択肢を選べる可能性が高い。一例だが、医療保険の加入には、年齢や病気の既往歴等による制限がある。備えは高齢期より前の若く元気なうちから、将来を見据えて準備をすることが有効である。困ってから相談するのではなく、将来を見据えて、早めに相談して備えをしていくことが望ましい。
経済面の備えをしておきたい場合は、日頃から取引のある金融機関、不動産業者、士業の専門家等と自身の希望する高齢期の過ごし方や、収入・資産の状況・運用方法等について話し合い、相談をしながら、具体的な準備を行うことが、人生100年時代においては有効な自衛策となる。
一口に高齢者といっても、年齢、性別、健康状態、収入、資産、金融取引の知識や経験、判断能力、職業、家族、人的ネットワーク、価値観、ライフスタイルはさまざまである。画一的な資産寿命の延命策が通用しない時代となり、個々人に合った対応策が求められることから、専門家のアドバイスを参考に意思決定をすることが必要となっている。
長期的な展望に立ってお金の寿命を延伸すること、将来の判断能力の低下についての対応策をとること、将来に向けての自分の意思を明確にして具体的な対策をとること等、取り組むべきことは多い。
本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。
レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。