社会政策コンサルティング部 チーフコンサルタント 羽田 圭子
まとめ
高齢期の長期化により、高齢期の中にもライフステージがみられるようになっている。日頃から、誕生日や「人生会議の日」などの機会に、家族や専門家と話し合いながら、意思決定と準備を行い、人生観やそれまでの生き方と連続性を保ちつつ、高齢期のライフステージを上手にシフトしていくことが望まれる。その延長として人生の最終段階を迎える、そんな人生100年はいかがだろうか。
<参考>看取りをされた50代、60代アンケート調査の主な結果
1.アンケート調査の概要
- 最近10年に家族・近親者を看取った経験のある方に対するアンケート調査
|
調査期間 |
2018年1月 |
|
調査対象 |
インターネット調査会社のモニターのうち、50代60代の男女を対象としてスクリーニング調査を実施して、最近10年に家族・近親者を看取った経験のある方1,000人を抽出して、本調査を行った。 |
|
有効回答数 |
1,000人 |
2.アンケート調査の主な結果
(1)亡くなられた方続柄
- 最近10年間に亡くなられた方の続柄は、回答者が50代60代ということから、「父親」が51.0%、「母親」が44.0%と多く、次いで「おじ」、「おば」がそれぞれ2割台と親の世代が多い。一方、「夫」1.4%、「妻」1.1%と配偶者を看取った人は少ない。
図表3 亡くなられた方の続柄
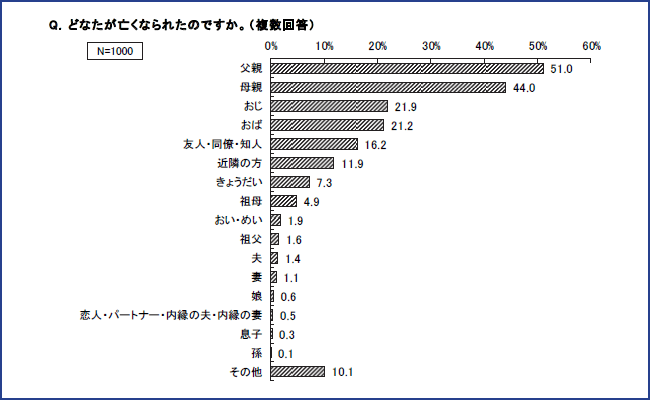
(2)援助者・支援者は時の経過で変わるが、身近な方や関係機関である
- 本人や家族・近親者を支えてくれた人については、「家族・近親者」「親族」は「亡くなる2~3ヶ月前」、「亡くなられた2~3カ月後」ともに支えとなり続けている。
- 「医療・介護関係者」は「亡くなる2~3カ月前」の支援で関わる割合が高く、「亡くなられた2~3カ月後」には割合が低くなっている。職種でみると、「医師」「看護師」「ケアマネジャー・施設の相談員・社会福祉士」「ホームヘルパー等の介護従事者」「病院のソーシャルワーカー」等の割合が高く、医療・介護がチームで提供されていることがうかがえる。
- 一方、「葬儀社」「宗教関係者」「弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士等の専門家」「保険会社」「銀行・郵便局等の金融機関」「不動産業者」「成年後見人」は「亡くなる2~3カ月前」よりも「亡くなられた2~3カ月後」の方が高くなっている。
- エンドオブライフ・ケアのキーパーソンは「家族・近親者」「親族」であるが、その他、さまざまな援助者・支援者も時期やニーズに応じて関わっていることがうかがえる。選択肢の関係機関の多くは、生活に身近な機関である。
- エンドオブライフ・ケアだからと、新規に関係を築くのではなく、日頃からの付き合いや取引等をベースとしたものが多いのではないかと推察される。
- 成年後見人の割合は「亡くなる2~3カ月前」が0.1%、「亡くなられた2~3カ月後」が0.2%と割合は低く、成年後見制度の利用促進が期待される。
- 人生の最終段階においては、家族・近親者、親族の果たす役割が大きいが、そこに多種多様な関係機関が関わり、支えとなっている現状が明らかとなった。
図表4 本人が亡くなる2~3カ月前後の支え
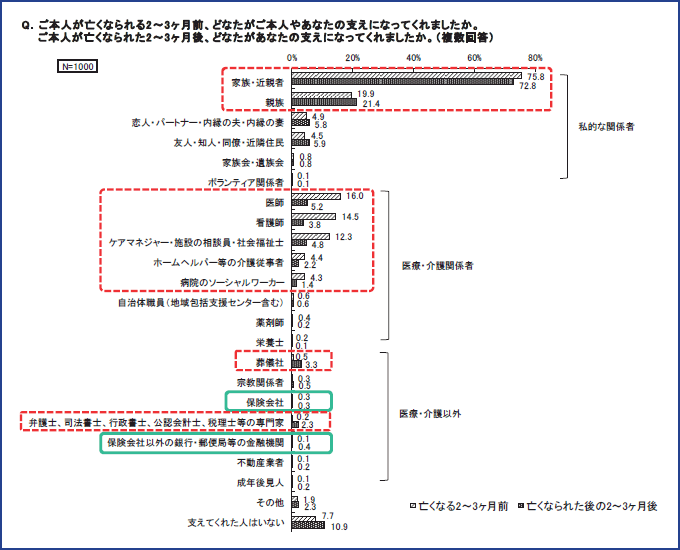
- *「支えてくれた人はいない」を選択した場合、それ以外の選択肢は選べない設定となっている。
(3)判断能力の衰え
- 加齢や病気等によって人の判断能力は低下していくが、人は生きている限り、複雑かつ重要な事項について意思決定と事務処理を求められ続ける。
- 判断能力についてみると、「衰えが見られた」が、「亡くなる1年前」の50.9%から、「亡くなる2~3カ月前」64.5%と6割以上に上昇している。人生の最終段階においては1年以上にわたり、半数以上の方に判断能力に衰えがみられ、本人の意思決定を支援する必要性がうかがえる。
図表5 人生の最終段階における本人の判断能力
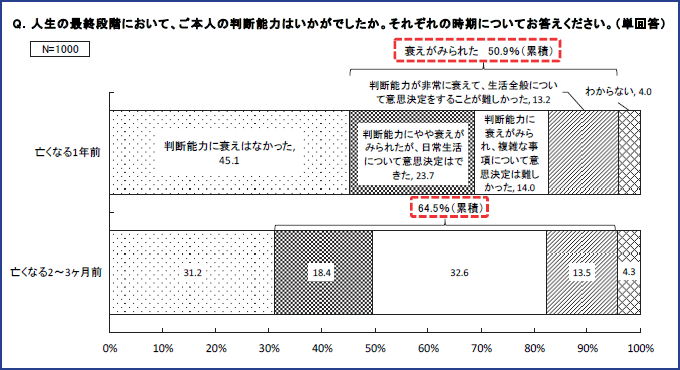
(4)「エンドオブライフ・ケアについて決めておいたり準備しておくとよいこと」は「終末期医療、延命治療についての希望」など様々
- 50代60代の人が「自身の最終段階について、決めておいたり準備しておくとよいこと」については、「終末期医療、延命治療についての希望」が53.2%と最も多い。次いで、「自身の葬儀・墓についての希望」38.6%、「自身の金融資産などの処分や相続についての希望」37.7%、「自身の所有する家・土地などの処分や相続についての希望」31.5%、「人生の最終段階を過ごす場所についての希望」30.6%、「家族・近親者、友人に感謝の気持ちや希望を伝えること」28.4%、「息を引き取る場所についての希望」18.2%など、さまざまな事柄について準備をする意向を持っている。
図表6 エンドオブライフ・ケアの充実について
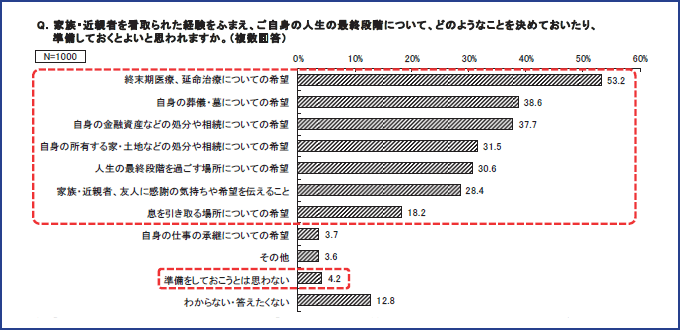
- *「準備しておこうとは思わない」、「わからない・答えたくない」を選択した場合、それ以外の選択肢は選べない 設定となっている。
本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。
レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。