環境エネルギー第2部 シニアコンサルタント 永井 祐介
グリーンボンドの対象活動を巡る議論
グリーンボンドにより投資家に適切に訴求するには、資金使途の適切な選定が重要である。グリーンボンドは黎明期でもあり、これまでは資金使途のグリーン性はあまり厳しく問われなかったが、最近ではグリーン性の疑わしいものを排除しグリーン性の優れたものを高く評価するために、資金使途に関する基準作りも進んでいる。そこで本章では、既存のガイドライン類と現在検討中のEU基準案を紹介する。
3.1.既存のガイドライン類
(1)ICMA「グリーンボンド原則」
現在世界で広く参照されているガイドラインはICMA(国際資本市場協会)が作成した「グリーンボンド原則」である。この原則は、グリーンボンドの透明性確保と情報開示を促進するためのガイドラインであり、グリーンボンド発行主体が策定・公表すべき要素([1]資金使途、[2]プロジェクトの評価及び選定のプロセス、[3]調達資金の管理、[4]レポーティング)を規定している。
但しこの原則は、あくまでも透明性や情報開示に焦点を置いたものであり、資金使途の例示はしているが、資金使途を限定する性格のものではない。
(2)環境省「グリーンボンドガイドライン」
日本の環境省がICMAの原則を参考に作成したものが「グリーンボンドガイドライン」である。ICMAの原則と同じ4要素の手続きについて、対応方法の例や日本の特性に即した解釈を示したものであり、資金使途の例示はしているが限定はしていない。むしろ基本的考え方として「グリーンボンドが投資の対象として選択されるか否かは、最終的には市場に委ねられるものと考えられる。」と明記している。
現在、このガイドラインの見直しが行われているが、資金使途の厳格化については今のところ時期尚早と整理されている。
(3)CBI「気候ボンド基準」
一方で、資金使途について明確な基準を設定しているのが、国際NGOのCBI(気候債券イニシアティブ)(5)が作成した「気候ボンド基準」である。これは、グリーンボンドの透明性や情報開示ではなく、資金使途がパリ協定の目標に対して十分かどうかを認証するための基準であり、活動毎に基準値が設定されている。既に風力、太陽光、電車、水、住宅等の11の活動の基準が策定済みであり、今後も廃棄物や農業、送電網、IT等の様々な基準が策定される予定である(6)(図表3参照)。
この基準は、先述したICMAの原則や環境省ガイドラインと補完関係にある。すなわち、グリーンボンドの全体枠組みである4要素([1]資金使途、[2]プロジェクトの評価及び選定のプロセス、[3]調達資金の管理、[4]レポーティング)についてICMAの原則や環境省ガイドラインに準拠した上で、資金使途のグリーン性についてCBI基準に準拠することでグリーンボンドのグリーン性の説得力を高める、といった使い方がされている。
CBIは規制当局ではないが、主要なグリーンボンド指数の中にはCBIが認めたものしかグリーンボンドと認めないもの(7)もあり、またCBIのメンバーは後述するEUやISOにおける基準作りにも関与している等、その影響力は大きい。
またCBIは基準策定や認証とは別の活動として、世界各国で発行されたグリーンボンドの資金使途についてグリーンと呼べるか否かを独自に判断し、ホームページ上で公表する活動も行っている。企業にとっては、せっかく自社の戦略訴求のためにグリーンボンドを発行しても、CBIに批判されることで評判が落ちる可能性もある。そのため、CBIの基準や最近の類似グリーンボンドに対するCBIの評価等を把握しておくことも重要である。
図表3 CBI基準策定状況
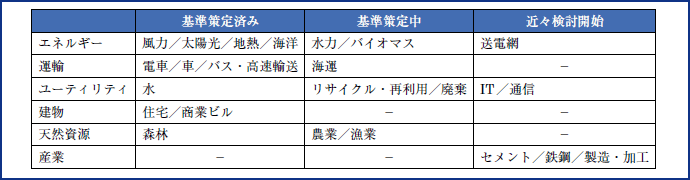
(資料)CBI資料を元にみずほ情報総研作成
3.2.EU:サステナブルな活動に関する基準(タクソノミー)
(1)背景
資金使途に関する公的基準作りで最も先行しているのはEUである。EUは2018年3月に、金融システムにおけるサステナブル考慮の強化等を促進するために「EUサステナブルファイナンス行動計画」を策定。現在、同計画の最優先事項として、脱炭素社会とSDGs達成に資する「環境的にサステナブルな活動」の定義や基準値を定める「タクソノミー(taxonomy)」を策定中である(本稿ではタクソノミーおよびその中の基準を総称して「EU基準」と呼ぶ)。2021年末までに気候変動緩和(8)・適応(9)・水・循環・汚染削減・生態系の6つの環境分野のEU基準を完成予定であり、2019年6月には先行して気候変動緩和と適応分野の案が公表された(詳細は後述)。
EU基準完成後は、「EUグリーンボンド」と認められるには資金使途の活動がEU基準を満たす必要がある。またサステナビリティをテーマにしたファンドや資産運用は、EU基準への適合率の開示が求められる。なお融資は適用対象ではないが、銀行がEU基準に適合した活動向けのローン商品を組む可能性はある(10)。
企業にとっては、EU 基準に適合する活動を増やす事により、グリーンボンドやグリーンファンド、グリーンローン等による資金調達の可能性を高めることが出来る。更に、EU 基準は企業評価の指標としても活用される可能性も高く、グリーンな資金調達を行わない企業にとっても影響が大きい。
図表4 企業の資金調達とEU 基準(タクソノミー)の位置づけ
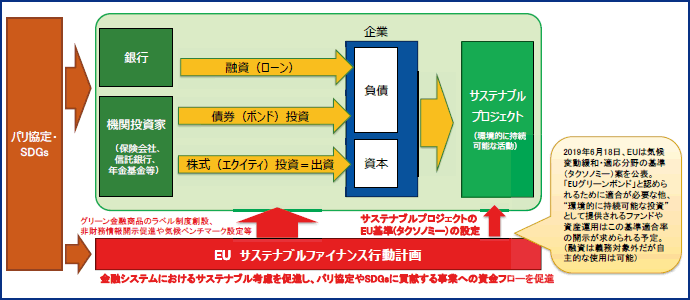
(資料)みずほ情報総研作成
(2)気候変動緩和に関するEU基準案
2019年6月に公開された気候変動緩和に関するEU基準案では、CO2排出量の多い部門や主要な温室効果ガス削減・吸収対策として、7部門の67種の活動について「環境的にサステナブルな活動」と認められる為の基準等が示された(図表5、図表6参照)。
これらの基準の最大の特徴は、「2050年CO2排出量実質ゼロ(ネットゼロ)(11)」を念頭においた非常に高い水準となっている点である。これまで環境に優しい活動の代名詞でもあった「ガス火力発電」や「ハイブリッド自動車」も認めない他、石油からのプラスチック製造を認めない等、脱炭素社会における各産業の姿を示しているとも言える(具体的には、ガス火力発電の基準はライフサイクル排出量100gCO2e/kWhとなっており、CCS(CO2の回収・隔離)無しでの基準達成は困難であるほか、乗用車も50gCO2/km(WLTP(12))となっており、ハイブリッドではなくプラグインハイブリット等でないと達成できない水準となっている。プラスチック製造はリサイクル品または再生可能資源からの製造のみが認められている(図表6参照))。
この基準案のもう一つの特徴が、「[1]:既に脱炭素(CO2排出ゼロ)な活動」に加えて、「[2]:現時点では脱炭素ではないが、2050年脱炭素への移行段階の活動」、「[3]:[1]や[2]を支える活動」も適格とした点である。
[1]とは、例えば、再エネ発電や電車、電気自動車等の直接的CO2排出が無い活動である。これらは活動開始時点で既に脱炭素社会に適合するものであり、適格であることが非常にわかりやすい。
[2]とは、例えば、CO2排出の少ない発電や自動車等、排出ゼロの活動ではないが、排出ゼロへの移行段階と認められる活動である。具体的には、発電と自動車の基準値はそれぞれ100gCO2e/kWh、50gCO2/kmから開始されて次第に厳格化され、それぞれ2050年、2026年には0となる(図表6参照)。また、工業の低炭素化に向けた活動もここに含まれ、例えばアルミ、製鉄、セメント、化学品等における省エネ投資も、その投資によりEU内トップ事業者の原単位基準等をクリアした場合には適格となる。
[3]とは、[1]や[2]の活動を可能にする活動のことであり、「低炭素技術の製造」として、再生可能エネルギー向けの製品・主要部品・機器・機械や、低炭素輸送車両・鉄道車両・船舶の製造、ビル向け省エネ設備(断熱窓、省エネ家電、ヒートポンプ等)の製造、その他低炭素製品の製造(カーボンフットプリント評価を行い、第三者検証を得ることが条件)が位置づけられている(図表6参照)。
なお[1]と[2]は自社の排出削減を行う「Greening of」と呼ばれる活動であり、[3]は自社技術等により他者の削減に貢献する「Greening by」と呼ばれる活動である。
図表5 気候変動緩和分野のEU 基準(タクソノミー)が示された7部門・67活動
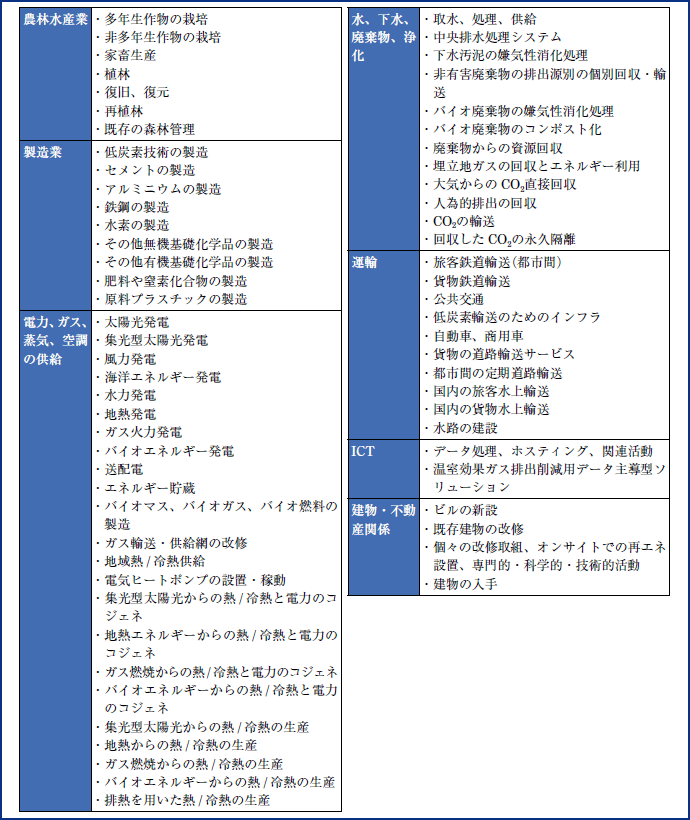
(資料)EU資料を元にみずほ情報総研作成
図表6 EU 基準(タクソノミー)例
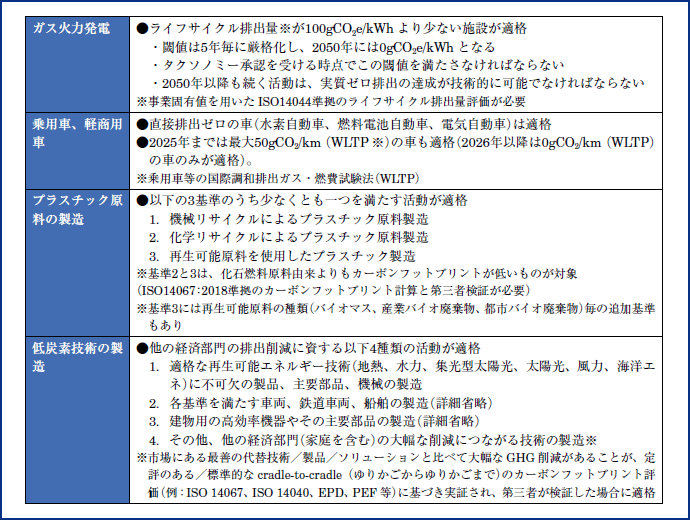
(資料)EU資料を元にみずほ情報総研作成
本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。
レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。