環境エネルギー第2部 シニアコンサルタント 永井 祐介
新たなグリーンボンドの考え方 ―移行と他者貢献―
このEU基準はEU域外におけるグリーンファイナンスやサステナブルファイナンスの考え方にも大きな影響を与えうる。実際、EU はこの 基準のグローバル展開を目指すことを公言して おり、2019年10月には中国やインド、カナダ等 とフォーラムを立ち上げた(13)ほか、先行して議論されているISOにおけるグリーンボンド等の基準検討(14)にも参加している。EU基準で示された基準値は非常に高く、そのまま他国に適用される可能性は低いが、先述した[1]~[3]を適格と認めるという考え方(すなわち、[1]再エネ導入等の「既に脱炭素な活動」に加えて、[2]製造プロセスの低炭素化等の「脱炭素への移行」、[3]低炭素製品・サービスの販売等の「他者の削減への貢献」を認める考え方。図表7参照)等がグローバルスタンダードとなる可能性もある。
図表7 グリーンボンド適格事業の3つの考え方
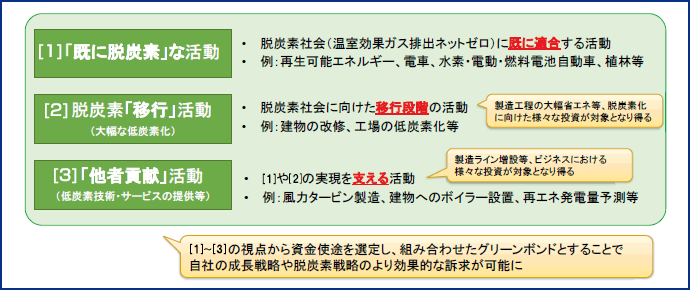
(資料)みずほ情報総研作成
企業から見ると、この考え方は製造プロセスの低炭素化や低炭素製品の販売等も含めた企業全体としての取り組みを、グリーンボンド適格とし得るものである。自社の成長戦略や環境ビジョン等を訴求する為には、グリーン性の説明しやすい一部の環境取組だけでなく、自社事業の中核となる投資や気候変動による影響や機会に対応する投資こそグリーンボンドで資金調達を行い訴求することが重要であり、[1]~[3]を組み合わせる考え方は有効であろう。
そしてその際には、先述した[2]や[3]の考え方、つまり、脱炭素社会への移行経路や他社の活動への貢献量等についての説明を適切に行うことが必要である。
[2]の脱炭素「移行」グリーンボンドは、厳密に言えば、活動毎にパリ協定に沿った削減経路を設定(又は既存のものを参照)し、その削減経路と整合する(活動が終了時点においても削減経路で示された当該年の排出原単位等を満たす)活動を適格とする考え方である(図表8参照)。少し柔軟に解釈すると、活動毎の削減経路は示さずとも、企業として2050年CO2排出実質ゼロ目標にコミットして中期目標(2030年XX%削減等)を設定し、その目標達成のための活動を適格とする考え方もあり得る(このような考え方は個別活動のグリーン性の評価基準であるEU基準では認められないかもしれないが、個別活動ではなく事業者のESGパフォーマンス向上に注目する「サステナビリティ・リンク・ボンド」等の考え方には沿うものであり、移行グリーンボンドの一つとして有効と考えられる)。なお、SBT(Science Based Target)の設定等を行ってきた企業は、その内容も活用して脱炭素「移行」グリーンボンド発行が可能と考えられる。
図表8 脱炭素「移行」活動への適合の考え方
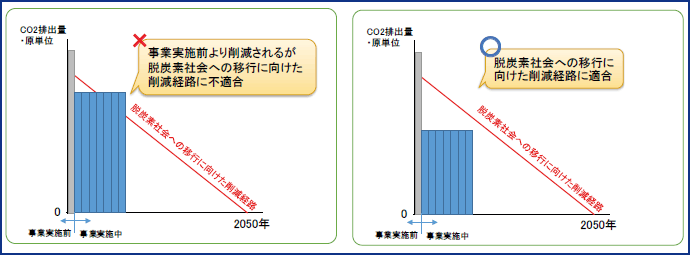
(資料)みずほ情報総研作成
[3]の「他者貢献」グリーンボンドは、厳密に言えば、当該製品の材料調達・輸送・製造・使用・廃棄・再利用に伴う温室効果ガス排出量を評価し、それが市場の最善代替技術と比較して大幅な削減に繋がる事等を示せれば、適格とする考え方である。これまで、LCA等によって自社製品・サービスの他社への貢献量等の評価を行ってきた企業は、その内容も踏まえ、こうした「他者貢献」グリーンボンドの発行が可能と考えられる。
参考までに、グリーンボンド資金使途候補事業を[1]~[3]の考え方の視点で検討する際のフローを図表9に示す。
図表9 3つの考え方への適合検討フロー
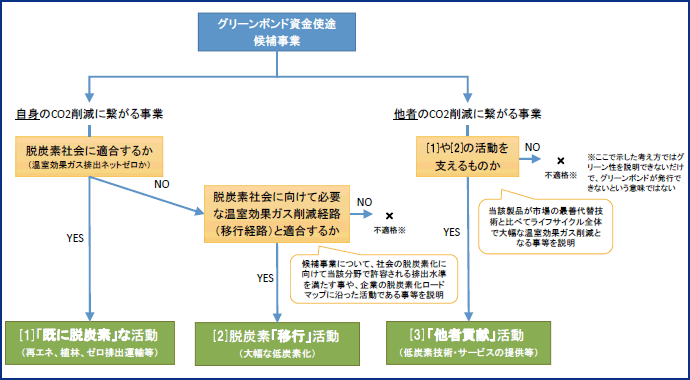
(資料)みずほ情報総研作成
終わりに
これまで見てきたように、グリーンボンドとは自社の成長戦略や環境ビジョンを投資家等に訴求し、投資家層を拡大する手法である。グリーンボンド活用の際に実務上悩ましい点が資金使途の選定であるが、資金使途についての公的基準はまだなく、判断に迷うことも多い。そのため、これまではグリーンな活動であることが説明しやすい再エネ発電や省エネビル(認証制度が整っているためグリーンなビルであることについて共通認識が持ちやすい)を対象とするグリーンボンドが多かった。
しかしEU基準(タクソノミー)案等も示しているように、再エネではなく化石燃料を使用する活動や、低炭素製品や部品を製造する活動のように、グリーンな活動であることの説明が単純ではない活動も、CO2排出実質ゼロへの削減経路と合わせて説明する事や、LCA的視点で評価を行う事等によりグリーンボンドとして認められるようになってきた。実際に国内でもLNG船や電気自動車部品製造を資金使途とするグリーンボンドの事例等が出てきている。
更に、本稿では紹介を割愛したが、最近では海洋プラスチック問題等の様々な環境問題をテーマとしたグリーンボンド、幅広い社会問題を対象とする「ソーシャルボンド」や「サステナビリティボンド」、更には資金使途を限定せず発行体のESG目標等への達成状況に応じて利回りが変わる「サステナビリティ・リンク・ボンド」等、様々なボンドも生まれてきている。 こうしたグリーンボンドの対象拡大や様々なボンド手法の登場により、これまでグリーンボンド等とは無関係と考えていたような業種にも、グリーンボンド等の発行機会が到来している。まだグリーンボンド等を発行していない企業においても、この機会を活かし、自社戦略の訴求や資金調達基盤の強化を図ることが重要ではないか(15)。
注
- (1)2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標。貧困、飢餓、保健、教育、ジェンダー、水・衛生、エネルギー、成長・雇用、イノベーション、不平等、都市、生産・消費、気候変動、海洋資源、陸上資源、平和、パートナーシップの17のゴールと169のターゲットから構成される。
- (2)なお、環境以外の社会課題の解決に繋がる活動を資金使途とする「ソーシャルボンド」や、環境と環境以外の社会課題の解決に繋がる活動を資金使途とする(つまりグリーン+ソーシャルな)「サステナビリティボンド」、それらのローン版としての「グリーンローン」「ソーシャルローン」「サステナビリティローン」等の様々な類似スキームがあるが、それぞれのメリットや論点は共通性があるため、本稿では最も発行が多く議論も進んでいるグリーンボンドを例に整理する。
- (3)例えば現在多くの企業がTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)に基づく気候変動リスクと機会の財務的影響の把握・開示やSBT(ScienceBased Targets:パリ協定目標に整合した意欲的な温室効果ガス削減目標)の設定等に取組んでいるが、これらの企業が次の一手としてグリーンボンド発行に進み、発行事例が更に増加する可能性もある。
- (4)資金使途はグリーンな活動に限定されるものの、償還金の原資は当該グリーン活動には限定されない。例えば風力発電を資金使途とするグリーンボンドにおいて、その風力発電が失敗してもグリーンボンドを発行した企業が残っていれば、グリーンボンド購入者は他事業からの収益を元に償還金を受け取ることが出来る。また、厳密には、資金使途と償還金原資が同一である「プロジェクト債」のグリーンボンドも存在するが、その発行量は限定的である。
- (5)Climate Bonds Initiativeは、ロンドンに拠点を置く国際NGOで、100兆ドルの債券市場を気候変動対策のために活用することを目的とし、低炭素・気候レジリエントな経済への迅速な移行のために必要なプロジェクトや資産への投資を促進する活動を行っている(なお、みずほ証券もCBIのPartnerである)。日本国内では、鉄道建設・運輸施設整備支援機構と明電舎がCBI基準に準拠したグリーンボンドを発行している(2019年11月時点)。
- (6)基準作りには民間企業も参加可能であり、参加することで基準作りに影響を与える事や、国際的な議論動向をいち早く把握する事も有益と考えられる(例えば海運の基準策定には日本郵船が参加している)
- (7)米国の指数会社S&P Dow Jonesやドイツの指数会社Solactiveが提供しているグリーンボンド指数
- (8)CO2等の温室効果ガスの排出削減や吸収増加により気候変動の進行抑制を目指す活動。再エネ、省エネ、植林等。
- (9)既に起こりつつある気候変動の影響に対処し、被害を回避・軽減していく活動。防災減災、農作物の改良等。
- (10)国連環境計画の金融イニシアティブ(UNEP FI)と欧州銀行協会(EBF)は、銀行がタクソノミーを融資判断で適用するためのガイドラインを検討中である。2020年2~3月にガイドライン公表予定。
- (11)人為的なCO2の排出量と人為的な吸収量を均衡させ、その排出量を実質ゼロ(ネットゼロ)とすること。パリ協定が言及している気温上昇を1.5℃に抑えるという目標を50%の確率で実現するには、CO2等の温室効果ガス排出量を2030年までに45%削減し、2050年前後に実質ゼロにする必要があると言われており、EU基準はその水準を目指している。「2050年温室効果ガス排出実質ゼロ」は、2019年9月の国連気候行動サミットにおいて、欧州を中心とする66の国・自治体、93の企業、12の投資家が表明・賛同をする等、気候変動対策としての先進性を示す目安となりつつある。
- (12)WLTP:乗用車等の国際調和排出ガス・燃費試験法
- (13)2019年10月、EUは中国、インド、カナダ等7か国と共にIPSF(サステナブルファイナンスに関する国際プラットフォーム)を立ち上げ。今後タクソノミーや開示、基準やラベルに関する好事例の共有や協調を行う予定。
- (14)ISOにおいてグリーンファイナンスやサステナブルファイナンスに関する4つの国際規格が検討中であり、その一つであるISO14030では資金使途に関する基準(タクソノミー)が議論中。
- (15)みずほ情報総研では、気候変動対策に関する政策立案支援や民間コンサルティングに加えて、みずほ証券と連携したグリーンボンド等の発行支援も実施しております。お気軽にご相談ください。
本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。
レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。