環境エネルギー第1部 地球環境チーム コンサルタント 長島 圭吾 シニアコンサルタント 熊久保 和宏
既往手法とコ・イノベーションの整理
このように、中長期的な気候変動対策に関する国際協力では、コ・イノベーションが重要となるが、コ・イノベーションは未だ新しい手法で、解釈や具体的なイメージが明確ではない。そこで、本項では、既往手法を参照しながら、コ・イノベーションとはどのような手法なのか、整理を試みる。
(1)既往手法の整理
はじめに、国際協力における既往手法として、環境省「気候変動緩和策に関する国際協力ビジョン」の検討において取り上げられた、技術移転、現地化、ジュガード・イノベーション、リバース・イノベーションの4つの手法について確認する。
第一の手法は、技術移転である。図表4の左上にあるとおり、先進国内での課題・ニーズがまず先にあり、その課題を先進国のソリューションで解決する([1])。そこで活用したソリューションを、そのまま途上国に移転し([2])、そのソリューションで途上国の課題・ニーズを解決する([3])。
第二の手法は、現地化である。図表4の右上にあるとおり、先進国内で課題・ニーズがまず先にあり、その課題を先進国のソリューションで解決する([1])。次に、現地化では、活用したソリューションを途上国の課題・ニーズに応じてカスタマイズし([2])、そのソリューションで途上国の課題・ニーズを解決する([3])。先進国のソリューションをそのまま途上国に展開しない点で、技術移転とは異なる。
第三の手法は、ジュガード(4)・イノベーションである。図表4の左下にあるように、途上国特有の市場環境・ニーズがまず先にあり、それに対応するソリューションが生まれる([1])もので、生まれたソリューションが先進国に還元されるかどうかは問わない([2])。
第四の手法は、リバース・イノベーションである。図表4の右下にあるように、先進国に潜在的な課題・ニーズがまず先にあり([1])、それに対応する技術的な能力が先進国内にある中で、途上国のほうがソリューションを創る環境が整っている等の理由で、先進国の技術的能力を途上国に持ち寄り([2])、途上国で現地に適したソリューションを生み出し、途上国の課題・ニーズに対応([3])した上で、先進国の潜在的な課題・ニーズを踏まえながらそれを先進国に取り入れる([4])ことで先進国の潜在的な課題・ニーズに対応させるものである([5])。
図表4 先進国の途上国に対する国際展開の手法(例)
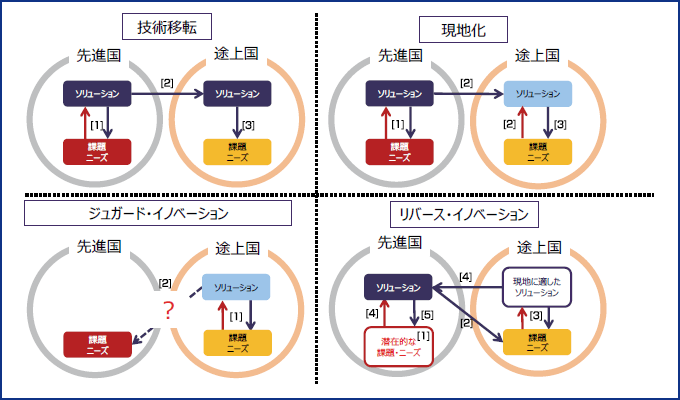
(資料)みずほ情報総研作成
(2)コ・イノベーションとは ―新しい時代の協力のあり方―
以上の4つの手法に対して、コ・イノベーションとは、どのような手法なのだろうか。冒頭で説明したように、コ・イノベーションとは、「我が国の技術や制度をパートナー国にそのまま導入・普及させる一方向のものではなく、パートナー国と我が国の協働により、パートナー国に適した脱炭素製品・サービス・技術の市場創出と経済社会システム、ライフスタイルの大きな変革をもたらすイノベーション」である。すなわち、図表5に示したとおり、途上国では、社会・経済の成長とともにビジネスの環境が徐々に整い、先進国と共通の課題が出現する([1])。それぞれの強みを活かしつつ、途上国と我が国の協働により共通のソリューションを生み出し([2])、そのソリューションで先進国・途上国の課題・ニーズを解決する([3])ものである。
「Co」という言葉には「一緒に」の意味がある。途上国を“パートナー”と捉え、一緒にその国に合った製品やサービスの市場を創り、イノベーションにつなげていきたい、というメッセージがこの言葉には込められていると感じる。これまでの国際展開の手法に、新しい手法が提示された形だ。
図表5 コ・イノベーションのイメージ
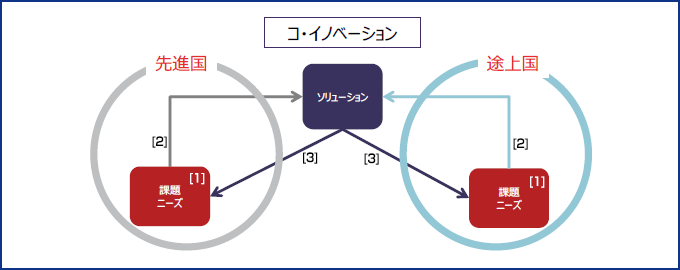
(資料)みずほ情報総研作成
今後の気候変動対策における国際協力のあり方
以上をふまえ、中長期的な気候変動対策に関する国際協力において重要となるコ・イノベーションを促進するために、今後、どのような考え方や取組が必要とされるのか、考えてみたい。これに関連して、今年1月に「コ・イノベーション」をテーマに当社が開催したフォーラム(5)において、官民4名の有識者から様々な意見があった。ここでは、コ・イノベーションを促進するためには、政府による具体的な目標設定やその実現のための政策の策定・実施が必要であるとの意見が挙げられた。具体的には、政府として何を目指すのかというゴールが明確に示されているからこそ企業は中長期的なビジョンを掲げることができるということ、そして投資環境整備は、政府による目標や政策によって担保されるということであった。それでは今後、政府には、コ・イノベーションを促進するためにどのような目標や政策の策定が求められるのか、以下に3つ取りあげたい。
[1] 気候変動緩和策に関する国際協力の長期目標の策定
まず、気候変動緩和策に関する国際協力の長期目標の策定である。気候変動緩和策に関する国際協力に関連して現在定められている目標としては、日本の約束草案(2020年以降の新たな温室効果ガス排出削減目標(6))においてはJCM(二国間クレジット制度)の日本政府事業分により2030年度まで累積で5,000万から1億t-CO2の削減目標が記載されており、内閣府「エネルギー・環境イノベーション戦略(7)」においては、2050年に全世界で数10~100億トン規模の削減ポテンシャルが記載されている。長期についてはポテンシャルの記載に留まっており、目標値はない。2018年6月より、首相官邸で「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略策定に向けた懇談会」が開催され、2050年を見据えた議論が始まっており(8)、気候変動緩和策に関する国際協力においても、明確な長期の定量目標の策定について議論が行われることを期待したい。
[2] 気候変動緩和策に関する国際協力のロードマップの策定
次に、気候変動緩和策に関する国際協力のロードマップの策定である。気候変動緩和策に関する国際協力の実行にあたっては、政府、自治体、業界団体、企業、専門家、NGO、研究機関等、様々なステークホルダーによる取組が必要となる。2018年3月に策定された「気候変動緩和策に関する国際協力ビジョン」及び2018年6月より首相官邸で開催されている「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略策定に向けた懇談会」等を受けて、どのような体制で進めていくか、どの主体がどのような削減行動をすべきなのか、より具体化するロードマップを策定し、様々なステークホルダーの取組強化の促進が重要と考えられる。
[3] 気候変動適応策への拡充
最後に、気候変動適応策への拡充である。途上国においては、気候変動の適応にも高いニーズが存在しており、市場規模も拡大傾向にある(9)。しかし、2018年3月に策定された「気候変動緩和策に関する国際協力ビジョン」では、適応策については、「このビジョンは気候変動緩和策を対象とするものであるが、持続可能な開発目標(SDGs)に基づく施策の推進の観点も含め、適応策についても積極的な国際協力を行う」と記載するに留まっている。2018年6月に公布された気候変動適応法においては、4つの柱の1つとして「適応の国際展開等」が位置づけられており、適応策に関する国際協力についても、中長期のビジョン、ロードマップの策定が重要と考えられる。
おわりに
本稿では、気候変動緩和策に関する国際展開において重要な手法となるコ・イノベーションについて、必要とされる背景や既往手法も踏まえた整理を行った。今後、コ・イノベーションの促進が期待されるが、そのためには、政府による明確な目標や政策の策定が必要となるだろう。2018年6月より首相官邸では「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略策定に向けた懇談会」が開催され、2050年を見据えた議論が始まっており、2019年6月には、G20(金融世界経済に関する首脳会合)が日本で初めて開催される。世界が日本に注目する中、気候変動緩和策に関する国際協力の長期目標やロードマップの策定、気候変動適応策への拡充など、明確な目標や政策の策定に期待したい。
注
- (1)
- (2)環境省「気候変動緩和策に関する国際協力ビジョン」によると、パートナー国とは、「我が国と気候変動緩和策に係る国際協力を行う途上国」とされる。
- (3)IEA(International Energy Agency:国際エネルギー機関)は、第1次石油危機後の1974年に、キッシンジャー米国務長官(当時)の提唱を受けて、OECD の枠内における機関として設立された。事務局所在地はパリ。エネルギー政策全般をカバーし、[1]石油・ガス供給途絶等の緊急時への準備・対応と市場の分析、[2]中長期の需給見通し、[3]エネルギー源多様化、[4]電力セキュリティ、[5]エネルギー技術・開発協力、[6]省エネルギーの研究・普及、[7]加盟国のエネルギー政策の相互審査、[8]非加盟国との協力等に注力している。
- (4)ジュガード(Jugaad)はヒンディー語で「革新的な解決策」や「創意工夫と賢さから生まれた解決策」の意。
- (5)
- (6)
- (7)
- (8)
- (9)国連環境計画(2018)「The Adaptation Gap Report」によると、「気温上昇を産業革命前から2℃に抑えた」状態では、適応対策にかかるコストは2025~2030年では年間1,400億米ドル~3,000億米ドル、2030~2050年では年間2,800億米ドル~5,000億米ドルと試算している。
本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。
レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。
関連情報
この執筆者(熊久保 和宏)はこちらも執筆しています
-
2019年1月29日