環境エネルギー第1部
チーフコンサルタント 佐野 翔一 コンサルタント 横尾 祐輔 次長 松井 重和
調査結果の分析(続き)
(5)LED照明の効率に対する意識
LED照明は寿命が長く、一度設置されると長期にわたって使用される。そのため、もし、エネルギー消費効率の悪いLED照明が導入されると、それが長期にわたり使用され、省エネ余地を損なう可能性がある。最新のLED照明にはエネルギー消費効率が200lm/W(6)程度の製品が登場している一方で、100lm/W程度の製品もあるなど、製品によって効率に大きな差がある。このような状況を踏まえると、地球温暖化対策計画の見直しに関する議論や長期的な大幅削減を視野に入れる場合、単にLED照明の普及を図るだけでなく、より高効率なLED照明の普及を図る必要があると考えられる。このような問題意識のもと、以下2点の調査を実施した。
- LED照明のエネルギー消費効率に関する知識の有無(事業所の担当者は、LED照明にも様々なエネルギー消費効率の製品があることを認識しているか否か)。
- 直近1年にLED照明への改修を実施した事業所における、照明器具選定の際のエネルギー消費効率の考慮の程度。
図表10に、LED照明のエネルギー消費効率に関する知識の有無に関する結果を示す。本調査において「LED照明でも製品によりエネルギー消費効率に相当の差がある状況を知っていたか」について尋ねたところ、全体ではおよそ半数の45%の事業者が「知っていた」と回答し、製品によってエネルギー消費効率に差がある状況がある程度認知されていることが確認された。建物用途別に見ると、ホテル・旅館、娯楽施設などでは60%以上の事業者が「知っていた」と回答した。一方で、中小規模の事業所が多いと考えられる飲食店や福祉施設などでは30~40%程度となっており、建物用途によって差がある状況が確認された。
図表11に、直近1年にLED照明への改修を実施した事業所における、照明器具選定の際のエネルギー消費効率の考慮の程度を示す。およそ半数の54%の事業者が投資回収年などの経済性も考慮しつつある程度効率の高い製品を選択していたが、17%の事業者はエネルギー消費効率を意識せずに製品を選択しており、必ずしも効率のよいLED照明が導入されているとは限らない可能性が示された。後者の割合はそれほど大きくないものの、限られた省エネ余地の中でさらに省エネ対策を進めようとしている現状においては、見逃せない割合であるだろう。
図表10 建物用途別のLED 照明のエネルギー消費効率に関する知識の保有状況
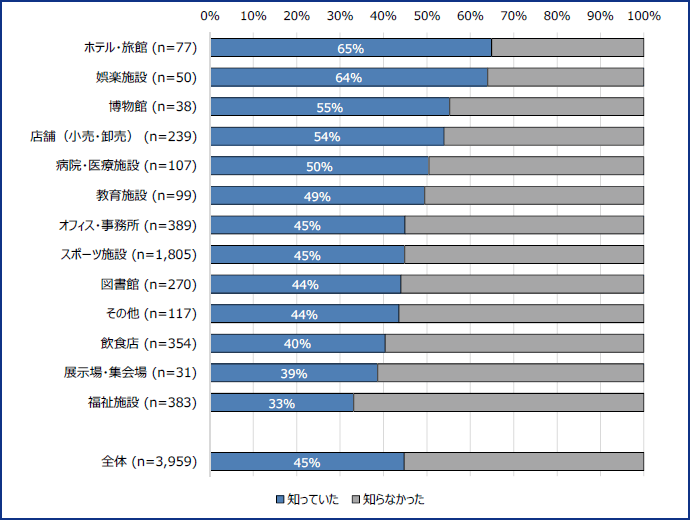
(資料)みずほ情報総研「平成30年度民生部門における低炭素化対策・施策検討委託業務報告書」(環境省委託事業)
図表11 直近1年間に改修を行った事業所における照明を改修した際のLED 照明のエネルギー消費効率に対する意識
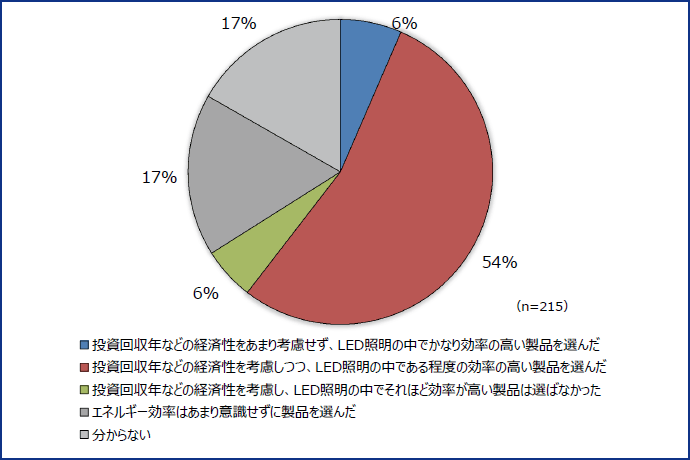
(資料)みずほ情報総研「平成30年度民生部門における低炭素化対策・施策検討委託業務報告書」(環境省委託事業)
照明の温暖化対策の更なる推進に向けて
前述の分析結果より、直近(2015年~2018年)に竣工した建築物ではLED照明導入比率は80%に及ぶこと、既築建築物でのLED照明への改修が進んでいること、しかし目標対比での改修ペースは十分とはいえないこと、特にオフィス・事務所においてはテナントビルでの導入ペースが遅いことが明らかとなった。テナントビルでの導入ペースが遅い要因としては既述のとおりオーナー・テナント問題が考えられる。この問題を解決する方法の一つとして「グリーンリース」の普及が考えられる。グリーンリースとは、ビルオーナーとテナントが協働し、不動産の省エネなどの環境負荷の低減や執務環境の改善について契約や覚書等によって自主的に取り決め、その取り決め内容を実践していく取組である(7)。この取組を円滑に進めるためには、オーナーとテナントの仲介ができ、契約等の手続きにも詳しいプレーヤーが必要となる。環境省と国土交通省は昨年度まで「テナントビルの省CO2促進事業」などの予算により、この取組を支援してきた。しかし、そのようなプレーヤーはまだ十分には育っておらず、グリーンリースも進んでいない。長期戦略においても、オーナー・テナント問題は取り上げられていることも踏まえれば、前述のようなプレーヤーを育成するためにも、引き続き政策的支援が必要ではないだろうか。
また、LED照明の導入は全体としては進んでいるものの、必ずしも効率のよいLED照明が導入されていない可能性が示唆された。照明器具は法定耐用年数が15年であり、長期間にわたって使用されると考えられる。地球温暖化対策計画の見直しや長期的な大幅削減を視野に入れた場合は、より高効率なLED照明の導入を推進していくべきであると考えられる。そのためには、単に高効率なLED照明の導入に対する支援を行うだけでなく、高効率な製品の認知度を高める普及啓発も必要となるだろう。また、中小規模の事業所が多いと考えられる飲食店や福祉施設などが主たるターゲットとなることを踏まえ、セグメントに応じたアプローチ手法や発信内容の工夫も必要となるだろう。各セグメントにおける省エネに関する情報取得チャネル、設備導入に関する意思決定プロセス、担当者の省エネに関する理解度等に応じた普及啓発が望まれる。
注
- (1)民生部門は家庭部門と業務部門の総称。
- (2)地球温暖化対策計画では計画に掲げた110個の対策(業務部門以外も含む)の進捗状況を毎年点検してAからEの5段階で評価をしている。2019年3月に公表された最新の評価結果ではB以上の評価を得た対策は30個(約27%)であった。
A .このまま取組を続ければ目標水準を上回ると考えられる対策のうち、実績が既に目標水準を上回るもの:10件
B .このまま取組を続ければ目標水準を上回ると考えられる対策(A.を除く):20件
C .このまま取組を続ければ目標水準と同等程度になると考えられる対策:50件
D .取組がこのままの場合には目標水準を下回ると考えられる対策:25件
E .その他定量的なデータが得られないもの等:5件 - (3)主要なエリアの照明の種類について回答があったサンプルのうち、主要なエリアの照明の種類が「LED照明」であると回答したサンプルの割合。
- (4)社団法人照明学会・社団法人日本照明器具工業会(2011)「えっ…まだ昭和の器具をお使いですか?」より。
- (5)
- (6)lm/Wは全光束(lm)を効率(W)で除したエネルギー消費効率を表す単位で、数値が大きいほどエネルギー消費効率が優れている。
- (7)
グリーンリースの定義は環境省ホームページ「グリーンビルナビ」に基づく。
本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。
レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。