みずほ情報総研 環境エネルギー第2部 コンサルタント 内藤 秀治
ボランタリー・クレジットを巡る、4つのメガトレンド
前項に記載した背景から、ボランタリー・クレジットの取引量は直近数年間で大きく増加し、市場が大きく変化している。また、企業による自主的な活用以外にも様々な動きが出てきており、それらも含め市場を理解する必要がある。ここでは、最近のクレジット市場に影響を与えている主要な要因・トレンドを下図の通り整理した。
図3 ボランタリー・クレジットを取り巻く、4つのメガトレンド
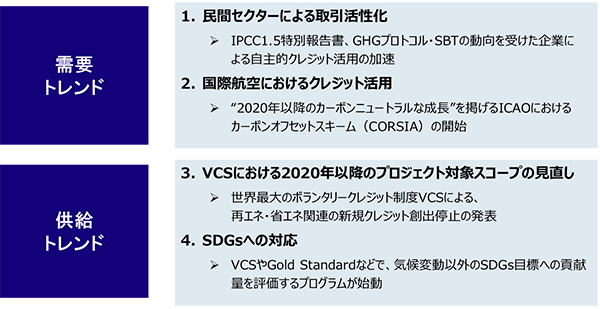
(出所)みずほ情報総研作成
(1)民間セクターによる取引活性化
まずは、直近のボランタリー・クレジット取引量の推移について、ボランタリー・クレジットの盛り上がりを象徴するグラフを下図に示す。2017年から2018年にかけ大幅な取引量が増加しており、その傾向は2019年も継続している。
図4 直近のボランタリー・クレジット取引量の推移
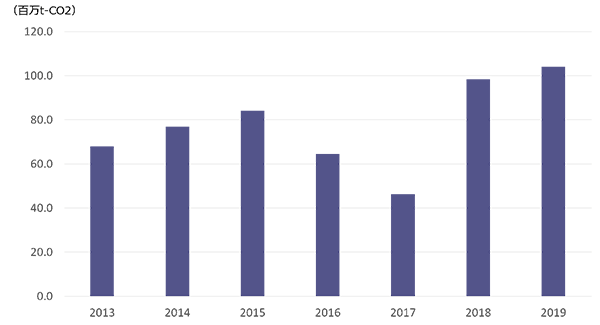
(出所)State of the Voluntary Carbon Markets 2019・2020よりみずほ情報総研作成
この盛り上がりを引き起こした主な要因として、IPCC1.5℃特別報告書の公表とGHGプロトコル・SBTによるネットゼロに向けた新たなガイダンス策定の動向が挙げられよう。既に筆者が執筆したコラムでも紹介しているとおり*3、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)が2018年10月に公表した「1.5℃特別報告書」において、産業革命以前からの気温上昇を1.5℃未満に抑えるためのGHG排出削減経路として、(1)2050年前後までに世界全体で排出ゼロ、(2)それ以降はさらなる固定・吸収(Carbon Removal)が必要であることが示された。
この内容を受け、これまで土地利用に関連する温室効果ガスの固定・吸収を評価対象としていなかったGHGプロトコルやSBTが炭素貯留や土地利用によるCarbon Removal効果を別途評価するための新たなガイダンスの策定開始を発表し、この検討事項にCarbon Removalに資するクレジット活用も採用された。これにより、森林吸収や農地貯留等のプロジェクト実施によって創出されたクレジットの活用は、自主的な排出削減の訴求に加え、SBTネットゼロ等へのコミットにも資する可能性があり、ボランタリー・クレジットの中でも特に注目を集めている状況である。
また、2020年9月2日、マークカーニー(イングランド銀行総裁、国連気候アクション・ファイナンス特使)らが主導し、民間セクターにおけるクレジット市場拡大を目的としたタスクフォース「Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets(TSVCM)」を設立した。同タスクフォースには、下表に示す通り数多くのグローバル企業や金融・機関投資家が参加しており、ネットゼロ社会実現に向け「現在のクレジット市場を15倍以上にする必要性」等の将来のクレジット市場に対する具体的な提言を行っており、今後の動向が注目されている。
表1 TSVCMタスクフォース・諮問グループメンバー(一部抜粋)
|
クレジット関係 |
Verra、Gold Standard、American Carbon Registry、IETA、 South Pole、IHS Markit、Ecosystem Marketplace |
|
エネルギー関係 |
BP、Shell、RWE、Total、BHP Billiton、 |
|
農林業・穀物関係 |
Bunge、Natural Capital Partners、The Nature Conservancy |
|
海運関係 |
Maersk |
|
金融・投資家関係 |
BlackRock、Bank of America、Goldman Sachs、BNP Paribas、USB、Standard Chartered、Citi、AXA Investment Managers、World Bank、S&P Global Platts、CDP |
|
その他(欧米) |
DSM、Uniliever、Nestle、Microsoft、BSR(Transform to Net Zero)、Salesforce、XCHG、Coca-Cola Company |
|
その他(欧米以外) |
TaTa、Mahindra、Temasek、KenGen、Ita? Unibanco、Elion |
これらの例は、民間セクターにおける取引活性化に関する一事例であるが、既存の相対取引から発展し、「長期調達契約」や「先物取引」等にも対応可能な"新市場"が、グローバル企業を中心に形成される見込みであり、現状のボランタリー・クレジット市場の把握と今後の展開を予想する上で、見逃すことが出来ない動きである。
(2)国際航空におけるクレジット活用
民間セクターの自主的な活用拡大と双璧をなす動向が、国際航空によるクレジット活用の動きである。国際民間航空機関(ICAO)では、第37回総会において、グローバル削減目標の一つとして 2020年以降GHG排出を増加させない(" Well-to-wake greenhouse gas (GHG) emissions not exceeding 2020 levels in 2035")ことを掲げており、その達成手段として、「国際民間航空のためのカーボン・オフセット及び削減スキーム」(Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation:CORSIA)が 2021年より開始され、最大25億トンのクレジット需要が予想されている*4。
COVID-19の影響により、国際航空業界における排出量が短期的に大幅増加する可能性は低いと考えられるが、中長期的な経済活動の回復・増加に伴うクレジット需要は相当量発生することが推察され、こちらもクレジット市況を把握する上で注視すべき動向である。
また、国際航空に近い業界として、国際空港評議会(ACI)が主導するAirport Carbon Accreditation(ACA)においても、カーボン・ニュートラル・ネットゼロ実現に向けたクレジット活用の動きが拡大している。今後、企業による自主的な取組みに併せて、業界団体が主導するプログラム・イニシアティブの動向にも注目が集まることが予想されよう。
(3)VCSにおける2020年以降のプロジェクト対象スコープ見直し
これまで需要側のトレンドを解説したが、供給側でも大きな動きがあった。その一つが、世界最大のクレジット制度であるVCS(Verified Carbon Standard)のプロジェクトスコープの見直しである。2019年9月に公表されたスコープの見直し結果を下図に示す。
図5 VCSのプロジェクト対象スコープ見直し概要
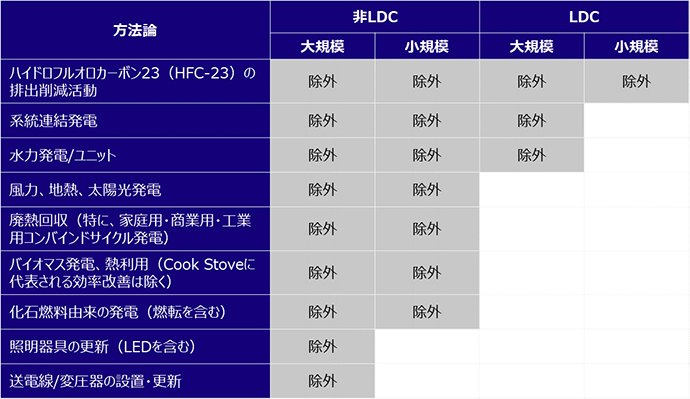
(出所)VCS Standard Version4.0よりみずほ情報総研作成
これまでVCSでは上図にして示す省エネ・再エネプロジェクト由来より多くのクレジットが創出されてきたが、VCSを運営するVerraは、これらのプロジェクトのAdditionality(追加性)が既にないことを根拠として、一部方法論やLDC(Least Developed Countries)で実施されるプロジェクトを除き、スコープ対象外とすることを発表した。また、同様にWWFが主導し運営されるGold Standardにおいても再エネ案件の対象制限を発表し、[1]世界銀行によって分類される高中所得国および高所得国にある国または地域で実施されるプロジェクト、[2]再生可能エネルギーの浸透レベルが総グリッド容量の3.5%を超える国で実施されるプロジェクトは、2020年1月以降対象外となった*5。このスコープ見直しによるクレジット市場への影響は非常に大きく、2017年から2019年にかけては、“スコープ外対象のクレジットの買いだめ”とも推測される取引量の変化が下図の通り見られる。グラフだけを見た場合、一見、再生可能エネルギー由来のクレジット取引が今後も加速するようにも考えられるが、VCSのスコープ見直しを考慮すると“一時的な増加”の可能性が高いと筆者は考えている。
図6 クレジット種別ごとの取引量推移
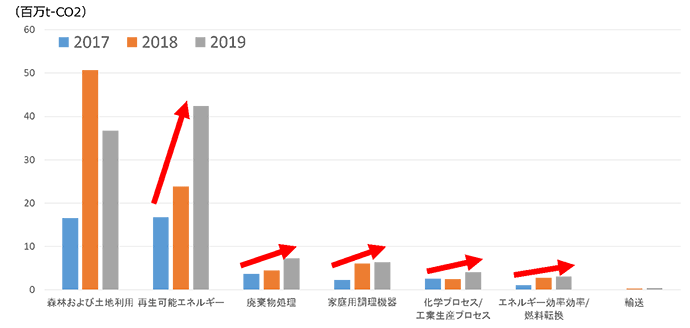
(出所)State of the Voluntary Carbon Markets 2019・2020よりみずほ情報総研作成
(4)SDGsへの対応
近年SDGsへの対応も企業価値を高める取組みの一つである。この潮流を受け、いくつかの制度においては、GHG排出削減以外の副次的な効果を評価するフレームワークの開発にも着手している。その概況を下図にて整理した。
図7 主要ボランタリー・クレジット制度におけるSDGsへの対応例
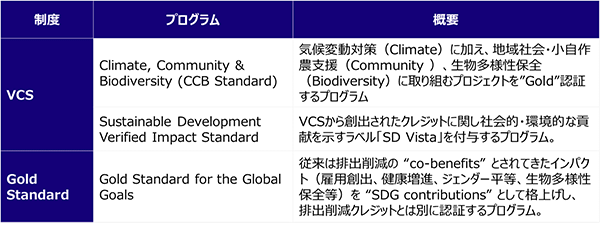
(出所)Verra、Gold Standard公表資料よりみずほ情報総研作成
例えば、VCSは「CCB Standard」や「Sustainable Development Verified Impact Standard」を開始しており、その他Gold Standardにおいても、「Gold Standard for the Global Goals」と呼ばれるSDGsインパクトの評価プログラムが動いている状況である。これらの動きはまだ開発段階や小規模に実施されている段階であるが、クレジット活用を促進するプログラム(CORSIA・ACA等)においては、使用可能なクレジット基準の一つに“Do no harm”を設け、間接的にSDGsを考慮している他、TSVCMにおいても「RECOMMENDED ACTION」の中で、“クレジット活用による副次的効果”としてSDGsへの貢献を推奨している。この動きが更に拡大した場合、“通常のボランタリー・クレジット”と“SDGsラベル付きボランタリー・クレジット”といった区別がなされ、“CO2削減価値”以外の評価軸による差別化も起こり得るだろう。
本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。
レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。
関連情報
この執筆者はこちらも執筆しています
-
2020年6月18日
―1.5℃目標に向けた新たな選択肢として―
-
2019年4月26日