みずほ情報総研 環境エネルギー第2部 コンサルタント 内藤 秀治
今後のクレジット市場に影響しうる新たな動き
前項で述べた最近の市場トレンドに加え、今後のクレジット市場やクレジット・オフセットプログラム等の制度設計に大きな影響を及ぼす可能性のある、着目すべき2つの新たな動きを紹介する。既にクレジット市場に参加している事業者の“次なる一手”から、将来起こりうる変化を“先読み”することで、クレジット活用によるビジネスチャンス獲得にも繋がるだろう。
(1)クレジットのトークン化
ボランタリー・クレジットを調達する上での障壁の一つは、クレジット価格が不透明であることではないだろうか。冒頭で解説した通り、相対にて取引されるため価格情報はオープンにされておらず、事業計画を立てることは困難を極める。この点を問題の出発点として、現在いくつかのグループでは、クレジットのトークン化による透明性の確保をする試みが開始されている。例えば、2020年7月には、XpansivやMicrosoftらが主導するThe Inter Work Alliance (IWA) Sustainability Business Working Groupがクレジットのトークン化着手を発表した他、2020年12月には、Upholdが主導するUniversal Protocol AllianceがREDD+由来のVCSクレジットをトークン化した「Universal Carbon(UPCO2)」を発表した。
図8 UPCO2価格推移
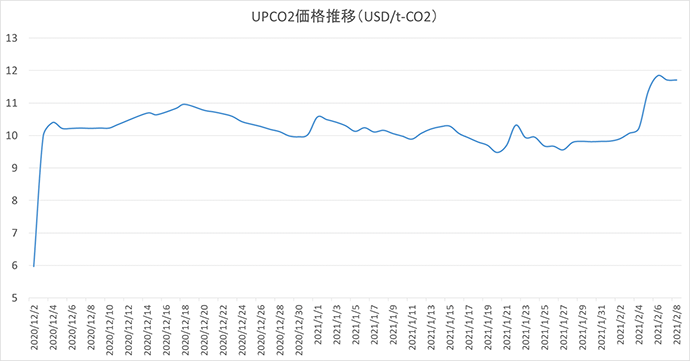
(出所)Upholdホームページよりみずほ情報総研作成
クレジットのトークン化は短期的には「透明性確保」に加え、クレジット創出までの煩雑な「MRVの効率化・コスト削減」にも効果を発揮することが期待されるが、中長期的にはパリ協定第6条で議論されている市場メカニズム制度や各国の削減目標(NDC)とのダブルカウント回避にも有効な手段とも言えよう。既に試行的な論文も発表されており、UNEP、Microsoft、ベルリン工科大、デンマーク工科大が発表した「Blockchain Application for the Paris Agreement Carbon Market Mechanism-A Decision Framework and Architecture」*6では、パリ協定第6.2条で議論されているITMOs(internationally transferred mitigation outcomes)のダブルカウント防止手法と併せて、NDCとボランタリー市場とのダブルカウント防止の解決策として、トークンによる管理を提案している。仮にNDCとボランタリー市場がトークン化により関係性を持った場合、クレジット価格は各国のキャップ&トレード価格や炭素税等の影響を受ける可能性もあるだろう。
(2)Oil and Gas業界によるクレジット創出事業者の買収
トークン化されたクレジット取引に併せて筆者が注視している動きが、巨大資本企業によるクレジット創出事業者買収の動向である。今後クレジット調達を検討する際、安定した価格で長期的に取引できるか否かが着目点になると考えられるが、これまで解説してきた通り、ボランタリー・クレジット市場は刻々と変化しており、外部調達をする限りは長期的かつ安定調達が必ずしも保障されるとは限らない。
そこで、民間セクターの中で、特に大規模にクレジット調達を行っているOil and Gas業界では、外部からのクレジット調達から更に加速し、クレジット創出事業者の買収に踏み込んでいる。例えば、Shell Australiaは2020年8月にSelect Carbonを、BPは2020年12月にFinite Carbonの買収を発表しており、今後も同様の動きが拡大する可能性が高いと筆者は考えている*7。今後クレジット調達を検討するに当たっては、市場動向に併せて、このようなグローバル企業が展開する戦略にも注視する必要がありそうだ。
最後に
ここまで解説したボランタリー・クレジットを取り巻くトレンドを一言でまとめると、「需要拡大×供給クレジットの高付加価値化」と言えよう。このトレンドは、更に戦略的な立ち位置を築く「機会」になり得るが、参入障壁が高まる「リスク」にもなり得るため、いずれの動向にも注視が必要である。また、グローバルでは様々な利害関係者がプラットフォームを形成し、ボランタリー・クレジットの活用に加え、新たなクレジット市場や仕組みも検討される等、動向は刻々と変化している状況である。
今後、ボランタリー・クレジットの活用目的を“目標達成に向けた現実解”から“自社ビジネス拡大のツール”まで拡大するためには、流動的に変化する市場動向やその要因を適切に整理・分析しておくことが重要であり、GHGプロトコルやTSVCM、IWA等のプラットフォーム及び参画企業・団体の動きが着目点の一つとなろう。
注
- *1)まずは発電施設を対象とするが、今後、石油化学、化学、建材、鉄鋼、非鉄金属、製紙、航空にも範囲を広げる予定。
- *2)例えば、米国のカリフォルニア州排出権取引制度では、現在排出枠の8%までクレジットの使用が可能である。
- *3)
- *4)2019年8月に公開された第40回総会ワーキングペーパーにおける推計値であり、COVID-19の影響や近年生産・供給が拡大している代替航空燃料(Sustainable
Aviation Fuel:SAF)の動向は考慮されていない点に注意が必要。
- *5)例外として、国連が定める後発開発途上国(LDC)、小島嶼開発途上国(SIDS)、または内陸開発途上国(LLDC)で実施プロジェクト、その他、特殊な状況(紛争地域等)がある場合は免除される。
- *6)
- *7)一例として、bp、Eni、Equinor、Galp、Occidental、Repsol、Royal Dutch Shell、Totalの大手エネルギー会社8社は、2020年12月17日「エネルギーの移行に係る6つの原則」の合意を発表し、その一つに炭素吸収源の開発が挙げられている。
本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。
レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。
関連情報
この執筆者はこちらも執筆しています
-
2020年6月18日
―1.5℃目標に向けた新たな選択肢として―
-
2019年4月26日