
みずほリサーチ&テクノロジーズの社会政策コンサルティング部はPFM(パブリック・ファンド・マネジメント、補助金事務局)業務の分野で存在感を発揮し、事業の公募から事業後フォローまでを一貫して担ってきました。数々のPFM業務に携わってきた鹿内 智浩と日諸 恵利が、その社会的意義、やりがいを語ります。
大切なのは現場を知ること。事業者を深く理解して、柔軟にサポート

▲社会政策コンサルティング部 上席主任コンサルタント 鹿内 智浩
国が支出する各種補助金は公的資金であり、政策に沿って本来の目的通り正しく活用されなくてはなりません。みずほリサーチ&テクノロジーズの社会政策コンサルティング部が果たすのは、いわばその番人としての役割。補助金の執行・管理をワンストップで行うPFM業務を手がけています。
鹿内:補助金の種類は実にさまざま。震災復興関連のものからサプライチェーン強靭化のためのもの、先端技術の実用化のためのものなどもあります。これらの補助金の公募を国の所管部署と共に立ち上げ、補助対象とすべき事業の精査や最終的に支払う補助金額の確認、事業全体の効果分析など、長期にわたった執行・管理を行っています。
社会政策コンサルティング部でPFM業務に携わる社会レジリエンス推進チームは約25名の社員と40名以上の派遣社員から構成されていて、中でも私は「津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金」、「サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金」などの事業でプロジェクトリーダーや進捗管理を務めています。
一方、医療政策や医療産業の分野で、官公庁や自治体からの受託調査研究や民間コンサルティングなどに携わってきた日諸。2023年4月から社会レジリエンス推進チームで活躍しています。
日諸:将来のパンデミックに備え、ワクチンをはじめとしたバイオ医薬品製造の国産化を実現するための「ワクチン生産体制強化のためのバイオ医薬品製造拠点等整備事業費補助金」にメインで携わっています。それと並行して力を入れているのが、チームのカルチャー改革です。70名近いメンバーがより快適かつモチベーション高く、やりがいを持って働くことができるような職場環境の整備を進めています。
ともにPFM業務に携わる鹿内と日諸。大きな社会的意義と責任感を感じていると言います。
鹿内:当部で担うPFM業務には、東日本大震災からの復興やコロナ禍で露呈したサプライチェーン強靭化など、社会課題の解決に向けた国の政策を実現するという大きな意義があります。その推進部分を担う責任は重大ですが、そのぶん、やりがいを感じながら取り組んできました。
一方、私たちが向き合っていくのは個別の事業者さまです。各社の事業計画を確認し、補助事業のルールから逸脱しないよう助言などを通じてゴールへと導くという大切な役割も担っています。
日諸:総額1兆円を超える資金の執行を管理する仕事なので、責任の重さは相当なものです。また、1人で10~20件の担当案件を抱えていて、各事業者さまがスケジュール通り適切に事業を遂行されているか、困っていらっしゃることや課題はないかなどを定期的に確認する、伴走者のような役割も担っています。高いマネジメント能力とコミュニケーション能力が求められる、やりがいのある仕事だと感じています。
そんなふたりが仕事に臨む上で大切にしているのが、現場を知り、事業者に寄り添う姿勢です。
鹿内:現場を知ることはとても大事ですね。提案された事業計画が補助金事業のスキームに合っているか確認したり、補助金を投入することが適切かを判断するために現地を視察したり。また、補助金が本来の目的通りに利用されているかどうかを確認するため、実態についてヒアリングを実施することも。PFM業務では、こうしたプロセスがとても重要だと考えています。
日諸:担当する事業者さまの規模や業種はさまざまです。ワクチン関連の補助金であれば大手企業や新進気鋭のベンチャー企業が比較的多いですが、一方で震災復興関連の補助金では地元で商店や飲食店、旅館などを営む小規模の事業者さまの割合も多くなります。
多様な事業者さまとやり取りを行うので、それぞれの事業者さまの抱えている背景や、担当の方のキャラクターなどによっても柔軟にコミュニケーションスタイルを変えながら、各事業者さまを深く理解し、適切かつ効果的なサポートができるよう心がけています。
伴走しながら支援していく。事業者のその後の活躍を見ることが大きな励みに

▲社会政策コンサルティング部 主任コンサルタント 日諸 恵利
学生時代から東北で地域活性化活動に従事してきた日諸。入社して1年後の2011年3月には、地元が東日本大震災の被害に。それだけに、社会政策コンサルティング部で「自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金」や「津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金」などの震災復興を目的としたPFM業務に携われることに、大きなやりがいを感じていると言います。
日諸:発災当時、家族の安否がわからず不安な状態が続いていました。一方、オフィスでは本棚が倒れてきたり貯水槽が壊れてパソコンが水浸しになったりしたことを鮮烈に覚えています。
あれから10年以上が経過しましたが、震災復興関連のPFM業務に携われるのはとても光栄なこと。まだまだ震災の爪痕が残る中、地域を復興させようと頑張っている方に出会うと、力になりたいとモチベーションが湧いてきます。
一方の鹿内は2011年、PFM業務の立ち上げ段階から参画。以来、10年以上にわたって同業務にコアメンバーとして携わり続けてきました。
鹿内:当初はPFM業務の運用方法が十分確立できていない中、すべてが手さぐりでしたが、徐々にノウハウや知見が蓄積されてきました。メンバーが増えて組織が拡大してきた近年は、個人が培ってきた経験やノウハウを組織の共有財産として活用していく活動に注力しています。
長くPFM事業に携わる中で、補助金を活用して事業を大きく成長させる事業者を目にしたことも。確かな手ごたえを感じていると鹿内は言います。
鹿内:とくに印象的だったのは、設立間もないあるベンチャー企業を支援したときです。その事業者さまは資金繰りが難しかったのですが、補助金は事後払いとなるのが原則です。定められた基準の中でどのような対応ができるのか、補助金を所管する経済産業省と幾度と議論し、現場にも足を運んで確認に行くなど、かなり苦労しました。
しかしその後、順調に事業を拡大し、現在ではかなり名の知れた存在に。地域にも貢献するなど、めざましい成長を遂げました。伴走させていただいた事業者さまの活躍を目にするのは、この仕事をする上で大きな励みになっています。
変化と学びに満ちたPFM業務。これまでに経験したことのないダイナミズムを感じて

2022年までは医療・福祉政策チームに所属していた日諸。社会レジリエンス推進チームへの異動後、新鮮な経験ができていると話します。
日諸:医療・福祉政策チーム時代は、自分たちが書いた企画書を採択していただく側でした。ところが現在は、補助金の公募をかけ、各事業者さまから提出された提案書について、審査・採択するための有識者委員会を運営しています。採択する側に立つのはこれが初めて。新しい役割を担う中で、いかに公平・中立に採択をするのか、その視点や姿勢など、多くを学んでいます。
また、PFM業務のおもしろさを日ごとに感じていると言う日諸。
日諸:異動前の勝手な想像でしたが、社会レジリエンス推進チームの仕事は、システマティックな事務作業の積み重ねが多い業務なのだと思っていました。でも実際は、事業者さまの経営者や企画部署の方々とのやり取りや、官公庁の方とのセッションや調整の機会が多く、総合的な人間力が問われていると感じます。
案件を採択したり伴走支援したりするためには、その事業計画に関する専門分野だけではなく、企業会計や法務、建築設備といった幅広い分野の知識やスキルが欠かせません。とても挑戦しがいのある仕事だと思っています。
日諸の意見にうなずく鹿内。PFM業務の醍醐味についてこう続けます。
鹿内:机上で身につく知識だけでなく、足を使った現場の情報も求められますが、さまざまな事業に深く携われるのがPFM業務の魅力。国策に関わる世界規模のメーカーの事業から被災地のにぎわい創出に貢献する事業まで、業種も企業規模も異なる多様な事業者さまの事業計画に触れられる、とても稀有な仕事だと感じます。
日諸もまた、多種多様な企業を支援できるやりがいを実感してきました。
日諸:土地・建物・設備などへの投資を行う補助金の執行を通じて、企業にとって最たる機密情報とも言える新規事業計画や投資計画に触れる機会が多くあります。そうした情報に幾度となく触れることで、企業経営や社会基盤整備に対する解像度が高まりました。これまでに経験したことのないダイナミズムを感じています。
一人ひとりがやりがいを感じながら、チームワークを発揮してこそ機能するPFM業務
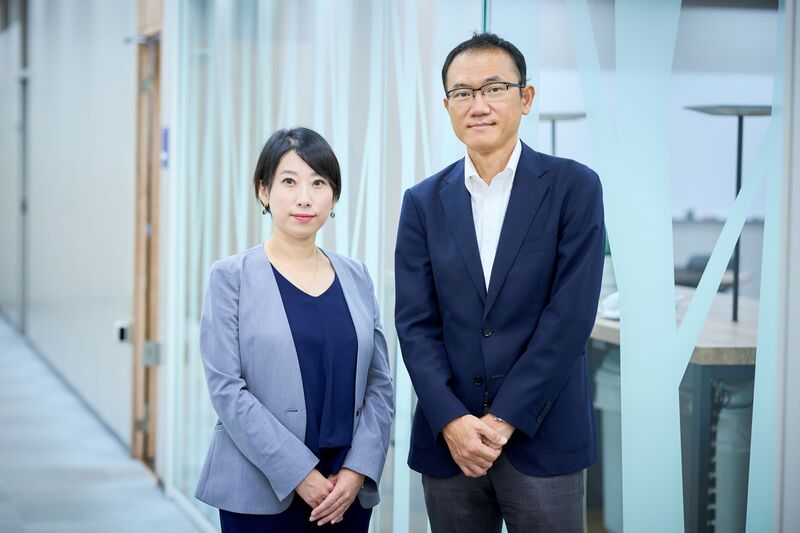
担当範囲を広げつつ、高い専門性を維持することがこれからの課題と話す鹿内。自身の将来をこう展望します。
鹿内:さまざまな分野を扱おうとすれば、どうしても力が分散してしまい各分野の知識が浅くなりがちです。組織も拡大してきたので、今後はたとえば半導体や食品加工、流通といった分野ごとに担当を分け、各自が専門性を追求できるような体制にしていければ、各自の成長に加え、組織としての付加価値向上にもつながるものと考えています。
その上で、補助金事業がもたらす効果の多面的な分析を強化し、官公庁や事業者さまからよりいっそう頼られる存在へと成長していきたいです。
一方、これまで取り組んできたカルチャー改革にますます注力していきたいと言う日諸。めざすのは、組織力の向上です。
日諸:通常のコンサルティング業務は、プロジェクトリーダーの指揮のもと、アサインされた数名のメンバーが各々の担当業務を遂行します。プロジェクトはおおむねリーダー1人がマネジメントすることで機能しますが、補助金1事業あたり数千億円規模の資金の執行管理を担うPFM業務は、それでは成立しません。
何十人という関わるメンバー全員が与えられたミッションを遂行し、それぞれが有機的に連携することで初めて機能します。オーケストラを指揮していくように、一人ひとりがやりがいを感じながら、チームワークを発揮できる環境づくりを牽引していきたいです。
それが実現できるのは、働きやすい職場や豊富な成長機会があってこそ。社会レジリエンス推進チームで働く魅力についてふたりはこう強調します。
日諸:育児と仕事を両立できるだろうかと不安な方がいらっしゃるかもしれませんが、各自が理想のワークライフバランスをかなえるための手厚い支援体制があるのが当チームの特長です。子どもが急に発熱するなどのアクシデント時にはフォローし合うチーム体制が構築できていますし、キャリアアップのチャンスはどんなワークスタイルのメンバーにも開かれています。
鹿内:現場に足を運んでさまざまな事業や業界の知見を得ることは、コンサルタントを志す方にとって貴重な経験になるはず。全国各地に出張の機会が多く、さまざまな土地の良さを体感できるのもこの仕事の魅力のひとつだと思います。
さまざまな事業者に真摯に向き合い、現場に足を運び、高精度の支援を提供してきた鹿内と日諸。伴走した事業者の活躍ぶりを見ると、PFM業務の社会的意義や価値を感じると言います。手がける範囲を着実に広げながら、ふたりはこれからも社会の課題解決や事業者の成長に貢献し続けます。
※ 記載内容は2023年10月時点のものです
(CONTACT)

お問い合わせ
お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。
サービスに関するお問い合わせはこちら
メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。
mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp
その他のお問い合わせはこちら
mhricon-info@mizuho-rt.co.jp












