環境エネルギー第1部 地球環境チーム コンサルタント 内藤 彩 コンサルタント 川村 淳貴
自動車関係諸税のあり方についての考察(続き)
(2)自動車関係諸税を巡る世界の潮流
中長期的な選択肢として、大きく3つの選択肢が考えられる。1つ目は、2.で言及したカーボンプライシングの強化である。炭素税の引上げによりガソリン等の燃料の価格が上昇することで、燃料消費量を減少させ、環境負荷の低減につなげつつ、税収を確保することが可能となる。2つ目が、電気自動車に対する課税である。従来型のガソリン車やディーゼル車から、電気で駆動するBEVやPHEVへシフトすることにより、現行の車体課税や炭素税の税収の減少では補足できない税収の確保につながる可能性がある。3つ目が走行距離課税である。走行距離は車種や燃料消費量に依存せず、あらゆる自動車に対して課すことができるため、安定的に財源を確保しつつ、自動車走行そのものを減少させ、環境負荷を低減させる可能性がある。次節では、この3つの選択肢の観点から、諸外国の動向を参照したい。
[1] 選択肢1:炭素税によるエネルギー税の引上げ
まず、世界の多くの国で、ガソリンや軽油に対する課税が導入されているが、日本において、これらの税を引上げる余地があるのか、検討してみたい。図表11は、ガソリン及び軽油について、日本を含む14カ国の2018年1月時点のエネルギー税及び炭素税の税率をCO2排出量1トン当たりに換算した値を比較したものである。これをみると、日本の税率は北米、豪州に次いで低い水準であり、税率全体に占める炭素税の割合をみても、炭素税を導入している国のうち最も低いことが読み取れる。
では、実際に消費者が直面する本体価格や消費税等を考慮するとどうだろうか。図表12は、さらに本体価格及び消費税を加えたガソリン及び軽油の燃料価格で比較したものである。これをみても、日本は、税率の水準と同様に、北米、豪州に次いで低い水準であることがわかる。もちろん、産業構造やエネルギー構成等、各国事情が異なることから、税率の多寡をもって良し悪しを判断することには留意が必要だが、これを見る限り、日本にとって、炭素税によるエネルギー税の引上げを検討する余地は残っているといえる。
図表11 ガソリン・軽油のエネルギー税及び炭素税の税率(2018年1月時点)
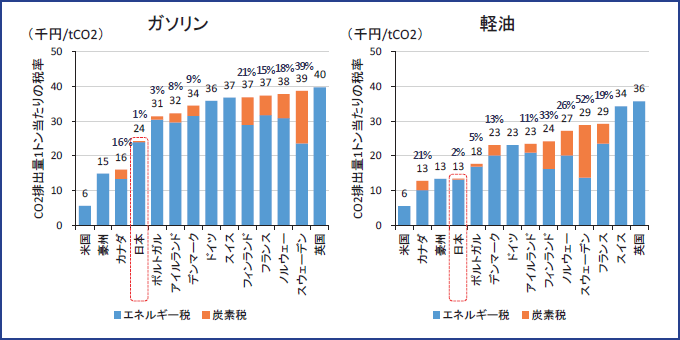
(注)パーセンテージは、税率全体に占める炭素税の割合を示す。
(資料)各国政府資料等よりみずほ情報総研作成
図表12 ガソリン・軽油のCO2排出量1トン当たりの価格(14)
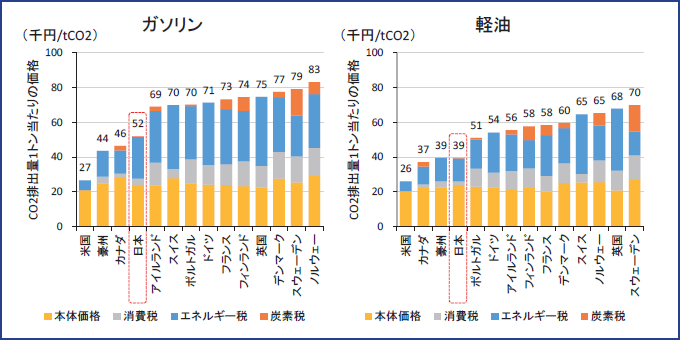
(資料)IEA(2017)「Energy Prices and Taxes Quarterly Statistics, Third Quarter 2017」及び各国政府資料等よりみずほ情報総研作成
[2] 選択肢2:電気自動車に対する課税
次に、電気自動車に対する課税については、米国の一部の州で事例がある。アイダホ州では、Electric Vehicle Fee 及びPlug-in HybridVehicle Feeという税があり、新車登録時に、従来の登録料に加えBEVの場合は140USDが、PHEVの場合は75USDが上乗せされる(15)。ミシガン州でも同様に、車両重量に応じてPHEVは30~100USD、BEVは100~200USDが登録料に上乗せされる(16)。ジョージア州では、2018年7月より、代替燃料車に対する年間登録料(Annual Licensing Fees)として、自家用PHEVに対して年間213.69USDを徴収する制度が導入されている(17)。
同様の検討は国レベルでも行われている。BEV及びPHEVの新車販売シェアが2018年時点で48.3%(18)と世界で最も電気自動車の普及が進んでいるノルウェーでは、BEV及びPHEVの車体課税(取得税、保有税)を免税としており、その結果、図表13のように、自動車関係諸税の減収という大きな問題に直面している(19)。そこで政府は、2018年に、車両重量が2トン以上のBEVに対して自動車登録税を適用させる法案(いわゆる「テスラ税(20)」)を提案したが、自動車業界からの反発等で、導入は見送られている。
香港においても、2017年4月、自動車関係諸税の減収への懸念から、BEVに対する自動車登録税全額免除を中止し、免税額の上限(97,500HKD)を設定した。しかし、ここでも自動車業界の大きな反発を受け、2018年2月に、保有車両を廃車した上で新車のBEVを購入することを条件に、登録税免除の上限を引上げることとした(97,500→250,000HKD)(21)。
このように、電気自動車を普及させるために税制上の優遇措置を実施してきた経緯もある中で、一転して電気自動車の税負担を増やす政策に舵を切ることについては、産業界との合意形成などの難題がある。
これ以外に、既存の電力消費量に対する課税を強化するという方法も考えられるが、これを課すことにより、電気自動車への移行が妨げられる可能性がある。加えてガソリン車やディーゼル車は、基本的にスタンドで給油するため課税ポイントを特定できるが、電気自動車の場合、公共の充電ステーションのほかに自宅や職場で給電する場合もあり、自動車用途のみの電力消費量を区別することが難しい。したがって、自動車用途の電力消費に対する課税の強化も容易でないといえる。
図表13 ノルウェーの自動車関係諸税収の推移とゼロエミッション車の割合
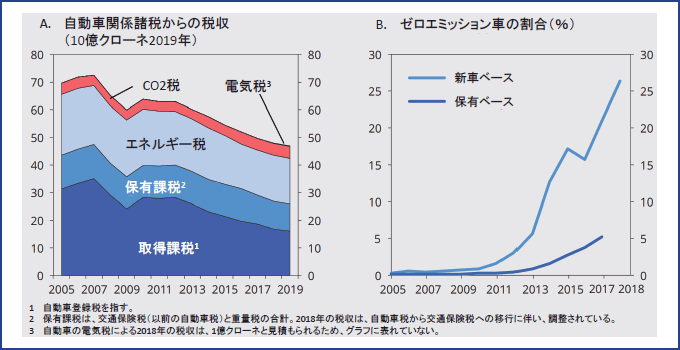
(資料)ノルウェー財務省「Skatter, avgifter og toll 2019」よりみずほ情報総研作成
[3] 選択肢3:走行距離に応じた課税
最後に、特に近年注目を集める走行距離課税について概観する。図表14の通り、欧州では、1993年の欧州指令で重量貨物車のインフラ費用に対する課金の考え方が規定されてから、複数の国でビニエット(vignette)方式と呼ばれる、一定期間の道路利用に対するステッカー購入等による方式で課金が実施された。その後2000年代に入り、スイスを皮切りにオーストリア、ドイツなど、重量貨物車を対象に徐々に走行距離に応じた通行税や課徴金の導入が進められてきた。また2017年5月には、走行距離に応じた課金の対象を乗用車や軽量貨物車まで拡大することを目的に、欧州委員会が現行指令の改定案を提出しており、2018年10月に欧州議会で第一読会が実施され、審議が進められている。また、米国では、カリフォルニア州やワシントン州、デラウェア州などで実証実験が進められており、中でもオレゴン州では2013年7月に乗用車に対する走行距離課税の導入に関する法令が制定されている。
一例として、図表15に、ドイツの重量貨物車通行税(LKW-Malt)と米国オレゴン州の道路利用課徴金(OReGO)の概要をまとめている。
ドイツは、2005年に車載器とGNSS(全球測位衛星システム)の無線方式により走行距離を算定して課税するシステムを導入した(22)。この際ドイツ政府は、重量貨物車通行税を導入する代わりに、運送業界向けの補償として自動車税の税率を引き下げている。その後、対象区域や対象車両を拡大して現行制度に至っている。税率の設定においては、2011年の欧州指令(Eurovignette III)を踏まえ、道路損傷、大気汚染、騒音に対する税率が設定されている(23)。このように、走行距離に応じた課税には、自動車の走行に係る様々な外部費用の内部化を課税根拠とし、複数の課税標準を組み合わせていることがわかる。
米国オレゴン州は、複数回のパイロット事業を経て、2015年に乗用車に対する道路利用課徴金の運用を開始した。制度参加者に対しては、走行距離に応じた道路利用課徴金を支払う代わりに既存のエネルギー税の還付を認めたり、プライバシー保護の観点から、GPS対応とGPS非対応を利用者に選択させたりすることで、社会的な受容性を高めている(24)。
一方で、成功に至らなかった事例もある。例えば、オランダでは2012年から乗用車を含む全車両への導入を見据えた走行距離課金(Kilometerheffing)を導入する予定であったが、2010年の政権交代を機に検討が止まった。フランスでも同様に、2013年に重量貨物車通行税(Ecotaxe)を導入する予定であったが、運送業界からの反発を受け、2014年10月に導入の無期限延期を決定した。既存のエネルギー税に上乗せする形で走行距離課税を課す計画であったことや、高速道路有料化の馴染みのない地域から反発を受けたことなどが反対の要因として挙げられる。
このように、走行距離に応じた課税には、テクノロジーやプライバシーの問題、既存の税との調整などの課題はあるものの、欧米諸国では徐々に走行距離課税の導入が始まっており、今後経験も蓄積されていくものと考えられる。
図表14 欧米諸国における主な走行距離課税の経緯
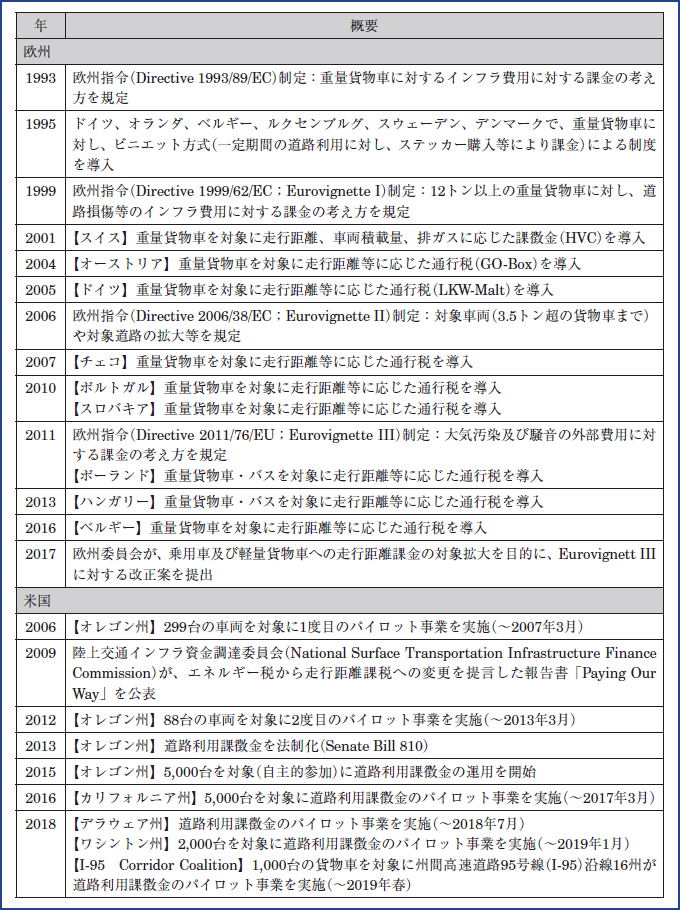
(資料)みずほ情報総研作成
図表15 ドイツLKW-Malt と米国オレゴン州OReGO の概要(2019年1月時点)
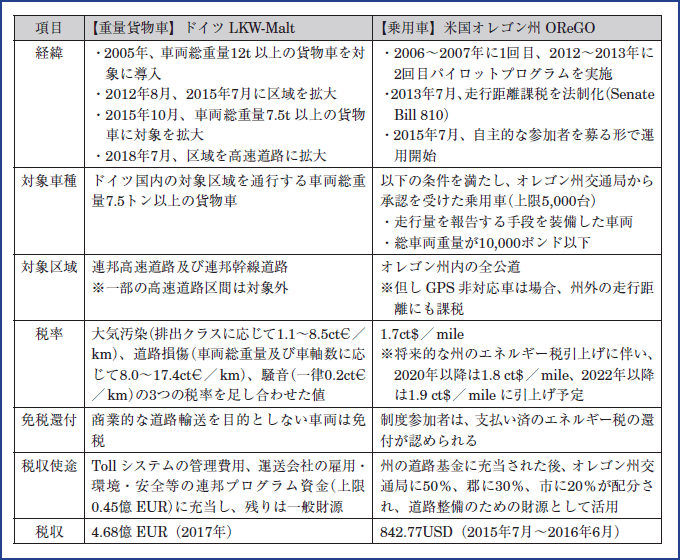
(資料)みずほ情報総研作成
本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。
レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。
関連情報
この執筆者(川村 淳貴)はこちらも執筆しています
-
2019年2月26日
ー環境負荷の低減の観点からー