環境エネルギー第1部 地球環境チーム コンサルタント 内藤 彩 コンサルタント 川村 淳貴
自動車関係諸税のあり方についての考察(続き)
(3)今後の日本の自動車関係諸税のあり方
以上の通り、自動車関係諸税について、炭素税の引上げ、電気自動車への課税、そして走行距離に応じた課税の3つの選択肢が考えられるが、日本の次世代自動車の普及目標も踏まえながら、今後の政策のあり方について検討を行いたい。
日本では、図表8の通り、新車販売台数ベースでハイブリッド車:30~40%、電気自動車及びプラグインハイブリッド車:20~30%、燃料電池自動車:~3%、クリーンディーゼル車:5~10%とする目標を掲げている。2050年に向けては、2018年8月に公表された経済産業省「自動車新時代戦略会議 中間整理(案)」において、世界で供給する日本車について、電動車(xEV)を100%とする目標を掲げており、乗用車においてはBEV・PHEVへのシフトを加速させる方向性が明確に示されている。
他方で、バスや貨物車については、明確な方向性が示されていないが、IEAの世界を対象とした推計によれば、貨物車は航続距離の長さや車両重量の大きさの問題から、乗用車に比べBEV・PHEVの普及が遅れる見込みとなっている(25)。日本においても短期的にはBEV・PHEVへの急激なシフトは生じないと考えられる。
このように、乗用車においては近い将来起こり得るBEV・PHEV等への移行を考慮すると、環境負荷の軽減につながる移行を阻害せず、かつ税収を確保できる税制の検討に可能な限り早期に着手することが望ましい。時間的な制約や実現可能性を考慮すると、短期的には、乗用車に対する追加的な炭素税によるエネルギー税の引上げにより、税収を維持しつつ移行を促すことが適当と考えられる。
一方、貨物車は乗用車と比べてBEV・PHEV等への移行が難しいことから、炭素税によるエネルギー税の引上げは単なる負担の増加となり、貨物車ユーザーから反発を受ける可能性がある。逆に言えば、BEV・PHEV等への移行が乗用車と比べて時間がかかることから、既存のエネルギー税を引下げる代わりに、走行距離課税を導入することの受容性は高く、BEV・PHEV等への移行を阻害する影響も小さい。また、貨物車は乗用車と比べてGPS等の位置情報によるプライバシー保護の敷居も低いと考えられる。
以上を踏まえ、図表16に、次世代自動車の普及に連動した自動車関係諸税の移行イメージを記した。貨物車については、先行的に走行距離課税の導入を検討し、インフラや徴税方法等の技術的な土台を作りつつ、中期的には走行距離課税に一本化する(2030年頃)。乗用車については、BEV・PHEV等への移行がある程度進んだ段階で、徐々に炭素税やエネルギー税から走行距離課税に移行を進め、BEV・PHEV等が定着した段階(2050年頃)で走行距離課税に一本化することで、環境負荷の軽減を実現しつつ、かつ安定的な財源を確保することができるのではないだろうか。他方で、プライバシー保護等の問題により、特に乗用車における走行距離課税への移行が困難な場合は、BEV・PHEV等への移行を阻害しないように留意しつつ、電気自動車への課税を強化することも選択肢になり得るだろう。
図表16 次世代自動車の普及に連動した自動車関係諸税の移行イメージ
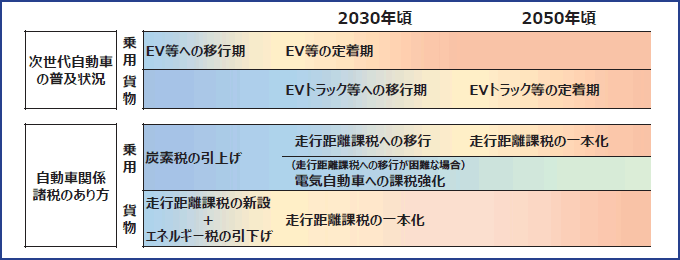
(資料)みずほ情報総研作成
おわりに
本稿では、脱炭素化に向けて日本が今後取り組むべき重要な政策として、「カーボンプライシング」と「自動車関係諸税」を取りあげ、諸外国の事例を参照しつつ、中長期的な施策のあり方の一例について考察を行った。
現段階では、カーボンプライシングや中長期的な自動車関係諸税のあり方については、政府として詳細な制度設計や明確な見通しを示すに至っていない。しかし、世界的な脱炭素化が進む中で、日本の政治経済も、遅かれ早かれ、脱炭素化に向け舵を切ることになる。
脱炭素化に向けては、カーボンプライシングによって経済全体に排出削減のシグナルを送り、負の側面を緩和する措置を取りつつ排出削減を進めていく必要がある一方で、CO2排出量の大幅削減が進むにつれ、環境負荷の低減という目的は達成され、カーボンプライシングの役割は収束していく。自動車関係諸税においては、次世代自動車の普及という時間軸を踏まえながら、カーボンプライシングだけでなく、走行距離課税や電気自動車への課税等への移行により、財源確保としての役割も求められる。「カーボンプライシング」にしろ「自動車関係諸税」にしろ、時間軸を意識したきめ細やかな設計が必要となる。
「カーボンプライシング」と「自動車関係諸税」のあり方について、政府によって、早期に具体的な検討が行われることを期待したい。
注
- 1)スウェーデン政府(2017)「The Swedish climatepolicy framework」
- 2)IEA「CO2 Emissions from Fuel Combustion 2017」。炭素税率は1スウェーデンクローネ=13.4円で日本円に換算。(2015~2017年の為替レート(TTM)の平均値、みずほ銀行)
- 3)自由民主党・公明党(2018)「平成31年度税制改正大綱」
- 4)カーボンプライシングのあり方に関する検討会(2018)「『カーボンプライシングのあり方に関する検討会』取りまとめ」
- 5)経済産業省 長期地球温暖化対策プラットフォーム(2017)「長期地球温暖化対策プラットフォーム報告書─我が国の地球温暖化対策の進むべき方向─」
- 6)日本経済団体連合会(2017)「今後の地球温暖化対策に関する提言」
- 7)環境省「2016年度(平成28年度)の温室効果ガス排出量(確報値)について」
- 8)環境省(2017)「長期低炭素ビジョン」
- 9)2018年11月以降、フランス各地で、燃料価格の高騰やエネルギー関連税の引き上げ等に反対するデモが発生。デモ参加者が、蛍光の黄色いベストを着ることから「黄色いベスト運動」と呼ばれている。
- 10)ブリティッシュ・コロンビア州政府(2018)「CleanBC: our nature. our power. our future.」
- 11)環境省「2016年度(平成28年度)の温室効果ガス排出量(確報値)について」
- 12)経済産業省「自動車産業戦略2014」
- 13)揮発油税、地方揮発油税、軽油引取税は、2008年4月1日~同年4月30日に暫定税率が失効したことで一時的な減収が生じている。
- 14)本体価格及び消費税は、IEA(2017)「Energy Pricesand Taxes Quarterly Statistics, Third Quarter2017」の2016年の平均値を採用。本体価格は、電力の小売価格から消費税及びエネルギー課税を除いた価格を指す。炭素税率及びエネルギー税率は、各国資料等を基にみずほ情報総研作成。税率は2018年1月時点。為替レート:1USD=約114円、1CAD=約88円、1AUD=約86円、1EUR=約127円、1GBP=約159円、1CHF= 約117円、1DKK = 約17円、1SEK= 約13円、1NOK= 約14円。(2015~2017年の為替レート(TTM)の平均値、みずほ銀行)
- 15)アイダホ州議会「アイダホ州法TITLE 49 MOTORVEHICLES, CHAPTER 4 MOTOR VEHICLEREGISTRATION, 49-457」
- 16)ミシガン州議会「ミシガン自動車法典Act 300 of1949, Section 257.801」
- 17)ジョージア州議会「Georgia Department ofRevenue Motor Vehicle Bulletin AlternativeFuel Vehicles ? Annual Licensing Fees Effective:July 1, 2018」
- 18)European Alternative Fuels Observatory ウェブページ
- 19)ノルウェー財務省「Skatter, avgifter og toll 2019」
- 20)ノルウェー財務省ウェブページ「Engangsavgiftinnfores for de tyngste elbilene」
- 21)香港政府環境保護部ウェブページ「Promotion ofElectric Vehicles in Hong Kong」
- 22)ドイツ連邦交通デジタルインフラ省ウェブページ「The HGV tolling scheme」
- 23)ドイツ連邦司法省「Bundesfernstrasenmautgesetz? BFStrMG」
- 24)オレゴン州交通局「Oregon?s Road Usage ChargeThe OReGO Program Final Report」
- 25)IEA「Energy Technology Perspectives 2017」
本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。
レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。
関連情報
この執筆者(川村 淳貴)はこちらも執筆しています
-
2019年2月26日
ー環境負荷の低減の観点からー