グローバルイノベーション&エネルギー部
コンサルタント 境澤 亮祐
コンサルタント 古林 知哉
チーフコンサルタント 蓮見 知弘
〈参考〉FIT制度における再生可能エネルギーの導入と国民負担の状況(2018年12月時点)
FIT制度以降再生可能エネルギー電源の認定量、導入量および買取価格、国民負担について、2018年12月までの推移および2030年度の累積の導入量見通しを整理した。各図において認定量・導入量を棒グラフ、買取価格を折れ線グラフで表記している。なお、いずれの電源も特に断りが無ければ、認定量、導入量は、FIT制度開始後の新規認定分のみを対象とし、FIT開始前の移行認定分は含んでいない。また、買取価格は10kW未満の太陽光発電が税込み表示であり、それ以外は税抜き表示となる。
(1)太陽光発電
FIT制度開始により、最も認定・導入が進んだ再生可能エネルギーである太陽光発電について、主として住宅向けの発電容量10kW未満と、ビルの屋上設置やメガソーラー向けの10kW以上の2つの区分で整理した。
はじめに、10kW未満の太陽光発電の認定量・導入量・買取価格の推移を図表9に示す。FIT制度開始から2016年度までは、毎年100万kW程度のペースで認定され、その後鈍化し、2018年12月時点では616万kWが認定されている。一方、導入量は、認定量の約8割に相当する80万kW/年程度の水準であったが、2017年度より事業認定の取得から1年以内に運転を開始しない場合、買取の権利を失う「失効」とする制度変更が行われたため、2017年度は、認定量97%とこれまでの中で最も高水準で導入された。2018年12月時点における、FIT制度開始以前を含む累積導入量は1,053万kWとなり、すでに2030年度見通しである900万kWを早々に超過している状況である。
買取価格については、FIT制度開始時点では42円/kWhであったが、太陽光パネルを中心に市場拡大に伴うコスト低減が進んだこともあり、2018年度には26円/kWh、出力抑制対応の場合は28円/kWhまで低下している。
2019年には、2009年に開始した余剰価格買取制度から移行された設備が10年間の買取期間を終えて、FIT制度から卒業することになっている。
次に、10kW以上の太陽光発電の認定量・導入量・買取価格の推移を図表10に示す。事業参入の容易さに加え、40円/kWhの買取価格の高さの後押しもあり、認定量は2012年度の1,868万kWから急増し、2016年度にピークとなる7,905万kWに達した。その後、FIT制度の改正で電力会社との接続契約のない案件が失効したため、2018年12月末時点では6,651万kWに落ち着いている。一方、導入量は2015年度までは年間で約700万kW程度の水準であったが、2016年度以降は、系統工事の遅れ等もあり、年間約500万kWとやや鈍化した。2018年12月末におけるFIT制度開始以前を含む累積導入量は3,722万kWとなり、2030年度見通しの5,500万kWの約7割に達した。2017年度以降は、事業認定取得から3年以内に運転開始をしない場合は20年の買取期間が短くなるという制度改正から、2020年度までに導入が加速すると予想される。さらに、2018年12月には、2012年度から2015年度までに認定された運転開始期限が設定されていない未稼動案件の早期稼動を促すため、2019年3月までに電力会社に対する系統連系工事申込を行っていない案件については、「調達価格を見直すこと」、「1年以内に運転開始ができない場合は買取期間を短くすること」が示された4。また、2018年12月21日には、運用の詳細についても示されたところである5。
買取価格は、FIT制度開始時点では40円/kWhであったが、10kW未満の太陽光発電と同様のコスト低減に加えて、安価な海外メーカーの導入が進んだことや、海外メーカーとの競争力強化の観点もあり、2018年度には17円/kWhにまで減じられた。2MW以上のメガソーラーは、2017年度からあらかじめ決められた募集枠に到達するまで、低価格で事業を行うことが可能な事業者から順に権利を獲得する入札制度が導入された。なお、2019年度においては、入札制度の対象も500kW以上となる見込みであり、入札対象外の10kW以上の買取価格は2018年度の17円/kWhから▲18%の14円/kWhまで減じられる。
図表9 10kW 未満の太陽光発電の認定量・導入量・買取価格の推移
(左:FIT 制度下における認定量・導入量と買取価格、右:累積導入量と見通し)
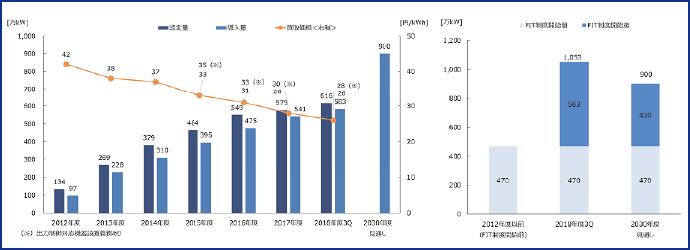
(資料)資源エネルギー庁「固定価格買取制度情報公開用ウェブサイト」、「調達価格等算定委員会資料」よりみずほ情報総研作成
図表10 10kW 以上の太陽光発電の認定量・導入量・買取価格の推移
(左:FIT 制度下における認定量・導入量と買取価格、右:累積導入量と見通し)
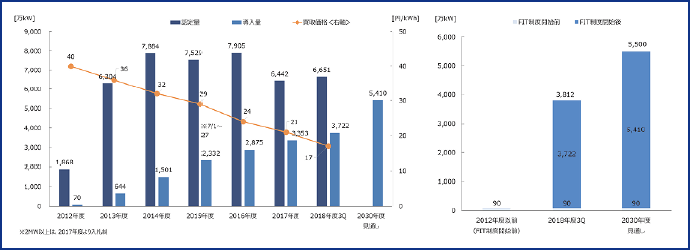
(資料)資源エネルギー庁「固定価格買取制度情報公開用ウェブサイト」、「調達価格等算定委員会資料」よりみずほ情報総研作成
(2)風力発電
風力発電の認定量・導入量・買取価格の推移を図表11に示す。風力発電についての2018年度時点のFIT制度における買取区分は、陸上風力が新設とリプレースで2区分、洋上風力が着床式と浮体式で2区分の合計4区分になっているが、認定量や導入量は、これらを区別することなく整理した。
風力発電の認定量は、FIT制度開始から発電容量が年間50万kWのペースで増加し2015年度末では284万kWにとどまっていたが、環境影響評価の手続きが進んだことも影響し、2016年度の1年間で約400万kW急増、その後は、相応の失効もあったことで、2018年12月時点では709万kWに落ち着いている。一方、導入量は、年間約10万kWの水準で増加し、2018年12月末時点のFIT制度開始以前も含めた累積導入量は371万kWとなり、これは2030年度見通しである1,000万kWの約37%の水準である。
買取価格は、20kW未満の場合、制度開始から2017年度までは55円/kWhと高水準であったが、その高い買取価格と、規模の性質上、国民全体が受益を得るような電源ではないこと等もあり、2018年度から20kW以上の買取価格に一本化された。20kW以上については、制度開始から2017年9月末までは22円/kWhとしていたが、海外と比べて発電コストが高く、国際競争力強化の観点から2017年10月から21円/kWh、2018年度は20円/kWhと減じられた。また、洋上風力については、2014年に民間でも事業計画が立ち上がりつつあることを背景に、買取価格が36円/kWhと設定され、2018年度まで変更はない。
今後は、着床式の洋上風力発電が北海道や東北地域といった風況のよいエリアを中心に導入が期待される。政府としても、その動きを加速化させるため、一般海域における洋上風力発電のルール作りを始めている。2018年の臨時国会において、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律が可決され、2019年度の施行に向けて、促進区域の指定基準や指定手続等の運用の検討が進められている。この一般海域の海域利用ルール整備により、今後多くの洋上風力発電が導入されることが期待される。海域利用ルールの適用される案件は競争による価格低減を見込み、入札制で買取価格が決定されるとともに、海域利用ルール適用外の案件についても、大量導入によるコスト低減が見込まれることから2020年度以降の買取価格は2019年度に決定することとなっている。
図表11 風力発電の認定量・導入量・買取価格の推移
(左:FIT 制度下における認定量・導入量と買取価格、右:累積導入量と見通し)
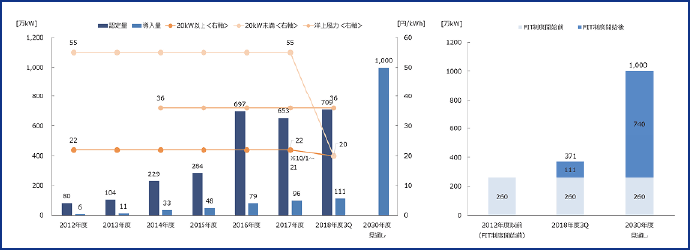
(資料)資源エネルギー庁「固定価格買取制度情報公開用ウェブサイト」、「調達価格等算定委員会資料」よりみずほ情報総研作成
(3)地熱発電
地熱発電の認定量・導入量・買取価格の推移を図表12に示す。地熱発電についての2018年度時点のFIT制度における買取区分は、新設の場合、発電規模別に15,000kW未満、15,000kW以上の2区分がある。これに加えリプレース枠として全設備更新型と地下設備流用型の2区分に対しそれぞれが前述の規模区分があるため、新設と合わせ合計6区分が設定されている。ここでは、認定量や導入量は、これらを区別することなく整理した。
認定量は、FIT制度開始から、大型の開発が1件のみで、ほとんどが数千kW級の中規模発電と、数百kW級の小規模発電が主流である。そのため、認定量は制度開始から2018年12月末までで8.4万kWにとどまっている。同様に、導入量は同2.3万kWにとどまっており、FIT制度開始以前を含む累積導入量52.3万kWは、2030年度見通しである140~155万kWの4割弱の水準という状況にある。このような中、2018年度には松尾八幡平(7,499kW)が、2019年度には山葵沢(42,000kW)が運転を開始した。
買取価格は、新設を対象とする2つの区分においてFIT制度開始から2018年9月までの間、15,000kW未満が40円/kWh、15,000kW以上が26円/kWhで変更されていない。その結果として、買取価格が原因で大規模な開発が停滞しているのではないかとの意見もあり、実態の把握が求められている。
大規模な地熱発電は、洋上風力発電と同様に地元関係者との合意形成に加え、開発にあたっては資源リスクが存在するため、一般的に計画から運転開始まで長い時間を要する電源である。そのため、現在は環境影響評価の対象にならない7,500kW未満の案件の開発や、既存の温泉井を使って発電する小規模な発電が主流になっている。今後の一層の導入に向けては、大規模な開発の支援だけではなく、現在開発が進んでいる案件の加速化、新規開発地点の発掘のためのヒートホール調査や空中物理探査の充実が求められている。また、2050年を見据えた新しい技術開発の検討も進められている。
図表12 地熱発電認定量・導入量・買取価格の推移
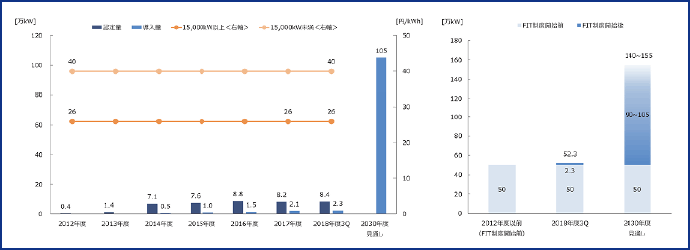
(資料)資源エネルギー庁「固定価格買取制度情報公開用ウェブサイト」、「調達価格等算定委員会資料」よりみずほ情報総研作成
本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。
レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。
関連情報
この執筆者(古林 知哉)はこちらも執筆しています
-
2019年6月3日