グローバルイノベーション&エネルギー部
コンサルタント 境澤 亮祐
コンサルタント 古林 知哉
チーフコンサルタント 蓮見 知弘
〈参考〉FIT制度における再生可能エネルギーの導入と国民負担の状況(2018年12月時点)(続き)
(4)中小水力発電
中小水力発電の認定量・導入量・買取価格の推移を図表13に示す。中小水力発電についての2018年度時点のFIT制度における買取区分は、規模別である200kW未満、200kW以上1,000kW未満、1,000kW以上5,000kW未満、5,000kW以上30,000kW未満の4区分に対し、新設および既設導水路活用型2区分があるため、合計8つの買取区分が設定されている。ここでは、認定量や導入量は、これらを区別することなく整理した。
認定量は、FIT制度開始から2016年度末までは、年間で約20万kWのペースで増加したものの、その後は伸びが鈍化し、2018年12月末までで120万kWとなっている。これに対して導入量は、2018年12月末時点で35万kW、FIT制度開始以前を含む累積導入量は、994万kWであり、2030年度見通し1,090~1,161万kWに対し約9割の水準である。
買取価格は、3つの区分において設定されており、FIT制度開始から2018年度まで、200kW未満が34円/kWh、200kW以上1,000kW未満が29円/kWhと変更されていない。しかしながら、1,000kW以上30,000kW未満については、2016年度までは24円/kWhだったが、2017年度より細分化され、1,000kW以上5,000kW未満が27円/kWh、5,000kW以上30,000kW未満が20円/kWhと変更になった。
2030年度見通しは、一般水力を含めた水力発電全体としてのものであり、中小水力発電のみで達成率を試算すると、約15~26%の水準にとどまっている。一方、すでに大規模な一般水力の開発が進められてきたことから、中小水力発電の開発案件は限定的となっている。こうした状況から新設よりもリプレース時の増強が期待されるが、認定量が急速に増えることは考えにくく、現在認定を受けている案件の確実な導入が求められる。
図表13 中小水力発電の認定量・導入量・買取価格の推移
(左:FIT 制度下における認定量・導入量と買取価格、右:累積導入量と見通し)
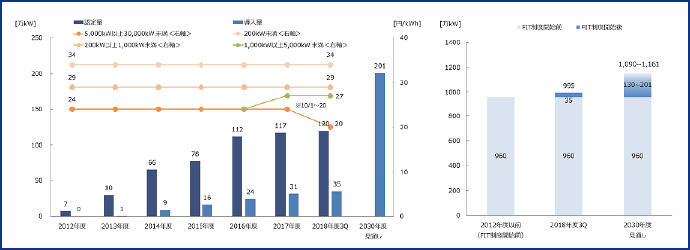
(資料)資源エネルギー庁「固定価格買取制度情報公開用ウェブサイト」、「調達価格等算定委員会資料」よりみずほ情報総研作成
(5)バイオマス発電
バイオマス発電の認定量・導入量・買取価格の推移を図表14に示す。バイオマス発電についての2018年度時点の買取区分は、メタン発酵ガス、間伐材等由来の木質バイオマス、一般木質バイオマス・農作物残さ、バイオマス液体燃料、建築資材廃棄物、一般廃棄物その他のバイオマスといった6つの燃料種に加え、そのうちの2種はさらに発電規模が2つに区分されていることから、合計8区分が設定されている。ここでは、認定量や導入量は、これらを区別することなく整理した。
認定量は、FIT制度開始から年間で約90万kWのペースで増加、2015年度末には370万kWに達したが、2017年度に一般木質バイオマス・農作物残さの買取価格が下がることを受けて、前年度の2016年度に駆け込みで認定を取得する事業者が殺到し、1,242万kWまで増加した。その後、制度改正より、電力会社との系統接続の承諾が期限内に得られなかった案件が失効になったことにより、2018年12月末時点では873万kWに落ち着いている。一方、導入量は、年間約20万kWのペースで増加、2018年12月末ではFIT制度開始以前を含めた累積導入量は382万kWであり、2030年度見通し602~728万kWの約5~6割の水準である。
買取価格は、燃料種によって価格の見直し等の方向性が異なっている。一般木質バイオマス・農作物残さは、買取区分の細分化と買取価格の低減が図られ、10,000kW以上の一般木質バイオマス・農作物残さやバイオマス液体燃料は、2018年度より入札制に移行した。それ以外の燃料種は、間伐材等由来の木質バイオマスの買取区分の新設以外は、変更がない。
バイオマス発電においても、未稼働の太陽光発電の案件と同様に、国民負担の抑制に向けた対応として、バイオマス比率の変更にあたって制約を設けることなった6。具体的には、石炭等の混焼の場合は、バイオマス比率を増やす場合、または40%以上減らす場合は、バイオマス全体の買取価格の変更を行うこと、バイオマス専焼においても、買取区分ごとのバイオマス比率を20%以上増加させる場合は、増加した燃料に対し最新の買取価格を設定することとなった。
図表14 バイオマス発電の認定量・導入量・買取価格の推移
(左:FIT 制度下における認定量・導入量と買取価格、右:累積導入量と見通し)
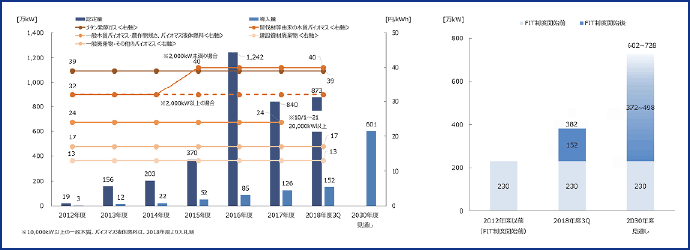
(資料)資源エネルギー庁「固定価格買取制度情報公開用ウェブサイト」、「調達価格等算定委員会資料」よりみずほ情報総研作成
(6)国民負担
FIT制度下での再生可能エネルギーの買取総額と再生可能エネルギー発電促進賦課金(以下、「賦課金」という)単価の推移を図表15に示す。 再生可能エネルギーの買取総額はFIT制度が開始された2012年度では1,782億円であったが、その後は、主として太陽光発電の導入量の増加に伴い2016年度には2兆円を超え、2018年度では12月末のペースで年度末まで推移した場合、3兆円を超える可能性があり、2030年時点の想定である3.7~4兆円へは、あと数年で到達する可能性が高い。また、賦課金単価においては、2012年度は0.22円/kWhであったが、その後急激に伸び2016年度で2円/kWhを超えた。その後、ややペースが鈍化したが、2018年度は2.90円/kWh、2019年度は2.95円/kWhとなった。このように、再生可能エネルギーを導入することで電気料金が高くなり、需要家である企業の国際競争力が失われる懸念から、省エネ対策等の取組を継続している企業に対しては、賦課金を減免する制度が設けられている。
図表15 FIT 制度下における再生可能エネルギーの買取金額と賦課金単価の推移
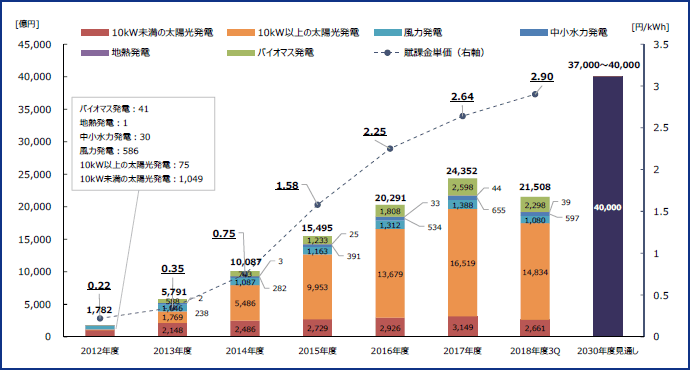
(資料)資源エネルギー庁「固定価格買取制度情報公開用ウェブサイト」、「調達価格等算定委員会資料」よりみずほ情報総研作成
注
- (1)正確には「一般送配電事業者」であるが、本レポートでは一般になじみがあり、かつこれまで一般的に使われてきた「電力会社」と表記する。
参考文献
- *1)
- *2)
- *3)
- *4)
- *5)資源エネルギー庁 事業用太陽光発電の未稼働案件への新たな対応に係る詳細運用等について(お知らせ)
(PDF/442KB) - *5)資源エネルギー庁 「既認定案件による国民負担抑制に向けた対応(バイオマス比率の変更への対応)
(PDF/1,680KB)
本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。
レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。
関連情報
この執筆者(古林 知哉)はこちらも執筆しています
-
2019年6月3日