環境エネルギー第2部 コンサルタント 中村 悠一郎
高度化法と再エネ電力の自家消費モデルの関係性
ここまで、高度化法と再エネ電力の自家消費モデルという、再エネを巡る2つの側面を見てきた。ここで、再エネ電力の自家消費モデルの拡大によって、高度化法の達成に必要な非化石証書の流通量の拡大にはブレーキがかかる(場合によっては減少する)可能性について指摘したい。そのために、以下では高度化法と再エネ電力の自家消費モデルの関係性について、簡易的なシミュレーションを用いて検討する。
(1)仮想電力システムの想定
初めに、仮想的に電力システムを想定し、電力システム全体の非化石電源比率と、高度化法上の非化石電源比率のそれぞれの考え方について整理する。
まず需要側の側面から電力システムを想定する。例えば、家庭と工場という2種類の電力の需要家と、彼らの電力需要を満たすだけの電力供給を行う供給者から成る電力システムを想定する。この電力システムにおいて、24時間の電力需要パターンが図表4のとおりであるとする。なお、各時刻における電力量の値は、仮想電力システムにおける1日の総需要(=総供給)に対する比率を表す。例えば、10時には1日の総需要のうち約8%の需要が存在することを意味する。図表4において、家庭需要及び工場需要それぞれの面積(積分値)は、1日におけるそれぞれの主体の合計需要量を意味する。今回の想定では、1日の総需要量のうち、家庭需要が20%、工場需要が80%を占めることと仮定した。
図表4 仮想電力システムにおける1日の電力需要パターン
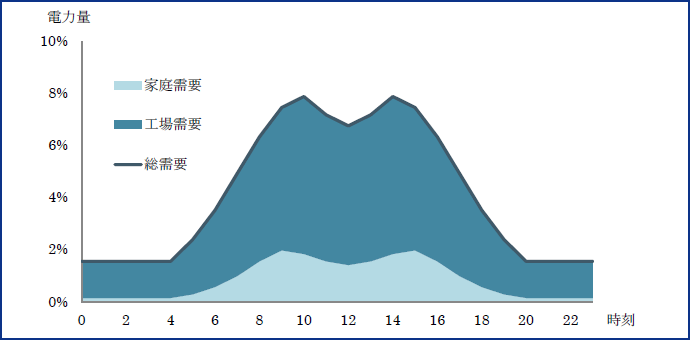
* 図中の値は仮想のもの
(資料)筆者作成
次に、供給側の側面から電力システムを想定する。まず、当該家庭は太陽光発電設備を保有し、以下のルールで運用することと仮定する。
- 「太陽光発電量<家庭需要」の時間帯においては全量を自家消費
- 「太陽光発電量>家庭需要」の時間帯においては、家庭需要に相当する分を自家消費し、余剰電力分を電力系統へ逆潮流
また、供給者においては、電力システム全体の総需要から、家庭が太陽光発電で自ら賄う電力量及び家庭から逆潮流した電力量(=太陽光発電量)を除く分を「系統供給」という形で供給を行うこととする。なお、系統供給は化石電源のみとし、この電力システムにおいては家庭の太陽光発電のみが非化石電源として存在することとする。
これらの前提条件に基づく、当該電力システムにおける電力供給パターンは図表5のとおりとなる。このとき、家庭の太陽光発電設備の発電量は「自家消費+逆潮流」で表現される。図表4と同様に、図表5における自家消費、逆潮流、系統供給それぞれの面積(積分値)は、1日におけるそれぞれの合計供給量を意味する。今回の想定では、1日の総供給量のうち、自家消費が16%、逆潮流が9%、系統供給が75%を占めることと仮定した。また、太陽光発電量は「自家消費+逆潮流」であることから、これらを積算すると25%(16%+9%)の発電が行われたこととなる。
当該電力システムにおける1日の需要と供給の内訳を図表6に整理する。
図表5 仮想電力システムにおける1日の電力供給パターン
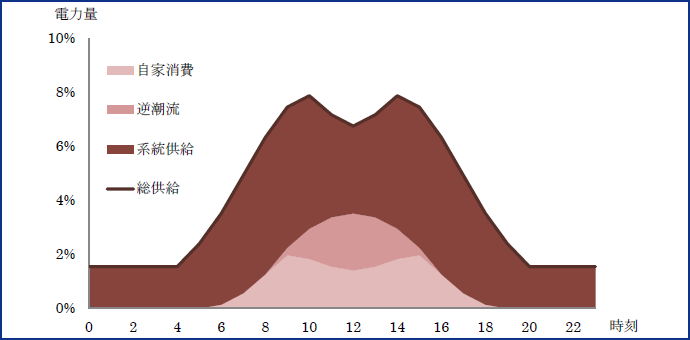
* 図中の値は仮想のもの
(資料)筆者作成
図表6 仮想電力システムにおける1日の需要と供給の内訳
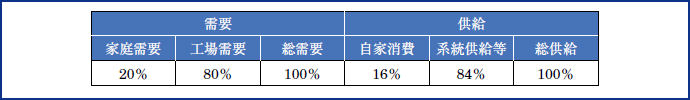
* 系統供給等は太陽光発電の逆潮流量9%と供給者による供給量75%の和
(資料)筆者作成
以上を踏まえ、当該電力システムにおける[1]全体(電力系統+電力系統以外)の非化石電源比率と、[2]高度化法上(電力系統のみ)の非化石電源比率、2種類を算出すると図表7のとおりとなる。なお、ここでいう電力系統以外とは、家庭における自家消費分を意味する。
当然のことながら、家庭における自家消費分を考慮する場合としない場合で、非化石電源比率は異なる。今回の想定では、電力システムに占める家庭需要の割合が大きいため、15ポイントという大きな差となっているが、実際にはここまで大きな乖離は生じないと考えられる。
ここまで、電力システム全体の非化石電源比率と、高度化法上の非化石電源比率、2種類の考え方について整理した。さて、上記の電力システムにおいて、今度は再エネ電力の自家消費モデルが進んだ場合を検討する。具体的には、家庭が蓄電池を導入し、太陽光発電の自家消費量を増大させた場合に、図表7の2種類の非化石電源比率がどのように変化するかを確認する。
図表7 仮想電力システムにおける2種類の非化石電源比率
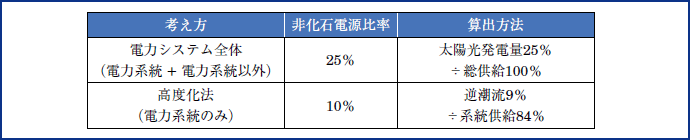
(資料)筆者作成
(2)仮想電力システムにおける再エネ電力の自家消費モデルの拡大
上記と全く同様の電力システムにおいて、家庭が蓄電池を導入した場合を考えたい。具体的には、次の通り、太陽光発電と蓄電池が稼働することと想定する。
- 「太陽光発電量<家庭需要」の時間帯においては、蓄電池に電力が残っている場合にはそれを放電することで不足分を賄い、それでもなお不足する場合には、系統供給を受けることで充足
- 「太陽光発電量>家庭需要」の時間帯においては、余剰電力を蓄電池の上限容量に達するまで充電にまわし、上限容量に達してもなお余る電力については、電力系統へ逆潮流
なお、ここでは蓄電池の充放電ロスや瞬間的に充放電できる量の上限等は考慮しないこととし、上限容量としては、仮に本シミュレーションにおける1日の終了時点でちょうど放電しき容量を設定する(結果的に、総需要に対して14%に相当する容量を上限として設定した)。
これらの前提条件に基づく、当該電力システムにおける電力供給パターンは図表8のとおりとなる(電力需要パターンは図表4と同じである)。このとき、家庭の太陽光発電設備の発電量は「自家消費(太陽光)+自家消費(蓄電池)+逆潮流」で表現される。なお、自家消費(太陽光)とは、(蓄電池を介さずに)直接自家消費された分を、自家消費(蓄電池)とは、「太陽光発電量>家庭需要」の時間帯に一度蓄電池に充電されたのち、異なる時間帯に放電することで自家消費された分を、それぞれ意味する。
図表8 蓄電池導入後の仮想電力システムにおける1日の電力供給パターン
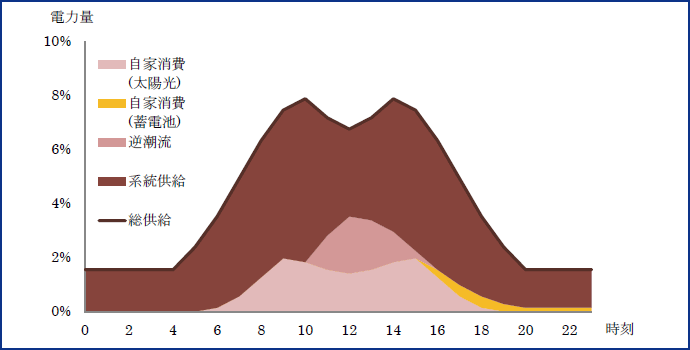
* 図中の値は仮想のもの
(資料)筆者作成
図表5と比較すると、9時から11時の間において逆潮流が欠けている。これは、余剰電力を蓄電池へ充電している時間帯である。一方、12時から15時までは同じような逆潮流を行っている。これは、蓄電池の上限容量に達したことによって充電が行われず、余剰電力が全て逆潮流している時間帯である。一方、新たに16時から23時まで自家消費(蓄電池)が生じている。これは、蓄電池に充電した電力を放電することで家庭需要を賄っている時間帯である。
(1)の場合と同様に、当該電力システムにおける1日の需要と供給の内訳を図表9に整理する。上記のとおり、太陽光発電量は「自家消費(太陽光)+自家消費(蓄電池)+逆潮流」であることから、25%(16%+2%+7%)の発電が行われたこととなる。これは(1)の場合と同様である。また、蓄電池の導入により、自家消費が増大し、系統供給が減少している。
図表9 蓄電池導入後の仮想電力システムにおける需要と供給の内訳
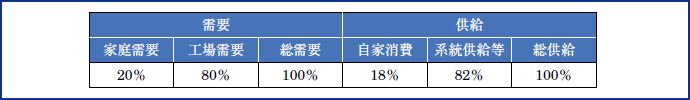
* 系統供給は太陽光発電の逆潮流量7%と供給者による供給量75%の和
(資料)筆者作成
さて、当該電力システムにおける[1]全体(電力系統+電力系統以外)の非化石電源比率と、[2]高度化法上(電力系統のみ)の非化石電源比率、2種類を算出すると図表10のとおりとなる。なお、ここでいう電力系統以外とは、家庭における自家消費分(自家消費(太陽光)+自家消費(蓄電池))を意味する。
図表10 蓄電池導入後の仮想電力システムにおける2種類の非化石電源比率
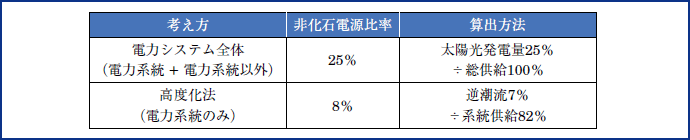
(資料)筆者作成
前掲と同様に、家庭における自家消費分を考慮する場合としない場合で、やはり非化石電源比率は異なる。しかし、より重要な事実として、図表11に示すとおり、電力システム全体の非化石電源比率は25%のままである一方、高度化法上の非化石電源比率は10%から8%へと2ポイント低下している点があげられる。
これは、[1]蓄電池の導入により電力系統の再エネ電力の量が減少し、電力系統以外の再エネ電力の量が増大したこと、[2]高度化法が電力系統のみを対象としていること、2点が原因となって生じている。以下では、この現象が意味することを考察し、高度化法の達成に係る政策の在り方について提言する。
図表11 蓄電池導入前後の仮想電力システムにおける2種類の非化石電源比率比較
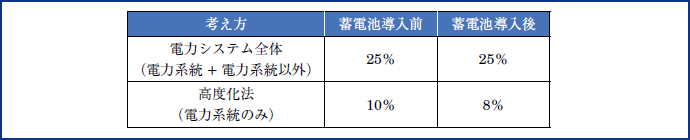
(資料)筆者作成
本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。
レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。