環境エネルギー第2部 コンサルタント 中村 悠一郎
シミュレーション結果の考察と政策の在り方に関する提言
(1)非化石証書の流通量拡大へのブレーキ
前掲のシミュレーションによって示されたとおり、蓄電池の導入によって自家消費が拡大すると、電力系統を流れる再エネ電力の絶対量が減少し、結果として、発行・流通可能な非化石証書の量も減少することとなる。つまり、資源エネルギー庁が推進する再エネを巡る2つの側面:高度化法と再エネ電力の自家消費モデルは、必ずしもそれぞれの目的達成のために寄与しえない関係にある。もちろん、自家消費の拡大によって電力系統への負荷が軽減されれば、その分、新規に導入可能な再エネ電源の規模が拡大する可能性もあり、一概に非化石証書の流通量が減少するとは言い難い。しかしながら、少なくとも自家消費されることで、非化石証書として発行することができず、高度化法上、埋没する非化石価値が存在することは事実である。したがって、再エネ電力の自家消費モデルの拡大は非化石証書の流通量の拡大にブレーキをかけ(場合によっては減少させ)、小売電気事業者における高度化法達成を困難にする可能性があるといえる。
実際、2018年度の電力調査統計に基づけば、1,000kW以上の自家消費用の非化石電源に由来する発電量は約110億kWhに達し、そのうちの約7割が自家消費されたと仮定すれば、約70億kWhの非化石電力が埋没していると推計される*2。また、同年度末時点におけるFIT導入量に基づけば、家庭用太陽光発電に由来する発電量は約110億kWhに相当すると見込まれ、そのうち約3割が自家消費されたと仮定すれば、約30億kWhの非化石電力が埋没していると推計される*3。即ち、2018年度時点で、少なくとも合計約100億kWhに相当する非化石電力が、高度化法上、活用されずに埋没している。
電力調査統計及び資源エネルギー庁の試算に基づき、高度化法の対象となる新電力47社が購入しなければならない非化石電力の量を推計したところ、合計で約90億kWhと求められた6,8(平均約2億kWh/社)。つまり、少なくとも現時点で、高度化法の対象となる新電力全体が必要とする規模と同等か、それ以上の非化石電力が、非化石証書として発行されることなく埋没していることを意味する*4,*5(図表12)。
今後、再エネ電力の自家消費モデルが拡大すれば、この埋没量は更に増大すると考えられる。1.(1)で述べたとおり、国が定める2030年目標と比して、現時点で原子力及び再エネどちらも、10ポイント以上電力量が不足している状況で、今後の埋没量の増大が非化石電力の需給バランスに影響を与える可能性も示唆される。
図表12 新電力47社が必要とする非化石電力量と高度化法上埋没している非化石電力量の比較
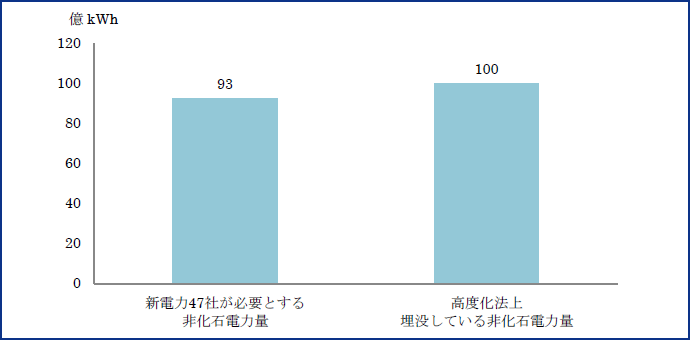
(資料)電力・ガス基本政策小委員会資料、電力調査統計に基づき筆者作成
(2)高度化法の達成に係る政策の在り方についての提言
ここまでの検討・考察を通じ、再エネ電力の自家消費モデルの拡大により、高度化法上、埋没する非化石電力が増大し、非化石証書の流通量拡大にはブレーキがかかる(又は減少に転じる)可能性があること、その規模は現時点でも決して無視できる規模ではないことが示された。
このような事象が発生する原因は、高度化法が電力系統のみを対象としている点にある。高度化法のそもそもの目的である、「エネルギーを安定的かつ適切に供給するため」に、「資源の枯渇のおそれが少なく、環境への負荷が少ない太陽光やバイオマスといった再生可能エネルギー源や原子力などを含む、非化石エネルギー源の導入を一層進める」ことは、決して電力系統のみに制限されるものではないはずである。本質的には、自家消費も含め、日本全体として非化石エネルギーの導入拡大を促進するものであるといえよう。
これらを踏まえれば、高度化法の達成に係る政策の在り方として、電力系統に限らず、電力系統以外の非化石電力についても、その非化石価値を適切に評価・反映する仕組み作りが求められる。具体的には、自家消費された非化石価値を顕在化し、小売電気事業者や電力の需要家等の様々なプレーヤーが自由に取引でき、かつ、その価値が高度化法達成のために活用できる制度設計が今後は必要と考えられる。
注
- *1)発電や燃料の精製等で生じるロスも含めて、日本全体として必要とするエネルギー量。
- *2)2018年度電力調査統計「自家用発電実績」より、水力及び新エネルギー等の発電電力量は合計約108億kWh。このうち、化石電源も含む全ての自家用発電の自家消費率68.1%(同統計より)に基づき、自家消費量を約73億kWhと推計6。
- *3)固定価格買取制度情報公表用ウェブサイト「A表 都道府県別認定・導入量(2019年3月末時点)」より、家庭用に導入されたと考えられる10kW未満の設備導入量を約1,080万kWと算出。設備利用率を12%と想定し、発電量を約113億kWhと推計7。
- *4)このことが即ち、高度化法達成に係る非化石電力の需給逼迫を引き起こすというわけではない。2020年度から2022年度までの期間においては、各社が購入しなければならない非化石電力の量の総和は、激変緩和措置により非化石電力の総供給量よりも少なく設定される。このため、非化石電力の埋没の有無に依らず、当面は「総需要<総供給」という関係が持続する。
- *5)なお、自家消費された非化石電力が持つ排出係数ゼロ等の環境価値について、一部はJ-クレジットやグリーン電力証書として発行されている。
参考文献
- 1.資源エネルギー庁,2019.平成30年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2019).(最終閲覧日:2019年12月4日)
- 2.地球温暖化対策推進本部,2015.日本の約束草案.
(PDF/200KB)(最終閲覧日:2019年12月4日) - 3.資源エネルギー庁,2019.総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会 第20回配布資料8.
(PDF/693KB) - 4.資源エネルギー庁,2019.総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会/電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会 中間整理(第3次).
(PDF/1,650KB)(最終閲覧日:2019年12月4日) - 5.日本能率協会総合研究所,2019.家庭用蓄電池─DB有望市場予測レポート─.
- 6.資源エネルギー庁,2019.電力調査統計表 過去のデータ(最終閲覧日:2019年12月4日)
- 7.資源エネルギー庁,2019.固定価格買取制度 情報公表用ウェブサイト.(最終閲覧日:2019年12月4日)
- 8.資源エネルギー庁,2019.総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会 第22回配布資料6.
(PDF/1,650KB)
本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。
レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。