環境エネルギー第1部 チーフコンサルタント 川村 淳貴
本稿では、我が国が抱える現行の自動車関係諸税の課題を整理した上で、中長期を見据えた税制の選択肢の一つとして自動車の外部性を考慮した走行距離課税に着目する。さらに、走行距離課税をめぐる国内外の動向を踏まえ、この度構築した税収試算ツールを用いて国内で走行距離課税を導入した際の試行的な分析を行い、車種や地域性の観点から考察する。
我が国における自動車の外部性を考慮した走行距離課税の検討(PDF/1,566KB)
はじめに
消費税率10%への引上げが決定した2018年末の政府・与党による平成31年度税制改正大綱(1)では、消費税率引上げに伴う自動車の駆け込み需要とその後の反動減への対策として、自動車税種別割の恒久的な税率引下げや、購入時に課される自動車取得税の廃止と1年間の時限的な減税を加えた自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の導入など、自動車関係諸税の一部に改正が加えられた。
同大綱の検討事項では、「自動車関係諸税については、技術革新や保有から利用への変化等の自動車を取り巻く環境変化の動向、環境負荷の低減に対する要請の高まり等を踏まえつつ、国・地方を通じた財源を安定的に確保していくことを前提に、その課税のあり方について、中長期的な視点に立って検討を行う。」という文言が記載され、産業・環境・財政等の様々な観点から自動車関係諸税に係る見直しの検討が進められる見通しである。
上記の税制改正における議論の過程では、複数の報道機関において走行距離に応じた課税(以下、走行距離課税という。)に関する報道がなされた(2)(3)。確かに、カーシェアや電気自動車など新たな技術・サービスに依らず、あらゆる自動車に共通する走行距離に課税する案は、安定的な財源の確保を実現する有力な選択肢の一つである。しかしながら、走行距離課税の有用性はこれだけではない。走行時の場所や時間帯、道路の種類等に応じた税率の設定により、騒音や大気汚染、道路損傷などの自動車利用による様々な負の外部性(ある経済主体の行動が他の経済主体に損害を与え、影響を及ぼす主体がその対価を払わないでいること)に精緻に対処できるという利点を持つ。他方で、税制の見直しにおいては、税負担者の負担感や公平感といった社会的受容性の観点から、税制の見直しが既存税制の税収総額に影響を与えないことを指す税収中立性を確保することが望ましく、どのような税体系であればどの程度の税収が見込めるかという点を明らかにすることも重要である。以上を踏まえて、本稿では次の構成で議論を進めていく。1章では、自動車関係諸税の見直しの方向性として、現行の自動車関係諸税の課題や課税根拠の観点から外部性に着目すべき根拠を整理する。2章では、外部性に関する国内外の研究事例を整理しつつ、走行距離課税の優位性を明らかにする。3章では、自動車の外部性を考慮した走行距離課税の事例として、関連する欧州指令の動向や導入国における制度設計、欧州委員会が実施する外部費用に関する評価を取り上げる。4章では、日本で外部性を考慮した走行距離課税を導入することを念頭に置き、税収中立性を定量的に評価するための分析ツールを構築し、試行的な分析を行った上で、車種(乗用車・バス・貨物車等)や地域性による税負担額の観点から考察する。
現行税制が抱える課題と税制の見直しの方向性
はじめに、現在、7つの税目で構成される自動車関係諸税に対し、自動車業界から税制の簡素化が求められていることや、一部の税目で電気自動車やシェアリングサービスへの対応に支障が生じていることから、取得段階と保有段階の税の役割が弱まりつつあることを示す。その上で、課税根拠の観点から「自動車の外部性を考慮した走行段階の課税への移行」という見直しの方向性を導く。
(1)自動車関係諸税の複雑さ
最初に、現行の自動車関係諸税について整理しておきたい。自動車関係諸税は「取得」「保有」「走行」の3つの段階において7つの税目で構成されている(図表1)。
取得段階では、自動車税環境性能割又は軽自動車税環境性能割(旧自動車取得税)がその車の取得価額(車両購入価格等)に応じて課される。保有段階では、毎年4月1日時点での自動車の所有者に対して、自動車税種別割又は軽自動車税種別割が車両の種別や総排気量等に応じて毎年課され、車検時には自動車重量税が車両の重量に応じて課される。なお、保有段階の税目には、エコカー減税やグリーン化特例と呼ばれる車両の環境性能に応じて税負担を軽減する時限的措置も併せて講じられる。走行段階では、ガソリンに対する揮発油税及び地方揮発油税、軽油に対する軽油引取税、LPG に対する石油ガス税がそれぞれ課されており、走行時の燃料消費量に応じて税を負担している。
このように、自動車関係諸税には数多くの税目が異なる段階で課されることから、特に自動車業界から「取得時には、自動車税の環境性能割・消費税・自動車税の初年度月割課税の3つが課せられ、複雑な体系となっており、簡素化の観点から自動車税の初年度割課税は廃止すべき」との要望や「自動車重量税は、創設の経緯等からすると本来であれば直ちに廃止すべきだが、保有時の税負担軽減・税制の簡素化の観点から、先ずは本則税率に上乗せされている“当分の間税率”を廃止すべき」との要望など、取得段階や保有段階の一部の税目の廃止による簡素化の要望が根強く残っている(4)(5)。
また、取得段階の環境性能割や保有段階のエコカー減税・グリーン化特例と呼ばれる、省エネ法で定める2020年度の燃費基準値の達成率に応じて減税措置が講じられているが、図表2に示すように各税目で減税率がそれぞれ異なっている状況も確認できる。こうした環境インセンティブの不均一性は、税制の簡素化が進むことで是正される可能性がある。
図表1 日本の自動車関係諸税の全体像
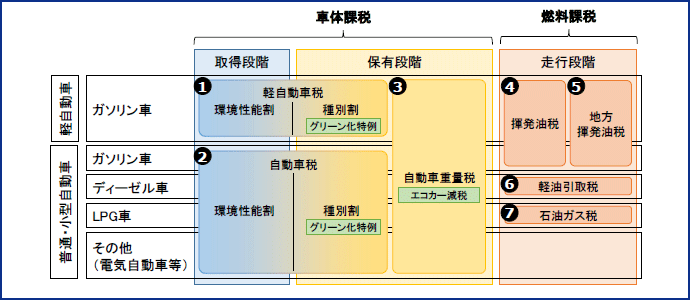
(注)これらに加えて車両や燃料の購入時には消費税も課されるが、本稿では扱わないこととする。
(資料)みずほ情報総研作成
図表2 乗用車に対する環境性能に応じた減税率
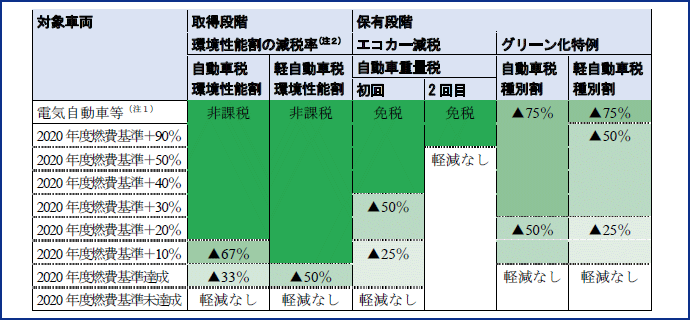
(注1)電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、プラグインハイブリッド車、クリーンディーゼル車を指す。
(注2)実際の環境性能割は、環境性能に応じて取得価額に対する税率が設定される(自家用乗用車は0・1・2・3%の4段階、軽乗用車及び営業用乗用車は0・1・2%の3段階)。ここでは、エコカー減税やグリーン化特例と比較可能とするため、最高税率からの実質的な減税率として記載している。
(注3)ここでは、消費税率引上げ及び新型コロナウイルス拡大に伴う環境性能割に対する2021年3月末までの例外的な減税措置を外した減税率を示している。
(資料)みずほ情報総研作成
(2) 電気自動車における課税標準の喪失やシェアカー利用時の税負担構造の違い
CASE(Connected(コネクテッド)、Autonomous(自動運転)、Shared & Services(シェアリング/サービス)、Electric(電気自動車)の頭文字を取った造語)が象徴するように、ここ数年で自動車にまつわる新しい技術やサービスが急速に広まりつつある。このような時代の潮流は、我が国の自動車関係諸税にも影響を及ぼしている。
例えば、内燃機関を持たない電気自動車や燃料電池自動車では、総排気量がゼロになるため、総排気量に応じて税率が定められる自動車税種別割では、常に最低税率が適用される。また、図表1に示すように、自動車用途の電力等に課される走行段階の税目は現時点で創設されておらず、車両の燃料種によっては税負担の公平性が担保されない。特に電力においては、ガソリンスタンドのような燃料の供給設備が、公的な充電ステーションだけでなく自宅や職場等にもある。後者は自動車用途とそれ以外の用途が区別できない限り税を課すことが困難であり、このことが電気自動車に対する燃料課税の導入を難しくしている。
また、シェアリングサービスの普及は、自動車を保有せずに利用するユーザーを増加させる。従来、取得段階及び保有段階の税金(以下、車体課税という。)の負担者は、所有者でもあり利用者でもあるユーザーであったが、シェアカーを利用する場合、車体課税が保険料や車両メンテナンス費等と一体化されてシェアカーの利用料金に内包される。これは、個々の税目に対する負担感や認知度合いが自家用車ユーザーに比べて相対的に薄まる可能性や、シェアカー事業者が利用料金に車体課税を適切に転嫁せず、自家用車とシェアカーでユーザーの税負担に格差を生じさせる可能性がある。そしてこれらは、次項で整理する各車体課税が本来備える性格を曖昧にすることにもつながる。
(3) 課税根拠からみる外部性を考慮することの重要性
前項で整理したように、現行の車体課税は、電気自動車やシェアリングサービスの普及に対応しきれない可能性が高く、また根強い自動車業界からの税制の簡素化の要望も踏まえると、車体課税の役割は徐々に弱まっていくと予想される。
今後中長期的な検討を行う際は、車体課税が本来持つ役割を活かした形で自動車関係諸税の見直しを行うことが望ましい。そこでまず、各税目の課税根拠から車体課税の役割を把握する(図表3)。
このうち、総排気量に紐づく「財産税的性格」は、文字通り乗用車を財産とみなし、所有に対して税を負担する能力を見出すものであり、総排気量が大きいほど税負担は大きくなる。だが、先述のように電気自動車や燃料電池自動車は排気量という概念自体がないため、総排気量の大きさを財産税の指標とすることは今後難しくなるだろう。
一方で、環境性能割や自動車重量税の課税根拠とされる「社会的費用」とは、自動車がもたらす大気汚染や渋滞、交通事故等に伴い社会全体が被る損失を指す。具体的には道路建設費用や交通事故による医療費用、公害対策費用等が挙げられ、図表3にある「道路損傷負担金」や「環境損傷負担金」も内包している。このうち、社会的費用を発生させる主体が直接負担していない損失に伴う費用を外部費用と呼び、そのような外部費用を構成する要素を外部性と呼ぶが、先述した自動車に関連する交通事故や道路建設、大気汚染等による外部性は今後も対策が必要な事項であり、自動車の外部性に対応するという車体課税の役割を維持していく必要がある。
以上を踏まえると、中長期的な自動車関係諸税の見直しの方向性として、“車体課税を縮小させつつ自動車の外部性を考慮した走行段階の課税に移行する”という選択肢が浮かび上がってくる。次章では、外部性と走行段階の課税に焦点を当てて、我が国に望ましい課税方式の検討を進めていく。
図表3 車体課税の課税根拠
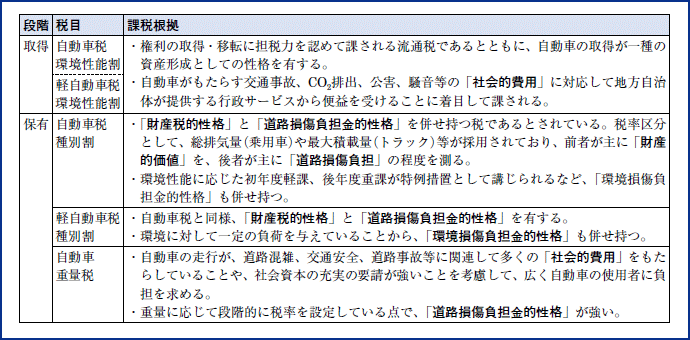
(資料)総務省「自動車関係税制のあり方に関する検討会報告書」(6)、東京都税制調査会「平成30年度東京都税制調査会答申」(7)等に基づきみずほ情報総研作成
本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。
レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。
関連情報
この執筆者はこちらも執筆しています
-
2019年3月
―「カーボンプライシング」と「自動車関係諸税」のあり方についての考察―
-
2019年2月26日
―環境負荷の低減の観点から―