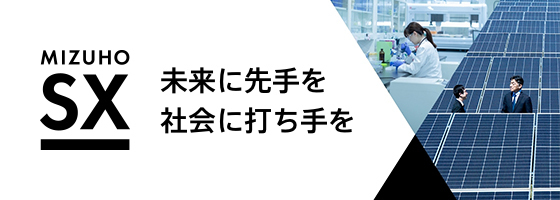*本稿は、『週刊東洋経済』 2023年7月22日号(発行:東洋経済新報社)の「経済を見る眼」に掲載されたものを、同編集部の承諾のもと掲載しております。
本年7月から、国土交通省、厚生労働省、法務省の合同で、住宅確保に困難を抱える人々への「居住支援」をテーマにした検討会が始まった。
居住支援には一律の定義があるわけではないが、①入居前の住宅確保への支援、②入居後の居住継続への支援、③さらに高齢者の場合は死後対応、が挙げられる。住宅確保のみならず、入居後の見守りや生活支援、さらに死後対応などを一体的に提供する点が特徴である。縦割り行政では対応できず、住宅を管轄する国交省と、生活困窮者や刑余者などへの福祉的支援を担う厚労省や法務省との連携が肝となる取り組みだ。
ところで、住宅確保要配慮者(以下、要配慮者)とは、どのような人々か。低所得者、高齢者、障害者、子育て世帯、DV(ドメスティックバイオレンス)被害者、刑余者、外国人などが挙げられており、居住の不安定な幅広い層が対象となる。各自の状況はさまざまだが、頼れる人がいないなど、孤立する人が少なくないと思われる。
一方、全国で空き家は増えている。それにもかかわらず、大家が要配慮者に家を貸し渋るのは、家賃滞納、孤独死、死亡後の家財処分、近隣住民とのトラブルなどのリスクが高いとみているためだ。
こうした状況を受けて、2017年に制定された新たな住宅セーフティネット法では、都道府県が不動産会社や福祉団体などを「居住支援法人」に指定し、空き家を持つ大家と要配慮者をマッチングする仕組みを整えた。注目すべきは、入居後の支援が、大家の不安を低減し、要配慮者への借家供給を増やす効果があると考えられている点だ。例えば、見守りは孤独死のリスクを低下させる。生活相談や生活支援によって生活を再建できれば、家賃滞納も減少していく。
しかし、これまでの状況を見ると、大家の不安を低減するほどの居住支援が行われてきたとは言いがたい。その一因は、入居後の支援の多くが、居住支援法人の持ち出しで実施されている点である。
例えば、筆者も関与した全国居住支援法人協議会の調査によれば、居住支援法人の約6割は「生活支援」を自法人の独自事業として行っていた。公的制度を活用して生活支援を提供する法人も4割弱あるものの、持ち出しが多くなれば、居住支援の継続は難しくなる。
また、今後、住宅確保に強みを持つ「不動産会社系」の居住支援法人と、生活相談などに強みを持つ「福祉団体系」との連携強化も必要になる。この点、福祉団体の中には、要配慮者の住宅確保のために、自ら物件を所有して居住支援を行うところもある。しかし、これができるのは、ある程度体力のある福祉団体に限られるので、不動産系との連携強化が望まれる。
住宅は生活の基盤であるが、箱としての住宅だけでは、入居後の生活を維持できないこともある。とくに孤立に陥りやすい要配慮者は、居住支援を通じて、支援者との対話を行い、生活再建に向けたエネルギーを回復させる必要がある。そして、徐々に社会参加することで、他者との関係性も広がっていく。住宅に居住支援がつくことで、生活基盤が築かれるだろう。
(CONTACT)

お問い合わせ
お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。
サービスに関するお問い合わせはこちら
メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。
mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp
その他のお問い合わせはこちら
mhricon-info@mizuho-rt.co.jp