環境エネルギー第1部 地球環境チーム コンサルタント 内藤 彩 コンサルタント 川村 淳貴
- ※図表10の右側のグラフ(走行段階の税)において、「地方揮発油税(緑色)」の値に誤りがあったため訂正いたしました(2019年11月)。
はじめに
気候変動分野における歴史的な転換点と呼ばれるパリ協定では、今世紀後半に世界の温室効果ガスの排出と吸収をバランスさせ排出をゼロにするという「脱炭素化」の目標が打ち出された。それから3年が経過したが、日本における脱炭素化の実現には未だ多くの課題が山積し、日本の長期目標である2050年80%削減についても、実現の目途は立っていない。2050年あるいはその先の脱炭素化に向けて、政府としてどのような政策を打ち出していくべきか。
本稿では、脱炭素化に向けた効果が期待され、中長期的な制度設計のあり方について今まさに議論の重要な局面を迎えている「カーボンプライシング」及び「自動車関係諸税」という二つの施策に着目し、これらの施策のあるべき方向性について、考察を行いたい。
カーボンプライシングと自動車関係諸税に着目する理由
(1)部門によって削減効果に違いが生じるカーボンプライシング(スウェーデンにおけるカーボンプライシングの事例より)
日本の議論に入る前に、脱炭素化に向けて取り組む諸外国の事例について紹介することとする。ここでは、特に野心的な目標を掲げるスウェーデンを取り上げる。
スウェーデンでは、2017年2月に発表した「気候政策枠組(The Swedish climate policyframework)」(1)において、2045年までに温室効果ガス排出と吸収をバランスさせる(脱炭素化)という目標が打ち出された。パリ協定では今世紀後半に脱炭素化を目指すこととされている中、今世紀前半のうちに脱炭素化を達成するという非常に野心的な目標である。
スウェーデンは、CO2排出1トン当たりに価格負担を求める「カーボンプライシング」の代表的施策である炭素税を1991年から導入しており、現在の税率はCO2排出1トンあたり約15,000円と世界最高水準である。またもう一つの代表的な施策である排出量取引制度についても、2005年から欧州地域に導入されたEU-ETS(EUEmissions Trading System)に参加している。こうした施策により、すべての部門に広く排出削減のシグナルを送ることで、図表1の通り、炭素価格の引上げに呼応する形でCO2排出量の削減に成功した。
しかし、カーボンプライシングを長期にわたり実施してきたことで、カーボンプライシングの課題も浮彫りになってきた。図表1を見ると、青色の運輸部門については排出削減が進んでいないことが見てとれ、少なくともスウェーデンにおいては、カーボンプライシングによって排出削減が進みやすい部門と、進みにくい部門があることが明らかとなった。排出削減が進まなかった要因は明らかではないが、特に運輸部門において現状ではガソリン・ディーゼル車を代替する技術が安価でないため、より高額な炭素価格が必要である可能性が考えられる。スウェーデンでは運輸部門の排出削減を進めるために、「気候政策枠組」において「運輸部門の温室効果ガス排出量を2030年までに2010年比で少なくとも70%削減」という個別の目標を設定し、電気自動車の普及促進策などを強化することにより、脱炭素化を目指している。
現在日本では、脱炭素化の推進に十分なカーボンプライシングの導入について議論が行われているものの導入に至っておらず、スウェーデンからは大きく出遅れている状況にある。今後、日本が脱炭素化に向けて舵を切る上で、諸外国の最新の知見を取り入れたカーボンプライシングの導入と制度設計のあり方について、議論の加速化が求められている。
図表1 スウェーデンにおける部門別エネルギー起源CO2排出量の推移(2)
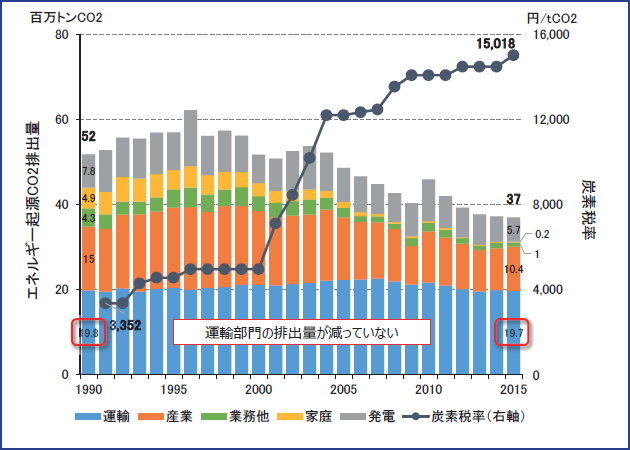
(資料)IEA「CO2 Emissions from Fuel Combustion 2017」よりみずほ情報総研作成
(2)変革期にある自動車利用における自動車関係諸税(日本の税制改正を巡る動きより)
日本における脱炭素化政策のあり方を検討するに当たり、日本で既に実施されている施策、特に日本の政治のハイライトでもある、税制をめぐる動きについてみておきたい。昨年12月に政府・与党がまとめた平成31年度税制改正大綱では、今後の検討事項として、以下の文言が記載された(3):
「自動車関係諸税については、技術革新や保有から利用への変化等の自動車を取り巻く環境変化の動向、環境負荷の低減に対する要請の高まり等を踏まえつつ、国・地方を通じた財源を安定的に確保していくことを前提に、その課税のあり方について、中長期的な視点に立って検討を行う。」
まず、特筆すべきが「自動車関係諸税」である。自動車産業は、CASE(Connected(コネクテッド)、Autonomous(自動運転)、Shared & Services(シェアリング/サービス)、Electric(電気自動車)の頭文字を取った造語)という言葉が象徴するように、100年に一度の変革期にあると言われている。その1つであるシェアリングの観点では、レンタカーやカーシェアリングの普及により、自動車を保有せずに利用することを選択する消費者も増えてきている。そのような時代の潮流を踏まえ、今般の与党税制改正大綱において、自動車関係諸税の今後の方向性として、「保有から利用」という記載がなされた。
現在の日本の税制では、自動車の取得、保有、利用の各段階で税金が課されている。一般に、取得段階の税(自動車取得税)と保有段階の税(自動車税、軽自動車税、自動車重量税)が車体課税と呼ばれている。2019年10月の消費税増税時に自動車取得税が廃止され、自動車税及び軽自動車税の環境性能割と呼ばれる取得段階の課税に置き換わるが、名目上は保有段階の税のみが残る予定である。他方で、ガソリンや軽油など燃料に対する課税は、利用段階の税に該当する。
燃料に対する課税の選択肢の一つが、前節でも取り上げた「カーボンプライシング」、特に炭素税である。CO2の排出に応じて課税される炭素税は、CO2の排出削減を進める施策であるため、前述の引用文でも言及されている「環境負荷の低減」にも資する施策である。一方で、CO2の排出に応じて課税されるということは、脱炭素化が進むほど税収が落ち込むことにつながり、長期的には「国・地方を通じた財源を安定的に確保」する観点で課題を残す。いずれにせよ、長期的な視点から、これらの課題を総合的に実現する自動車関係諸税のあり方について、今後検討が行われていくだろう。
以上のように、海外の先進事例及び最近の日本の税制をめぐる議論から、「カーボンプライシング」と「自動車関係諸税」が、脱炭素化に向けた政策オプションの一つとして重要であるとともに、議論の重要な局面を迎えていることが伺える。
以降では、これら2つの施策を取りあげ、それぞれについて日本の現状と課題を整理した上で、諸外国の事例も参照しながら、今後あるべき姿について考察を行う。
本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。
レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。
関連情報
この執筆者(川村 淳貴)はこちらも執筆しています
-
2019年2月26日
ー環境負荷の低減の観点からー