環境エネルギー第2部 チーフコンサルタント 中村 悠一郎
小売電気事業者に求められる対応戦略
ここでは、高度化法の対象事業者が、どのような戦略に基づき目標達成に向けた対応を実施するべきか、非化石証書の需給バランスを踏まえ、検討する。
(1)非化石証書の需給バランス
2020年度以降は全ての非化石電源から、その発電量に応じた非化石証書が発行されることから、高度化法中間目標下における非化石価値取引市場の需給バランスとは、非化石証書の需給バランスに等しい。そこで、公開情報に基づき、2020年度の非化石証書の需給バランスを推計した結果が図表2である。なお、FIT非化石証書とは、固定価格買取制度を利用している電源に由来する非化石証書を、非FIT 非化石証書とは、それ以外の電源に由来する非化石証書を、それぞれ意味する。前者は、国が入札販売を行うため、全ての事業者が公平にアクセス可能である。
一方、後者は、特定の事業者が保有しており、必ずしもすべての事業者が公平にアクセスできるわけではない。図表2に示す通り、第一フェーズにおいては、各事業者の目標値を引下げる「激変緩和措置」がとられることから、非化石証書全体としては供給超過の状態が持続すると見込まれる。
さて、非化石電源を保有する事業者においては、事業者ごとに販売電力量の一定割合までの非化石証書を自らの目標達成のために活用(内部調達)することが認められており、当該規模以上は外部調達しなければならない(所定の規模を超えて保有する非化石証書については、外部へ販売することが望ましいとされている)。一方、非化石電源を保有しない事業者においては、基本的には目標達成に必要な非化石証書の全量を市場や他社から外部調達しなければならない。このため、供給と需要の双方から内部調達分を控除した図表3が、各事業者が実際に直面する需給バランスといえる。市場に流通するFIT 非化石証書が全事業者の外部調達需要を上回っており、少なくとも第一フェーズにおいては、非化石証書の価格が高騰する可能性は低い。
しかし、この需給バランスはあくまで第一フェーズにおける激変緩和措置によるものである。現行の中間目標の設定条件の下、仮に激変緩和措置が撤廃されたとすれば、総量としての需要と供給は一致し(1)、全ての事業者が公平にアクセス可能なFIT 非化石証書の供給量より、外部調達分の需要量の方が上回ると見込まれる(図表4参照)。内部調達等に関する制度設計次第ではあるが、この場合、非化石証書の取引価格は高騰する可能性がある。
激変緩和措置がどの時点で撤廃されるかは現時点で未定であるが、「2030年度44%以上」という高度化法目標の達成に向けて、決して遠くない将来において実現すると推察される。このため、中間目標が課されている小売電気事業者においては、中長期的な目線での高度化法への対応戦略の策定が今から求められる。
図表2 非化石証書全体の需給バランス
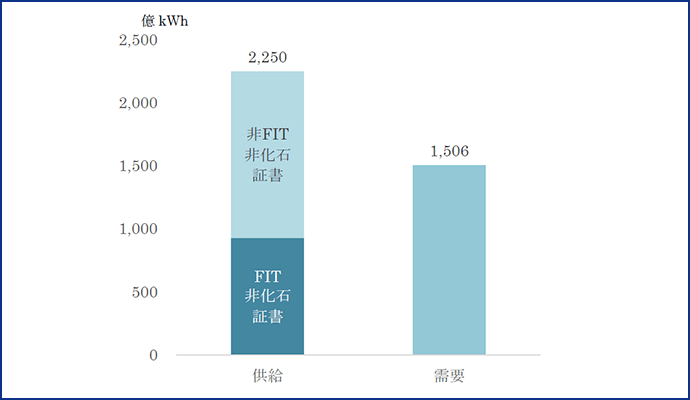
(資料)各種公開情報に基づきみずほ情報総研が作成
図表3 内部調達分を控除した非化石証書の需給バランス
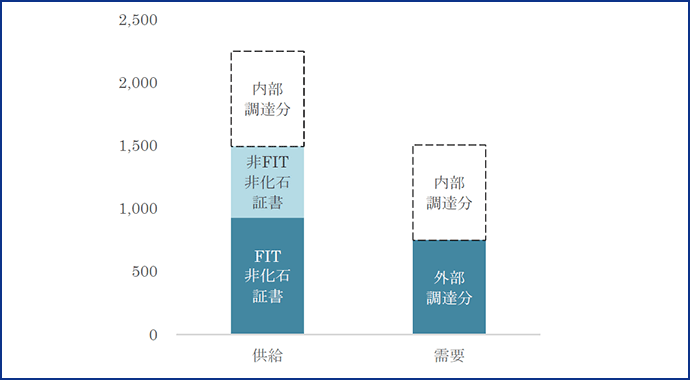
(資料)各種公開情報に基づきみずほ情報総研が作成
図表4 激変緩和措置分を加算した非化石証書の需給バランス
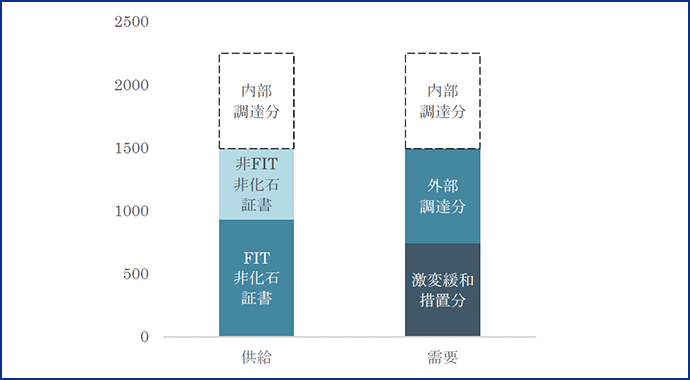
(資料)各種公開情報に基づきみずほ情報総研が作成
(2)対応戦略の策定に向けた考え方
高度化法への対応に際しては、制度設計や上記の需給バランス、他社動向等を踏まえた戦略の構築が必要とされる。具体的には、入口としての非化石価値の調達戦略と、出口としての非化石価値の販売戦略、それぞれがかみ合い、全体として最適となる戦略である。調達戦略の基本的な考え方は、いかに安価に非化石価値を調達するか、そして販売戦略の基本的な考え方は、いかに調達原資を回収するか(すなわち電力の需要家へ価格転嫁するか)である(図表5)。
まず、調達戦略の考え方について、非化石価値の調達方法は図表6のフローの通り整理される。
小売電気事業者においては、図表6に示す7通りの調達方法を組み合わせて、非化石価値を調達する。既存の電源を取得する方法[3]及び方法[4]については、例えば太陽光発電のセカンダリーマーケットとしてすでに市場が拡大している。
7通りの調達方法のうち、内部調達に分類される方法[1]から方法[4]については、電源の開発や取得(場合によってはM&A)が関係するため、時間軸としては中長期的な調達方法といえる。一方、外部調達の方法[5]から方法[7]については、既存の電源から供給される非化石証書を取り扱うものであり、時間軸としては短中期的な調達方法といえる。あるいは、財務戦略として大きな固定資本を保有しない事業者の場合には、方法[5]から方法[7]の外部調達のみで調達戦略を構築する必要がある。各方法の時間軸や自社の経営戦略等を踏まえて、2030年度までの調達戦略を構築することとなる。
例えば、方法[1]の場合、一般に大きな初期投資を伴うが、太陽光発電や風力発電等、発電コストの下落が著しい再エネ電源の場合、ライフサイクル全体での調達コストは安価にとどまる可能性がある。直近での方法[1]の採用は難しくとも、発電コストの予測や電力市場の取引価格の動向等を踏まえ、最適な時点での採用を目指すことが望ましい。方法[6]の場合、非FIT 非化石証書の市場取引においては入札下限価格が設定されていないため、方法[5]よりも相対的に安価に調達できる可能性がある(2)。
次に、販売戦略について、近年の再エネ電力やCO2排出削減等に対する需要の高まりを踏まえて、再エネ電力メニューやCO2フリーメニューとして電力商品を設計・販売し、非化石価値の調達コストを小売価格に転嫁する方法が考えられる。実際、様々な旧一般電気事業者や新電力事業者が、趣向を凝らした電力メニューを展開しており、一部の電力の需要家において実際にそれらの電力メニューを購入している事例が確認できる。このため、販売戦略として再エネ電力メニューやCO2フリーメニューを設計・販売することは、調達コストの原資を回収する方法として効果的と考えられる。
但し、電力の需要家の立場からすれば、これらの電力メニューは必ずしも一様ではなく、電力メニューの設計方法等によって、見え方や評価は異なると考えられる。その結果として、それらの電力メニューに対して支払うプレミアム価格も異なると推察される。例えば、「特定の再エネ電源で発電された電力と、同じくそこで創出された非化石証書をセットで供給するような電力メニュー」の場合と、「電力市場で調達した出自不明の電力と、やはり出自不明の非化石証書を組み合わせて供給するような電力メニュー」の場合とでは、電力の需要家にとっての価値は異なるだろう(図表7)。
したがって、顧客のターゲットと供給規模、電力メニューの設計方法、顧客が受容可能なプレミアム価格等を踏まえ、原資の回収を最大化する販売戦略を構築することが求められる。その際には、非化石価値に関する需要曲線等も重要なヒントとなるだろう。
このように、高度化法に相対する小売電気事業者においては、調達戦略と販売戦略を組み合わせ、調達コストの最小化と原資の回収の最大化、それぞれが実現する最適な戦略を構築することが、2030年度までの高度化法対応において必要である。
図表5 非化石価値の調達・販売戦略の考え方
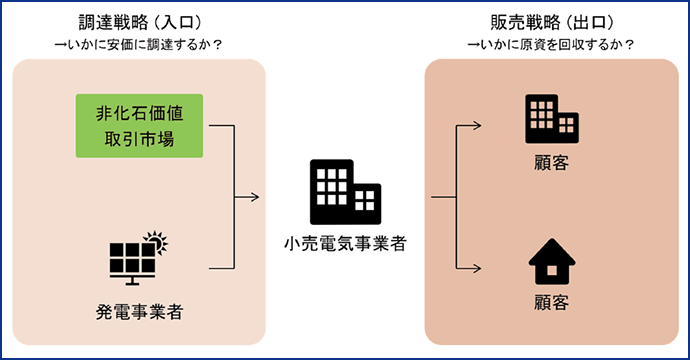
(資料)みずほ情報総研作成
図表6 非化石価値の調達方法
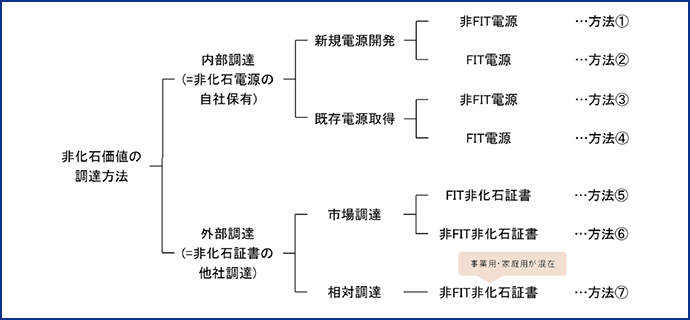
* 方法[2]及び方法[7]の場合、非化石価値は発電事業者の手元を離れるため、直接的な非化石価値の調達にはつながらない点に注意。
(資料)みずほ情報総研作成
図表7 電力と非化石証書の供給方法のイメージ
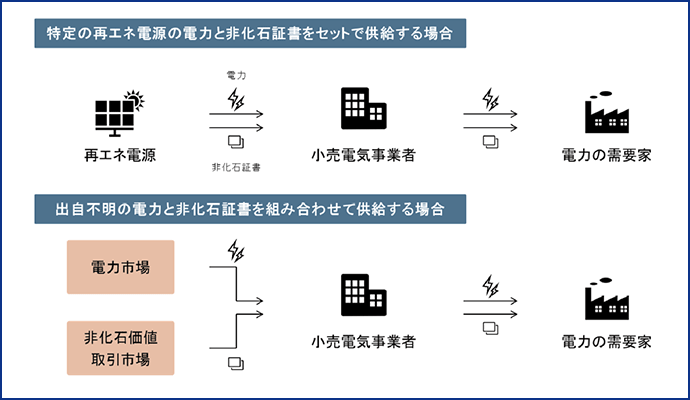
(資料)みずほ情報総研作成
本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。
レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。
関連情報
この執筆者はこちらも執筆しています
-
2018年9月9日
-
2020年3月
-
2019年1月