環境エネルギー第2部 チーフコンサルタント 中村 悠一郎
高度化法対応戦略のヒント:“ 三方良し” の最適解
前章にて、小売電気事業者の高度化法対応戦略の策定において、入口としての調達戦略及び出口としての販売戦略の重要性について述べた。しかしながら、非化石価値の取引において、発電から消費に至る電力の商流の各プレーヤー(発電事業者・小売電気事業者・需要家等)それぞれの利害は必ずしも一致しない。それぞれのプレーヤーが置かれている外部・内部環境もまた異なるものである(図表8)。
つまり、小売電気事業者として、調達コストの最小化、調達原資回収の最大化を“一方的に”追及する対応戦略では、当然のことながら発電事業者や需要家と利害の衝突が生じることとなる。このため、発電事業者と需要家も含めたそれぞれのプレーヤーの利害をバランスするような、いわゆる“三方良し”となる最適解を模索することが重要と考えられる。高度化法は少なくとも2030年度まで持続する法律だからこそ、長期的な目線でそれぞれが協力しあう関係が必要であろう。
最適解の実現に向けては、例えば欧米諸国で急速に拡大する「コーポレートPPA」等が一つのヒントとなる。コーポレートPPAとは、発電事業者と需要家の間で「固定価格×一定期間」の再エネ電力の受給契約(PPA)を締結する契約形態である。発電事業者にとっては、長期間の安定収入が確保でき、資金調達の観点でメリットを有する。特に電力市場で自ら電力を購入できる国・地域の需要家にとっては、燃料価格の変動等に伴う電力価格の変動リスクを低減できるといったメリットを有する。なお、国・地域の電力システムによっては、発電事業者と需要家が直接契約を締結することができないため、小売電気事業者が両者の間を取り持つこととなる。
コーポレートPPAには、電力と非化石価値の取り扱いに応じて、「Physical PPA(又はSleevedPPA)」と「Virtual PPA(又はSynthetic PPA)」の2種類のパターンが存在する(3)。それぞれの特徴を図表9に示す。
取引方法や価格等に違いはあるものの、いずれも本質的には発電事業者と需要家双方における「固定価格×一定期間」の売買契約を目指すものであり、それぞれにメリットが生じる契約形態である。このように、各プレーヤーの利害をバランスする再エネ電力・非化石価値の取引は、すでに欧米諸国で実施されている。
日本においては、現時点の再エネ電源の発電コストの下では、特にPhysical PPAの事業性を確保することが難しい。それでも、発電コストの下落や高度化法対応をきっかけとした様々な事業者の創意工夫等により、コーポレートPPAやそれに相当するスキームが日本でも実現可能となるだろう。
エネルギー政策上の重要な法律の一つである高度化法の対応に向けて、小売電気事業者においては入口と出口の双方をにらんだ難しい戦略の構築が求められている。発電事業者と需要家の間を取り持つ小売電気事業者だからこそ、“一方的”ではない、各社の利害を適度にバランスする“三方良し”の考え方をベースとした対応戦略の構築が必要であろう。
図表8 非化石価値の取引に係る各プレーヤーの利害関係
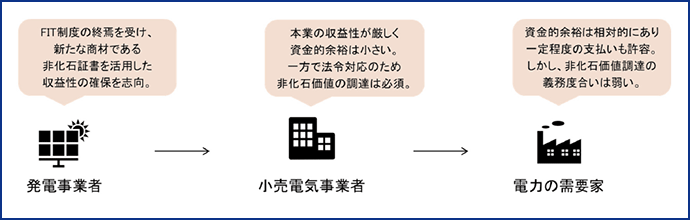
(資料)みずほ情報総研作成
図表9 Physical PPA とVirtual PPA の特徴
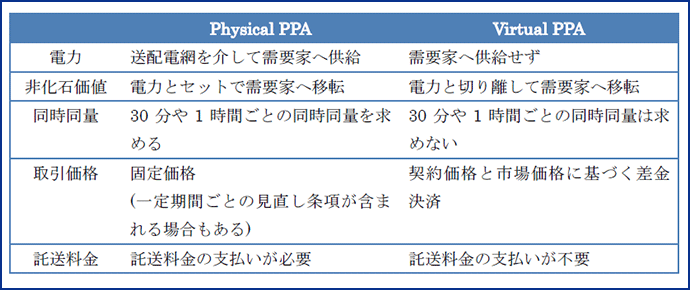
(資料)みずほ情報総研作成
注
- (1)現行の中間目標の設定ルールでは、激変緩和措置が撤廃されれば非化石証書の需給バランスは必ず一致する。
- (2)2020年11月11日及び12日に入札結果が公表され、非FIT 非化石証書(再エネ指定なし)は1.1円/kWhにて、非FIT 非化石証書(再エネ指定)は1.2円/kWh にて、それぞれ約定した。
- (3)広義のコーポレートPPAには、再エネ電源と需要地点を専用の電線で接続するオンサイト型と、一般の送配電網を介して再エネ電源と需要地点を接続するオフサイト型が含まれる場合がある。本稿では後者のオフサイト型のみをコーポレートPPAと定義する。
参考文献
- 1.
地球温暖化対策推進本部,2015.日本の約束草案.(最終検索日:2020年10月13日)
- 2.
資源エネルギー庁,2019.総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会 第20回配布資料8.(最終検索日:2020年10月13日)
- 3.
資源エネルギー庁,2019.総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会 制度検討作業部会 第30回配布資料3-1.(最終検索日:2020年10月13日)
- 4.
- 5.
資源エネルギー庁,2019.総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会 制度検討作業部会 第36回配布資料3.(最終検索日:2020年10月13日)
- 6.
本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。
レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。
関連情報
この執筆者はこちらも執筆しています
-
2018年9月9日
-
2020年3月
-
2019年1月