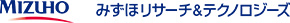サステナの落とし穴(6)
新たな道筋としての「社会的インパクト評価」
2024年5月27日 サステナビリティコンサルティング第2部 大谷 智一
これまで5回の連載を通じて各分野の専門家より、サステナビリティは特定課題の一側面からではなく、さまざまな観点からの評価・分析が必要であること、また、企業はTCFD・TNFDの統合開示に向けて進んでいることを紹介した。本稿では、このさまざまな観点からの評価・分析に対する社会の新たな動きを紹介し、対応策について考察する。
まず、統合的アプローチと思想が近いものとして「社会的インパクト評価」に関する社会の取り組みについて紹介する。2024年3月29日に金融庁から「インパクト投資(インパクトファイナンス)に関する基本的指針」が公表された。本指針は、2022年10月より8回にわたり各分野の専門家により議論がなされた内容について取りまとめたものである。
インパクト投資は、投資として一定の「投資収益」確保を図りつつ、「社会・環境的効果」の実現を企図する投資である。インパクト投資は従来のESGの概念や手法では必ずしも捉えきれない課題(生物多様性の保全、ダイバーシティの拡充、少子高齢化や地域固有の課題への対応など)に対峙する企業・事業の成長可能性等を理解・評価する投資手法である。
インパクト投資における3つの軸

出所:GSG国内諮問委員会「インパクト投資拡大に向けた提言書2019」
この社会的インパクトを評価する手法として「インパクト測定・マネジメント」がある。国連環境計画・金融イニシアティブ(UNEP FI)では、インパクトを計測する項目として「インパクトレーダー」を公表し、下表のようなインパクトを示している。
UNEP FIにおけるインパクト項目
左右スクロールで表全体を閲覧できます
| カテゴリー | インパクト |
|---|---|
| 社会 | 水、食糧、住居、健康および安全性、健康と衛生、インフラ、教育、雇用、賃金、社会的保護、インフラ(エネルギー、移動手段)、コネクティビティ(情報)、文化と伝統、紛争、現代奴隷、児童労働、データプライバシー、自然災害、ジェンダー平等、民族・人種平等、年齢差別、その他の社会的弱者、市民的事由、法の支配 |
| 資源環境 | 水、大気、土壌、生息地、生物種、資源強度、廃棄物 |
| 社会経済 | ファイナンス、ジェンダー平等、民族・人種平等、年齢差別、その他の社会的弱者、セクターの多様性、零細・中小企業の反映、経済収束 |
出所:UNEP FI IMPACT RADAR 2022 を基に、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成
サステナブルファイナンスの1つであるポジティブインパクトファイナンスでは、これらのインパクトについて、企業の事業活動が与えるポジティブ面とネガティブ面の影響を分析し、ポジティブ面は向上させ、ネガティブ面は改善を目指す。特にネガティブ面について企業は改善に向けた取り組みを実施し、可能な限り定量的指標を設定し、その状況をモニタリングすることを推奨している。
また、その他の取り組みとして、インパクトの計測に向けて、それぞれのインパクトの比較のためインパクト加重会計など貨幣価値換算での定量化が試みられている。インパクトを定量的に把握し、それらを正確に評価することはインパクトの創出のためには必要不可欠である。しかし、そのデータを継続的に把握する手間や人それぞれの価値観に影響される内容の定量化は簡単ではなく、社会的インパクト評価の普及に向けた大きな課題となっている。
本連載では、領域間に潜むトレードオフの関係性について考察してきたが、1つのプロジェクトや事業においては、あるインパクトのポジティブな効果を得ようとすると他のインパクトにおいてネガティブな効果が共存してしまうことが大きな課題であることは、これまで示してきたとおりである。本来我々が目指さなければならないのは、地球温暖化の緩和や生態系の回復などサステナブルな社会の実現を図ることであり、指標を設け定量化することは状況把握のための手段でしかない。そう考えると、企業という単位で考えた場合には、ポジティブ、ネガティブの両側面を併せ持った事業を複数実施していることを前提に、それら両方のインパクトをロジックモデルなどにより構造化し、組織内で適切に理解したうえで、インパクト創出に向けて統合的に考えることで、企業としてのポジティブ、ネガティブインパクトのポートフォリオを構築することが可能になるのではないだろうか。GSG(The Global Steering Group for Impact Investment)国内諮問委員会では、自然資本や人的資本などの経営資本の活用を通じて企業価値の向上を実現し、インパクトや収益を創出する循環「ポジティブ・フィードバック・ループ」を提唱している。また、定量化は容易ではないものの、データ蓄積がなされるまでは、前後の変化の比較によるアプローチ(例:前年との比較)などの代替的な手法によりインパクト全体の改善状況を確認することで対応が可能である。
インパクト評価は、ESGのさらなる発展形として模索段階ではある。しかし、企業が、特定課題の一側面だけではなく、事業活動のインパクトを統合的に考え、インパクトを構造化し、可能な限り定量化を図ることは、間違いなく企業の社会的インパクトを成長させ、企業価値の向上につながり、本来の目的であるサステナブルな社会の実現に近づく取り組みとなるであろう。
「ポジティブ・フィードバック・ループ」の概念図

出所:GSG国内諮問委員会 インパクトIPOワーキンググループ 「インパクト企業の資本市場における情報開示及び対話のためのガイダンス」を基に、みずほフィナンシャルグループにて一部改変
関連情報
【連載】サステナの落とし穴
- 2024年3月15日
- 非財務情報開示に見る統合的アプローチ
- サステナの落とし穴(5)
- 2023年12月26日
- 「化学物質管理」の過去事例から学ぶサステナ技術評価のススメ
- サステナの落とし穴(4)
- 2023年11月30日
- 「資源循環」と他のサステナビリティとの関係性
- サステナの落とし穴(3)