社会政策コンサルティング部 主席コンサルタント 仁科 幸一
新聞はスペイン風邪をどう伝えたのか
スペイン風邪の流行が社会にどのような影響をあたえ、人々はこれをどう受け止めたのだろうか。現在となっては、文献等から推察する以外に方法はない。そこで、当時の新聞報道に注目してみたい(22)。新聞記事は人びとの社会意識そのものではないが、読者の関心や興味のない記事を選んで掲載する新聞はない。新聞記事をたどることで、当時の読者が何に関心をもっていたかをさぐる手がかりになると考えられる。
(1)当時のメディア環境
当時のメディア環境を整理しておきたい。テレビはもちろんラジオ放送も開始されておらず(23)、商業映画は無声映画の黎明期。マスメディアは新聞、雑誌、書籍といった印刷媒体しかなかった。まだ全国紙は確立しておらず、各地に地方紙が乱立していた。東京では、大阪から進出した東京朝日新聞と東京日日新聞(現毎日新聞)、報知新聞、時事新報、國民新聞が東京五大新聞とよばれていた。雑誌は中央公論、婦人公論などの月刊誌が主流だった(24)。
速水融氏は、各地の30紙の横断的分析を通じて、スペイン風邪流行下の諸相を明らかにしている(25)。このような作業は筆者の手に余るので、東京朝日新聞のデータベース検索を使い、「感冒」の語がつかわれている記事を閲覧した。検索の対象期間は、1918年(大正7)4月~1921(大正10)年12月とした。
(2)記事の件数と掲載日数(図表8、図表9)
第1波の初期にあたる1918(大正7)年10月に記事件数が30件(掲載日数11日)と急に立ち上がり、翌11月には67件(25日)とピークを示している。なお、10月も下旬以降に記事が集中しており、22日以降はほぼ毎日、1日に複数の記事が掲載されている。その後、年末年始はいったん件数・日数ともに減るが、2月は53件(26日)にはねあがっている。3月以降は日数・件数ともに減少し、5月には流行前に近い水準にもどっている。
第2波の初期にあたる10月下旬ごろから記事の件数が増加し始め、翌年1月は62件(28日)とほぼ毎日複数の記事が掲載される状態になっている。しかし翌2月には12件に急減し8月には0件となっている。
第3波とされる1920(大正9)年8月以降は、依然と比べて記事の件数は低い水準で推移し、7月と8月は0件にまで減っている。
図表9は、記事の件数と死亡者数の推移を一図に重ね合わせたものである。内務省報告書に月別死亡者数が掲載されている月に限って表示しているが、死亡者数と記事件数が関連していることがわかる。第3波については、死亡者は第1・2波に比べて格段に少なく、図表3に示したように死亡率も第2波に比べて格段に低かった。
図表8 東京朝日新聞に掲載された記事の件数と掲載日数(月別)
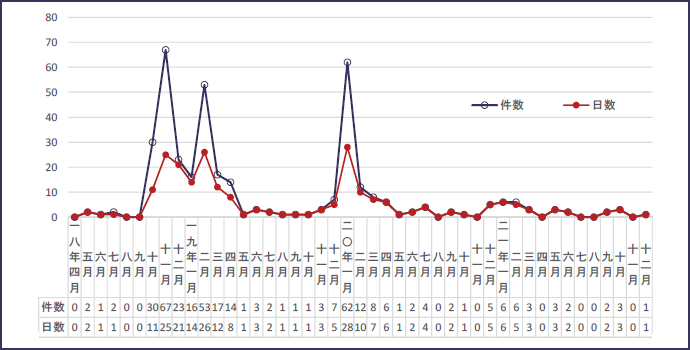
(出所)朝日新聞社「聞蔵II」より筆者作成
(注)「感冒」を検索キーワードとし、1918年(大正7)4月~1921(大正10)1年2月を検索対象期間とした。
図表9 東京朝日新聞に掲載された記事件数とスペイン
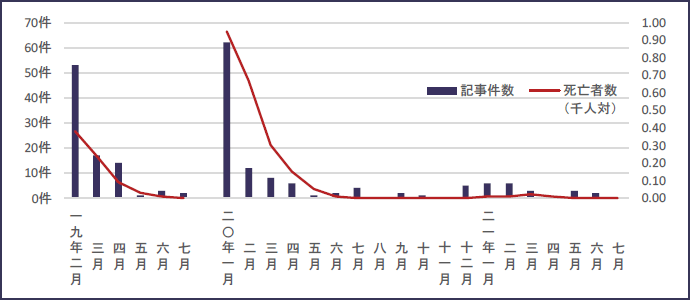
(出所)朝日新聞社「聞蔵II」より筆者作成
(注)内務省報告書に月別死亡者数が掲載されている月のみを図化した
(3)東京朝日新聞は何を伝えたのか
[1] 流行前:1918(大正7)年4~7月
第1波の直前にあたる5月に大相撲の力士の休場、7月に福島県の陸軍連隊での集団感染が報じられている。おそらくこれらは国内での流行の前兆だったのだろう(26)。
[2] 第1波:1918(大正7)年8月~1919(大正8)年7月
10月の上旬に福井県の陸軍連隊で集団感染が発生した以外、中旬まではこれといった記事はない。記事件数が急増するのは下旬以降。東京の師範学校や旧制中学校の修学旅行での集団感染、学校の遠足や運動会の中止、警察、駅、電報局での集団感染発生と業務への影響、地方の看護婦不足などが報じられている。人びとが感染拡大を身近に実感するようになってきたのはこのころと推察される。
同じ10月下旬に内務省衛生局が各府県にスペイン風邪への注意通知を発出し(25日)、流行地への防疫官の派遣(26日)、文部省が各府県知事へ防疫に関する通知を発出(27日)、警視庁警視総監が東京府下に流行感冒についての注意告諭を発出(27日)している。当時の官公庁の意思決定スピードはわからないが、これらが数日の間に発出されていることから、内務省では1か月程度早い時期に感染拡大の兆候を把握し、対策の立案や官庁間の調整にあたったものとみられる。
11月以降、軍隊での集団感染、村落あるいは一家の全滅といったできごとの報道に加え、解説的な記事が掲載され始める。おそらく、記者が取材を重ねる中でニュースソースを拡大したこと、そして何よりも読者がそういう情報を求めるようになってきたためと考えられる。年末年始にかけて流行拡大のテンポはいったん鈍ったものの、1月の中旬以降にふたたび拡大。これに呼応するかのように2月は訃報も含めて記事件数が増えている。しかし、3月以降は感染拡大が沈静化してきたため、記事も減っている。読者の関心を引くニュースが少なくなり、同時に読者の関心も薄くなったのだろう。
[3] 第2波: 1919(大正8)年10月~1920(大正9)年7月
11月6日に「スペイン風邪流行拡大の兆し」という記事が掲載される。第1波の際には軍や学校での集団感染報道が先行していたのに対して、第2波では特定集団での集団感染報道は12月以降である。すでに市中感染が拡大していたため、第1波のように集団感染が先行しこれが市中に拡大するという構図が成り立たなくなっていたのかもしれない。また、第1波の報道では、軍と学校の集団感染が中心であったのに対し、工場での集団感染や交通機関等への影響も紹介されるようになっている。これも市中感染が拡大したことの傍証であるかもしれない。
1月に、東京市と警視庁は第1波の際に内務省が示した方針にもりこんだ施策を実行に移している。予防接種の無料実施、貧困な感冒患者の市立避病院(現感染症病床)での受け入れ、活動写真や劇場の引幕も利用した警視庁による一般向け予防啓発の展開などである。
2月下旬には死亡者が減少傾向にあるということ、3月下旬には市立避病院の貧困感冒患者の受け入れ終了が報じられている。以降、報道は低調になっていく。
[4] 第3波:1920(大正9)年8月~1921(大正10)年7月
図表3に示したように、第3波の患者数も死亡者数も段違いに規模が小さい。このためであろう、記事は毎月数件程度で推移し、軍や工場での集団発生が5件、ほかは訃報、解説記事が報じられるにとどまっている。感染規模が小さくなったこの時期は、読者の関心も薄くなったのだろう。
[5] スペイン風邪報道の特徴
東京朝日新聞に掲載された記事を概観すると2つの特徴をみいだすことができる。
第1は、スペイン風邪報道に定量的な情報が少ない点だ。特に第1波の流行期は極端に患者数や死亡者数といった定量情報が少なく、時間の経過とともに少しずつふえている。流行の初期には官庁も定量的な情報を収集しきれていなかったのかもしれない。しかし第2波の記事の中での定量情報の扱いは「そえもの程度」という印象がぬぐえない。おそらく、官庁サイドの事情もさることながら、記者と読者の定量情報への関心、いいかえればデータリテラシー(データ読解力)が低かったのではないかと筆者は想像している。
データリテラシーは当時と比べて高くなったのだろうか。この点について、筆者は残念な印象しかもてない。死亡者数や感染者数を事実として報道することに異論はないが、たとえば特別区別の感染者数の実数だけを報道することには疑問がある。同じ特別区といっても、人口がもっとも多い世田谷区(約94万人)と最少の千代田区(約7万人)にはおよそ14倍の差がある。これを無視することは誤解のもとにならないだろうか。せめて、人口10万人あたりの指標をしめすべきだと筆者は考える。これではマスコミ、そして一般国民のデータリテラシーは大正時代からあまり進歩がなかったといわざるをえない。
第2は、記事の扱いが意外に軽いという点だ。当時の東京朝日新聞は朝刊のみの8ページ。1面は全て広告、記事は2面以降に11段で組まれている。読者の関心の高い記事を紙面の上部にレイアウトしているはずだが、死者数が多い時期であっても、スペイン風邪の記事は意外に中段より下に置かれることが多い。スペイン風邪が常に読者の最大関心事というわけではなかったのかもしれない。
(4)なぜスペイン風邪は忘れられたのか
速水融氏の大著(27)の序章は、「“忘れられた”史上最大のインフルエンザ」というタイトルがつけられている。速水氏はこの中で、「驚くべきことに、このスペインインフルエンザについて、日本ではそれをタイトルとした一冊の著作もなく、論文すらごく少数あるに過ぎない」。「事情は日本だけではない。この主題に関し、最もよく書かれた著作は、アメリカの歴史家アルフレッド・W・クロスビーの『史上最悪のインフルエンザ-忘れられたパンデミック』である…アメリカでもクロスビーはその著書に“忘れられた(Forgotten)”を入れねばならなかった」としるしている。
- 第一次世界大戦への関心の方が高かった。
- スペイン風邪の死亡率は他の感染症に比べて高いとはいえなかった。
- 流行は数年で収束し再燃しなかった。
- 超有名な人物の命を奪わなかった。
さらに速水氏は日本の事情として以下を指摘している。
- 日本の産業が軽工業から重工業に転換するこの時期、社会の諸相が大きく変動する中で、当時の人びとはスペイン風邪のインパクトを軽くしか感じなかった。
- コレラのように致死率の高い感染症と比べて軽い病気と感じた。
- 流行後まもない1923(大正12)年に発生した関東大震災のインパクトが大きく、その後の昭和大恐慌、満州事変、日中戦争、太平洋戦争といった後の重大なできごともあいまって、スペイン風邪は記憶の片隅に追いやられてしまった。
スペイン風邪が収束した翌年の感染症の患者数・死亡者数・死亡率(図表10)をみると、スペイン風邪の患者数も死亡者も赤痢や腸チフスと比べて破格に多いが、死亡率はきわめて低い。赤痢や腸チフスはいったん感染すれば死亡リスクが高いという点で、恐ろしい感染症だったのである。
また、当時国民病といわれ恐れられていた結核と死亡者数はほぼ同水準である。当時結核が恐れられたのは、発症から死亡までの期間が長いため家計へのダメージが大きかったことにある。一方、スペイン風邪では年単位で寝こむということはない。しかも、スペイン風邪はおよそ34か月で収束したのに対して、他の感染症はそれ以前も以降もくりかえし発生した。こうしたことから、スペイン風邪が当時の人びとの与える不安感は相対的に小さかったといえそうだ。
さらにもう一つの仮説も考えられる。当時の新聞記事の扱いや感染症の状況を考えあわせると、当時の人びとはスペイン風邪を深刻にとらえていなかったのかもしれない。つまり、スペイン風邪は忘れられたのではなく、強く記憶されなかったということではないだろうか。
図表10 1922(大正11)年の感染症の患者数・死亡者数・死亡率
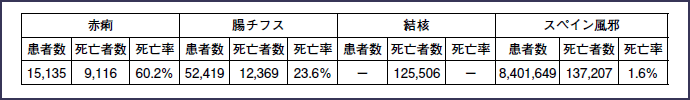
(出所)患者数は伝染病統計、死亡者数は人口動態統計、スペイン風邪については内務省報告書より筆者作成
(注1)死亡率=死亡者数÷患者数
(注2)結核の患者数は伝染病統計の調査対象外のため不詳
(注3)スペイン風邪は流行期間の合計を12か月に換算した計数
本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。
レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。
関連情報
この執筆者はこちらも執筆しています
-
2020年3月
―社会生活基本調査にみる30年の余暇活動の変化―
-
2019年9月