社会政策コンサルティング部 主席コンサルタント 仁科 幸一
参考資料と脚注
(参考資料)東京朝日新聞に掲載された主要記事
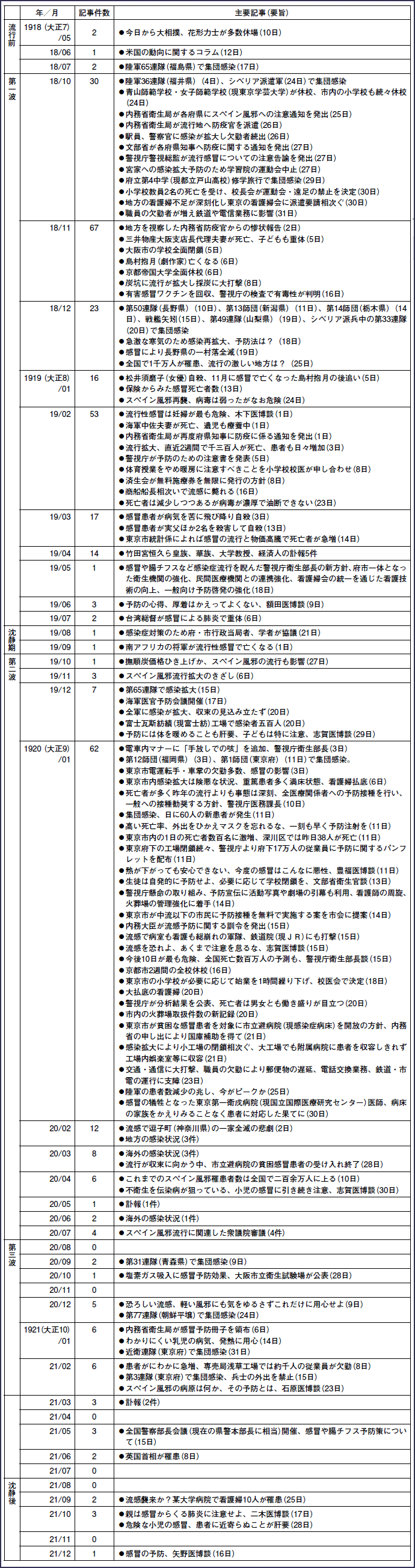
注
- (1)いわゆる風邪とインフルエンザでは重篤度が全く異なることはいうまでもない。
- (2)アルフレッド・W・クロスビー『史上最悪のインフルエンザ―忘れられたパンデミック』(みすず書房・2004年)。原書は「AMERICA’S FORGOTTENPANDEMIC」1989。
- (3)スペイン風邪の発症者の増加が収束につながったという指摘もある。(とやまスペイン風邪研究会「悪疫と飢餓」能登印刷出版部2020年)
- (4)範囲や時期については論者によって異なるが、普通選挙、言論・集会・結社の自由、男女平等、労働基本権の獲得、児童の創造性や自主性を重視する教育を求める思想潮流。明治期以来の教育水準の向上とホワイトカラーの増加を背景に、明治維新で形成された社会秩序の見直し気運が高まっていた。
- (5)速水融「日本を襲ったスペイン・インフルエンザ」藤原書店・2006年
- (6)速水融前掲書
- (7)P. Spreeuwenberg “Reassessing the Global Mortality Burden of the 1918 Influenza Pandemic.” American Journal of Epidemiology 187 (12)
- (8)United Nations Department of Economic and Social Affairs
- (9)United Nations Department of Economic and Social Affairs
- (10)細菌は単細胞の微生物で、一定の環境が整えば自分自身で増殖することができる。これに対してウイルスは、蛋白質の外殻、内部に遺伝子(DNA、RNA)を持っただけの微生物。他の細胞に入り込まないと生存も増殖もできない。ウイルスは感染した細胞を破壊させながら増殖を繰り返して他の細胞に感染し、最悪の場合宿主を死に至らしめる。
- (11)アラスカの凍土に埋葬されていた遺体から肺組織検体が採取されたことで判明した。
- (12)当時は治安維持行政の一環として道府県警察部が所管していた。致死率の高いコレラが発生した際には、警察官が伝染病予防法に基づいて出動し、発生源周辺の封鎖と患者の隔離を行っていた。
- (13)速水融氏は超過死亡数に着目した方法で死者数を推計している。これは、特定原因で平年よりも死亡者が増加した場合、平年値から推計した死亡者数との差を特定原因による死亡者数とみなす方法である。前掲書によれば、スペイン風邪の死者数は、内務省報告書をおよそ6万4千人多い45,3152人と推計している。内務省報告書では府県によって欠損値があること、死因の正確な特定は困難であったと考えられることから、速水氏の推計の方が実態に近いと筆者は考えている。
- (14)特定の感染症に対する免疫を持っている者の割合が高ければ高いほど、免疫を持たない者が感染者と接触する確率が下がることで感染の拡大が抑制される。
- (15)サイトカインとは免疫機能を調整する内分泌物質。体内でのウイルスの増殖に対応して分泌され免疫機能を昂進させる。これが過剰に分泌されると免疫細胞が体内の正常な臓器も攻撃し(免疫機能の暴走)、呼吸困難や多臓器不全などを引き起こして患者を死亡させてしまう。
- (16)神奈川県、三重県、岐阜県、佐賀県、熊本県、愛媛県
- (17) 東京府、京都府、大阪府、北海道、青森県、福島県、茨城県、群馬県、長野県、新潟県、富山県、石川県、静岡県、愛知県、奈良県、和歌山県、鳥取県、広島県、山口県、香川県、福岡県、大分県、鹿児島県
- (18)念のため速水融氏が推計した道府県別死亡率データも同じ方法で分析した結果、回帰式はy=-0.0467x+3.4073、決定係数(R2)は0.0036と、内務省報告書のデータと同様に相関は認められなかった。
- (19)府県知事及び北海道庁長官(現在の北海道知事に相当)がこれにあたる。当時の地方行政制度では、道府県知事及び北海道庁長官には内務省官僚が任命されていた。
- (20)原敬自身が書いていた日記。大正政治史研究の一級資料といわれている。
- (21)磯田道史「感染症の日本史」文春新書・2020年
- (22)本稿の執筆あたり、雑誌がスペイン風邪をどのように扱ったかをさぐるべく、国会図書館に収蔵されている「中央公論」、「婦人公論」、「雄弁」、東京朝日新聞に掲載されていた雑誌広告を検索した。筆者があたった範囲ではスペイン風邪を記事にした雑誌はみつからなかった。このこと自体、たいへん興味深いことであるが、本稿ではその事実をしめすにとどめる。
- (23)わが国でラジオ放送が始まったのは1925(大正14)年、テレビ放送が始まったのは1953(昭和28)年。
- (24)週刊東洋経済が週刊化されたのが1919(大正8)年、新聞社系の週刊誌サンデー毎日と週刊朝日が創刊されたのが1922(大正11)年である。
- (25)速水融前掲書
- (26)速水融氏の前掲書によれば、わが国におけるスペイン風邪流行の最初の兆候は、1918(大正7)年4月、当時日本統治下にあった台湾に巡業中の大相撲力士に発生した悪性感冒の集団感染であった。
- (27)速水融前掲書
- (28)わが国では2020年度末に接種が開始される予定。なお、スペイン風邪についてはワクチンが開発され、当時の内務省衛生局も接種を勧奨したが、病原を細菌と見誤っていたため薬効はなかった。
- (29)内務省報告書によるスペイン風邪の死亡者総数は388,754人(人口10万人対679.8人)、2021年1月15日時点の新型コロナ感染症の死亡者数は4,363人(人口10万人対3.47人)。
- (30)「医療介護総合確保推進法」もとづき、入院医療の機能ごとに必要な病床数を推計し、地域の医療関係者の協議(地域医療構想調整会議」)を通じて医療機関の機能分化と連携を構想して効率的な医療提供体制を実現する取組み。新型コロナ禍の影響により実質的な検討がとまっている地域が少なくない。
本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。
レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。
関連情報
この執筆者はこちらも執筆しています
-
2020年3月
―社会生活基本調査にみる30年の余暇活動の変化―
-
2019年9月