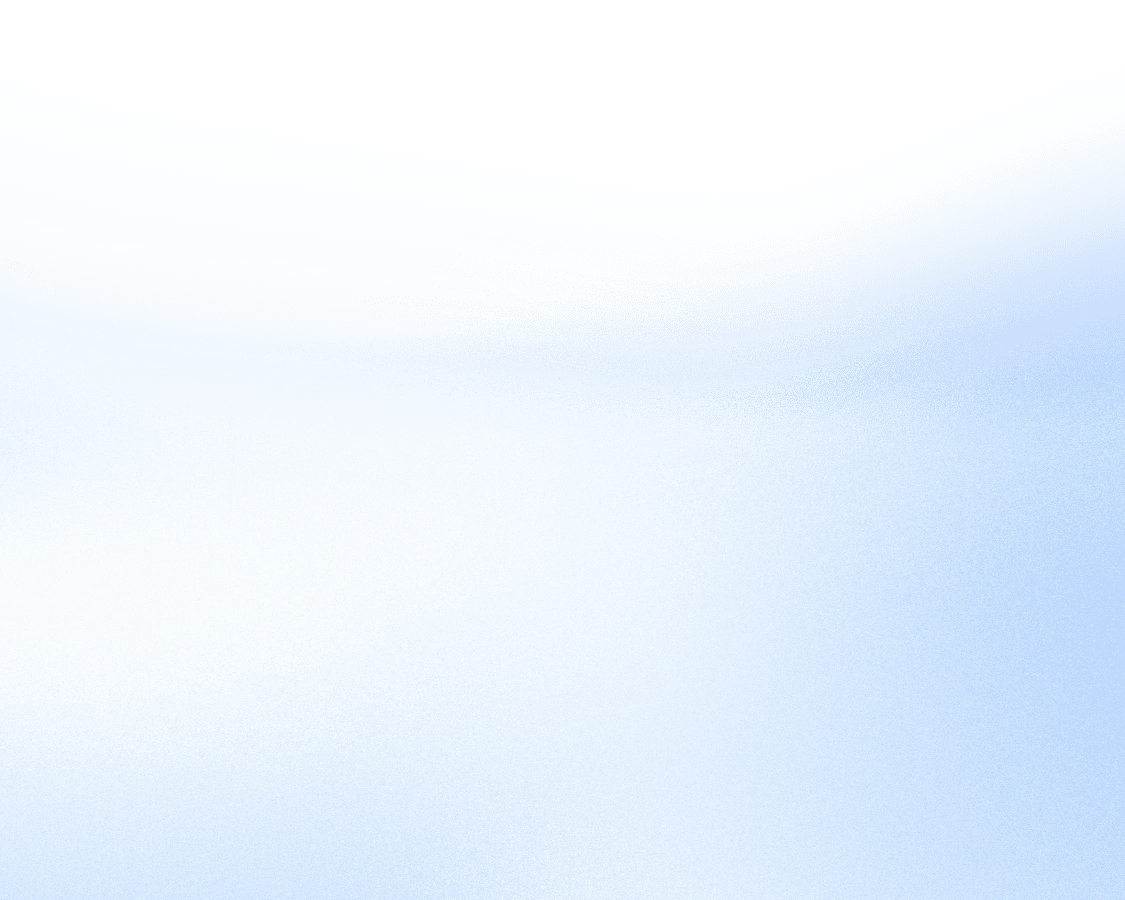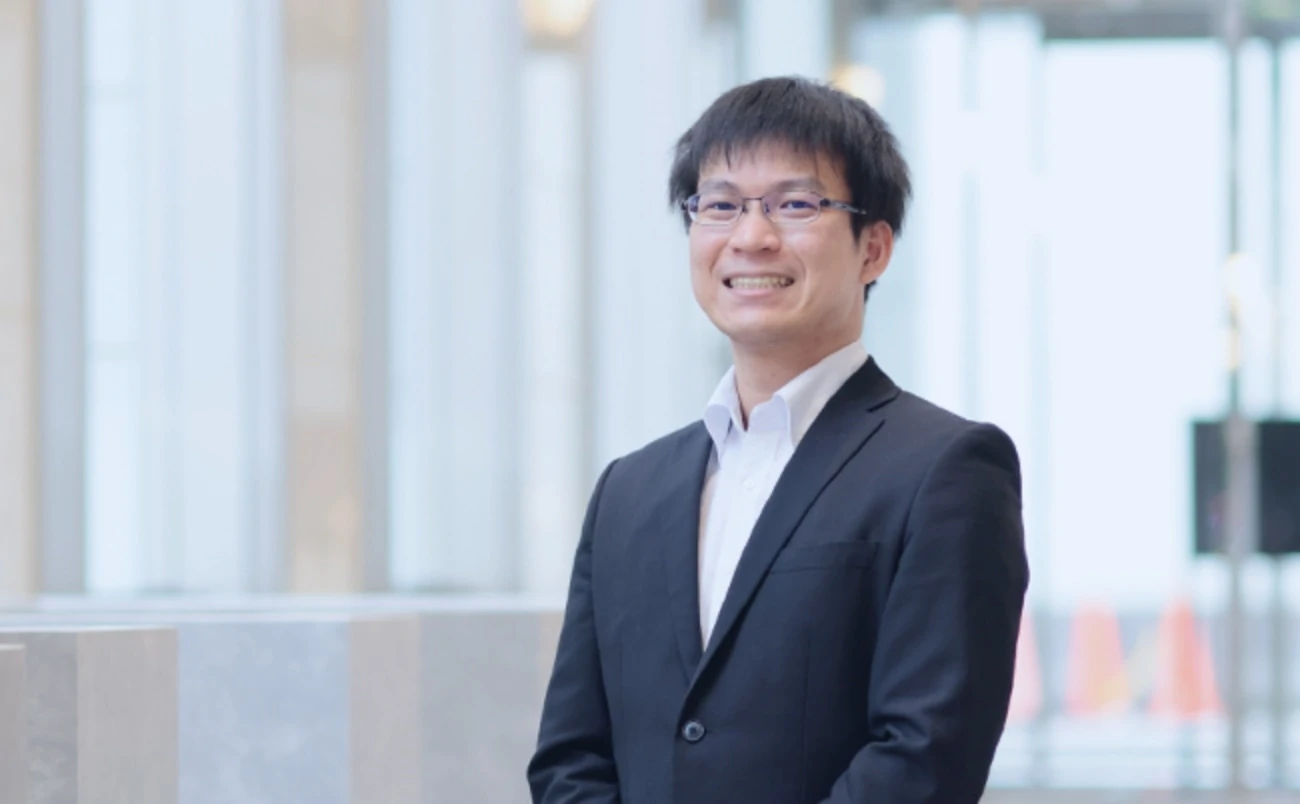低軌道衛星に甚大な被害を
もたらす可能性も。
「宇宙天気」の予報は、
私たちの社会にとって身近な問題。
「いつの日か、宇宙旅行の時代が来る。宇宙天気の予報が身近になる。」
このように鋤田が語る「宇宙天気」とは、宇宙環境の変化のこと。私たちが暮らす地球が属する太陽系の中心には、活発に活動している太陽が存在する。太陽からは常に高エネルギーの粒子や電磁波が放出されている。これらが地球に到達すると「磁気嵐」と呼ばれる現象を引き起こし、低軌道衛星や地上の送電システムなどに甚大な影響を及ぼす可能性がある。
「最近、民間企業による人工衛星の打ち上げが増加しており、これらの衛星のほとんどは小型のため、磁気嵐の影響を受けやすく、場合によっては衛星の損失につながりかねません。損害を未然に防ぐ技術が注目され、日本でも政府が検討会を設けて対策に向けた議論が行われています。」(鋤田)
鋤田が取り組んでいる研究開発は、このような宇宙環境の変化をテーマとしたものだ。なかでも磁気嵐に着目し、この磁気嵐の変化をAIで予測する研究を進めている。宇宙天気の予報は未来のことではなく、私たちの社会にとって身近な問題なのである。

幼い頃から抱いていた想いが
先進の技術と出会って
具現化された。
「宇宙×AI」というチャレンジングな研究テーマ。
鋤田が宇宙に興味を感じるようになったきっかけは、幼い頃に両親がプレゼントしてくれた星座の本だった。宇宙の壮大な謎に惹かれ、しだいに天文学への関心が高まっていった。大学で専攻したのも、宇宙に関わる研究。しかし、鋤田はここで一度、宇宙から離れる決断をしたという。
「大学院まで行って論文も書き、自分の中で宇宙についてひと区切りつきました。宇宙以外のことに携わってみたいという想いもあり、研究を通じて習得したプログラミングなどのITスキルを活かそうと、当社に入社したのです。」(鋤田)
そうして入社して金融系のシステム開発などに携わるうちに、鋤田はもう一つの運命的な領域ともいえるAIと出会うことになる。きっかけは入社5年目、AIをテーマとした社内ワーキンググループに参加したことだった。
「AIが社会に実装され始めて注目を集めた時期でした。AIについては、なんとなく“万能”のようなイメージを抱いていたのですが、意外に制約や課題が多いことを知って、逆に興味が膨らんできたのです。」(鋤田)
2018年には、技術開発推進部内に新設されたAI Powerhouseに異動する。この部署のミッションは、AI技術を利用して新しい事業を創出すること。しかし、提案するアイデアがなかなかプロジェクト化につながらず、忸怩たる思いで試行錯誤を続けることになった。ブレイクスルーのきっかけは、ある日のこと、「自分が本当に好きなことをテーマにすればいいんじゃないか」という先輩からのアドバイスだったそうだ。
「自分が本当に好きなものとはなんだろう…?そう考えた時に頭の中に真っ先に浮かんだのが宇宙のことでした。ちょうど社会的に宇宙天気が注目され始めた時期で、タイミング的にもよかった。」(鋤田)
このチャンスを逃したくない。そう強く思った鋤田は、一気に企画書を書き上げ、上司に提案した。「宇宙×AI」というテーマは壮大で、もちろん〈みずほ〉にとっても初めての領域だ。チャレンジングなテーマだけに自信満々というわけにはいかなかった。それでも企画を精査した上司は鋤田に告げた。「おもしろそうだ、やってみよう」。こうして2020年、プロジェクトが動き始めた。

研究だけで終わらせたくない。
社会に実装してこそ、当社が研究開発する意味がある。
鋤田はプロジェクトにおいて、宇宙天気の中でも低軌道衛星に影響を与える磁気嵐に着目した。これは、大学院時代に宇宙天気の研究をしていたことが背景にある。具体的には、人工衛星による観測データを用いて、磁気嵐の規模を示すDst指数をAI技術で予測する研究に取り組んだ。
「Dst指数に関するAIによる予測は以前から研究されていましたが、精度は高くないという状況でした。さらに先行研究をリサーチしたところ、最新のAI技術を用いたものが少ないことに気づきました。そこで “Transformer”による研究に着手したのです。」(鋤田)
この “Transformer”は、生成AIなどでも採用されている深層学習のアルゴリズムである。鋤田は最適な解を得るため、AIに学習させるパラメータを少しずつ変えるなど試行錯誤を重ね、その成果に関する論文を関連学会に発表したのは2023年7月のこと。この分野で実績のある研究者から直接声をかけられるなど、高い評価を得ることができた。
しかし、鋤田たち研究チームはアカデミアでの実績に満足することはなかった。次にチャレンジしたのは、実用化を見据えたアプローチ。学生時代に培った人脈も活かして、国の研究機関や民間企業が集まる協議会に参加してプレゼンテーションを行った。
「研究だけで終わらせたくない。社会に実装してこそ、当社が研究開発する意味があると考えています。さまざま企業と意見を交換し、私たちの成果をアピールするとともに、最前線でニーズを収集しています。民間企業と連携して彼らが蓄積しているデータを活用することで、AI予測の精度をさらに高めることもできます。」(鋤田)

日本の宇宙開発を加速するサービスを目指し、
〈みずほ〉×「宇宙」の新しい可能性に挑んでいく。
独自に開発したAIモデルは特許も取得している。さらに鋤田たちのプロジェクトは、ビジネスとしても成果をあげつつある。2024年の夏、ある研究開発法人から案件を受注し、先方のデータを用いて、より高度な予測に向けた研究が始まった。このような実績がバックボーンとなれば、社会実装に向けた民間企業とのビジネスも加速していくはずだ。
「この研究の成果を、日本の、世界の宇宙開発を加速させるサービスにまで昇華させたい。そのためにも、私たちのチャレンジを積極的に社会に伝えていこうと思っています。」(鋤田)
今後の目標についてこのように話す鋤田は、最近研究成果とはまた別の手応えを感じて驚いている。それは〈みずほ〉×「宇宙」という新しい可能性だ。「〈みずほ〉というと金融のイメージが大きいが、こんな面白い取り組みをしているとは知らなかった」。展示会に出展した際など、このような声を聞くことが増えてきた。〈みずほ〉のブランドに新しい価値をもたらすかもしれない、インパクトの大きさが、プロジェクトを前進させるエネルギーになっている。
「子どもの頃から抱いていた宇宙への想いを、社会に出るタイミングで一度断ち切りました。でも、それがあったからこそAIと出会い、『宇宙×AI』というプロジェクトを立ち上げることができた。不思議な巡り合わせを感じるとともに、それを実現させてくれた当社の恵まれた環境に感謝しています。」(鋤田)
当社には、たくさんの想いや夢を持ち、さまざまな専門分野に精通した人材が結集している。さて、「宇宙」という新たな領域への挑戦を経て、〈みずほ〉というブランドは次にどのような価値を創造していくのだろうか。
※所属部署は取材当時のものになります。