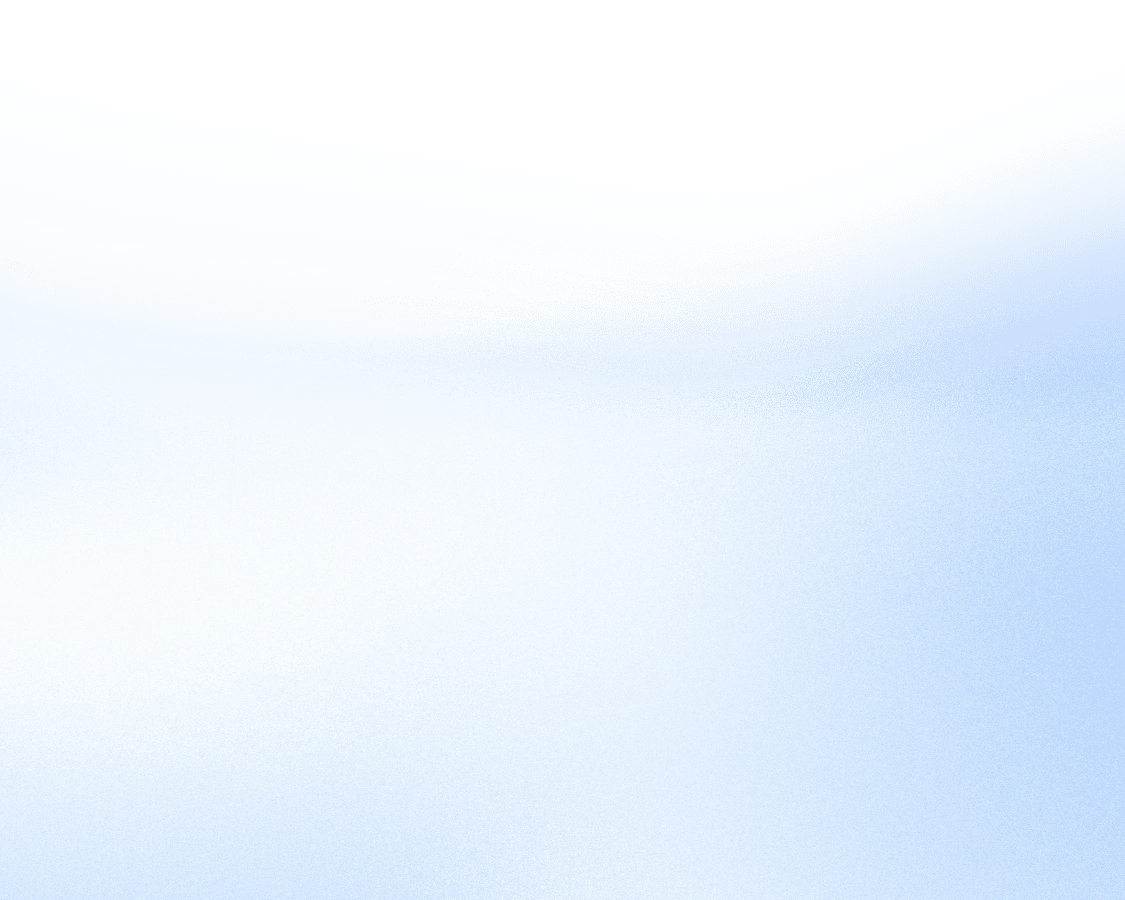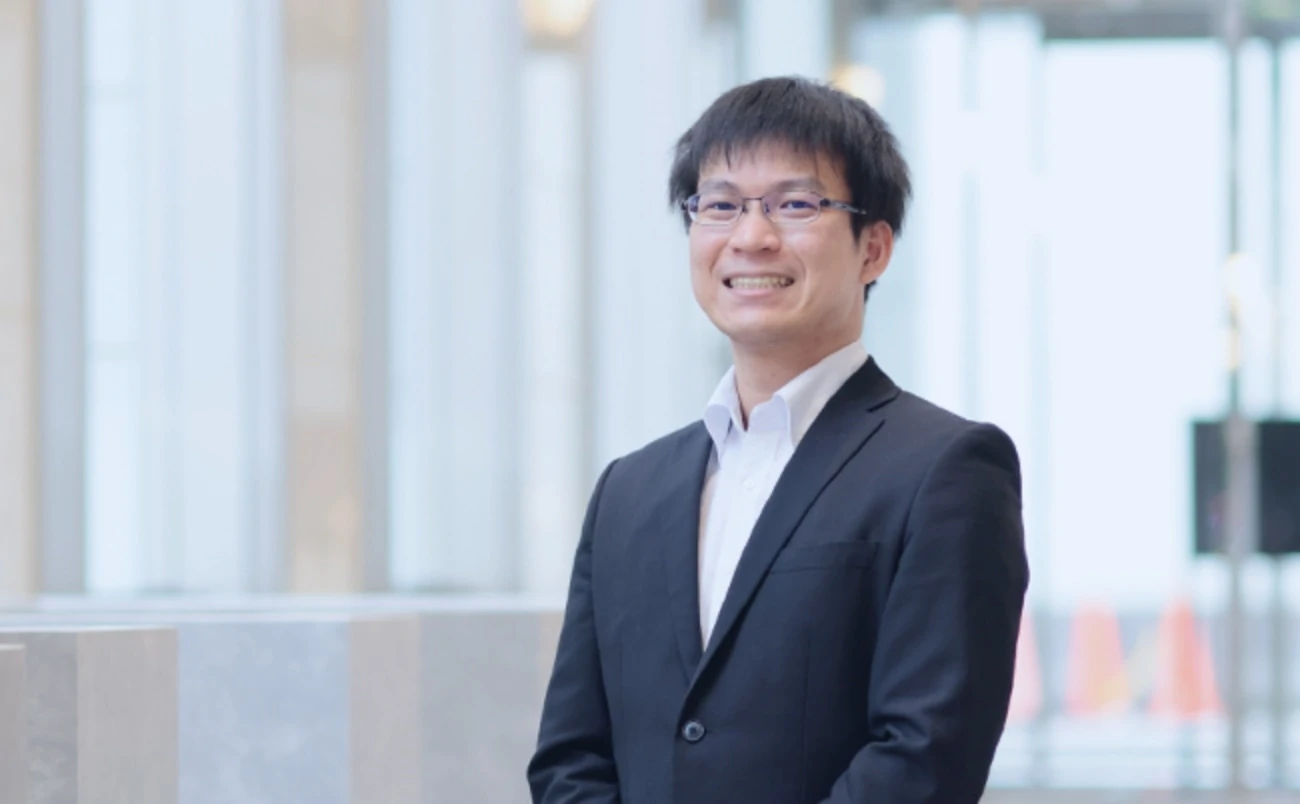政策やロードマップを策定する官公庁や
発電事業者のリスクヘッジをサポート。
Question まずは、お2人の仕事内容について教えてください。

平山
私たちが所属するサステナビリティコンサルティング第1部は、環境分野において官民双方へのコンサルティング業務やシンクタンクといった機能を担っています。そのなかで、私自身は地球環境チームに所属しており、環境省が脱炭素・気候変動に関する政策を立案する際の支援、国立環境研究所などと共同で実施する学術的なシナリオ研究等を行っています。具体的には、日本政府が掲げるカーボンニュートラル実現に関する目標数値に対する実現可能性を検証・裏付けしていくような調査がこれに当たります。例えば、目標達成のためにどのような革新的な脱炭素技術がどの程度普及する必要があるのか、そのためにはどの程度の規模のコストが発生するのかを推計する定量的なモデルシミュレーション分析を実施したり、脱炭素社会の実現に向けてどのようなステークホルダー間の協力が効果的なのかを把握するために、国内外を含めた企業の動向調査など、定性的な調査を実施しています。日本が見据えるべき中長期的なロードマップ策定に資する調査・分析・情報提供を行い、日本の脱炭素社会の実現に貢献しています。

境澤
私の場合は、「エネルギーの脱炭素化」をテーマに活動をしています。具体的には、再生可能エネルギーといわれる水素やアンモニアに代表される新エネルギーや太陽光・風力電力などの再生可能エネルギーの導入を推し進めるにあたって顕在化している課題に対して、技術面、あるいは制度面での動向調査や、導入にあたっての事業リスクモデルの開発等を通じた民間企業の支援行っています。特に、再生可能エネルギーの開発に取り組む発電事業者を対象として、事業リスクのシミュレーションモデルの開発と、それを活用したコンサルティングを行っています。例えば、太陽光発電の発電量は年々増加傾向にありますが、特定の時間帯に需要を超過して発電をするケースが出てきました。安定した電力供給を維持するためには、超過分は売電することができず、事業性という観点で見れば不採算となります。こういった影響を踏まえて、事業化にあたって起こりうるリスクを提示しながらコンサルティングにあたるわけです。

Question カーボンニュートラル・脱炭素に関わる仕事のやりがい、難しさとは?

平山
幅広い分野の見識が求められる点は、やりがいでもあり難しさでもあります。例えば、脱炭素の共通の目標の下でも、その達成に向けたアプローチに関する考え方やとらえ方は、中央省庁間でそれぞれ少しずつ異なることがあります。政策案としてまとめるには、国全体を俯瞰し作り上げる必要があるものの、ここ数年間で、脱炭素に関する取り組みや意識は急激に広がりました。政府だけでなく、産業界や投資家の動向なども含めて総合的にとらえる必要性も増しており、単に「CO2の排出量を推計する」だけでは、問題の本質を見定め、的確な示唆出しを行うことが困難になってきているのです。
より広い視野での分析を行うために、研究機関や民間シンクタンクがそれぞれ高い専門性を有する分野のモデル推計を行いながら連携し、日本全体のシナリオ分析を共創していく体制を整備してきました。当社がそのプラットフォームの役割を担いながら、各機関の強みを活かした統合的なモデル分析に乗り出しているため、より広角的な見地からの推計や分析が可能になっています。

境澤
国内では再生可能エネルギーの主力電源化に向けてFIP制度や新市場の設立など新しい制度の導入が積極的に進められています。将来の事業リスクのシミュレーションモデルを開発するうえでも、現状を分析するうえでも、考慮するべき要素が複雑化しており、すべてを詳細に把握することが難しくなってきています。一方で、政策の進展に対応した事業性評価のニーズはこれまで以上に高まっていくと考えています。複雑なだけに将来を正確に見通すことは難しいですが、関連する要素をしっかりパラメータとして設定し、どういった要素がお客さまの大きなリスクとなり得るのかを分析できるシミュレーションモデルを開発すれば、みずほリサーチ&テクノロジーズの大きな武器になると思いますね。
また、実際に発電事業を実施しているお客さまや、学識者、社内・みずほグループ内の専門家と意見交換を行う機会も多く、よい刺激をいただきながら、自身の知見をアップデートできているかと思います。


Question 今後の活動予定や目標を教えてください。

平山
これまでの支援を通じて、日本政府が宣言した2030年温室効果ガス46%削減、2050年カーボンニュートラルという目標は、国際的に見ても遜色のない内容になっていると思います。また、進捗状況の点検と目標値の更新は、今後も継続的に求められます。目標達成に向けた政策を進める中央官庁の「政治的な視点」と、私たちシンクタンクの有する「科学的な視点」をつなぎ、市民や企業などの様々なステークホルダーにとって実現可能なシナリオを描いていきたいですね。
特に、コンサルティングやシンポジウム開催を通じて、一企業でもある当社が、「国」と「民間企業を含めた市民」との橋渡し役になっていると実感しています。今後も自身の専門性や総合力を高め、企業のグリーンな成長や市民の方の脱炭素への理解をより深めることに貢献していきたいと思っています。

境澤
少し前までは、「蓄電池」「水素」「CCS」など、個別領域での技術的な動向調査やコンサルティングが実施されていましたが、今後はカーボンニュートラルの達成や、それにともなう日本のエネルギー構成のあり方という観点で、すべてを組み合わせた議論が欠かせません。また、国内の電源供給というテーマでも、政策支援や制度策定の議論が目まぐるしく展開されています。先ほど困難な点として挙げたパラメータの広範囲化や複雑化は、より進んでいくことでしょう。ここにしっかり追随して、シミュレーションモデルをブラッシュアップしていくことが目標です。
当社には、各領域に精通した先輩社員や、平山さんのように官公庁の政策決定に関わっている社員が数多くいます。また、みずほ銀行の産業調査部やプロジェクトファイナンス営業部などは、エネルギー領域を含めた産業動向やファイナンス支援に精通しています。今まで以上に〈みずほ〉の連携を強化し、自身の幅を広げつつ専門性の高いソリューション開発を進めていきたいですね。

※所属部署は取材当時のものになります。